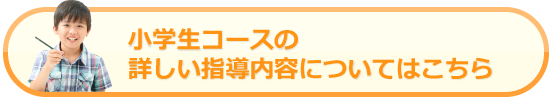中学受験の正しい勉強法とは?志望校合格を勝ち取るために必要なこと
中学受験を控え、順調に偏差値を上げ続けられている家庭もあれば、成績の伸び悩みやモチベーションの低下に頭を抱えている家庭もあるでしょう。また、「何から手をつければ分からない」という声もよく耳にします。
今回は、志望校合格を勝ち取るために知っておきたい、中学受験の正しい勉強法について解説します!
中学受験対策は、いつから始めるのがいい?

中学受験を目指した勉強を始める最適な時期は、志望校の難易度やお子さんのレベルによって変わるため、一概に「〇年生から」という正解はありません。
ここでは平均的な「受験対策の開始時期」と、お子さんに合わせたスタート時期の見極め方を見ていきましょう。
平均的な中学受験対策の開始時期
一般的に中学受験の対策は「小4」とされています。実際、中学受験を経験した保護者を対象としたアンケート結果でも、4人に1人近くが「小3(新小4)の2月ごろにスタートした」と回答しています。
しかし逆にいうと、4人に3人は開始時期にばらつきがある、ということも示しています。
「中学受験対策は小4からスタートした方が良い」と言われるのには、中学受験対策を行う塾のカリキュラムが関係しています。学習塾の中学受験カリキュラムが「小3冬(2月ごろ)」から始まるから、というのがその理由ですね。
学習塾が「2月」からカリキュラムを始めるのは、ゴールを受験本番「小6の2月」に設定するからです。そこから1年ずつ前倒してきているというわけです。
また小学校の勉強は小5から量・内容とも難しくなるということも関係しています。小5から学習課題がぐっと増えるため、それに対応できる生活リズムや勉強体力を小4のあいだに確立しておきたいのですね。
「受験本番が2月」「小5から勉強が難しくなる」この2点が、中学受験対策は小4から始めた方がいい、と言われる理由です。
つまり、お子さんに学習習慣がついていて、これまで学んできた内容がしっかり理解できており、難化する小5からの勉強にもついていけそうであれば、必ずしも「小4から」始めなくても大丈夫、ということになります。
また入試本番が2月ではなく1月、12月といった学校を受ける場合は、スタート時期としてふさわしいのは2月ではないかもしれませんね。|
お子さんの現状と目標をよく照らし合わせ、客観的に差を測る冷静さが大切です。\
早いうちから始めたほうが良いケース
中には中学受験の対策を早い時期から始めたほうが良いタイプのお子さんもいます。具体的には、次のようなタイプでしょう。
- 首都圏の超難関校を志望している
- 勉強の習慣がついていない
- 親が忙しく、子どもの勉強を見てやれない
激戦となる首都圏の超難関校を志望する場合は、専門の塾で受験対策を受けることがほとんどです。しかし合格実績のある塾はどこも人気で、本来なら小4から入塾すれば間に合うところを、「入塾枠を確保するために」小3、小2、場合によっては小1から子どもを通わせておくご家庭も多いといいます。小4から入塾しようと思っても、下の学年からの持ち上がり生のために入塾枠がない!なんてことになりかねないからです。
超難関校・人気校を受験する場合は、受験対策というよりも「塾の席を確保するために」早期から対策を始めざるを得ないのが現状です。
また勉強の習慣がついていないお子さんも、早めから対策を始めた方がいいでしょう。小学生にとって、「机に向かう習慣をつける」ことと、「勉強する」ことを両立させるのはハードルが高いものです。分からない勉強に無理やり長時間取り組まされた結果、受験も勉強も嫌になってしまっては元も子もありません。
学習習慣がない場合は、まず習慣付けを目的として低学年から受験対策をはじめることをおすすめします。取り組む課題は簡単なもので構いません。習慣がありさえすれば、勉強内容が難しくなってからも心理的な負担感少なく取り組み続けられるでしょう。
親が忙しく、細やかに見てあげられないが中学受験をしたい、という場合も早期に対策をスタートさせても良いケースです。低学年のうちから塾に通わせ、塾で一通りの面倒を見てもらうように環境を整えてしまう、ということです。
しかし中学受験は「親の受験」と言われるくらい、家庭で面倒を見てあげないといけない部分が多いのも事実。学年が上がり、親のサポートが必要になったときにどのように対応するかということも、予め考えておいたほうが良いかもしれません。
中学受験に必要な小学生の勉強時間

勉強時間は、受験が近づくにつれて伸ばしていく必要があります。身につけなければいけない単元数が多くなり、過去問対策や模試の見直しなども増えるため、少しずつ増やせるようにしていきましょう。
4年生であれば、学校と塾以外の自己学習を、平日は1日1~2時間、休日は1日4時間程度が目安です。
5年生であれば、平日は1日1~2時間、休日は1日5~6時間を目安にします。
6年生であれば、平日は1日2時間、休日は1日8~10時間、夏休み40日間で400時間というのがベースです。
志望校の難易度や今の偏差値との開き具合にもよりますが、難関校を目指すなら必須の分量です。
勉強時間を確保する方法
遊びたい盛りでもある小学生が勉強時間を確保するには、「帰宅直後」と「夕食後」の2つの時間帯を活用するのがおすすめです。
学校から帰ってきたら、ランドセルの中身を片付ける流れで机に向かう習慣を付けたいですね。とくに帰宅直後は「学校の宿題」という、子どもにとっても「何をするかが明確な課題」がありますから、スムーズに勉強に着手しやすいのです。
もう1つ大切にしたい時間帯は「夕食後」です。リラックスした雰囲気になる夕食後は、ついダラダラと時間を過ごしがちですが、ここでスパッと気持ちを切り替え、勉強に向かうようにしましょう。そのためには家族の協力も欠かせません。夕食時はテレビをつけない、食べ終わったらダラダラせず動くなど、本人が動きやすい雰囲気を作ってあげてください。
勉強方法は本人に合ったやり方を
勉強時間という「量」も大切ですが、一方で「質」も同じくらい大切です。勉強の質とは、勉強のやり方ということ。そしてこのやり方は、まずは本人が「これならできる!」「やってみたい」と思える方法であることが大切です。
世の中にはさまざまな勉強法があふれていますが、「あの子に合ったものがうちの子にも合う」とは限りません。またどんな勉強法でも、結局「やる気になって、継続して」はじめて成果は出るものです。
方法をいくつか提示し、本人に選ばせても良いでしょう。また慣れるまでは保護者が寄り添って、一緒にやってみるというアプローチもOK!一人でできるようになった、続けられたというときは褒めることも忘れないでくださいね。
★ 小学生の勉強方法を詳しくアドバイス!こちらもどうぞ。
『【徹底解説】小学生の効率的な勉強法と学習姿勢を伸ばす方法!今日からすぐに取り入れられる!』
他の習い事は続けるorやめる必要があるのか

習い事の頻度にもよりますが、塾のカリキュラムを欠席する必要がある・土日の模試に参加できない・物理的に宿題をこなす時間がない等の場合は、無理に続けない方がよいでしょう。一方、習い事が本人の支えでありいいガス抜きになっていたり、勉強を阻害せずできたりしているなら、やめる必要はありません。
ただし、5年生以上では受験に向けての対策にしぼっていく必要があります。
あくまでも気晴らしの一環として続けるものとして捉え、第一は勉強にあると心得ておきましょう。
【科目別】中学受験の正しい勉強法とは

中学受験を乗り切るためには、科目ごとに効率よく勉強することが大切です。まずは、抑えておきたいポイントをチェックしましょう。
算数の勉強法
基礎である計算力は、「量をこなすこと」「体で覚えること」が欠かせません。一朝一夕では身につかない力ですから、筋トレと同じように、日々コツコツ取り組みましょう。
中学受験ならではの出題である△△算(植木算・流水算・ニュートン算)や面積図などの特殊解法は、基本パターンを繰り返し解くことでモノにします。
どのパターンの解法を使えばいいか選択できるよう、土台を作っていきましょう。
国語の勉強法
漢字は、算数の計算力と同じようにコツコツ取り組みます。
トメ・ハネ・ハライをないがしろにせず、例文を作りながら覚えていくのが効果的です。ことわざや四字熟語も同じように、どのシーンでどんな使い方をする単語なのかを意識しながら勉強しましょう。
文章題を理解する力を上げるには、日々の音読が効果的です。
音読が上手な人は、文節やまとまりを瞬時に理解する力に長けています。逆に、音読でひっかかるところは言葉の意味を理解するのに時間がかかるポイントだと分かります。
特に難関校を受験する場合、テクニックのみに頼らず、「文章に触れることが楽しい!」と思えるような経験を積んでおくことをおすすめします。
理科の勉強法
原理や仕組みを理解することはもちろんですが、習ったことを身近なシーンで体験することが重要です。月の満ち欠けを習った後で実際に月や星座を観察したり、テコの原理を習った後でバランスよく洗濯ものを干すのを手伝ったりすることで、理科と日常生活の関わりに気づけます。
「知識」を「知恵」に昇華できれば理解も早まり、入試問題への応用も効きやすくなるでしょう。
社会の勉強法
地理を学ぶ上で白地図は必ず使用します。山脈・特産品・県庁所在地・平野・気候などさまざまな観点で白地図を繰り返し埋め、世界地図まで広げていきましょう。
歴史は、「イメージを掴むこと」が大切です。その時代ごとの服装・文化・セリフの言い回し・人間関係などを学ぶには、漫画やドラマを活用しながら勉強するのがおすすめです。語句や年代だけでなく、時代背景を読み取ることを意識しましょう。
時事問題は、ジャーナリストによる解説番組やニュースを親子で見ながら会話することで、自分ごととして捉えやすくなります。
特に、6年生の10月までのニュースはまんべんなくチェックしましょう。ちょうど10月頃から受験問題の作成が始まりますから、それ以前の時事問題は出題されやすくなります。
【学年別】小学生の正しい勉強法とは

中学受験に臨むには、数年単位での長期的な勉強計画が必要です。ここでは、学年ごとの勉強法について学んでいきましょう。
低学年の勉強方法
1~3年生の低学年のうちに取り組みたい内容として、3つ挙げられます。
まず1つ目は、机に向かう習慣をつけることです。
少しの量でも、短い時間でも、簡単な問題でも構いませんから、毎日決められた時間に机で勉強するように意識します。学校の宿題だけにこだわらず、市販のワークや問題集に取り組むのもいでしょう。
2つ目は、成功体験を積んでおくことです。
小さな成功でも褒め、スモールステップで課題をクリアしていく喜びを体験しましょう。「少し頑張ればできるかも!」という自信をつけることで勉強に前向きになり、解ける喜びや挑戦する楽しさが身につきます。
3つ目は、子どもの好奇心や疑問に真正面から向かうことです。
「なんで?どうして?」に答えるのは大変ですが、面倒でも1つずつ広い、親が分からなかったら子どもと一緒に考えたり調べたりしましょう。スマートフォンで検索して答える際も、「どういう単語を入れて検索したら情報が出てくるかな?」と問い、一緒に解決することが大切です。
小学校低学年のうちから受験を意識して頑張る子どもは少ないものです。アメとムチのつもりで「宿題しなければお小遣い減額!」「これ終わったらゲームしていいよ」など条件をつけてしまうと、アメをもらうためだけに勉強するようになってしまいます。親が上手くリードしながら、学ぶ楽しみを教えていきましょう。
4~5年生の勉強法
どの塾でも、4年生から中学受験対策が本格化します。
4年生からは学習に耐えられる体力づくりを意識していきましょう。質よりも時間と量を意識し、学習するボリュームを増やします。
5年生からは学習内容に目を向けます。入試で出題される単元の多くは、5~6年生で学びます。ギリギリ解けるかどうかの難易度を多く取り上げつつ、ステップアップのための反復練習をしていきましょう。
6年生の勉強法
6年生の夏休みまでに、小学生で学ぶ全ての単元を教え終わる塾がほとんどです。
夏休み中に基礎の総復習を行い、抜けているポイントを確認しましょう。「夏が受験の天王山」とは中学・高校・大学受験のすべてにおいて言われることですが、まさしくここが最後の復習ポイントです。
9月以降は過去問に取り組み、志望校の特色を把握しながら補足的に学習していきます。
中学受験で挫折しないための勉強法

中学受験をするに当たり、挫折しにくい勉強法があります。
まず1つは、教える人と教えない人を決めることです。
家でも家庭でも、先生からも親からも常に指導されてしまうと、子どもの逃げ場がなくなり、追い詰められてしまいます。結果的に効率が下がったり「机に向かうのが嫌だ」と感じたりすることで挫折しやすくなります。
本人が休憩できる場所や時間を用意することで、長期間の受験勉強を乗り切れるようになります。
次に、結果ではなく経過の良さを認めてあげることです。
結果が大事なのはもちろんですが、頑張りを認め、褒めてあげることも大切です。サボりがちでなかなか勉強しない姿に親が心配になってしまうこともありますが、テキストを持った瞬間に「勉強する!?偉いね!」と褒めてあげるくらい大袈裟でもいいでしょう。
結果に言及する場合もポジティブな発言を心掛け、伸びしろを発見するような姿勢でいることが大切です。
中学受験対策は、塾に行った方がいい?

塾に通った方がよいのかどうか、というのも気になる点ですよね。結論からいうと、中学受験の場合は塾に通い、専用の対策を受けることをおすすめします。もしお近くに志望中学の対策を行っている塾がない、という場合は「オンライン指導」という選択肢もありますので、検討してみてください。
塾に通うことで得られるメリット
難関、あるいは都道府県内でトップレベルの私立中学では、小学校の学習課程から逸脱する問題を出題してくることがあります。非常に難しい問題や特殊な考え方が必要な計算、あるいは教科書には載っていない知識問題を出すところも多いのです。「中学受験特有」と言われるこうした問題に対応するには、小学校の勉強や独学では限界があります。
また多くの公立中高一貫校では「適性検査」と呼ばれる試験が課されます。適性検査は従来の教科試験とは異なり、複数教科を横断的に網羅した問題や総合的な視点が問われる問題、思考力・発想力を試す問題などが出題されるのです。これらの問題も、通常の小学校のテストやドリルでは対応しきれないと言われています。
学習塾に通うと、中学校ごとの出題形式を分析し傾向を踏まえたカリキュラムに沿って対策することが可能。これが塾で中学受験対策を行うメリットです。
塾の選び方
中学受験対策用の塾を選ぶ場合のポイントは次の通りです。
- 志望中学の対策を行っているか
- 授業スタイルは子どもに合っているか
- 校舎の雰囲気は好ましいか
- 立地は通いやすいか、負担なく通える距離か
志望校の対策を行っているかは、最も大切なポイント。集団指導か個別指導か、校舎の雰囲気は子どもに合いそうかなどもチェックしてあげてください。体験授業を申し込み、保護者も一緒に行ってみると校風がつかみやすいですよ。
また立地・通塾方法も重要です。子どもが自転車で通っていても、送迎が必要になる事態もあるかもしれません。また評判の良い塾でも、通塾にあまりに時間がかかっては継続しにくいものです。実際に通い続けることをシミュレーションして検討してみてくださいね。
★ 中学受験|ピッタリの塾の選び方について、詳しくはこちらもどうぞ!
『【完全ガイド】中学受験を成功させる塾の選び方|お子さまにピッタリの塾と出会うコツ徹底解説』
「オンライン家庭教師」という選択肢もある!
通える範囲に志望校対策をしている塾がない、あるいは子どもに合いそうな塾がない……、そんな場合には『オンライン家庭教師』という選択肢があります。
オンライン家庭教師とは、パソコンやタブレットなどを使い、講師と生徒をリアルタイムで接続、マンツーマンで勉強を見る指導スタイルのことです。外出を控えたい時でも勉強の機会を確保できる、また居住地の制約を受けずに先生を選ぶことができるといった利点から、いま人気を集めています。
たとえばオンライン家庭教師ピースでは、お子さんの目標や勉強のクセ、学習の理解度などもすべて踏まえた「最適カリキュラム」を作成。採用率5%という選考を潜り抜けた精鋭講師が、マンツーマンでじっくり教えます。宿題の計画表も作ってくれるので、授業時間以外に何をやったらいい?という悩みもなくなるんですよ。
ピースは全国の国公私立中学の受験に対応!お子さんの様子をしっかりお聞きし、ピッタリの先生をマッチングした上で体験授業を受けられますので、まずはお気軽に問い合せてみてください。
オンライン専業10年以上の実績!不明瞭な料金はいただきません|オンライン家庭教師ピース
中学受験、親はどんなサポートをすればいい?

中学受験に合格するためには、親のサポートが欠かせません。そして実は、勉強面以外でも親の手が必要になる場面はとても多いのです。
中学受験を支える親がやるべきことを4つ、まとめました。
生活習慣(基本的なしつけ)を身につけさせる
基本的な生活習慣整っていることは、中学受験を成功させる大切なポイントです。ここでいう「生活習慣」とは整理整頓や物や情報の管理のこと。身の回りの整理整頓や管理ができる力は、そのまま知識の整理整頓や管理につながると言われています。実際、地頭が良いと言われる子や成績が良い子は、プリントや文房具も適切に整えられていることが多いものです。
- 学校や塾からのプリントは、きちんと出す
- 文房具はなくなる前に用意する
- 提出物の締切を守る
学校や塾は、こうした基本的な習慣を身につけさせることまでは面倒を見てくれません。ここは親の役割です。まず「自分のことは、自分できちんとできる」ように、生活の基盤を整えてあげましょう。
規則正しい生活をサポート
続いては「規則正しい生活」についてです。長時間の勉強が必要になることも多く、また真冬の2月に本番を迎える中学受験は、なにより「体力」が大切。基礎体力をしっかりとつけておくために、規則正しい生活はとても重要です。「もう小学生なんだから」と言わず、こまめに世話を焼いてあげてください(子どもが一番サボりがちな部分でもありますしね)。
- 毎日、決まった時間に起き、決まった時間に寝る
- 食事はバランス良く、しっかり食べる
- 適度に身体を動かす
- 手洗い、うがい等、感染症予防策を徹底する
- 予防接種を受けさせる
- 様子をよく見て、不調そうなら速やかに病院に連れて行く
受験生だからといって睡眠時間を削るのは禁物。睡眠不足はパフォーマンスの低下につながるだけではなく、体調不良の原因にもなるからです。元気な受験は、規則正しい生活から!無理をさせないよう、健康に気を配ってあげてください。
褒め、認め、やる気を出させるサポート
褒められると嬉しいですし、やる気もでますよね。褒めてくれたのが大好きなお母さん・お父さんならなおさらです。お子さんの取り組みを良く見て、たくさん褒め・認めてあげてください。それこそが、学校でも塾でもできない、親ならではの最高のサポートです。
よく「うちの子は秀でているところがなくて…、どこを褒めたらいいのでしょう」とおっしゃる保護者もいらっしゃいます。そんな方にはこう考えてみてください、「良くできたから褒める、のではない。頑張っているところ、真剣になっている姿、普段とほんの少し違う様子を見つけて、そのまま言葉にするだけで十分」と。
「良い点数だったから、褒める」「前回より良くできたから、褒める」という褒め方をしていると、テストが返ってきたときなど限定的な場面でしか褒められないのではないですか?でも「しっかり勉強している」「テレビをすぐに消して勉強に向かった」「じっとよく考えてやっているようだ」、こうした場面を褒めるようにしたら、それこそ毎日いくつも褒めタイミングが生まれます。
子どもとっても「お母さん・お父さんは、自分のそんなに細かいところまで見てくれていたのか!」と驚きとともに嬉しくなり、そして次のやる気につながる好循環が生まれます。
お子さんの「頑張っている姿」をたくさん見つけ、たくさん認めてあげてくださいね。きっと、「勉強しなさい!」って言わなくて済むようになりますよ。
★ つい「勉強しなさい!」と怒ってしまう方に…。
『子どもが勉強しない!やる気を引き出すために親が取り組むべきこととは!?』
情報収集は親の役割
親のサポート、最後は「情報収集」についてです。募集要項を見るとわかりますが、徹頭徹尾大人向けに書かれています。塾のカリキュラム説明や、受験までのスケジュールなども同じです。中学受験で勉強するのは本人ですが、勉強以外は「大人の世界」なのです。
ここは保護者のがんばりどころ。手間を惜しまず、必要な情報を集めてあげてください。集めた情報は必要なときにすぐに取り出せるよう、目的に応じて整理しておくことも大切です。
★ どの中学がいい?学校選びに迷ったらこちらをどうぞ!
『【中学選び完全ガイド】お子さまにピッタリの学校を見つけるポイント解説!|全国対応版』
正しい勉強法で中学受験を成功させましょう
受験は、今後の人生の分岐点になります。どんな学校でどんな勉強をして、そのためにどう対策したかは、合否に関わらず本人の大きな糧となるでしょう。
しかし、せっかくチャレンジするなら合格を目指したいのは誰しも同じです。ポイントを抑えて効率よく勉強してサクラサク春を迎えられるよう、本人も保護者も努力していきましょう!