子どもが勉強しないときにどうすればいい?親ができる対応方法を紹介
「子どもが勉強しない…」と困っている親御さんもいるのではないでしょうか? 「強制するのは気が引ける」けど「放置はしたくない」と考えている方も多いと思います。 お子さんの将来を考えると、勉強ができるようになってほしいですよね。 この記事では、子どもが勉強しないときにどうすればいいかについて、その理由や親ができる対応方法を解説します。 子どもとの接し方や子どもの成績で悩んでいる方は、参考にしてください。
勉強にやる気がない子どもは多い!

「私だけが悩んでいる」と不安になってしまっている方はいませんか?安心してください。この悩みは保護者の方からよく寄せられる悩みです。そしてこの悩みは昔から変わらず存在してきたものでもあります。
時代は変われども、子どもたちの勉強に対する意識は変わりません。勉強が自分の人生においてどのくらい大切なのかをきちんと理解する、その手助けを保護者の方々にはしていただきたいと考えています。
勉強しない子どもを放っておくとどうなる?
 まず、勉強しない子どもに対応せず、放っておくことのリスクを把握しておきましょう。 子どもを放っておくと、以下のようなリスクがあります。
まず、勉強しない子どもに対応せず、放っておくことのリスクを把握しておきましょう。 子どもを放っておくと、以下のようなリスクがあります。
- 周りの子と差が広がり自信がなくなる
- 授業がわからなくなりやる気を失う
- 志望する高校・大学に行けなくなる
- 将来もらえる給料が下がる
- 職業の選択肢が狭まる
それぞれのリスクについて、解説します。
リスク①:周りの子と差が広がり自信がなくなる
勉強しない子どもは成績がどんどん下がり、周りの子との差が広がり自信をなくしてしまいます。 勉強ができる子は授業中に手を挙げて積極的に授業に参加するため、テストの点数が高い傾向にあります。 一方で、勉強ができない子は勉強ができる子と自分を比べてしまい、自信をなくしてしまうため、やる気を失っていきます。 その結果、勉強しなくなってしまいます。
リスク②:授業がわからなくなりやる気を失う
勉強しない子どもは授業がわからなくなるため、やる気を失ってしまいます。 そのため、授業が退屈な時間になり、最悪の場合、勉強することが嫌いになってしまいます。 勉強嫌いになるのを防ぐためには、以下の点に注意してください。
- 授業についていけるようにする
- わからない点はその都度解消する
1度授業についていけなくなると、追いつくことが大変であるため、授業の疑問点はその都度解消することが大切です。
リスク③:志望する高校・大学に行けなくなる
勉強せず基礎的な学力がないと、志望する高校・大学に行けなくなってしまう可能性があります。 特に難関レベルの高校・大学に合格するためには、早い段階から基礎をしっかり固めて受験対策をしなければいけません。 小学校や中学校で勉強しないと基礎学力が身につかないため、高校・大学受験で苦労することになります。 そのため、勉強しない子は、志望校のレベルを下げなければいけないかもしれません。
リスク④:将来もらえる給料が下がる
勉強する習慣がなく学力が低い場合、将来もらえる給料が下がると言われています。 そもそも、大卒と高卒ではもらえる給料が異なり、大卒のほうが高い給料をもらえます。 そのため、勉強しなかったことで高卒になってしまうと、給料が下がってしまいます。 また、勉強のやり方を身につけていないと、キャリアアップのための資格勉強を効率的に進められないため、給料が上がるペースが遅くなるかもしれません。
リスク⑤:職業の選択肢が狭まる
勉強に集中して取り組まないと専門学校に合格できなかったり、資格を取得できなかったりして、職業の選択肢が狭まってしまうリスクがあります。 子どもの頃に勉強していない場合、勉強する習慣がなかったため、勉強のやり方がわかりません。 そのため、理想の職業に就くための資格などの勉強ができず、就職・転職に失敗するおそれがあります。 勉強する習慣を早いうちから身につけて、将来の選択肢を狭めないようにしてください!
子どもが勉強しない理由
 そもそも、子どもは勉強したくないわけではありません。 しかし、以下のような理由で子どもは勉強をしなくなってしまうのです。
そもそも、子どもは勉強したくないわけではありません。 しかし、以下のような理由で子どもは勉強をしなくなってしまうのです。
- 集中力がないから
- 勉強する意味を理解していないから
- 勉強を強制されているから
- 勉強の仕方がわからないから
- 学習環境が整っていないから
- 生活習慣が乱れているから
- 疲れているから
- ゲームに夢中になってしまっている
自分の子どもに当てはまる特徴がある方もいるのではないでしょうか。 勉強しない子どもが、どのような理由で勉強しないのかが把握できれば、適切な対応方法が見つかりますよ。
集中力がないから
子どもに集中力がないことから、勉強をしない(長時間できない)場合があります。 集中力がないと、他のことに気を取られてしまい、勉強を続けることができません。 例えば、勉強する場所の周りにテレビやゲーム、スマホなどがあると気が散ってしまいます。 子どもに集中力がない場合、気が散るような誘惑をなくしてあげることが大切ですよ。
勉強する意味を理解していないから
勉強する意味がわからないまま、勉強していても、モチベーションは下がる一方です。 学校で勉強する意味がよくわからないため、「なんで勉強しなきゃいけないんだろう?」と疑問に思っていることがあります。 親や先生が子どもに「将来勉強がどう活きるか」をわかりやすく伝えないと、勉強への意欲が湧きません。 勉強することの意味や目的、将来の夢を考える時間を子どもと一緒に作ってみてくださいね。
勉強を強制されているから
親や先生から勉強を強制されていると、反発して勉強しなくなり成績が悪くなります。 特に子どもが反抗期の場合、「勉強しなさい」と言われるほど勉強しなくなってしまいます。 子どもの将来が不安で勉強を強制したくなる気持ちはわかりますが、子どもを信頼して自分で勉強を始めるまで待つことも大切です。
勉強の仕方がわからないから
勉強の仕方がわからないから、子どもが勉強しない可能性もあります。 あるいは、勉強する意欲はあっても、やり方がわからないことから、勉強していない場合もあります。 このような子どもは勉強する意欲はあるので、責めないことが大切です。 適切な勉強の仕方を教えたら、勉強することができるので、成績が上がる可能性が高いです。
学習環境が整っていないから
学習環境が整っていないため、子どもが勉強しないケースもあります。 例えば、学習机がなかったり、部屋を片づけていなかったりすると、勉強する意欲が湧かないなどの理由で勉強しません。 また、学習スペースの近くにテレビやゲームなどがあると、勉強に集中できなくなります。 お子さんの学習環境はどのような状態になっているでしょうか? 「学習環境が整っているか」、1度チェックすることをオススメします。
生活習慣が乱れているから
生活習慣が乱れているため、勉強しない場合もあります。 というのは、生活習慣が乱れている子どもは、不規則な生活を強いられ、日中勉強に集中できないからです。 生活習慣が乱れていると、睡眠不足になってしまいます。 その結果、授業に集中できないため、わからないところが増えてしまいます。 また、2度寝や遅刻を繰り返すなど自己管理ができていないと、なまけ癖がついてしまう可能性もあります。 そのため、お子さんの生活習慣を見直すことが、勉強習慣を身につける第一歩ですよ。
疲れているから
子どもが習い事や部活などで疲れているから、勉強する元気がない可能性もあります。 習い事でスケジュールがぎっしり埋まっている小学生の場合、ただ勉強をこなすだけになってしまうことがあります。 中学生の場合、学年が上がるにつれて部活や行事で忙しくなるため、疲れてすぐに寝てしまう子もいます。 さらに、中学生は思春期の時期でもあり、学校での人間関係のトラブルが起きやすいです。 もし、お子さんが人間関係のトラブルに巻き込まれていたら、そのトラブルが気になって勉強どころではないかもしれません。 日頃からコミュニケーションを取り、子どもに変化があったときには相談に乗ってあげてください。
ゲームに夢中になってしまっている
今と昔で大きく違うのはこの点です。昔は友達と遊びに出かけるというように遊び相手がいないと成立しませんでしたが、今では家にいながらインターネットを使えば日本中・世界中の誰とでもオンラインで繋がることができてしまいます。さらには子どもたちもほとんど持っている「スマホ」でできてしまうのですから、これも勉強を後回しにしてしまう大きな要因といえます。
子どもが勉強しない原因が親にあるケース
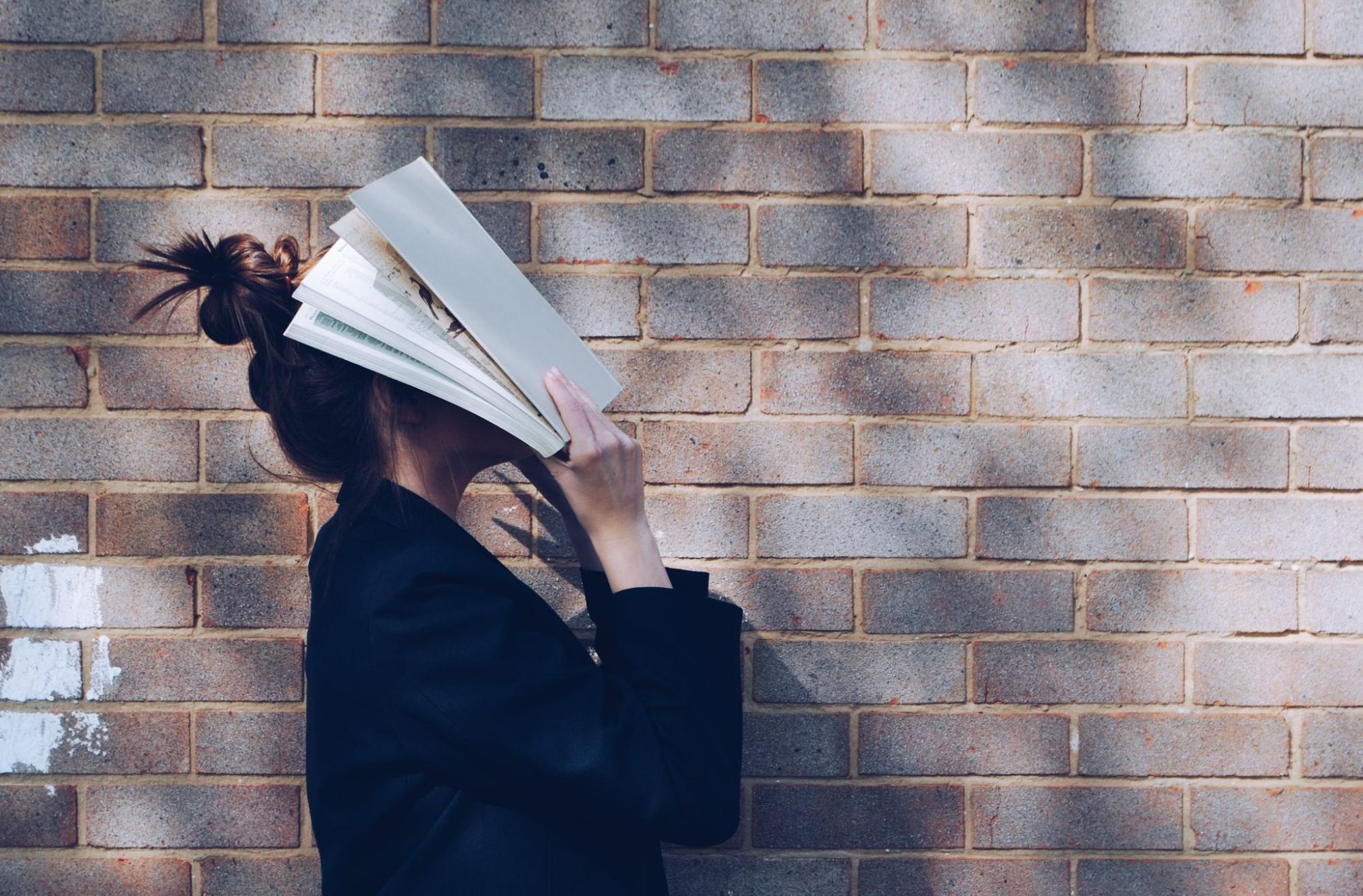 親が知らないうちに子どもの勉強意欲を損ねているケースがあります。 ここでは、子どもが勉強しない原因が親にある以下の3つのケースを紹介します。
親が知らないうちに子どもの勉強意欲を損ねているケースがあります。 ここでは、子どもが勉強しない原因が親にある以下の3つのケースを紹介します。
- 子どもが勉強しているときにくつろいでいる
- 子どもの自主性を損ねている
- 勉強してこなかったエピソードを話している
子どもとの接し方を振り返り、該当するものがあったら改善しましょう。
子どもが勉強しているときにくつろいでいる
子どもが一生懸命勉強しているそばで、テレビやスマホを見てくつろいでいないでしょうか。 子どもが勉強中に親が近くでくつろいでいると、気が散って勉強に集中できません。 また、子どもに「勉強しなさい」と言っているにもかかわらず、親がくつろいでいると説得力がなく、子どもも勉強する気がなくなります。 子どもが勉強しているときは、一緒に勉強したり、家事をしたりしましょう。
子どもの自主性を損ねている
子どもがやることに干渉しすぎると、子どもは自主性を損ねてやる気をなくしてしまいます。 過干渉の結果、子どもは何も考えずに勉強しているような状態になるため、自分で考える力が育ちません。 子どものやり方にある程度任せて、相談してきたらアドバイスするようにしてみてください。
勉強してこなかったエピソードを話している
親が「これまで勉強しなかった」エピソードを自慢げに話していると、子どもは勉強の必要性を感じなくなります。 「成績が悪くても問題ない」「下から数えたほうが早いくらい、成績が悪かった」などの勉強しなかったエピソードは、子どもに伝えないようにしましょう。 「勉強しなくても、将来困らない」と子どもが思って、勉強しなくなってしまうからです。 普段から勉強の意味や楽しさを伝えてあげることが大切なのです。
勉強に対してムキになりすぎている
これが一番大きな原因でしょう。保護者の方の焦りからとにかく「勉強をしなさい」という声掛けしかできていないケースは非常に多いです。人は指示をされただけでは動きません。 なぜそれをやる必要があるのか?それをやることで自分にどんなメリットがあるのかを伝えてあげる必要があります。実際にどのように声を掛けるべきなのかは後述します。
勉強しない子どもに親ができる対応方法
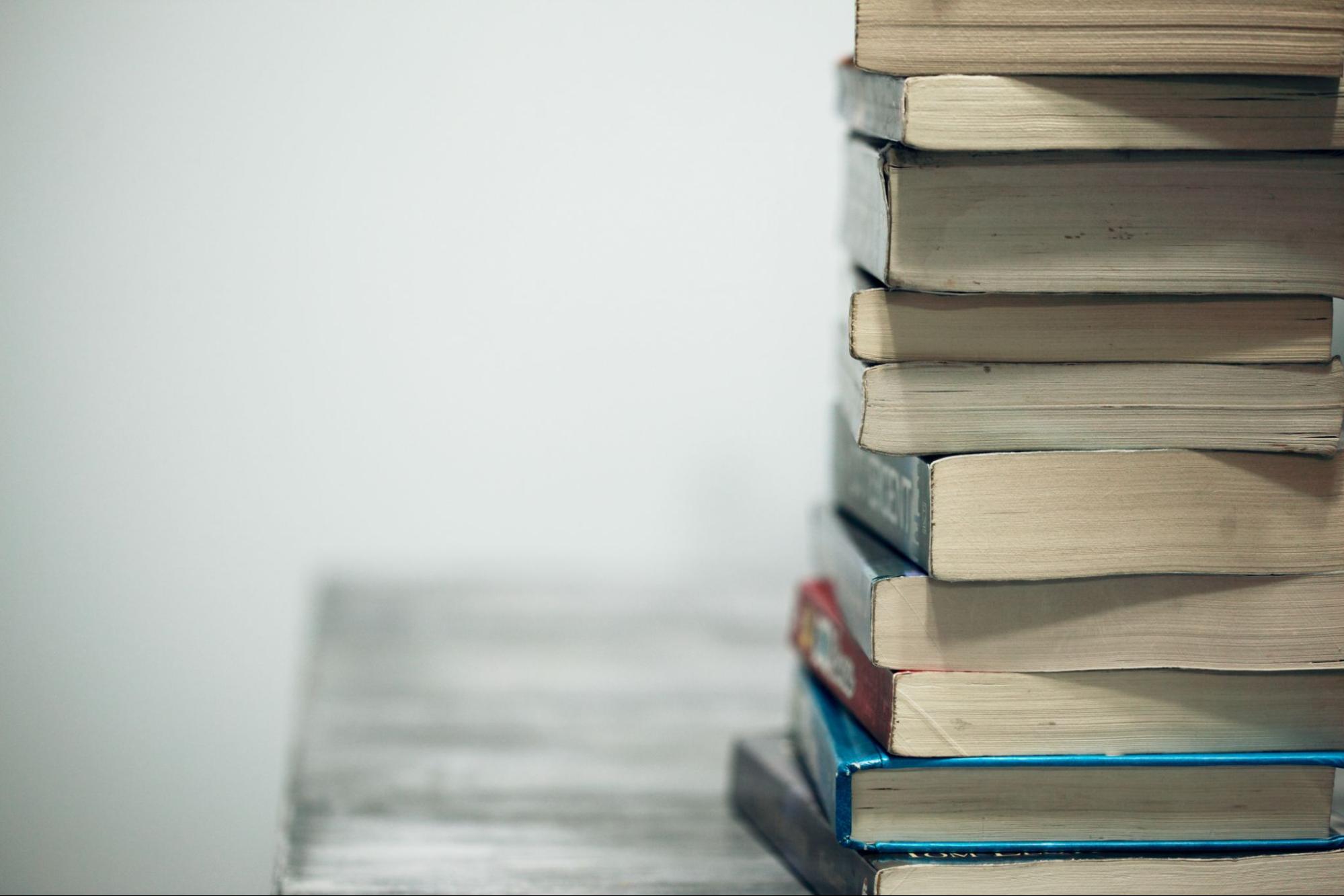 子どもが勉強しない場合、親にもできる対応方法があります。 以下のような対応をすれば、子どもは徐々に勉強するようになり、勉強する習慣を身につけることができます。
子どもが勉強しない場合、親にもできる対応方法があります。 以下のような対応をすれば、子どもは徐々に勉強するようになり、勉強する習慣を身につけることができます。
- 勉強する時間を子どもに決めてもらう
- 1日15分から勉強を始める
- 生活リズムを整える
- 学習環境を整える
- 勉強する理由・意味を一緒に考える
- 興味を持てる分野から勉強を始める
すべてを一気に実践するのではなく、できることから取り入れてみてください。
勉強する時間を子どもに決めてもらう
勉強する時間を子どもに決めてもらうことが、大切です。 子どもが自分で勉強する時間を決めると、自分との約束を守るために勉強します。 というのは、自分で決めた約束を破ることは気持ち悪い感覚だからです。 ここで注意したいのは、「親が勉強する時間を決めてはいけない」ことです。 なぜなら、親から強制された場合、子どもは反発してモチベーションが下がってしまうからです。 特に反抗期の子どもは、勉強しなくなるおそれがあります。 勉強する時間を子どもに決めてもらうと、子どもは「親から信頼されている」と実感でき、モチベーションが上がります。
1日15分から勉強を始める
長時間の勉強は苦痛で長続きしないため、まずは1日15分から勉強し始めることをオススメします。 「15分できたら終わり」というルールを決めて勉強すると、集中することができ、区切りのいいところまで勉強しようという気持ちになります。 このとき、15分で切り上げてもいいですが、続けて勉強したい場合は続けてください。 まず勉強する習慣を作ることが大切ですので、毎日続けることが大切ですよ。 「1日15分」という簡単な目標を設定して、子どもが毎日達成感を味わうことができれば、自信がつきます。
生活リズムを整える
日中集中して勉強できるように、子どもの生活リズムを整えてあげましょう。 具体的には、以下のようにすることがオススメです。
- 朝早く起きる手伝いをする
- 夜遅くまで起きないように一緒の時間に寝る
- 3食栄養のある食事を作る
親がリビングで楽しいテレビを夜遅くまで見ていると、子どもは気になって寝ることができません。 家族全員で部屋を暗くして、テレビを見ないようにすると効果的なのでオススメです。
学習環境を整える
子どもが勉強に集中できるように学習環境を整えることも、大切なことです。 そもそも子どもの学習スペースがない場合、机を購入したり整理整頓したりして、学習環境を整えましょう。 また、学習机の近くにテレビやゲームなどの誘惑物をなくすことによって、集中しやすい環境を作れます。 ぜひ学習環境を見直して、子どもが勉強しやすいようにしてあげてくださいね。
勉強する理由・意味を一緒に考える
勉強する意味がわからずモチベーションが下がっている場合、子どもと一緒に勉強する理由・意味を考えることをオススメします。 子どもと一緒に以下のようなことについて話し合うと、勉強をする理由・意味が明らかになるので、ぜひやってみてください。
- 将来の夢・目標
- 夢や目標を実現するために必要なこと
- 勉強が将来必要になる場面
勉強へのモチベーションを上げるためには、「将来、勉強がどこで必要になるか」を把握することが大切です。 親の経験を活かして、勉強の良さを伝えてみてください。 子どもが勉強する理由・意味を一緒に考えて、子どもの勉強意欲を高めましょう。
興味を持てる分野から勉強を始める
勉強への苦手意識が強い場合、まずは子どもが興味を持てる分野を探しましょう。 子どもが興味を持てる分野を見つけて、その分野から勉強を始めることをオススメします。 好きな分野から勉強を始めることで「わからないことを知る楽しさ」に気づくことができれば、勉強が楽しくなります。 まずは、子どもの好きな分野を把握することから始めてみてください。
学習を習慣づけるならオンライン家庭教師もオススメ
 子どもに学習を習慣づけてほしいなら、学習支援してくれるオンライン家庭教師もオススメです。 オンライン家庭教師とは、自宅でパソコンやタブレットを利用して受講できるサービスです。 自宅で子どもが授業を受けている姿を確認できるため、子どもが授業についていけているかを確認できます。 自分だけでは子どもの勉強に対応できないと感じている方は、オンライン家庭教師の利用を検討してみてください。
子どもに学習を習慣づけてほしいなら、学習支援してくれるオンライン家庭教師もオススメです。 オンライン家庭教師とは、自宅でパソコンやタブレットを利用して受講できるサービスです。 自宅で子どもが授業を受けている姿を確認できるため、子どもが授業についていけているかを確認できます。 自分だけでは子どもの勉強に対応できないと感じている方は、オンライン家庭教師の利用を検討してみてください。
勉強が楽しくなる「家庭教師ピース」
オンライン家庭教師の中でも、質の高い講師の授業によって成績が伸びる「家庭教師ピース」がオススメです! プロの家庭教師は勉強方法や自習のスケジュールを考えてくれるため、学習習慣を身につけやすいです。 また、子どもの学力に合わせてカリキュラムを作成できるため、「勉強への苦手意識がある」子も安心して利用できます。 さらに、オンライン家庭教師の料金体系はわかりにくい場合があるのですが、家庭教師ピースは授業料以外の金額は発生しません(入会金あり)! 「いくらお金がかかるか」心配している方もいるかと思いますが、信頼できる料金体系となっています。 勉強しない子どもへの対応に困っている方は、ぜひ1度家庭教師ピースの無料体験授業を受けてみてください! 無料体験授業のお申込み | オンライン家庭教師ピース
【体験談】勉強を教えるのではなく、勉強する「意味」を教える
ある塾長経験者の方のお話です。
*******
その当時、通っている生徒はほとんどが最初は「勉強嫌い」の子どもたちでした。私はそういった子どもたちには授業はしませんでした。なぜなら、授業をしても意味がないからです。勉強をする意味を見いだせていない子どもに授業をしてものれんに腕押しです。
そこで、私はいつも将来についての話をするようにしていました。現時点で自分が興味のあること(スポーツやゲームなどでも大丈夫です)を仕事としてやるにはどのような道を進む必要があるのか、大学は卒業する必要があるのか、高卒でも就職できるが難易度が高かったりお給料に違いがある、一体自分が1カ月生活するためにはどの程度のお金が必要なのか、将来に関するありとあらゆる情報をデータを示しながら話していきます。
最初は、大学に行くつもりがなかった子でしたが、話を続けているうちに、ある日塾に来て「おれ、大学目指すことにした!だから〇〇高校行く!」と言うようになりました。子どもたちに目標ができたのです。もちろん大学を目指すことが絶対に良いとは言いません。
しかし、大学に進むことで子どもたちが将来何かを目指したいと思った際に確実に人生の幅を広げてくれます。それを子どもたちに理解してもらった上で判断をしてもらう方が後に後悔に繋がりにくくなります。
*******
子どもたちにどうして勉強をするのか、その意味を考えさせることで目標ができることもあるようです。
まとめ
勉強しない子どもを放っておくと、自信をなくして、志望する高校・大学へ行けなくなるなどのリスクがあります。 さらに、勉強を強制されたり、勉強の仕方がわからなかったりすると、子どもは勉強へのモチベーションが下がります。 子どもが勉強するためには、一緒に勉強する理由・意味を考えたり、興味を持てる分野を見つけてあげることをオススメします。 親だけでは対応できないと困ったら、オンライン家庭教師の利用も検討してみてください。
















