LD(学習障害)の子どもの学習方法とは?
「何度教えても、どうしてこの部分だけが理解できないんだろう?」
「読み書きや計算が、どうしても苦手みたい…」
もし、お子さんの学習について、そうした疑問や不安を感じているなら、それはもしかするとLD(学習障害)という、生まれつきの特性が関係しているのかもしれません。
LDは、決して「怠けている」「やる気がない」ということではありません。お子さんが悪いわけでも、育て方が間違っていたわけでもありません。このブログでは、LDの特性を正しく理解し、お子さんに合った学習方法を見つけるためのヒントをご紹介します。
大切なのは、お子さんの「苦手」を責めるのではなく、お子さんの特性を理解し、「できること」を増やすための道筋を一緒に探していきましょう。
LD(学習障害)とは
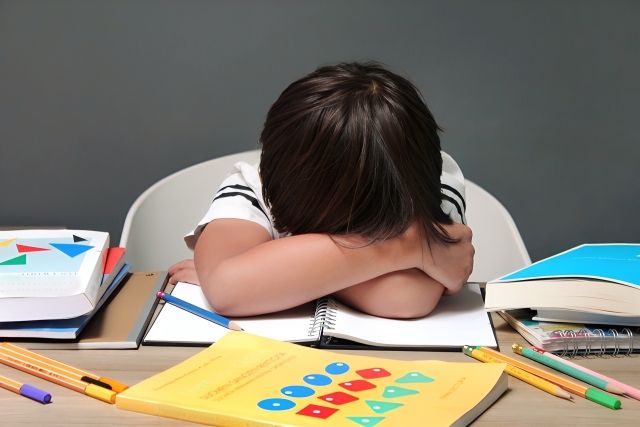
LD(学習障害)は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力を習得し、使用することに著しい困難がある状態を指します。
これは、生まれつきの脳の機能の偏りによるもので、「努力が足りない」「やる気がない」といった性格や育て方の問題ではありません。
LDの特性は、その表れ方が子どもによって大きく異なります。例えば、文章を読むことは苦手でも、話すことは得意だったり、計算はできても、文章問題になるとつまずいたりするなど、その困難は特定の学習能力に限られています。
この特性は、外から見えにくいため、周囲から「怠けている」「わがままだ」と誤解されてしまうことも少なくありません。しかし、LDは適切な支援と環境があれば、その困難を軽減し、学習能力を伸ばしていくことが十分に可能です。
LDの子どもの特徴は?

LDの子どもの特徴は、「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習能力の困難として現れます。これらの困難は、日々の生活の中での些細な行動から見えてくることがあります。
「読む」ことが苦手
ひらがな・カタカナの読み間違いが多い: 文字の形を正確に認識できなかったり、音と結びつけることが難しかったりします。例えば、「ぬ」と「め」、「さ」と「ち」などを混同することがあります。
文章をスムーズに読めない: 一文字ずつたどたどしく読んだり、同じ行を何度も読み返したりします。文章の内容を理解する前に、読むこと自体にエネルギーを使ってしまい、疲れやすい傾向があります。
音読を嫌がる: 読むことの困難さから、人前で音読することを極端に嫌がったり、緊張で声が出なくなったりすることがあります。
「書く」ことが苦手
- 鏡文字や左右反転の文字を書く
文字の方向を誤って認識し、「の」が反転したり、「く」が逆向きになったりすることがあります。
- 漢字を覚えるのが苦手
形が似た漢字を区別できなかったり、漢字の構成要素をバラバラに覚えてしまったりします。部首や画数を正確に認識できないケースも少なくありません。
- マス目からはみ出す
文字の大きさを揃えたり、マスの中に収めたりすることが難しく、文字がバラバラになってしまうことがあります。
「計算する」ことが苦手
- 数の概念が理解しにくい
「10個」や「5個」といった具体的なものの数え方はできても、抽象的な数の概念を理解することが難しい場合があります。
- 繰り上がり・繰り下がりの計算ができない
筆算のような、段階的な手順が必要な計算でつまずくことがあります。
- 文章問題が解けない
数字や計算式は理解できても、文章から必要な情報を読み取り、適切な計算方法を導き出すことが苦手です。
これらの特徴は、お子さんの「性格」や「やる気」の問題ではなく、脳の機能の特性によるものです。お子さんが「どうしてできないんだろう」と悩んでいる場合は、まずはお子さんの努力を認め、寄り添ってあげることが大切です。
LDはどのように診断される?
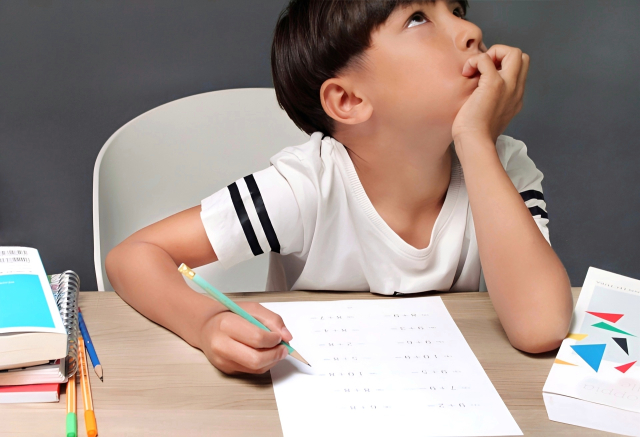
LDの診断は、日々の生活の中での気づきをもとに、専門家が行う総合的なアセスメントによってなされます。決して、単一のテストだけで判断されるわけではありません。
医療機関や教育相談機関への相談
まず、お子さんの学習上の困難について、小児科、児童精神科、神経内科などの専門の医療機関や、自治体の教育相談窓口に相談することから始まります。このとき、日頃のお子さんの様子(どのような時に困っているか、どんなミスが多いかなど)を具体的に伝えることが大切です。
知能検査
診断の第一歩として、知能検査が行われることが一般的です。これは、お子さんの全体的な知的発達の程度を把握するためです。LDの診断は、「知的発達に遅れがないにもかかわらず、特定の学習能力に困難がある」という前提で行われるため、この検査は非常に重要な意味を持ちます。
個別学力検査
読み書きや計算といった、特定の学習能力を詳しく調べるための個別学力検査が行われます。この検査によって、お子さんがどの分野でどの程度の困難を抱えているかが、客観的なデータとして示されます。
専門家による観察・面談
検査結果だけでなく、専門家によるお子さんとの面談や、学校での様子に関する情報収集も行われます。保護者や学校の先生からのヒアリングを通じて、お子さんの学習状況や日常生活での困難について、多角的に情報を集めます。
これらの結果を総合的に判断して、医師や専門家がLDであるかどうかを診断します。診断の目的は、「障害名をつける」ことではなく、お子さんの特性を正しく理解し、どのような支援が必要かを見つけることです。診断されたからといって悲観する必要はありません。むしろ、お子さんの困りごとの原因が明確になり、適切な支援への道が開ける第一歩となるのです。
LDのタイプ
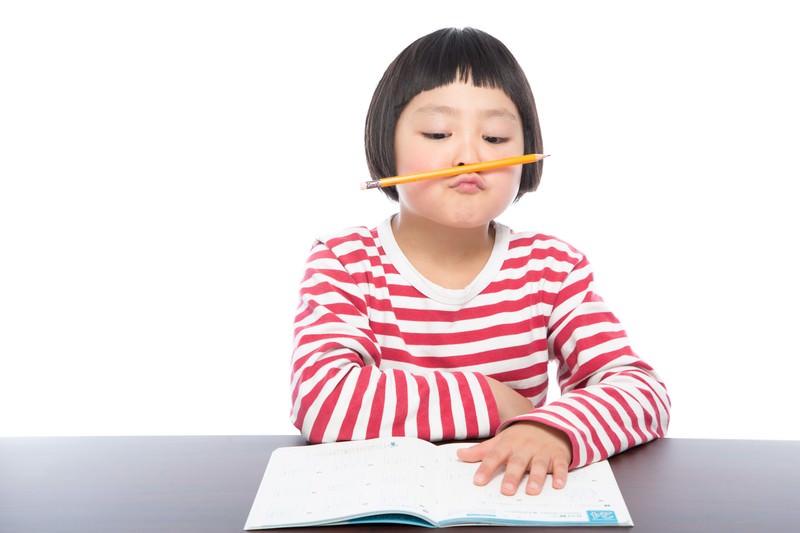
LDは、主に以下の3つのタイプに分類されます。1つのお子さんが複数のタイプの特徴を併せ持つこともあります。
これらのタイプを理解することで、お子さんの学習上の困難がどこにあるのかをより明確にすることができます。
読字障害(ディスレクシア)
読字障害(ディスレクシア)は、文字を文字を読んだり、言葉と文字を関連づけたりすることが困難なタイプです。音読がたどたどしかったり、文章を読むのに時間がかかったりします。
例えば、「ぬ」と「め」、「さ」と「ち」のように形が似ている文字を混同したり、文字の並びを認識するのが苦手な場合があります。知的な遅れはなく、読み以外の能力は平均以上であることも多いです。
書字表出障害(ディスグラフィア)
書字表出障害(ディスグラフィア)は、文字を書くことに困難を抱えるタイプです。文字の形を覚えることや、手を使って正確に文字を書くことが苦手です。
鏡文字を書いたり、マスからはみ出したり、漢字のへんとつくりがバラバラになってしまうことがあります。
口頭で説明することはできても、それを文字にすることが難しい場合も含まれます。
算数障害(ディスカリキュリア)
算数障害(ディスカリキュリア)は、計算や数の概念の理解に困難を抱えるタイプです。繰り上がり・繰り下がりの計算ができなかったり、数字の順序を間違えたりすることがあります。
また、文章問題から必要な情報を読み取り、計算式を立てることが苦手な場合も多いです。
LDの子どもが勉強をする時のコツ

LDのお子さんが学習でつまずくのは、「やり方」がその特性に合っていないからです。お子さんの特性を理解し、その困難を補うような学習方法を見つけることが、成功への第一歩となります。
「見る」「聞く」「触る」を組み合わせる
LDのお子さんは、特定の感覚から情報を得るのが苦手な場合があります。そこで、複数の感覚を同時に使うことで、脳が情報を処理しやすくなります。
- 五感で学ぶ
読み書きが苦手なら、ただ読むだけでなく、声に出して読み、指で文字をなぞるなど、複数の感覚を使いましょう。単語を覚えるときは、単語カードを見ながら、声に出して読み、手で書くといった方法が効果的です。
- マルチメディアの活用
映像や音声が豊富な学習アプリや動画教材を利用するのも良い方法です。目で見て、耳で聞いて、さらに自分で操作することで、理解が深まります。
学習を「見える化」して整理する
LDのお子さんは、情報やタスクを頭の中で整理することが苦手な場合があります。学習を「見える化」することで、混乱を防ぎ、スムーズに取り組めるようになります。
- 図やイラストで説明する
文章問題が苦手な場合、文章に出てくる状況や登場人物を簡単な図やイラストで描き起こすことで、問題の全体像を捉えやすくなります。
- チェックリストの活用
宿題や課題を始める前に、やるべきことを項目ごとに書き出し、一つずつ終わったらチェックマークをつけさせましょう。これにより、タスクの全体像を把握し、達成感も得られます。
困難を「補う」ツールを活用する
LDは、努力だけで克服できるものではありません。お子さんの困難を補うためのツールを積極的に活用しましょう。
- ICT機器の活用
スマートフォンの読み上げ機能や、音声入力機能を活用すれば、読み書きの負担を減らすことができます。特に読字障害のお子さんには、音声読み上げソフトが非常に有効です。
- 書字を助けるツール
文字を書くことに困難がある場合、鉛筆の持ち方を矯正するグリップや、行が斜めにならないように補助するシートなど、市販の学習支援ツールを試してみるのも良いでしょう。
得意を伸ばし、自信を育む
苦手なことにばかり焦点を当てるのではなく、お子さんの得意なことや興味があることを積極的に伸ばしてあげましょう。
- 好きな分野から学ぶ
例えば、歴史が好きなら、歴史マンガや歴史ドラマなど、お子さんが興味を持てる方法で学習を深めさせましょう。それが自信となり、苦手なことにも取り組む意欲につながります。
- 具体的な成功体験を積み重ねる
最初から難しい問題に取り組ませるのではなく、「今日はこの1問だけ解いてみよう」といったように、小さな目標を設定しましょう。目標をクリアするたびに、「できたね!すごいね!」と具体的に褒めてあげることで、自己肯定感を育むことができます。
これらのコツは、あくまで一般的なものであり、お子さんのタイプや個性によって効果は異なります。大切なのは、お子さんの学習に対する「困った」に寄り添い、「この子にはどんな方法が合うだろう?」と、一緒に試行錯誤していくことです。
LDの子どもをサポートする時の注意点

LDのお子さんをサポートする上で、最も大切なのは、お子さんの特性を深く理解し、その努力を認めることです。適切な声かけと心構えを持つことで、お子さんの学習意欲を損なうことなく、良い関係を築くことができます。
「やる気がない」と決めつけない
LDの特性を持つお子さんは、読み書きや計算がスムーズにできないために、学校の授業についていけず、学習への自信を失っていることが多いです。そのため、勉強を嫌がったり、取り組もうとしなかったりする姿を見て、「やる気がない」と誤解してしまうことがあります。
しかし、これはやる気の問題ではなく、困難を抱えているゆえの行動です。まずは「どうしてできないんだろう」と悩むお子さんの気持ちに寄り添い、「大丈夫、一緒に考えよう」と声をかけてあげましょう。お子さんの努力を認め、焦らず見守る姿勢が何よりも大切です。
「なぜできないの?」と問い詰めない
LDのお子さんは、特定の学習課題で繰り返し同じミスをすることがあります。その時、「どうしてこんな簡単なこともできないの?」と問い詰めることは絶対に避けましょう。このような言葉は、お子さんの自己肯定感を大きく傷つけてしまいます。
お子さんのミスを指摘するのではなく、「どうすればできるようになるかな?」と、解決策を一緒に探すスタンスをとりましょう。お子さん自身が、自分の学習方法や困難な点を客観的に見つめられるようになる手助けをしてあげてください。
他の子どもと比較しない
「お兄ちゃんはできたのに、どうしてあなたはできないの?」といった、他者との比較は、お子さんの心を深く傷つけます。LDの特性は一人ひとり異なるため、お子さん自身のペースで、昨日よりも今日、今日よりも明日、といった小さな成長を見つけて、具体的に褒めてあげることが重要です。
「昨日はここが難しかったけど、今日はここまでできたね!」
「この問題は大変だったけど、最後まで頑張ったね!」
といった、お子さんの努力の過程を認める言葉をかけるように心がけましょう。
これらの注意点を意識することで、お子さんとの間に信頼関係が生まれ、お子さんは安心して学習に取り組むことができるようになります。
LDの子どもへの支援方法
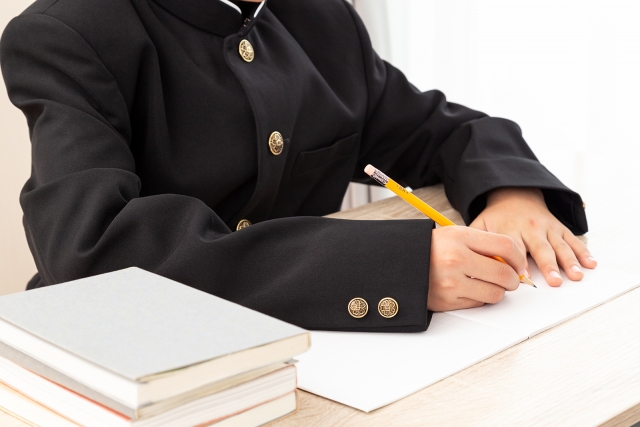
LDのお子さんへの支援は、お子さんの困っていることを軽減し、学習への意欲を維持することが大切です。学校と家庭が連携し、一貫したサポートをしていきましょう。
学校での支援
学校には、LDのお子さんが学びやすい環境を整えるための様々な支援策があります。
- 個別学習支援
多くの学校では、LDのお子さん向けに個別指導や少人数のグループ指導が提供されています。これにより、お子さんの学習ペースに合わせて、苦手な部分を集中的に学ぶことができます。
お子さんの特性に合わせて、学習上の困難を補うための配慮をしてもらえるよう相談しましょう。例えば、板書が苦手ならノートのコピーを渡してもらったり、読み書きが困難なら、テストで口頭での回答を許可してもらったりといった配慮です。
- ICT機器の活用
パソコンやタブレット、音声読み上げソフトなどのICT機器を授業で活用することも有効です。これにより、読み書きの負担を軽減し、お子さんが学習内容そのものに集中できるようになります。
- 特別支援教育コーディネーターとの連携
学校には、特別支援教育の専門家である「特別支援教育コーディネーター」がいます。この先生と密に連携し、お子さんの特性や家庭での様子を共有することで、より適切な支援を受けることができます。
家庭での支援
家庭でのサポートは、学校での学習を補完し、お子さんの自己肯定感を育む上で非常に大切です。
- 学習環境の整備
お子さんが集中しやすい環境を整えましょう。気が散るものを片付けたり、静かで落ち着いた場所を学習スペースにしたりといった工夫が有効です。
- 「できる」を増やす
苦手なことばかりに取り組ませるのではなく、お子さんが得意なことや好きなことを学習に取り入れましょう。例えば、歴史が好きなら歴史漫画やドキュメンタリーを観るなど、興味から学びを広げることが重要です。
- スモールステップでの学習
宿題や課題は、最初から全てを一度にやらせるのではなく、「まずこの3問だけやってみよう」といったように、細かく区切って進めるように促しましょう。小さな達成感を積み重ねることで、自信につながります。
- ポジティブな声かけ
失敗を責めるのではなく、お子さんの努力や成長を具体的に褒めるように心がけましょう。「頑張ったね」「最後までやり遂げたね」といった言葉が、お子さんの心を支えます。
LDのお子さんへの支援は、一人で抱え込まず、学校や専門機関と連携しながら進めていくことが大切です。お子さんの一番の理解者として、特性を尊重し、寄り添いながら、一緒に学習をしていきましょう。
まとめ
LD(学習障害)は、お子さんの「やる気がない」「努力が足りない」といったことではありません。それは、お子さんが生まれつき持っている個性であり、学習の過程で少しだけ特別なサポートが必要なだけなのです。
ご紹介したように、LDのお子さんの学習のつまずきは、適切な学習方法や環境を整えることで、大きく改善される可能性があります。大切なのは、お子さん自身が「どうしてできないんだろう」と悩んでいるその気持ちに寄り添い、お子さんが困っていることを一緒に解決していくことです。
そして、お子さんの「できないこと」を責めるのではなく、小さな「できた!」を見つけて、一緒に喜んであげてください。その積み重ねが、お子さんの自信となり、未来を切り開く大きな力になります。お子さんへの揺るぎない愛情と信頼こそが、最高のサポートです。
















