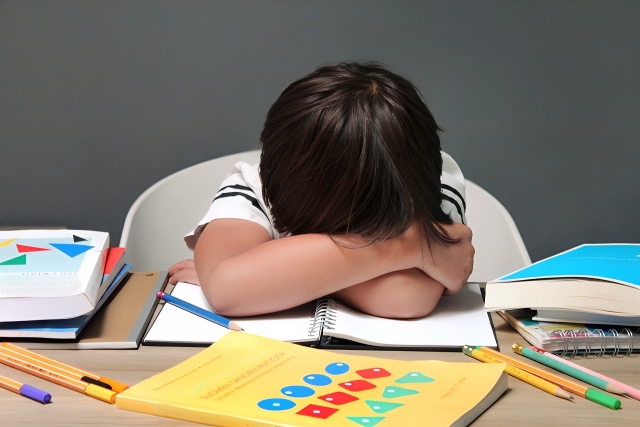ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの学習方法│受験はどうすればいい?
「うちの子、どうしてこんなに勉強が苦手なんだろう?」
お子さんの勉強について、そう感じたことはありませんか?何度教えても集中力が続かなかったり、特定の教科だけ極端に苦手だったり…。もしかしたら、それはお子さんの「ASD(自閉スペクトラム症)」という特性が関係しているのかもしれません。
このブログでは、ASDの特性を持つお子さんが、自分に合った学習方法を見つけ、自信を持って学ぶためのヒントをご紹介します。お子さんの「わからない」に寄り添い、一緒に「わかった!」という喜びを分かち合うための道しるべとして、ぜひお役立てください。
ASD(自閉スペクトラム症)とは
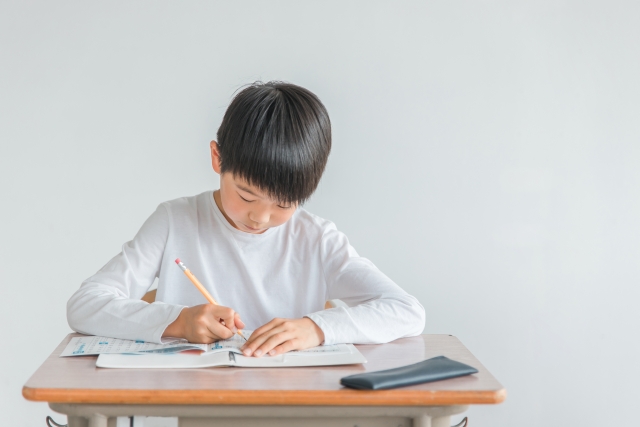
ASDの主な特性は、「対人関係やコミュニケーションでの困難」「特定の物事や活動への強いこだわり」「感覚の偏り」の3つに大きく分けられます。これらは、お子さんの学校生活や学習の様子にさまざまな形で現れます。
対人関係やコミュニケーションで困難を感じる
この特性は、授業中のグループワークや友達とのコミュニケーションに影響を及ぼすことがあります。
例えば、行間を読むことや、相手の気持ちを察することが苦手なため、先生の指示を文字通りに受け取ってしまったり、友達との会話で誤解が生じたりすることがあります。これが原因で、学校での人間関係にストレスを感じ、学習に集中できなくなるケースも少なくありません。
特定の物事や活動への強いこだわり
この特性は、お子さんの学習において、良くも悪くも影響します。
興味のある分野には驚くほどの集中力を発揮し、深く掘り下げていくことができます。
しかし、興味がないことには全く集中できないため、特定の教科の学習が進まないという課題に直面しやすくなります。「〇〇は好きだけど、△△は嫌い」という偏りがはっきりと現れることが多いのです。
感覚の偏り(過敏・鈍感)
音、光、匂い、肌触りなど、特定の感覚に過敏になったり、逆に鈍感になったりすることがあります。
例えば、教室のざわめきや蛍光灯の光が気になってしまい、授業に集中できない子がいます。これは本人の「やる気」の問題ではなく、感覚の特性によって学習環境にストレスを感じている状態です。
これらの特性を理解することで、お子さんの「どうしてこんなことを?」という行動の背景が見えてきます。そして、お子さんの特性に合わせた学習方法や環境を整えることが、学習意欲を高めることにつながります。
ASDの子どもは勉強が苦手なのか?
学習で困難を感じることも…
勉強が苦手」と一口に言っても、その理由はさまざまです。ASDのお子さんの場合、学習面での困難は、ASDの特性に起因していることがほとんどです。
たとえば、「対人関係やコミュニケーションで困難を感じる」という特性が、授業中のグループワークや発表を苦手と感じさせるかもしれません。
また、「特定の物事への強いこだわり」は、興味のある教科には驚くほどの集中力を発揮する一方で、興味のない教科には全く集中できないという「学習のムラ」を生み出します。
さらに、「感覚の偏り」があると、教室の音や光といった環境に気を取られ、授業内容に集中することが難しくなることもあります。
「苦手」を乗り越える可能性
ASDのお子さんは「勉強ができない」というわけではありません。ASDのお子さんは、物事を論理的に捉える力や、一度理解したことを正確に覚える力に優れている場合が多くあります。
また、強いこだわりは、好きなことや得意なことになると、驚くほどの集中力や知識の深さにつながります。
つまり、ASDのお子さんが学習でつまづくのは、「学び方や環境が、お子さんの特性に合っていないから」と考えられます。
大切なのは、「勉強が苦手」というレッテルを貼るのではなく、お子さんの特性を理解し、その特性に合わせた「学び方」や「学習環境」を整えてあげることです。
ASDの子どもが苦手が科目・得意な科目
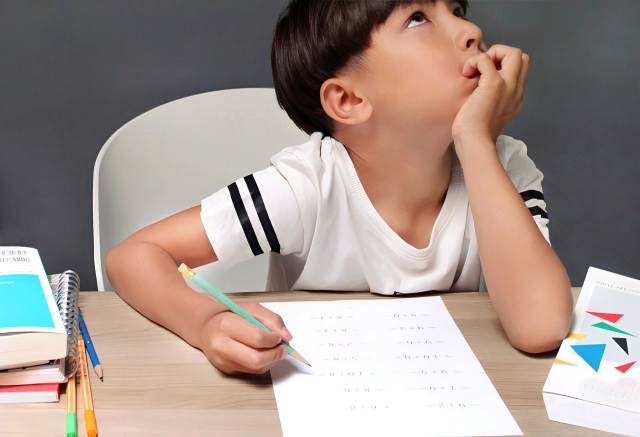
ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つお子さんの場合、「得意・不得意」がはっきりと分かれることが多く、その背景には、認知特性や感覚特性が深く関係しています。
ASDの子どもが得意になりやすい科目
ASDのお子さんが得意になりやすい科目は、論理的思考力やパターン認識能力を活かせる科目です。
-
- 算数・数学
多くのASDのお子さんは、物事を論理的に、そして体系的に考えることが得意です。そのため、算数や数学のように、明確なルールや公式に基づいて答えを導き出す科目は、その特性と非常に相性が良いと言えます。一度ルールを理解すれば、それを正確に適用することで、確実に正解にたどり着くことができるため、達成感も得やすいでしょう。
- 理科
理科の中でも、特に化学や物理のような分野は、法則や因果関係を追求するという点で、ASDのお子さんの興味を引きやすい傾向にあります。実験で起きる現象や、その背後にある科学的な原理を深く探求することに喜びを感じるお子さんも少なくありません。生物分野でも、特定の動植物の分類や生態に強い関心を示す場合があります。
- プログラミング・情報処理
コンピュータやプログラミングは、論理的な思考力がそのまま活かせる分野です。ASDのお子さんは、複雑なコードを正確に読み解き、手順通りにプログラムを組んでいく作業に、高い集中力を発揮することがあります。また、人間関係を介さずに、自分のペースで黙々と作業を進められる点も、この分野を好む理由の一つです。
ASDの子どもが苦手になりやすい科目
一方で、ASDのお子さんが苦手になりやすい科目は、抽象的な思考や、曖昧な表現の理解が必要とされる科目です。
- 国語(特に読解・作文)
国語の読解問題は、登場人物の「気持ち」や「心情」を読み取ることが求められます。しかし、ASDのお子さんは、人の感情や行間の意図を推し量ることが苦手な傾向にあります。また、作文では、自分の考えや気持ちを言葉で表現することに難しさを感じることがあります。
- 社会
歴史や地理といった社会科目は、暗記することが多く、必ずしも明確な因果関係だけで説明できない事柄も含まれます。特に、「なぜこのような出来事が起きたのか?」といった、人々の思惑や社会的な背景を理解することが求められる分野は、苦手意識を感じやすいかもしれません。
- 体育・音楽
体育や音楽は、身体の協調性や、他者との「非言語的なコミュニケーション」が求められる場面が多い科目です。集団行動や、周りの動きに合わせて動くことが苦手な場合、この科目でつまずくことがあります。また、特定の音や動きに感覚的な不快感を抱くお子さんもいます。
苦手科目を克服するためのヒント
苦手な科目を克服するためには、お子さんの特性に合わせた工夫が必要です。
- 具体的に説明する
国語や社会のような科目は、抽象的な概念を図やイラスト、年表などを使って視覚的に示しましょう。例えば、歴史上の出来事を「なぜ」と疑問に思ったら、その背景にある因果関係をフローチャートにして説明してあげるのも有効です。
- ルールを明確にする
体育や音楽など、集団行動が求められる科目の場合は、「どうすればいいか」を具体的に伝えてあげましょう。「みんなに合わせて」ではなく、「この合図で動いて」のように、明確なルールを示すことで、安心して取り組めるようになります。
大切なのは、「この科目が苦手」と決めつけるのではなく、「どうすれば、この子にとってわかりやすい学び方になるか」を一緒に考えていくことです。お子さんの得意な科目を伸ばしつつ、苦手な科目も少しずつ克服できるようにサポートしてあげましょう。
ASDの子どもが勉強をする時のコツ
視覚的に訴えかける
ASDのお子さんは、耳から入る情報よりも、目から入る情報を理解しやすい傾向があります。そのため、学習においては、視覚的なツールを積極的に活用することが非常に有効です。
- スケジュールを「見える化」する
その日にやるべきことや、学習の順番をイラストや写真付きのカード、ホワイトボードなどに書き出して提示しましょう。タスクが終わったら、自分でカードを裏返したり、チェックマークをつけたりすることで、達成感を得やすくなります。
- 教材の工夫
教科書やプリントの重要な部分に、色分けしたマーカーや付箋を使うなど、視覚的に整理された教材を用意してあげましょう。図やイラストを多用して、抽象的な概念を具体的に示すことも有効です。
環境を整える
学習に集中できない原因が、感覚の偏りにあることも少なくありません。お子さんが安心して学習に取り組めるよう、環境を整えてあげましょう。
- 気が散るものを排除する
机の上は、学習に必要なもの以外は置かないようにしましょう。窓の外の景色や、目に入ってくるものが気になる場合は、パーテーションや衝立を立てて、視界を遮る工夫も有効です。
- 感覚的な配慮
騒音が気になる場合は、イヤーマフやノイズキャンセリングヘッドホンを使ってみましょう。照明の光がまぶしい場合は、間接照明に切り替えたり、光の反射を抑えるような工夫をしてみてください。
成功体験を積み重ねる
ASDのお子さんは、完璧主義の傾向が強く、失敗を過度に恐れてしまうことがあります。小さな成功体験を積み重ねることで、「自分はできる」という自信を育んでいきましょう。
- スモールステップで進める
最初から難しい問題に取り組むのではなく、**「まずは1ページだけ」「今日はこの問題だけ」**というように、目標を細かく区切ってあげましょう。目標をクリアするたびに、「できたね!」と具体的に褒めてあげることが大切です。
- 得意なことから始める
お子さんが興味を持っていることや得意な教科から学習を始めることで、学習への抵抗感を減らすことができます。得意なことをさらに伸ばすことで、それが自信となり、苦手なことにも挑戦する意欲につながることがあります。
これらのコツは、あくまでも一般的なものであり、お子さんによって効果は異なります。大切なのは、お子さんの特性をよく観察し、「この子にはどんな方法が合うかな?」と、一緒に試行錯誤していくことです。
ASDの子どもが受験する学校の選び方

ASDのお子さんが受験する学校を選ぶ際には、学力だけでなく、その学校の環境や支援体制が、お子さんの特性に合っているかどうかを見極めることが非常に重要です。
学校の「支援体制」を重視する
- 特別支援教育コーディネーターの存在
多くの学校には、特別支援教育の推進役となる「特別支援教育コーディネーター」がいます。この先生に直接お会いして、お子さんの特性や配慮してほしい点を相談できるかを確認しましょう。
- 合理的配慮の有無
聴覚過敏なお子さんのためのイヤホン使用や、感覚過敏のための休憩場所の確保など、お子さんの特性に合わせた「合理的配慮」に対応してくれるか確認しましょう。
- 学校の「雰囲気」を見極める
オープンキャンパスや学校説明会への参加: 実際に学校を訪れ、校内の雰囲気や生徒の様子を肌で感じてみましょう。先生や在校生と話す機会があれば、お子さんとの相性を探る良い機会になります。在校生の多様性: 多様な個性を持った生徒が受け入れられているか、生徒たちが互いに尊重し合っているかどうかも重要な判断基準です。
- 「偏差値」だけにとらわれない
受験というと、つい偏差値に目が行きがちですが、ASDのお子さんの場合は、「居心地の良い環境」が何よりも重要です。多少学力が届かなくても、お子さんの特性を理解し、受け入れてくれる学校を選ぶことが、長期的な成長につながります。
ASDの子どもが受験をする時に気を付けたいこと

受験は、子どもたちにとって大きなプレッシャーのかかるイベントです。ASDのお子さんの場合、その特性ゆえに、定型発達のお子さんとは異なる注意点があります。
受験当日の「いつも通り」を大切に
ASDのお子さんは、急な変化や未知の状況に不安を感じやすい傾向があります。そのため、「いつも通り」を徹底することが、安心して受験に臨むための鍵となります。
- 入試会場の下見
事前に会場を下見し、「どんな場所に、どんな建物があるか」「試験会場はどんな雰囲気か」を一緒に確認しておきましょう。できれば、お子さんの写真や動画を撮って見せてあげることも有効です。視覚的に情報を整理することで、当日の不安を軽減できます。
- 慣れたものを身近に
普段から使っている鉛筆や消しゴム、腕時計、お守りなどを身につけさせてあげましょう。「いつもの自分」でいることで、緊張が和らぎ、本来の力を発揮しやすくなります。
- 独自の「ルーティン」を守る
ASDのお子さんは、決まった手順やルーティンに安心感を覚えます。お子さんの独自のルーティンがあれば、それは変えないようにしましょう。これは、受験本番でも大きな強みになります。
- 行動をパターン化する
試験当日の朝の行動(起きる時間、朝食、家を出る時間など)を、事前に決めておくことで、パニックを防ぐことができます。「朝起きたら、まず顔を洗って、それから朝ご飯を食べる」といったように、具体的なステップを親子で確認しておきましょう。
- 休憩時間の過ごし方を決めておく
休憩時間に何を食べるか、どう過ごすかを事前に決めておきましょう。好きな曲を聴いたり、お気に入りの本を読んだりする時間を設けることで、気分転換につながります。
- 質問する練習をする
試験中にわからないことがあった場合、質問ができるように練習しておくことも大切です。
「わからない時は、先生に聞いていいんだよ」と伝えておきましょう。「この問題、どういう意味ですか?」といった、具体的な質問の仕方を練習しておくことも有効です。
受験は、お子さんにとって大きな挑戦です。保護者の方は、お子さんの特性を理解し、「安心」と「自信」を与えてあげることが何よりも重要です。
ASDの子どもの保護者が勉強のサポートでできることとは
お子さんの日頃の様子を記録しておく
お子さんの行動や反応の背景には、必ず特性が隠されています。お子さんをよく観察し、「どんな時に集中できるか」「どんなことにこだわりがあるか」「どんな感覚に過敏か」といった情報を記録してみましょう。これは、お子さん自身の特性を理解するための大切な作業です。
「うちの子は、この方法で学ぶのが得意」「この環境だと落ち着く」といった、お子さんの様子を記録しておき、保護者だけでなく、学校の先生や塾の講師と共有することで、お子さんにとってより良い学習環境を整える手助けになります。
ポジティブな声かけを意識する
ASDのお子さんは、失敗を恐れる傾向が強いと述べましたが、これは自己肯定感が低くなりがちであることにもつながります。
日頃からお子さんが前向きな気持ちになれるよう、ポジティブな声掛けをするようにしましょう。
褒める時には「〇〇ができたね!」と、具体的に褒める
「ここが難しかったね。でも、この部分は頑張れたね」と、努力した過程を認めるようにしましょう。
「できないこと」に目を向けるのではなく、「できること」を見つけてあげることで、お子さんの自信を育むことができます。
専門機関や専門家と連携する
一人で抱え込まず、専門機関や専門家を頼ることも重要です。
スクールカウンセラーや教育相談窓口に相談してみる、専門の学習塾や療育施設を探してみるなど、専門家の意見を聞くことで、保護者の方自身の不安が和らぐだけでなく、お子さんの特性に合わせた、より専門的なサポートを受けることができます。
お子さんの学習をサポートすることは、簡単なことではありません。しかし、お子さんの「一番の理解者」として、特性を尊重し、寄り添っていくことが何よりも大切です。お子さんの成長を信じ、焦らず、一歩一歩進んでいきましょう。
まとめ
ASDのお子さんの学習をサポートすることは、ときに先の見えないトンネルを歩くように感じるかもしれません。どうすればいいのかわからず、一人で悩みを抱え込んでしまうこともあるでしょう。
しかし、お子さんの可能性は無限大です。ASDという特性は、個性であり、可能性でもあります。お子さんの特性を理解し、それに合った方法で学習を進めることで、きっと新しい「できた!」という喜びを見つけられるはずです。
何より、お子さんの「一番の理解者」として、寄り添ってあげてください。そして、焦らずお子さんのペースで、一歩ずつ進んでいきましょう。