起立性調節障害…学校・受験の両立はどうしたらいい?
「朝、どうしても起きられない…」
お子さんのそんな姿を見て、もしかして「怠けているのかな?」「やる気がないのかな?」と感じていませんか?
しかし、それはもしかすると、起立性調節障害(OD)という、自律神経の不調が原因かもしれません。ODは、決して「甘え」や「怠け」ではなく、脳や身体の働きに影響を及ぼす、れっきとした病気です。
この記事では、ODの症状に悩むお子さんが、学校や受験と上手に付き合い、自分のペースで学びを続けるためのヒントをご紹介します。ODを正しく理解し、お子さんが安心して学び続けられる環境を整えるために、ぜひお役立てください。
起立性調整障害とは?どんな症状がでる?
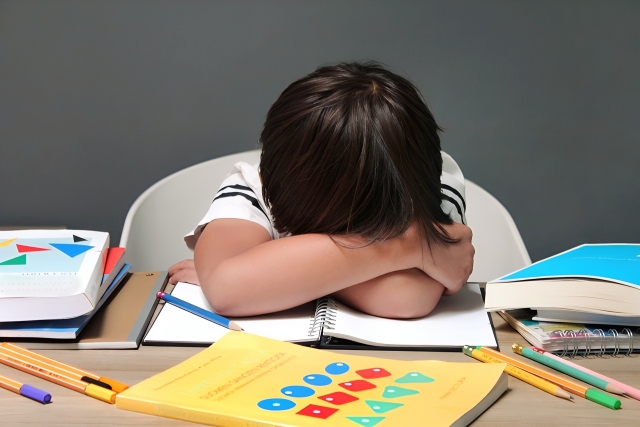
起立性調節障害(OD)は、自律神経(交感神経と副交感神経)の働きがアンバランスになることで、身体の様々な機能に不調が生じる病気です。思春期の子どもに多く見られ、「怠け」や「甘え」と誤解されやすいですが、決してそうではありません。
ODの症状は、自律神経の不調により、特に立ち上がるときや、朝の時間帯に強く現れるのが特徴です。
朝、起きられない
朝、ベッドからなかなか起き上がることができず、何度も「まだ眠い」と訴えます。
無理に起き上がらせようとすると、頭痛や吐き気を訴えたり、イライラしたりすることがあります。
立ちくらみ・めまい
立ち上がったときにクラっとしたり、目の前が真っ白になったりします。ひどい場合には、失神してしまうこともあります。
動悸・息切れ
少し歩いたり、階段を上ったりするだけで、心臓がドキドキしたり、息が切れたりします。これは、血圧が下がってしまうことによる、身体の代償反応です。
頭痛・腹痛
朝の登校前や、昼間に激しい頭痛や腹痛を訴えることがあります。特に、午前中に症状が強く出る傾向があります。
倦怠感・だるさ
身体が鉛のように重くだるく感じ、食欲不振や集中力の低下につながることがあります。学校に行く気力や、勉強する気力が湧かないのはこのためです。
顔色が悪い
血圧が低下し、脳や身体の血液循環が悪くなるため、顔色が青白くなることがあります。
これらの症状は、夕方や夜になると改善することが多いため、周囲からは「学校に行きたくないだけでは?」と誤解されてしまうことがあります。しかし、これらはお子さん自身の意志とは関係なく、身体的な不調によって引き起こされているのです。
起立性調整障害のお子さんの内申はどうなる?
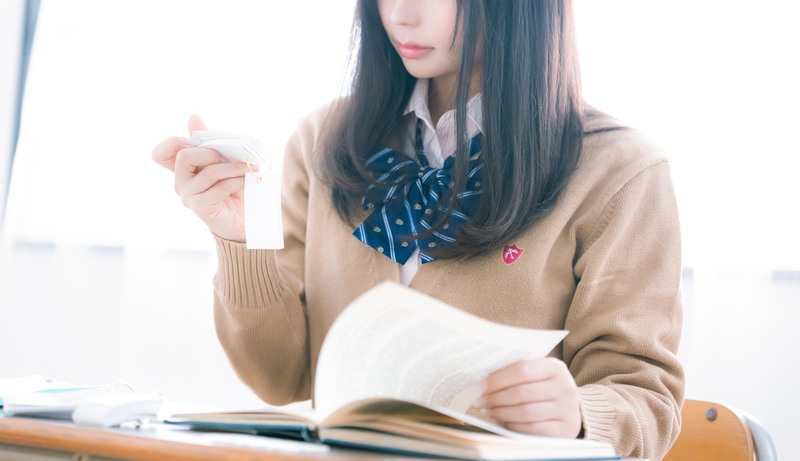
起立性調節障害(OD)のお子さんは、症状により学校を休みがちになるため、内申点への影響を心配される保護者の方は多いでしょう。しかし、適切な対応を取ることで、その影響を最小限に抑えることが可能です。
出席日数への配慮
内申点において、出席日数は重要な評価項目です。ODによる欠席は、学校に病気によるものであることを伝えることで、「やむを得ない欠席」として扱われ、内申に影響しないよう配慮してもらえる場合があります。
- 医師の診断書を提出する
ODと診断されたら、必ず医師に診断書を書いてもらい、学校に提出しましょう。
- 学校との密な連携
担任の先生や養護教諭、スクールカウンセラーと日頃からお子さんの体調について情報共有をすることが大切です。
学習評価への対策
ODの症状により、授業中の集中力が続かなかったり、テストが受けられなかったりすると内申に影響が出てしまいます。その場合でも、評価を挽回する手立てはあります。
- 別室受験や追試
体調が悪い場合でも、別室での定期テスト受験や追試を学校に相談しましょう。これにより、テストの点数で評価される機会を確保できます。
- 提出物や小テスト
授業中のパフォーマンスが難しくても、期限内の提出物や小テストを丁寧にこなすことで、評価を積み重ねることができます。
- 個別学習計画の相談
先生と相談し、お子さんの体調に合わせた無理のない範囲での学習計画を立ててもらいましょう。
総合的な評価へのアピール
内申点には、日々の授業態度だけでなく、意欲や努力も評価されます。ODの症状で学校での活動が制限されても、お子さんの頑張りを先生に伝えることで、評価に反映される可能性があります。
- 努力の過程を伝える
「朝、学校に来られた」「午後の授業に参加できた」といった、お子さんの小さな努力や成長を先生に具体的に伝えましょう。
- 無理のない範囲での活動参加
授業中の発表が難しければ、口頭ではなく、事前に作成したレポートを提出するなど、お子さんの体調に合わせた代替案を相談してみましょう。
内申点への影響は、学校や自治体によって対応が異なります。まずは、かかりつけ医と連携しながら、お子さんが無理なく学校生活を送れるよう、学校との対話を重ねることが何よりも重要です。
起立性調節障害のあるお子さんの勉強のコツ

起立性調節障害(OD)のお子さんは、症状により日中に学習に集中することが難しいため、定型発達のお子さんとは異なる工夫が必要です。お子さんの体調に寄り添いながら、無理のない範囲で学習を進めることが大切です。
勉強の「ゴールデンタイム」を見つける
ODのお子さんは、朝の体調が悪い一方で、午後から夕方にかけて体調が安定する傾向があります。この体調が比較的良い時間帯をゴールデンタイムと捉え、その時間帯に集中して学習に取り組みましょう。
無理に朝型にしようとせず、お子さんの体のリズムに合わせた学習計画を立てることが重要です。
「座ってする」にこだわらない
ODの症状の一つである立ちくらみや倦怠感により、長時間座って机に向かうことが困難な場合があります。
体調が悪いときは、無理に起き上がらせず、横になった状態で学習させましょう。単語を覚えたり、教科書を読んだりするだけでも、立派な勉強です。
リビングやベッドで: 勉強場所を机に限定せず、リビングのソファやベッドの上など、お子さんがリラックスして過ごせる場所で学習するのも良い方法です。
短時間・集中型の学習を取り入れる
ODのお子さんは、集中力が途切れやすい場合があります。長時間の学習はかえって負担になるため、短時間で集中して取り組むスタイルに切り替えましょう。
- ポモドーロ・テクニック
「25分集中、5分休憩」といったように、短い学習時間と休憩を繰り返す方法です。休憩中は、好きな音楽を聴いたり、ストレッチをしたりして、気分をリフレッシュさせましょう。
- 「5分でもいいからやってみる」
勉強へのハードルを下げることが大切です。「今日は教科書を5分だけ読もう」「問題集を1問だけ解いてみよう」といったように、小さな目標を設定することで、学習を始めるきっかけを作ってあげましょう。
ICTツールを積極的に活用する
学校に行けない日でも、ICTツールを活用することで、学習の遅れを最小限に抑えることができます。
オンライン授業や動画教材: 学校のオンライン授業を活用したり、塾が提供している動画教材などを利用したりすることで、自宅でも自分のペースで学習を進めることができます。
音声読み上げ機能: 教科書やプリントを読むのが辛いときは、スマートフォンの読み上げ機能を活用して、耳で情報を得るのも有効です。
これらのコツは、あくまで一般的なものであり、お子さんの症状や個性によって効果は異なります。大切なのは、お子さんの体調に寄り添い、無理のない範囲で、できることを見つけるというスタンスです。
起立性調節障害のあるお子さんがやってはいけないこと

起立性調節障害(OD)は、自律神経の不調からくる身体的な病気です。そのため、お子さんの症状を悪化させないためには、日常生活の中で特定の習慣を避けることが非常に重要です。
長時間のスマホやゲーム
夜遅くまでスマートフォンやゲームに夢中になることは、ODの症状を悪化させる最大の原因の一つです。
スマートフォンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、お子さんの睡眠リズムを乱してしまいます。また、ゲームに熱中することで自律神経のバランスがさらに崩れ、翌朝の体調不良につながります。
無理に朝早く起こすこと
「学校に行かせないと…」という気持ちから、お子さんを無理に朝早く起こそうとすることは逆効果です。
ODのお子さんは、朝の低血圧や脳血流の低下により、身体が覚醒しにくい状態にあります。無理に起こそうとすると、頭痛や吐き気、激しい倦怠感を引き起こし、お子さんにとって学校が「苦痛な場所」になってしまう可能性があります。
「怠け」や「甘え」だと責めること
ODの症状は、外見からは見えにくいため、周囲から「怠け」「甘え」と誤解されがちです。
しかし、これらの言葉は、お子さんの自己肯定感を大きく傷つけ、精神的なストレスを増大させます。ODは、お子さん自身の意志とは関係のない、身体的な病気であることを理解し、お子さんのつらい気持ちに寄り添ってあげることが何よりも大切です。
水分補給を怠ること
ODの症状は、脱水によって悪化することがあります。
起床時や日中、こまめに水分補給をしないと、血液量が減少し、さらに血圧が下がって立ちくらみなどの症状が強まります。特に、運動後や暑い日には、水分だけでなく塩分も補給することが重要です。
朝食を抜くこと
朝食は、身体を温め、自律神経を整える上で非常に重要な役割を果たします。
ODのお子さんは、朝食を抜くことで、低血糖になり、倦怠感や集中力低下の症状が悪化することがあります。食欲がない場合でも、スープやゼリー、ヨーグルトなど、無理のない範囲で口にできるものを少しでも摂取するようにしましょう。
これらの「やってはいけないこと」を避けることで、お子さんの症状を安定させ、学校や受験への負担を減らすことができます。
起立性調節障害のあるお子さんの受験で考慮すべきこと

起立性調節障害(OD)のお子さんにとって、受験は心身ともに大きな負担となります。体調の波に左右されずに本番で実力を発揮できるよう、事前の対策が非常に重要です。
受験校選びの際に「個別相談」を活用する
お子さんの特性を理解し、受け入れてくれる学校を選ぶことが何よりも大切です。受験校の個別相談会には積極的に参加し、ODの症状について正直に相談してみましょう。
学校の対応を確認する
学校に、別室受験や休憩時間の延長などの特別措置に対応してもらえるか、症状が悪化した場合の追試や個別対応について相談できるか、保健室など体調不良時に休める場所が確保されているかなどを相談してみましょう。
このような相談を通して、お子さんを理解し、サポートしてくれる学校かどうかを見極めることができます。
受験当日の「体調管理」を徹底する
受験当日は、緊張から症状が悪化することも考えられます。本番でパニックにならないよう、事前の準備が重要です。
事前に試験会場に足を運び、自宅から会場までの道のりや所要時間を確認しておきましょう。
受験当日に「初めての場所」で戸惑わないよう、建物の外観や最寄りのトイレの位置なども確認しておくと安心です。
当日朝は、無理にたくさん食べる必要はありませんが、スープやゼリーなど口にできるもので栄養を摂りましょう。
試験中は、こまめな水分・塩分補給を心がけましょう。塩分タブレットやスポーツドリンクも有効です。
また、体温調節がしやすいよう、脱ぎ着しやすい服装にしましょう。カーディガンや薄手のセーターなどがあると便利です。
「完璧」を目指さない
ODのお子さんにとって、受験勉強は体調と向き合いながら進める長期戦です。体調の良い日にまとめて勉強し、体調の悪い日は無理をしない、といった柔軟な学習計画を立てましょう。
- 優先順位をつける
すべての科目を満遍なくこなそうとせず、配点の高い科目や得意な科目に絞って対策を進めるのも一つの手です。苦手な分野は、基礎的な問題を確実に解けるようにするなど、目標を調整しましょう。
- 休む勇気を持つ
「勉強しなければ」というプレッシャーから、体調が悪くても無理をしてしまうことがありますが、これは症状を悪化させる原因になります。「今日は休む日」と割り切り、十分に睡眠をとったり、リラックスできる時間を作ったりすることが、結果的に受験を乗り切る力になります。
受験は、お子さんにとって大きな挑戦です。保護者の方は、お子さんの一番の理解者として、体調を尊重し、焦らず、寄り添ってあげることが何よりも重要です。
起立性調節障害のお子さんが目指しやすい学校とは

起立性調節障害(OD)のお子さんが安心して通える学校を選ぶには、偏差値だけでなく、お子さんの体調や特性を理解し、柔軟に対応してくれる学校をであるかを重視することが大切です。
登校時間やカリキュラムに柔軟性がある学校
ODのお子さんは、朝の体調不良で登校が難しいことが多いため、登校時間や授業開始時間に柔軟な対応をしてくれる学校が望ましいです。
- 「午後登校」や「登校時間遅延」を認めている学校
一部の私立学校や通信制高校には、午後の時間帯からの登校を認めているところがあります。こうした学校では、午前中の体調不良を考慮し、授業の遅れを補うためのサポート体制が整っていることが多いです。
- 単位制やフレックス制の学校
必須科目の単位を取得すれば卒業できる「単位制」の学校や、自分で時間割を組むことができる「フレックス制」の学校も、自分のペースで学習を進められるため、ODのお子さんに向いています。
きめ細かな支援体制がある学校
学校生活における精神的な負担を減らすためにも、生徒一人ひとりに目を配ってくれる、きめ細かな支援体制が整っている学校を選びましょう。
体調が悪くなったときに、安心して休める保健室や相談室などの場所があるか、そして、そこにいる先生がODについて理解があるかどうかが重要です。
学校見学の際には、保健室の雰囲気や、養護教諭の先生に直接話を聞いてみるのも良い方法です。
また、ODの特性を理解し、学校生活のサポートをしてくれる特別支援教育コーディネーターやスクールカウンセラーの先生がいるかどうかも重要なポイントです。
学校との連携窓口となってくれるため、保護者の方の不安も軽減されます。
お子さんが「行きたい」と思える学校
何よりも大切なのは、お子さん自身が「ここなら通えそう」「この学校に行きたい」と思えることです。お子さんが学校に対してポジティブなイメージを持てるかどうかが、ODの症状の安定にもつながります。
お子さんが興味のある部活動や、好きなことが見つかるような校風であるか、生徒が生き生きと過ごしている雰囲気があるかなど、お子さんと一緒に色々な学校を見てみましょう。
学校選びは、お子さんの将来を左右する大切な決断です。お子さんの体調を最優先に考え、その特性に合った環境を、焦らず、じっくりと探していきましょう。
起立性調整障害のお子さんの保護者がサポートできること

起立性調節障害(OD)のお子さんを持つ保護者の方は、お子さんの体調不良だけでなく、学校との関係や将来への不安など、多くの悩みを抱えていることでしょう。しかし、保護者の方のサポートが、お子さんの症状の改善や、心の安定に大きく影響します。
お子さんの「つらい」に共感する
最も大切なのは、お子さんの「つらさ」を心から理解し、共感してあげることです。ODの症状は外見から分かりにくいため、お子さん自身も「怠けている」「甘えている」と周囲から誤解されることに深く傷ついているかもしれません。
そんな時、家庭がお子さんにとって一番の「安心できる場所」であるようにしましょう。
「大丈夫、つらいよね」
「無理しなくていいよ」
といった言葉をかけ、お子さんの気持ちを否定せず、ありのまま受け入れてあげましょう。お子さんが安心して「つらい」と言える場所が、家庭であるようにすることが何よりも重要です。
生活リズムを整えるサポートをする
ODの症状を安定させるためには、自律神経を整えることが重要です。そのため、規則正しい生活リズムを確立できるように、保護者の方がサポートしてあげましょう。
- 朝は無理に起こさない
ODのお子さんは、朝の低血圧や倦怠感で起き上がることが困難です。無理に起こそうとせず、お子さんが自然に起きられる時間を大切にしましょう。これは「怠けさせる」のではなく、「体が目覚めるのを待つ」という大切なサポートです。
- 夜の過ごし方を見直す
スマホやゲームを夜遅くまで続けないよう、お子さんと一緒にルールを決めましょう。寝る1時間前には、スマホやタブレットから離れ、リラックスできる時間を作るよう促しましょう。夜の過ごし方が、翌朝の体調を左右すると覚えておきましょう。
学校や専門機関と連携する
一人で抱え込まず、学校や専門機関と連携しながら、お子さんに合ったサポート体制を築きましょう。
担任の先生や養護教諭、スクールカウンセラーとは、お子さんの症状や体調についてこまめに連絡をとり、情報共有をしましょう。
また、医師の診断書を学校に提出し、「別室受験」や「課題の提出期限延長」などの合理的配慮について相談しましょう。これにより、お子さんが無理なく学校生活を送れる道が開けます。
ODの専門医やカウンセラー、小児科医とも連携し、適切な治療やアドバイスを受けましょう。
お子さんの「良い部分」を見つける
ODの症状により、お子さん自身が「自分はダメだ」と自信を失っていることがあります。そんな時、保護者の方が、お子さんの「良い部分」を見つけて、具体的に褒めてあげることが、自己肯定感を育む上で非常に大切です。
「朝は起きられなかったけど、午後は頑張って勉強したね」「今日は体調が悪かったけど、休むという決断ができたのはすごいことだよ」といった、お子さんの努力や成長の過程を認める言葉をかけるように心がけましょう。
「結果」よりも「過程」に目を向けてあげることが、お子さんの心を支える大きな力になります。
まとめ
起立性調節障害(OD)と診断されたとき、保護者の方は様々なことで不安になるかもしれません。
できないことに焦りを感じるかもしれませんが、どうかお子さんの今を見てあげてください。
朝は起きられなくても、午後からなら動けるかもしれません。学校に行けなくても、家でできる勉強があるかもしれません。お子さんの症状に合わせた、無理なく今できることを一緒に探していきましょう。
















