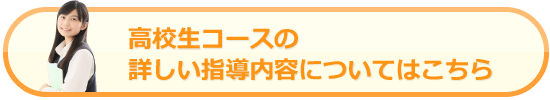高校を留年する人の特徴とは?留年の基準や回避する方法について
「高校を留年する人にはどんな特徴があるの?」
「高校留年にならないためにはどうしたらいい?」
このような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
この記事では、高校を留年する人の特徴について徹底解説。高校留年の基準や留年を回避する方法についてもくわしく説明します。高校を留年する人の特徴について気になる人はぜひ最後までご覧ください。
高校留年する人はどのくらいいる?
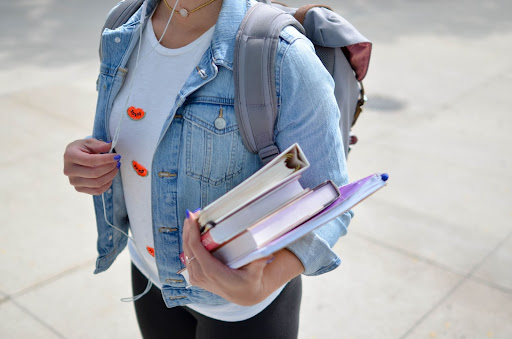
高校を留年する人の割合は、全体の0.3%です。文部科学省の調査によると、2021年度に国公立や私立の高校を留年した人数は8,268人でした。全体から見ると少ないですが、せっかく入った高校を留年してしまう生徒がいるとわかります。
2019年の同じ調査では10,719人、2020年では9,336人なので、留年する生徒は減少傾向であるといえます。
また、不登校からの欠席が高校留年の背景にあることも見逃せません。同じ調査で、不登校から高校を留年する生徒の数は3,006人でした。
参照:文部科学省「令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
高校留年の基準

高校留年になる基準は学校ごとに決められています。ここでは、高校留年の基準についてくわしく解説します。
高校の進級には単位が必要
高校の進級には決められた単位の取得が必要です。単位とは、科目ごとに決められた学習量を示す基準です。全日制高校では決められた単位数を取らないと進級や卒業ができない仕組みになっています。
単位は、50分授業を1単位時間とし、35単位時間受けたら1単位と数えられます。例えば、同じ科目を週1回ずつ受けたら年間35回分となり1単位を取得できる計算です。学習指導要領では科目ごとの標準単位数が決まっています。例えば「現代の国語」の標準単位数は2単位なので、週2回授業を受けると1年で取得可能です。
高校卒業までに必要な単位数は、学習指導要領で74単位と定められており、基準を満たすようカリキュラムを組んでいます。全日制高校の約7割が1週間の授業実数を30~32単位時間取っており、卒業までに85~94単位取れるよう時間割を組む高校が半数以上です。
全日制高校では、カリキュラムの関係上、その学年のうちに単位を取っていないと留年となります。卒業までに単位が取れるよう時間割を組むので、1年間で決められた単位をとれないと留年となってしまうのです。
単位取得に必要なもの①成績
単位取得には成績も重要な要素です。成績は学校の基準により、課題提出や定期テストの点数などでつけられます。
成績の目安としてわかりやすいのが定期テストの点数です。基準に満たない点数である「赤点」を取ると、留年につながる場合も。赤点は学校や教科によって基準があり、40点未満や平均点の半分以下などと決められています。
赤点を取った場合でも、すぐ留年になるわけではありません。追試や補習が行われるので、学習し直して基準点を取れれば留年を回避可能です。
単位取得に必要なもの②出席日数
単位取得には決められた日数を出席するのも必要です。単位を満たすための出席日数は学校により違いますが、年間出席日数の3分の1程度休むと留年になる可能性が高まります。だいたい60日程度の欠席が留年のボーダーラインです。
また、出席日数だけではなく、科目ごとの授業にどれだけ参加していたかも重要です。出席日数は足りていても、3分の1以上授業を受けていない科目があれば留年の対象に。出席日数と科目ごとの出席数が満たないと単位が取れず、留年してしまうのです。
単位取得には成績も出席日数も必要
単位を取るには成績と出席日数どちらの条件も満たさなければなりません。たとえ成績が良くても欠席が60日を超えていれば留年と判断される可能性もあります。逆に毎日出席していても、学力が伴わずテストの点数が悪ければ留年の可能性もあります。
高校を留年する人の特徴とは

高校を留年する人には、共通した特徴が見られます。ここでは、高校を留年する人の特徴について具体的に紹介します。
部活は高校生活の楽しみでもあります。部活の強さで高校を選んだ人もいるでしょう。ただし、高校生活は勉強面も頑張らなければなりません。部活の成績だけ良くても高校卒業できなければ意味がないのです。過度な部活のやりすぎで、留年しないよう気をつけましょう。
趣味の活動に没頭している人
高校を留年する人の特徴として、趣味の活動に没頭している人も挙げられます。学校よりも趣味の方が楽しく、成績を落としてしまう可能性があるためです。
高校生になると行動範囲も広がり、ゲームやオタ活、音楽活動などに没頭する人もいるでしょう。趣味の分野で活躍するのも楽しいものです。しかし、高校の単位を落とすような趣味への没頭は危険です。
趣味を続けるのはお金がかかります。高校を留年し中退したら、学歴は中卒となり給料が低くなってしまいます。長く趣味を続けるなら、しっかり高校に通い単位を落とさず卒業した方がいいのです。
素行が悪い人
素行が悪い生徒も、留年する人の特徴です。出席日数や成績が基準に満たないため、留年になる可能性があります。
素行の悪いと聞くと、夜遊びや警察沙汰などの非行行為を思い浮かべる人が多いでしょう。授業中の態度が悪かったり、特定の授業を欠席したりするのも素行が悪いといえます。素行不良の内容は違っても、単位取得に影響が出るのは同じです。
素行が悪い生徒は、遅刻したり、投稿しない日もあるでしょう。学校の規則に反するような行動は、停学処分などになる場合もあります。指導や処分を受けると、学校の居心地が悪くなり周りから浮いてしまう可能性も。
素行の悪さから留年になった場合は、そのまま中退する可能性もあります。将来後悔しないよう、行動を改めることを強くおすすめします。
体調が悪い人
高校を留年する特徴として、体調が悪く休みがちなケースです。欠席が多く、単位に必要な出席日数に満たないためです。
義務教育までは、病気による欠席でも進級や卒業はできました。しかし、全日制高校は単位制のため、休みが長引き授業を受けられない日が続くと留年になってしまう恐れが。登校したい気持ちはあっても、体調不良で学校に行けない場合でも、留年の可能性があるのです。
病気が治ってから復学する方法もありますが、同じ学校で後輩達と一緒に学ぶのは抵抗がある人もいるでしょう。体調と相談しながら単位取得を目指すか、単位制高校に転校するなどの方法がおすすめです。
高校留年はいきなり決まるのではない

高校留年はいきなり決まるのではなく、前もって学校から予告される場合がほとんどです。ここでは、高校留年の決定時期などについて、くわしく解説します。
学校の規定により時期は異なる
高校留年するかどうかは、学校の規定により時期が異なります。学校が決めた成績や出席日数などを満たしていないとき、早めに留年が決まる場合もあるためです。
早い時期に留年が決まるのは、出席日数が足りない場合です。出席日数の3分の1程度の欠席で留年になる可能性が。例えば、4月から6月まで欠席すると2か月休んだことになるため、夏休み前に留年の可能性を伝えられる場合もあるのです。
担任などから予告がある
留年しそうな場合は、担任などから予告されます。学校への呼び出しや面談などで説明されるケースがほとんどです。
出席日数や成績により単位が取れないと考えられる場合、留年の可能性があると伝えられます。登校日数や成績などの原因も伝えられるので、この時点で努力すれば進級できる可能性が高いといえます。
留年の予告は、これから頑張って進級を目指してほしいという学校や先生の気持ちも含まれています。留年の警告を受けたら、指示に従い単位取得を目指しましょう。
高校留年を回避する方法

高校留年になりそうな状態でも、その後の行動によっては進級できる可能性があります。ここでは、高校留年を回避する方法について、くわしく解説します。
追試を受ける
留年を回避する手段として、追試を受ける方法もあります。理解できなかった部分を学び直し、基準点を取れれば単位が取れます。
追試を受けるのは、赤点を取った生徒や長期間学校を休んでいてテストを受けていない生徒などです。基準の点数を取る必要があるので、前のテストで解けなかった問題を復習するなど自主学習が必須です。
追試は合格するまで何度も受けられる場合もありますし、回数が決まっている場合も。先生や学校の考え方によって違うので、1回で合格できるよう復習が大切です。
課題を提出する
課題を提出し内容が認められると、留年を回避できる場合があります。成績や授業態度として評価に加算され、単位の条件を満たすためです。
課題提出はテストと違い、自分でじっくり調べて問題に取り組めるのがメリットです。留年回避のため課題提出と言われたら、学習内容を復習し高得点を狙いましょう。自分で勉強するのが難しい場合は、塾や家庭教師などプロに頼むと心強いです。
今は自宅で学べるオンライン家庭教師も増えています。留年の不安があるお子さんの学習なら、オンライン家庭教師ならピースがおすすめです。オンライン家庭教師専業で10年以上の実績を持ち、学力に不安のある不登校や発達障害の指導に長けた講師が多数在籍。学力に不安のあるお子さんに寄り添い、理解するまで丁寧に復習します。
オンライン指導なので、他人の目を気にせず学べるのもメリットです。ピースで確かな学力を身につけ、進級や卒業を目指しませんか?無料体験授業を受け付けておりますので、興味のある方はぜひお申込みください。
補習を受ける
留年の救済措置として、補習を受ける方法があります。補習で理解できたか確かめるため、最後に追試を行い成績をチェックする場合も。足りない分の出席日数を補えるので、留年を回避するためぜひ参加しましょう。
高校の勉強についていけない…

高校を留年する人の中には、そもそも学校の勉強についていけない人もいます。
留年を回避するためにも、高校の勉強についていくには、そもそものついていけなくなった原因を知ることが大切です。
ついていけなくなる原因の代表的なものは以下のとおりです。
- 授業内容が難しい
- 授業ペースが速い
- 勉強方法が非効率である
- 部活が忙しくて疲れている
- 授業自体がつまらない
高校の授業内容やスピードだけでなく、勉強法や部活なども勉強についていけなくなる原因です。
それぞれについてより詳しく解説していきます。
授業内容が難しい
高校の授業は中学に比べて、難易度がかなり高くなります。
特に、英語と数学に関しては難しくなるため、高校でついていけなくなる生徒がいます。
英語は扱う語彙が増えるだけでなく、文法も複雑になるため難しいです。
また、扱う文章の内容は、社会科学や時事問題などになり、教養がないと読み解けなくなります。
数学は三角関数や微分・積分など抽象的な内容が増え、苦手になる生徒も多いです。
中学の段階でつまずいてしまって苦手意識をもっている方は、その後の高校でついていけなくなります。
授業ペースが速い
高校で扱う学習範囲は広いため、授業ペースが中学に比べると速いです。
進学校の場合、高校1~2年生で高校3年間分の学習内容をすべて済ませて、3年生の1年間は大学受験の対策をするケースもあります。
中学校では生徒の理解度に合わせて授業スピードを遅くしてくれることもありますが、高校ではそうではない学校も多いでしょう。
そのため、中学の感覚で高校の授業を受けると、ペースの違いによって勉強についていけなくなってしまいます。
勉強方法が非効率である
勉強方法が非効率であると、高校の勉強についていけなくなってしまいます。
やみくもに練習問題を解き続けるような単純作業では、効率が悪く成績が伸びにくいです。
また、教科書のすべての範囲を理解して覚えようとして、結果あまり覚えられていないこともあります。
勉強に時間を割いているにもかかわらず成績が伸びないと、勉強へのモチベーションが下がってしまいます。
部活が忙しくて疲れている
高校の部活は終了時間が8時くらいの学校が多く、帰宅したときには疲れていて、勉強に集中できない生徒も多いでしょう。
頻繁に練習試合で遠征が入っている場合、土日も1日中外にいることになるので、あまり勉強時間を確保できないこともあります。
勉強時間を確保できず、授業の予習復習に時間を割けないことによって、勉強についていけなくなってしまいます。
授業自体がつまらない
高校の授業自体が面白くなく、関心を持てず、授業内容が入ってこないこともあります。
先生によっては話が入ってこず、眠くなってしまうこともありますよね。
授業がわかりにくく、勉強へのモチベーションが下がり、結果として勉強についていけなくなってしまうケースが存在します。
高校の勉強についていけないときの解決策

高校の授業スピードや難易度を踏まえて、以下のような対策をすると高校の勉強についていけるようになります。
- 予習復習を行う
- 小テストで良い点数を取れるように準備する
- 簡単な問題集を解き進める
学校の授業についていくことが大切であり、そのためには上記のような「予習復習」や「問題集の活用」が必要です。
予習復習を行う
まず大切なことが、授業の予習復習を丁寧に行うことです。
予習復習は教科書の内容を中心に行い、わからないポイントは印をつけておき、あとで確認できるようにしておきましょう。
体験談 | 授業で聞くべきポイントを明確にしておく
私の場合、平日は遅くまで部活、土日は遠征であり、あまり勉強の時間が取れなかったため、効率性を意識していました。
英語と数学はついていけなくなると取り戻すのが大変なため、これら2教科に絞って予習復習をしていました。
特に予習のときには、まず重要なポイントに一通りざっと目を通します。
次に、理解するためにゆっくり時間をかけて教科書を読み、重要なポイントを見ていきます。
最後に例題を解説を読みながら解き、分からなかったポイントに印をつけていました。
「印をつけた内容を理解すること」を意識して、高校の授業を受けるようにしていました。
こうすることによって、長い授業の中で集中するべきポイントとそうでない所のメリハリがついて、学習効率が上がりますよ。
授業の予習をするときの参考にしてみてくださいね。
小テストで良い点数を取れるように準備する
高校の小テストで毎回良い点を取れるように、勉強することも大切です。
小テストは授業内容の中で重要なポイントを踏まえて作成されているため、高い点数を取っていくと成績が伸びていきます。
また、定期テスト前に小テストを復習することによって、効率よく学習できます。
体験談 | 英単語の小テストで満点を狙う
私が高校生のときは、毎週英語の授業の最初に英単語の小テストがありました。
英語の長文読解力を上げるためには語彙力がある程度必要と先生から言われていたので、小テストで満点を取れるように対策していました。
小テストで満点をとれるほど暗記すると、小テスト後から時間がたったときに再度暗記しようとしたときに、暗記しやすくなります。
学校で英単語や漢字の小テストがある場合、有効的に活用してみてください。
簡単な問題集を解き進める
高校の勉強内容の基礎を固めるためには、簡単な問題集を活用することもおすすめです。
問題集を解く中で、間違えた問題は理解度が浅いため、重点的に学習すると成績が上がっていきます。
インプットだけでなく、アウトプットを行うことによって、効率的に学習できます。
授業スピードが速くてついていけない場合や、授業がつまらなくて先生の話が入ってこない場合は簡単なレベルの問題集を活用してみてください。
【科目別】勉強についていけないときの勉強方法

ここからが科目別に、ついていけなくなったときの勉強法を紹介していきます。
英語
高校英語でついていけなくなったときは、以下のような勉強法がおすすめです。
- 英単語を覚える
- 英文法を覚える
- 授業の予習で、長文の文法構造を丁寧に分析する
重要な英単語・文法を暗記してないと、わからない単語・文法が出るたびに文章を読むスピードが落ちてしまい、内容がわからなくなります。
そのため、英単語や文法は優先的に暗記するようにしましょう。
授業の予習をするときは、長文の文法構造を丁寧に分析することで、文法への理解が深まります。
数学
数学は積み上げ型の科目であるため、ついていけなくなったときは早めに対策したほうがよいです。
以下のような勉強法を実践すると、効果的です。
- 教科書の例題を理解する(予習・復習)
- 新しい公式を理解する(予習)
- 問題を解くときすぐに答えを見ない
教科書の内容を中心に勉強を進めていき、例題が簡単に解けるまで何度も演習を繰り返しましょう。
国語
国語は現代文・古文・漢文によって勉強法が異なります。
現代文は問題演習を何度も行い、読解力を高めることがおすすめです。
問題の中で出てきた漢字や授業で扱った漢字はその場で暗記してしまいましょう。
古文・漢文は、単語や文法、句法を早めに暗記して、読解力を高めるとよいです。
理科
理科を学習するときは、重要語句や公式を効率よく暗記しましょう。
暗記するときは見るだけでなく、口に出したり、紙に書きだしたりするとよいです。
また、簡単な問題集を使って、計算問題の演習をすると学習効率が高まります。
社会
社会は理科と同様に、重要語句を暗記することが大切です。
一問一答のようなコンパクトな参考書を移動中や休憩中に見て、暗記していくとよいです。
また、歴史の流れを把握してから暗記すると、効率がさらに高まります。
高校留年が決まったあとはどうする?

高校留年が決まった場合、次に取る方法がいくつかあります。ここでは、高校留年が決まったあとの選択肢として4つ紹介します。
現在の高校で留年する
現在の高校で留年し、落とした単位を取りなおす方法があります。同じ学校でもう1年学び、進級を目指します。
デメリットは、1年下の後輩と一緒に過ごすことです。部活で後輩だった生徒と一緒のクラスになる可能性もあるでしょう。同級生が先輩となるので、関係性が微妙に感じる場合も。同じ高校では留年してまで通いたくない人もいるでしょう。
他の高校に転校する
高校留年が決まったら、他の高校に転校するのもひとつの方法です。一番いいのは通信制高校への転校です。通信制高校は、単位制を取っているので取れる単位に学年ごとの区切りはありません。前の学校で取った単位を引き継げる場合もあるので、同級生と同じ3年間で高校卒業を目指せる可能性があります。
退学して高卒認定試験を受ける
高校留年が決まったあと、いったん退学して高卒認定試験を受ける方法もあります。高卒認定試験は、高校を卒業できなかった人の学力を適切に評価するための制度です。試験に合格すれば高校卒業と同等以上の学力があると認められ、資格試験や大学などの受験資格が得られます。
高卒と同程度の学力があると認められるので、就職や進学時に役立ちます。出願者数の割合は、高校中退の人が48.6%と一番高く、中退後に高卒認定の資格を生かしたい人が多いと推測されます。
退学して高卒認定の勉強を一人でするのは難しいものです。効率よく勉強するなら、塾やオンライン家庭教師がおすすめです。高卒認定対策用の学校や予備校もありますが、近くにあるとは限りません。オンライン家庭教師なら、場所を問わず学習できるので利用しやすいでしょう。
高卒認定の学習をするなら、オンライン家庭教師ピースにお任せください。オンラインでの個別指導で、お子さんに合ったペースで学習できます。基礎から学び直せるので、高卒認定に必要な学力を身につけられます。
高校中退すると学習面の相談場所がないため、不安なお子さんや親御さんもいるでしょう。ピースでは、授業担当の講師とともに教務担当が学習面の相談にも対応します。学習とメンタル面のサポートで、自信を持って高卒認定試験に臨めますよ。
退学後のお子さんに合うかどうか不安な場合、まずはピースの無料体験授業をお試しください。ホームページの応募フォームやお電話でお申込みいただけます。
退学して就職する
高校を退学したあと、就職する方法もあります。やりたい仕事がある人や、社会経験を積みたい人に合った方法です。
しかし、高校中退では学歴が中卒となり、正社員での就職が難しいかもしれません。厚生労働省の調査では、中退直後の就職先はアルバイトやパートが約7割と高い結果でした。高卒よりも低い結果で、高校中退では安定した就職が難しいと推測されます。
高校を留年しそうな場合は早めに対策を

高校を留年しそうな場合は、早めの対策が重要です。出席日数や成績などで留年の危険がある場合は、早めに学校へ相談した方がよいでしょう。
留年の可能性がある場合、学校からの通知が必ずあります。ほとんどの学校では追試や補習など救済措置をとってくれるので、与えられた課題をクリアするのが一番です。そのまま高校卒業を目指した方が、今後の進路など選択肢が広がります。
万が一、留年が決まったら、そのあとどうするかを親子でよく話し合いましょう。単位制高校などに転校したり、退学して高卒認定を目指したりする方法もあります。将来何をしたいかを決めてから、今後の方向性を考えるとスムーズです。
まとめ
高校を留年する人の特徴には、部活や趣味への過度なのめりこみや、素行の悪さ、体調の悪さなどが考えられます。留年になるのは、出席日数の不足や成績の低下など、学校で決められた単位が取得できない場合です。
留年の可能性があるときは、学校から連絡があるので早めに手を打ちましょう。追試や補習で単位が取れれば留年を回避できます。万が一留年になった場合は、単位制高校への転校や高卒認定試験を受けるなどの道も。どのような進路をとるか、親子でよく相談するとよいでしょう。
単位取得や高卒認定の勉強を一人で行うのは大変です。オンライン家庭教師ピースは、人目を気にせず自分のペースで学習できるのが特徴。基礎力アップを目指した学習フォローで、進学や就職への夢をバックアップします。オンライン指導に興味のある方は、ぜひ無料体験授業にお申込みください。