WISC検査結果の活用方法・お子さんにあった最適な勉強方法とは?
お子さんに学習のつまずきがあって、WISC検査を受けさるか悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。また、すでにお子さんがWISC(ウィスク)検査を受けて、結果用紙を手に、「この数字やグラフが、一体何を意味しているんだろう…?」と、戸惑っている方もいるのではないでしょうか。
WISC検査の結果は、お子さんの「得意なこと」や「苦手なこと」を教えてくれます。
今回は、WISC検査がどのようなもので、その結果をどのように活かせばよいかを分かりやすく解説します。結果を基に、お子さんに合った最適な学習方法を見つけるための具体的な学習方法をご紹介していきます。
WISC検査とは?

WISC(ウィスク)検査とは、お子さんの知的な発達の特性を客観的に測定する心理検査です。正式名称は「ウェクスラー式児童用知能評価尺度」といい、世界中で最も広く使われている知能検査の一つです。
この検査は、お子さんの「得意なこと」と「苦手なこと」を詳しく分析し、全体的な知能だけでなく、思考力や記憶力、処理能力といった知能の偏りを明らかにすることを目的としています。単にIQ(知能指数)を測るだけでなく、お子さんがどのような方法で情報を処理し、学習しているかを知るための貴重な手がかりとなります。
検査は、知能検査の専門的な訓練を受けた心理士や医師によって行われます。いくつかの異なる課題(パズルを組み立てたり、質問に答えたり、数字を覚えたりするなど)を通して、お子さんの能力を多角的に評価していきます。
WISC検査の結果は、お子さんを「評価」したり、「優劣」をつけたりするためのものではありません。それは、お子さんの「学び方の個性」を理解し、その特性に合わせた最適な学習方法や、学校・家庭でのサポート方法を見つけるための羅針盤のようなものなのです。
WISC検査結果でわかること

WISC検査は、お子さんの知的発達を4つの主要な指標から多角的に分析します。これらの指標を理解することで、お子さんの学び方の個性がより明確になります。
1. 言語理解指標(VCI:Verbal Comprehension Index)
言語理解指標(VCI)は、言葉を理解し、言葉で表現する能力を測ります。言葉の概念や知識、そして言葉を使った思考力を示します。この指標が高いお子さんは、言葉で説明されたことをすぐに理解したり、語彙が豊富だったりする傾向があります。
- 指標が示すこと
言葉の知識、言葉を使った推論、思考力。
- 具体例
言葉の意味をどれだけ知っているか(語彙力)。
言葉を使って物事を説明したり、理由を考えたりする力。
文章から情報を読み取り、質問に正確に答える力。
VCIが高いお子さんは、言葉による説明や音読をすることで、学習内容を効率よく吸収できることが多いです。
2. 知覚推理指標(PRI:Perceptual Reasoning Index)
知覚推理指標(PRI)は、言葉を使わずに、目から入る情報を処理し、図形や絵を見て考える能力を測ります。視覚的な情報を基に、物事の共通点や相違点を見つけたり、問題を解決したりする力です。
- 指標が示すこと
視覚的な情報を整理し、推理する力、図形やパズルを解く力、空間認識能力。
- 具体例
パズルを完成させる、積み木で指定された形を作る。
図形の問題で、隠されたルールやパターンを見つけ出す。
地図を読み解いたり、物の位置関係を把握したりする力。
PRIが高いお子さんは、図やイラスト、グラフなど、視覚的な教材を使った学習方法が非常に効果的です。
3. ワーキングメモリー指標(WMI:Working Memory Index)
ワーキングメモリー指標(WMI)は、一時的に情報を記憶し、それを操作する能力を測ります。これは、脳の「作業台」のようなもので、計算や読解、推論など、多くの学習活動の土台となります。
- 指標が示すこと
短期記憶力、集中力、情報の処理能力。
- 具体例
先生の指示を一度で聞き取り、その通りに行動する。
筆算で、繰り上がりや繰り下がりの数字を覚えておく。
文章を読みながら、内容を頭の中で整理し、理解する。
WMIが低いと、聞き間違いや覚え間違いが頻繁に起こったり、集中力が続かないといった困難につながることがあります。
4. 処理速度指標(PSI:Processing Speed Index)
処理速度指標(PSI)は、視覚情報を素早く正確に処理する能力を測ります。これは、脳の「処理スピード」を示し、文字を書き写したり、問題を素早く解いたりする能力と関係しています。
- 指標が示すこと
情報の処理スピード、注意力、手先の器用さ。
- 具体例
与えられた記号を、見本通りに素早く書き写す。
テストや宿題を時間内に終わらせる。
板書をノートに書き写す。
PSIが低いと、時間がかかることで焦りを感じたり、ケアレスミスが多くなったりすることがあります。
これらの4つの指標をバランスよく理解することで、お子さんの学習のつまずきが、どの能力の特性によるものなのかを具体的に知ることができます。
言語理解指標(VCI)が低いお子さんの勉強のコツ

言語理解指標(VCI)が低いお子さんは、言葉で説明された内容を理解したり、言葉で自分の考えを表現したりすることに困難を抱えていることがあります。そのため、従来の「先生の話を聞いて、教科書を読んで学ぶ」という方法だけでは、学習内容が定着しにくいことがあります。
1. 視覚的なツールを積極的に活用する
言葉だけでは理解が難しい内容を、図やイラスト、写真を使って「見える化」することが非常に効果的です。
- 図解やマインドマップを使う
国語の物語文を読むとき、登場人物の関係や出来事の流れをマインドマップや相関図にまとめることで、文章の全体像を視覚的に把握できます。例えば、「AさんはBさんのことが好きで、Cさんに相談した」という文章を、矢印や吹き出しを使って図にすることで、言葉の情報を整理しやすくなります。
- 絵や写真と結びつける
英単語を覚えるとき、単語と日本語訳だけでなく、その単語が示すものの写真やイラストを一緒に提示しましょう。例えば、「apple」という単語を覚える際、「リンゴ」と書かれたカードと一緒にリンゴの絵を描いたり、写真を見せたりすることで、言葉とイメージが結びつきやすくなります。
2. 具体的な体験と結びつける
抽象的な言葉や概念は、お子さんにとって理解が困難な場合があります。学習内容を実体験や具体的な物事と結びつけることで、言葉の持つ意味を身体で感じ、理解を深めることができます。
- 理科の実験や社会科見学
「てこの原理」のような物理の概念は、教科書で読むだけではピンとこないかもしれません。実際に棒とブロックを使って「重いものを動かす」という体験をしてみることで、言葉だけでは伝わらない原理を体感できます。歴史を学ぶ際も、博物館や史跡を訪れることで、当時の雰囲気を肌で感じ、学習内容が記憶に残りやすくなります。
- 家庭での実践
「割り勘」や「おつり」の計算を学ぶときは、おもちゃのお金を使って実際に買い物ごっこをしてみましょう。具体的な行動を通して、抽象的な数の概念や計算方法を理解しやすくなります。
3. 「読む」・「書く」の負担を減らす
VCIが低いお子さんは、読み書きに多くのエネルギーを使ってしまい、内容を理解する前に疲れてしまうことがあります。
- 音声教材の活用
教科書やプリントを読むのが辛いときは、音声読み上げ機能や、音声教材を活用して、耳から情報を得るようにしましょう。これにより、読むことの負担が減り、内容理解に集中できます。
- 口頭での発表や説明
自分の考えを言葉で表現するのが苦手な場合は、絵を描いて説明する、短い単語で答えるなど、口頭での表現を促しましょう。また、作文が苦手な場合は、口頭で話した内容を保護者の方が書き留めてあげるのも有効です。
大切なのは、「言葉で理解できない」ことを責めるのではなく、お子さんが「どうすれば理解できるか」という新しい道筋を一緒に探してあげることです。お子さんの得意な「視覚」や「体験」といった感覚をフル活用することで、学習はよりスムーズに進みます。
知覚推理指標(PRI)が低いお子さんの勉強のコツ
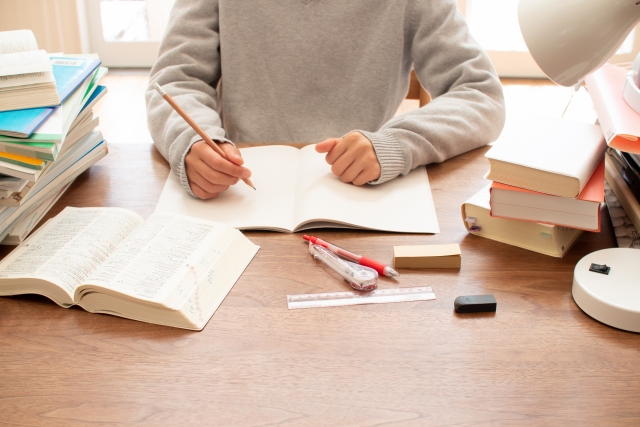
知覚推理指標(PRI)が低いお子さんは、言葉を使わない視覚的な情報処理や、図形・パズルを理解することに困難を抱えていることがあります。そのため、教科書や黒板に書かれた図形やグラフの情報を読み解くのが苦手だったり、地図が読めなかったりすることがあります。
1. 言葉で「見える化」する
PRIが低いお子さんは、視覚的な情報が苦手な一方で、言語理解力が高い場合があります。そこで、目から入る情報を言葉で「見える化」することで、理解を助けましょう。
- 口頭で説明する
図形の問題を解くとき、ただ黙って見せるだけでなく、「この形は、この線で区切られてるね」「この部分とこの部分が同じ形だね」のように、言葉で丁寧に説明してあげましょう。
- 言葉で手順を整理する
算数の図形問題や理科の実験の手順を、「まず、〇〇をします。次に、〇〇をします。」というように、言葉で箇条書きにして整理してあげることで、やるべきことが明確になります。
2. 具体的な「触れる」学習を取り入れる
抽象的な図形や概念を、実際に手で触れることのできる具体的な教材を使って学ぶことが非常に効果的です。
- 積み木やブロックを使う
空間図形の問題を解くとき、積み木やブロックを使って、実際に立体を組み立ててみましょう。自分で触って形を作ることで、頭の中で想像するだけでは難しかった空間認識能力を養うことができます。
- 工作や粘土遊び
図形やパズルの学習だけでなく、工作や粘土遊び、折り紙なども、手先の感覚を通して、形や空間を理解するのに役立ちます。
3. 苦手な部分を補うツールを活用する
- 地図アプリの活用
地図を読むのが苦手な場合は、無理に紙の地図を使わず、GPS機能のある地図アプリを活用しましょう。これにより、位置情報や道のりを正確に把握することができます。
- 動画教材の活用
複雑な図形や立体構造を理解するには、3Dアニメーションやシミュレーション動画を活用するのも良い方法です。動いている映像を見ることで、静止画では分かりにくかった部分を直感的に理解しやすくなります。
大切なのは、お子さんが「見る」ことが苦手な代わりに、「聞く」ことや「触れる」ことを得意としている可能性があるという点です。その得意な感覚を最大限に活かすことで、学習はよりスムーズに進みます。
ワーキングメモリー指標(WMI )が低いお子さんの勉強のコツ
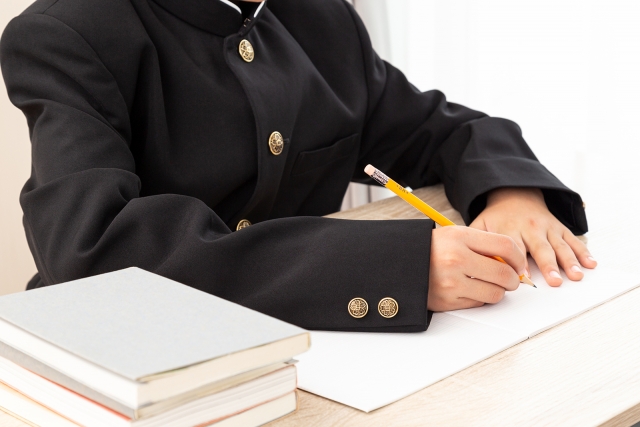
ワーキングメモリー(WMI)が低いお子さんは、一度にたくさんの情報を処理したり、一時的に記憶したりすることが苦手な場合があります。そのため、口頭での指示を一度で聞き取れなかったり、筆算の途中で数字を忘れてしまったりすることがあります。
1. 情報量を減らし、「見える化」する
一度に与えられる情報量を減らし、やるべきことを「見える化」することで、お子さんの負担を軽減することができます。
- 指示は一度に一つだけ
複数の指示を一度に与えるのではなく、「まず、鉛筆を出してね」、次に「その次に、教科書を〇〇ページ開いてね」のように、一つずつ丁寧に伝えましょう。
- やることリストを活用
宿題や準備物をリストに書き出し、終わったらチェックマークをつけさせましょう。これにより、頭の中だけで情報を記憶する必要がなくなり、タスクの全体像を把握しやすくなります。
2. 反復練習と五感を活用する
繰り返し練習し、複数の感覚を使って学ぶことで、短期的な記憶を長期的な記憶へと定着させることができます。
- 小分けにして反復練習
漢字や英単語を覚えるとき、一度に大量に覚えようとせず、5個ずつといったように小分けにして、何度も繰り返し練習しましょう。
- 声に出して覚える
目で見るだけでなく、声に出して読み、耳で聞くことで、記憶への定着を促すことができます。また、体を動かしながら覚えるのも効果的です。
3. 外部ツールを積極的に活用する
ワーキングメモリーの負担を補うために、外部のツールを積極的に活用しましょう。
- メモや付箋を使う
大切なことや忘れてはいけないことは、メモや付箋に書き出し、いつでも見られる場所に貼っておきましょう。
- 電卓や計算機
算数の筆算などで、繰り上がりや繰り下がりを覚えておくのが苦手な場合は、無理に暗算をさせず、電卓を使うことを許可してあげましょう。計算自体よりも、「どうすればこの問題が解けるか」という思考力に焦点を当てることが大切です。
大切なのは、「忘れてしまう」ことを責めるのではなく、「忘れても大丈夫なように工夫する」ことをお子さんと一緒に見つけることです。
処理速度指標(PSI)が低いお子さんの勉強のコツ
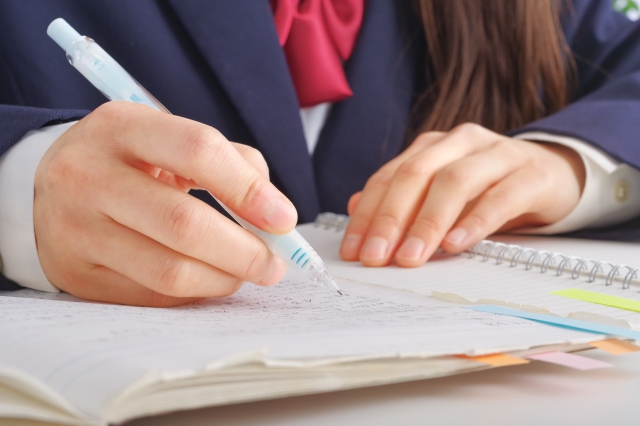
処理速度指標(PSI)が低いお子さんは、情報を素早く正確に処理することに困難を抱えていることがあります。そのため、テストで時間が足りなくなったり、板書をノートに書き写すのに時間がかかったりすることがあります。
1. 時間制限を設けずに取り組む
「早くしなさい」と急かすことは、お子さんにプレッシャーを与え、かえって処理速度を低下させてしまう可能性があります。まずは、時間制限を設けず、丁寧に、正確に取り組むことを重視しましょう。
- 時間的な余裕を持たせる
宿題や課題は、提出期限ぎりぎりではなく、余裕をもって取り組めるように、早めに計画を立てましょう。
テストの時には、時間配分を気にせず、「一問一問、丁寧に解く」練習をすることが大切です。
2. スモールステップで達成感を積み重ねる
一つのタスクを細かく区切って取り組むことで、お子さんが「できた!」という達成感を得やすくし、自己肯定感を高めましょう。
- タスクを細分化する
「漢字練習を100個」ではなく、「今日は漢字を10個練習する」というように、目標を小さく設定しましょう。「10分間でできること」を目標にするのも有効です。
3. ICTツールを積極的に活用する
情報処理の負担を補うためのツールを積極的に活用しましょう。
- パソコンやタブレット
ノートに板書を書き写すのが苦手な場合は、タブレットで写真を撮ったり、パソコンで入力したりすることを学校に相談してみましょう。文字を丁寧に書くことよりも、内容を理解することに焦点を当てることができます。
- デジタル教科書
紙の教科書よりも、デジタル教科書は文字の拡大や読み上げ機能などがあり、お子さんが情報を処理しやすいようにカスタマイズできる場合があります。
大切なのは、「処理速度が遅い」ことを直そうとするのではなく、「どうすれば、この子にとって一番効率の良い方法になるか」を一緒に探していくことです。お子さんのペースを尊重し、焦らず見守ってあげましょう。
お子さんのサポートで親ができること

WISC検査の結果を見て、お子さんに特定のサポートが必要だとわかったとき、親としてどのように動けばよいのでしょうか?
1. 専門家と連携する
一人で抱え込まず、専門家の意見を積極的に求めましょう。
- 検査結果について詳しく聞く
まずは検査を実施した心理士や医師に、結果の詳しい内容や、家庭でできるサポート方法について相談しましょう。
- 学校と連携する
担任の先生や特別支援教育コーディネーターに、検査結果を共有し、学校での具体的な配慮やサポート体制について話し合いましょう。板書は写真に撮るようにする、別室での学習をするなど、具体的な支援内容を提案することが大切です。
2. お子さんの特徴をまとめたノートを作る
検査結果を基に、お子さんの「得意なこと」と「苦手なこと」をまとめたノートを作ってみましょう。これにより、お子さんが困っているときに、どのようなサポートが必要かが明確になります。
「〇〇が苦手なので、〇〇のように手伝ってほしい」
「〇〇は得意なので、〇〇のような方法で学ぶと効率が良い」
このように、お子さん自身や、学校の先生、塾の先生と共有することで、お子さんへの理解が深まり、サポートがスムーズになります。
3. 完璧を目指さない
お子さんの得意と苦手の「差」が大きいと、「なぜ、得意なことはできるのに、苦手なことはできないの?」と感じてしまうかもしれません。しかし、それはお子さんの脳の特性によるものです。
完璧にすべてをこなせるようにするのではなく、苦手な部分を「補う」ことを考えましょう。例えば、ワーキングメモリーが苦手ならメモを取る、処理速度が遅いなら時間をかけても良いと伝えるなど、「弱点克服」よりも「弱点補完」に焦点を当てることが重要です。
まとめ
WISC検査の結果を見て、お子さんの苦手な部分にばかり目を向けるのではなく、お子さんの得意なこと、そして隠された才能を見つけてあげてください。そして、その特性を活かせるような学習方法や環境を一緒に探してあげましょう。
お子さんの「できない」は、やり方が合っていないだけかもしれません。WISC検査の結果は、お子さんの可能性を広げるための第一歩です。焦らず、お子さんのペースを尊重し、その成長を温かく見守っていきましょう。
















