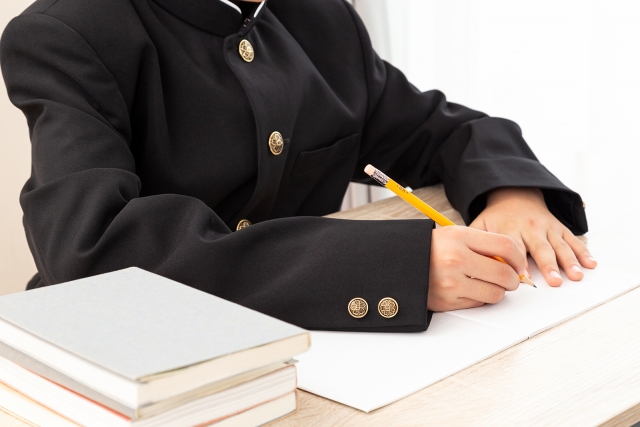探求活動のテーマはどうやって選べばいい?
「探究活動のテーマを決めなきゃいけないけど、何にすればいいかわからない…」
もし、あなたがそう思っているなら、ご安心ください。多くの中高校生が、探究活動のテーマ選びで同じように悩んでいます。
探究活動は、決して難解な研究をすることではありません。それは、あなたが「面白い!」「もっと知りたい!」と感じる、身近な疑問をじっくりと深掘りしていく、ワクワクするような学びです。
こちらでは探究活動のテーマを選ぶためのヒントや、具体的なアイデアをご紹介します。
あなたの「好き」や「気になる」を、探究活動のテーマにする方法を一緒に見つけていきましょう!
探究活動とは?

探究活動とは、あなたが自分で疑問を立て、情報を集め、分析し、自分なりの答えを導き出す一連の学びのプロセスです。
これは、ただ教科書を読んで知識を詰め込む「受け身の学習」とは全く違います。探究活動では、あなたが「先生」になり、「研究者」になって、自分の力で「なぜ?」という疑問を解き明かしていきます。このプロセスを通して、知識を深めるだけでなく、物事を論理的に考える力や、課題を解決する力、そして自分の考えを人に伝える力を養うことができます。
なぜ今、探究活動が重要視されているの?
探究活動が注目されているのには、大きく二つの理由があります。
- 社会が求める力が変わってきたから
現代社会では、AIや情報技術が急速に発展し、ただ知識を持っているだけでは通用しなくなってきました。これからの社会で求められるのは、未知の課題に自ら向き合い、多様な情報の中から必要なものを見つけ出し、新しい価値を生み出す力です。探究活動は、まさにその力を育むための最適な学びの場なのです。
- 大学入試が変わってきたから
多くの大学入試で、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜といった、学力試験だけではない、あなたの個性や意欲を評価する入試が増えています。探究活動で得た経験や成果は、こうした入試であなた自身をアピールするための大きな武器になります。探究活動は、あなたの「好き」や「気になる」を起点に、あなたの可能性を広げる学びです。難しく考えずに、まずは一歩踏み出してみましょう。
探究活動のテーマを選ぶ時のポイント

探究活動のテーマは、難しく考えなくても大丈夫です。あなた自身の「好き」「気になる」「困っている」といった感情から見つけるのが一番の近道です。ここでは、テーマを見つけるための3つのポイントを紹介します。
1. 身近な「なぜ?」から深掘りする
探究活動のテーマは、壮大なものでなくて構いません。むしろ、日常生活の中にある小さな疑問から始める方が、楽しく続けられます。
身近なことに「なぜ?」と問いかけてみましょう。
- なぜ、コンビニのおにぎりはこんなに種類が多いんだろう?
- なぜ、通学路のこの電柱だけ色が変わっているんだろう?
- なぜ、SNSのトレンドはこんなに早く変わるんだろう?
といった、身近な「なぜ?」をメモしてみましょう。その疑問を、少しずつ深掘りしていくと、探究のテーマが見つかるはずです。
2. 自分の「好き」や「興味」を広げる
あなたが夢中になっていることや、もっと知りたいと思っていることは何ですか?あなたの「好き」は、探究の大きなモチベーションになります。
好きなことの「背景」を調べてみるのもおすすめです。
- 好きな漫画やアニメの作者が、なぜそのキャラクター設定にしたのか?
- 好きなスポーツ選手の、なぜそのプレースタイルになったのか?
- 好きなアーティストの、なぜその曲調や歌詞なのか?
単に「好き」で終わらせず、その背景にある歴史や文化、技術などを調べてみると、探究のテーマが広がります。
3. 誰かの「困りごと」を解決してみる
探究活動は、社会の課題を解決する力を養う場でもあります。周りの人が困っていることや、不便に感じていることを観察してみましょう。
「〇〇だったらいいのに」ということについて、考えてみましょう。
- 「朝、通学路のここが渋滞して困る。どうすれば解消できるだろう?」
- 「図書館の本、探すのが大変。もっと簡単に探せる方法はないだろうか?」
- 「高齢者がスマホを使いこなせない。どうすれば使いやすくなるだろう?」
誰かの役に立ちたいという思いは、探究を最後までやり遂げる大きな原動力になります。
探究活動のテーマは、「これじゃないとダメ」という決まりはありません。あなたの好奇心を大切にして、まずは気軽にメモを始めてみましょう。
どうしても探究活動のテーマが思いつかない時はどうする?

「色々考えてみたけど、やっぱりテーマが見つからない…」と悩んでいる人もいるかもしれません。そんな時は、少し視点を変えてみましょう。
分野から「興味」を見つける
「テーマ」ではなく、まずは「分野」から絞り込んでみましょう。
- 医療 → 病気の予防、健康診断、AI医療
- 環境 → プラスチック問題、ゴミの削減、再生可能エネルギー
- テクノロジー → AI、VR、プログラミング、スマートホーム
など、漠然とでも「面白そう」と感じる分野があれば、その中から興味のあるキーワードをいくつか探してみましょう。
身近な社会問題から考える
ニュースや新聞、インターネットで報じられている社会問題に目を向けてみましょう。
- 少子高齢化 → 高齢者の見守り、子育て支援
- 貧困 → 子どもの貧困、フードロス
- 地域の過疎化 → 観光客誘致、伝統工芸の継承
社会問題は、すでに解決すべき課題が明確になっているため、テーマにしやすいです。その中でも、あなたが「自分にも何かできることはないか?」と感じるものを探してみましょう。
先生や友人に相談する
一人で悩まず、信頼できる先生や友人に相談してみるのも良い方法です。自分では気づかなかった、新しい視点やヒントを得られるかもしれません。
「こういうことに興味があるんだけど、テーマになるかな?」と、気軽に話しかけてみましょう。話しているうちに、テーマが明確になることもあります。
探究活動で失敗しやすい・避けた方がいいテーマ
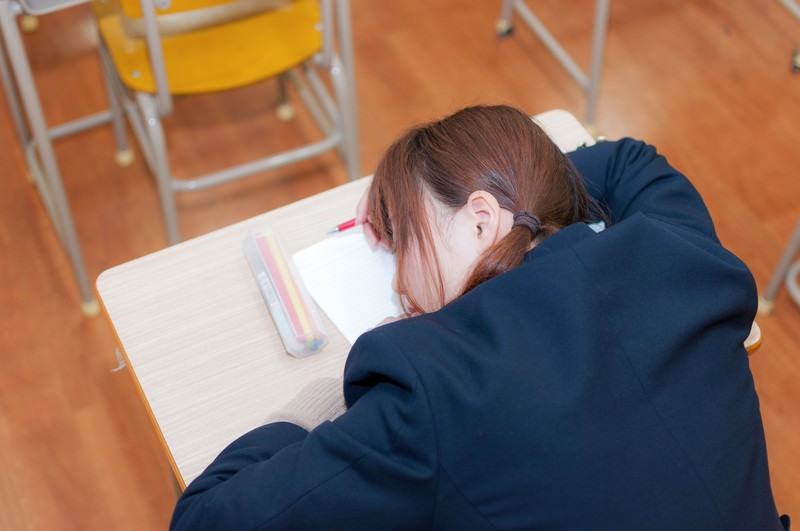
探究活動を成功させるためには、テーマ選びの段階で避けた方がいいポイントもあります。
範囲が広すぎるテーマ
テーマが広すぎると、何から手をつけていいか分からなくなり、最終的にまとまりのない内容になりがちです。
- 失敗例: 「日本の貧困問題について」
- 改善例: 「〇〇市におけるフードロス問題の現状と解決策」
地域、世代、特定の事象など、範囲を具体的に絞り込むと、深く掘り下げやすくなります。
すでに答えが出ているテーマ
インターネットで検索すればすぐに答えが出てしまうようなテーマは、探究活動の醍醐味である「自分で考えるプロセス」がなくなってしまいます。
- 失敗例: 「地球温暖化の原因は?」
- 改善例: 「地球温暖化対策として、高校生ができる具体的なアクションプランの提案」
既存の知識を調べるだけでなく、「自分ならどうするか?」という問いを加えると、オリジナリティのあるテーマになります。
調査が困難なテーマ
データや情報が少なく、調べることが難しいテーマも、途中で行き詰まってしまう可能性があります。
- 失敗例: 「宇宙人の生態について」
- 改善例: 「天文学の最新技術で、宇宙生命体を探す研究」
興味のある分野でも、実際に調査や分析が可能かどうかを事前に確認しておきましょう。
テーマを選ぶ際は、「広すぎないか?」「自分で考えられる要素があるか?」「調べられる情報があるか?」という3つの視点を意識してみてください。
探究活動の具体的な手順

テーマが決まったら、次は探究活動を具体的に進めていきましょう。以下の手順で進めると、効率よく探究活動を進められます。
疑問・問いを立てる
テーマを、さらに具体的な「問い」に落とし込みます。
例えば、「フードロス問題の解決策」というテーマであれば、「〇〇市の家庭でフードロスが発生する原因は何か?」「高校生がフードロスを減らすためにできることは?」という風に、より具体的な「問い」にします。
良い問いは、探究の方向性を明確にしてくれます。
情報収集
次に次のような方法で疑問に答えるための情報を集めます。
- 文献調査する…書籍、論文、新聞記事、インターネット記事
- フィールドワークに出る…実際に現場に出向いて観察する
- アンケートやインタビューを実施する…困っている人や専門家に直接話を聞く
複数の方法を組み合わせて、多角的に情報を集めることが大切です。
分析・考察
集めた情報を整理し、分析します。「なぜ、こういう結果になったのだろう?」と、自分の頭で考えることが最も重要なプロセスです。
まとめ・発表
集めた情報と考察を、レポートや発表資料にまとめます。
まとめでは結論を明確にし、自分の考えをはっきりと示しましょう。
また、「なぜそう言えるのか?」という根拠を、集めた情報から提示しましょう。
最後に探究活動で解決できなかった課題や、新たに生まれた疑問を提示すると、さらに深みが増します。
テーマは決まったのに…探究活動が行き詰った時の解決方法

探究活動は、途中で「これでいいのかな…?」と不安になったり、行き詰まったりすることがあります。そんな時は、以下の方法を試してみてください。
問いをもう一度見直す
行き詰まったときは、そもそも最初に立てた「問い」が適切でなかったり、広すぎたりすることが原因かもしれません。問いをより具体的に絞り込むことで、次にやるべきことが見えてきます。
別の角度から情報を集める
文献調査ばかりしていて行き詰まったら、フィールドワークやインタビューをしてみましょう。机上の情報だけでは分からなかった、新しい発見があるかもしれません。
先生や友人に相談する
先生は、探究活動の専門家です。行き詰まったら、「〇〇を調べているのですが、この先どうすればいいかわからなくなってしまいました」と具体的に相談してみましょう。先生は、あなたにヒントを与え、次のステップへ導いてくれます。
おすすめの探究活動テーマ20個
1. フードロス問題の現状と高校生ができる解決策
日本の食料廃棄は年間約523万トンにも上ると言われています。このテーマでは、なぜフードロスが起きるのか、その現状を具体的に探究します。
- 探究の切り口
家庭やスーパー、コンビニ、飲食店など、どこで、なぜフードロスが起きているのか。
- 具体的な進め方
地域のごみ処理施設やスーパーにインタビューやアンケートを行い、現状を調査します。フードバンクや子ども食堂へのボランティアを通して、フードロスの社会的な影響を肌で感じてみましょう。学園祭や地域のイベントで、フードロスを減らすためのレシピを考案し、発表するのも面白いでしょう。
- 得られる学び
社会問題への関心、データ分析能力、解決策を企画・実行する力。
2. プラスチックごみ削減に向けた高校生の意識調査
プラスチックごみによる海洋汚染は、世界的な問題です。このテーマでは、身近なプラスチックごみに焦点を当て、その削減方法を探ります。
- 探究の切り口
なぜプラスチックは私たちの生活からなくならないのか。プラスチックごみのリサイクルはどのように行われているのか。
- 具体的な進め方
学校内や地域のプラスチックごみの分別状況を調査し、改善点を提案します。クラスメイトや地域の住民にアンケートを行い、プラスチックごみに対する意識を調べます。オリジナルのエコバッグや再利用できるアイテムを制作し、発表するのも良いでしょう。
- 得られる学び
環境問題への意識、調査・分析能力、啓発活動の企画力。
3. SNSの利用時間と学業成績の相関関係
スマートフォンやSNSの利用は、多くの高校生にとって身近なテーマです。このテーマでは、SNSの利用が学業にどのような影響を与えるのかを探究します。
- 探究の切り口
SNSの利用が、集中力や睡眠時間にどのような影響を与えるのか。SNSを学業に活用する方法はあるのか。
- 具体的な進め方
クラスメイトにアンケートを行い、SNSの利用時間と学業成績の関係をデータで分析します。SNSを上手に活用している友人にインタビューし、その秘訣を探ります。SNSを自己管理に役立てるためのアプリや方法を考案し、提案します。
- 得られる学び
データ分析能力、論理的思考力、自己管理能力。
4. 地元の観光名所を増やすためのアイデア
自分の住む地域の魅力について、意外と知らないことが多いかもしれません。このテーマでは、地元を盛り上げるためのアイデアを探究します。
- 探究の切り口
地元の隠れた魅力や歴史的な背景は何か。なぜ、若者は地元の観光名所に興味を持たないのか。
- 具体的な進め方
地元の歴史資料館や観光協会に協力を仰ぎ、取材を行います。若者向けのSNS(TikTok、Instagramなど)を活用して、地元の魅力を発信する方法を考案します。オリジナルの観光ツアーやイベントを企画し、実行してみるのも面白いでしょう。
- 得られる学び
地域社会への貢献意識、企画力、情報発信力。
5. 伝統工芸品の若者への普及方法
日本の伝統工芸品は、素晴らしい技術と歴史を持っていますが、若者にはあまり馴染みがありません。このテーマでは、伝統工芸品と若者を結びつける方法を探ります。
- 探究の切り口
なぜ、若者は伝統工芸品に興味を持たないのか。伝統工芸品の魅力を伝えるためには、どのようなデザインや販売方法が有効か。
- 具体的な進め方
地域の伝統工芸品を制作している職人さんにインタビューし、その歴史や技術を学びます。若者に響くような、新しいデザインの伝統工芸品を考案し、3Dプリンターなどで試作品を制作してみるのも良いでしょう。SNSを活用した販売戦略を立て、実際に模擬販売を行うのも良い経験になります。
- 得られる学び
日本の伝統文化への理解、マーケティング思考、プレゼン能力。
6. AIがもたらす未来の職業と必要なスキル
AIは、私たちの社会を大きく変えようとしています。このテーマでは、AIの進化が将来の仕事にどのような影響を与えるのかを探究します。
- 探究の切り口
AIによってなくなる仕事、新しく生まれる仕事は何か。AI時代を生き抜くために、今から身につけるべきスキルは何か。
- 具体的な進め方
AIやロボット工学の専門家へのインタビューを試みます。書籍や論文、オンライン記事などを幅広く読み、将来の職業について調べます。AIを題材にしたディベートを行い、将来への展望や課題について議論します。
- 得られる学び
論理的思考力、情報収集力、未来予測能力。
7. ジェンダー平等を実現するために学校ができること
ジェンダー平等は、SDGs(持続可能な開発目標)の一つでもあります。このテーマでは、学校生活におけるジェンダーの課題に焦点を当て、その解決策を探ります。
- 探究の切り口
学校の制服や部活動、授業内容に、ジェンダーの偏りはあるか。
ジェンダー平等を推進するために、生徒会や生徒ができることは何か。
- 具体的な進め方
学校の規則や制服について調査し、生徒や先生にアンケートを行います。
ジェンダー問題に取り組んでいる専門家や団体にインタビューを試みます。
ジェンダー平等をテーマにした発表会やワークショップを企画し、実行します。
- 得られる学び
社会問題への関心、課題解決力、多様性を尊重する姿勢。
8. eスポーツがもたらす新たな可能性
eスポーツは、単なるゲームではなく、プロの競技として世界中で注目を集めています。このテーマでは、eスポーツの社会的、経済的な可能性を探ります。
- 探究の切り口
なぜeスポーツは、若者や企業から注目されているのか。
eスポーツは、スポーツや教育にどのような影響を与えるのか。
- 具体的な進め方
eスポーツのプロチームや大会運営者にインタビューを試みます。
eスポーツの歴史や市場規模について文献調査を行います。
実際にゲームをプレイし、チームで協力して勝利するプロセスから、コミュニケーションや戦略性を分析します。
- 得られる学び
新しい分野への探求心、データ分析能力、プレゼン能力。
9. 通学路の危険箇所マップ作成と改善提案
毎日通る通学路には、危険な場所が潜んでいるかもしれません。このテーマでは、通学路の安全を守るための方法を探ります。
- 探究の切り口
なぜ、その場所が危険なのか。交通量や見通しの悪さなど、具体的な原因を探ります。
危険な場所をどうすれば改善できるのか。
- 具体的な進め方
通学路を実際に歩き、危険な場所を特定し、写真や動画に記録します。
地元の警察署や自治体に取材し、事故の発生状況や交通安全対策について聞きます。
地図アプリやウェブサイトを活用して、危険箇所をまとめたオリジナルのマップを作成し、改善策を提案します。
- 得られる学び
地域社会への貢献意識、課題発見能力、情報整理能力。
10. 子どもの貧困問題を解決するためのフードバンクの活用
子どもの貧困は、日本でも深刻な社会問題です。このテーマでは、フードバンクの活動に焦点を当て、その課題と解決策を探ります。
- 探究の切り口
フードバンクは、どのように運営されているのか。
なぜ、フードバンクの存在を知らない人が多いのか。
- 具体的な進め方
地元のフードバンクに連絡を取り、ボランティア活動に参加してみます。
運営者や利用者にインタビューし、フードバンクの課題やニーズを探ります。
SNSを活用してフードバンクの存在を広めるための啓発活動を企画・実行します。
- 得られる学び
社会問題への関心、企画力、実践力。
11. 地域の高齢者の孤立を防ぐためのコミュニティ作り
核家族化が進む現代社会では、高齢者の孤立が問題となっています。このテーマでは、高齢者が安心して暮らせるコミュニティ作りを探ります。
- 探究の切り口
なぜ、高齢者は孤立してしまうのか。
テクノロジーや地域のイベントで、高齢者の孤立を防ぐことはできるか。
- 具体的な進め方
地元の老人ホームや高齢者施設にボランティアとして参加し、高齢者の方と交流します。
高齢者が集まる場所(公園、集会所など)で、高齢者の生活や困りごとについてインタビューをします。
スマートフォンを活用した簡単なコミュニケーションアプリや、世代間交流イベントを企画し、提案します。
- 得られる学び
課題発見能力、企画力、コミュニケーション能力。
12. 〇〇(あなたの町の)商店街を活性化させるには?
全国の商店街は、後継者不足や大型店の進出により、活気を失いつつあります。このテーマでは、地元の商店街を元気にするための方法を探ります。
- 探究の切り口
なぜ、商店街にお客さんが来ないのか。
商店街の強みや魅力は何か。
- 具体的な進め方
商店街の店主にインタビューし、商店街の歴史や現状、抱えている課題について聞きます。
SNSで商店街の魅力を発信するためのアカウントを立ち上げ、発信活動を行います。
若者向けの新商品を考案し、商店街の店舗と協力して、期間限定で販売する企画を立てます。
- 得られる学び
地域社会への貢献意識、マーケティング思考、実践力。
13. 日本の「もったいない」文化の海外への発信方法
「もったいない」という言葉は、環境保護や資源の有効活用を表す、日本独自の文化です。このテーマでは、「もったいない」文化を海外に広める方法を探ります。
- 探究の切り口
なぜ、海外には「もったいない」という概念がないのか。
海外の若者に響く、効果的な発信方法は何か。
- 具体的な進め方
海外の文化や環境問題に関する情報を文献調査します。
留学生や海外在住の友人にインタビューし、「もったいない」という言葉の受け止められ方について聞きます。
「もったいない」文化を伝えるための、オリジナルの動画やウェブサイトを制作します。
- 得られる学び
異文化理解、情報発信力、企画力。
14. 太陽光発電の効率を上げるための研究
再生可能エネルギーの一つである太陽光発電は、私たちの生活に欠かせないものになりつつあります。このテーマでは、太陽光発電の効率を上げるための方法を探究します。
- 探究の切り口
太陽光パネルの設置場所や角度は、発電効率にどのような影響を与えるのか。
天候や時間帯による発電効率の変化を分析する。
- 具体的な進め方
学校の太陽光パネルや、家庭用の太陽光パネルの発電量を記録し、データで分析します。
太陽光パネルの設置場所や角度を変えることで、発電量がどう変化するかを実験します。
太陽光発電の最新技術に関する論文や記事を読み、研究を深めます。
- 得られる学び
科学的な探究心、データ分析能力、課題解決力。
15. 災害発生時に役立つSNSの活用方法
地震や豪雨などの災害発生時、SNSは重要な情報源となります。このテーマでは、災害時にSNSをどのように活用すべきかを探究します。
- 探究の切り口
災害時にSNSでどのような情報が発信され、どのような情報が役立つのか。
フェイクニュースや誤情報を見分けるにはどうすればよいか。
- 具体的な進め方
過去の災害時のSNS投稿を分析し、デマや誤情報がどのように拡散されたかを調査します。
災害対策専門家や自治体の担当者にインタビューし、SNSの活用方法について聞きます。
災害時に役立つ情報を見分けるための、オリジナルのチェックリストを考案します。
- 得られる学び
メディアリテラシー、情報整理能力、課題解決力。
16. 地方の過疎化を食い止めるための移住促進策
地方の人口減少は、深刻な社会問題です。このテーマでは、地方への移住者を増やすためのアイデアを探ります。
探究の切り口:
なぜ、若者は地方に移住しないのか。
地方の魅力や強みは何か。
具体的な進め方:
地方に移住した人にインタビューし、移住を決めた理由や、移住後の生活について聞きます。
地方の自治体が実施している移住促進策を調査し、成功事例と失敗事例を分析します。
若者向けの移住体験ツアーや、地方での仕事を紹介するイベントを企画・提案します。
得られる学び: 社会問題への関心、企画力、情報発信力。
17. 学校の制服をサステナブルな素材に変える提案
ファッション業界では、環境に配慮したサステナブルな素材が注目されています。このテーマでは、学校の制服を環境に優しい素材に変えることを提案します。
- 探究の切り口
現在の制服は、どのような素材でできているのか。
サステナブルな素材には、どのようなものがあるのか。
サステナブルな素材を制服に使うことのメリット・デメリットは何か。
- 具体的な進め方
制服を製造している企業に取材を試み、制服の製造過程や素材について聞きます。
環境に配慮したファッションブランドについて調べ、その取り組みを分析します。
生徒や先生にアンケートを行い、サステナブルな制服への関心度を調査し、具体的な提案をまとめます。
- 得られる学び
環境問題への意識、企画力、交渉力。
18. 授業中の居眠りをなくすための研究
「授業中に眠くなってしまう…」というのは、多くの高校生の悩みです。このテーマでは、居眠りの原因を探り、その解決策を科学的に探究します。
- 探究の切り口
授業中の居眠りは、なぜ起きるのか。睡眠時間や食生活との関係は?
授業の受け方や、教室の環境(温度、照明)は、居眠りに影響するのか。
- 具体的な進め方
生徒にアンケートを行い、居眠りをする時間帯や、その時の体調についてデータを収集します。
居眠り防止に効果があると言われる方法(ストレッチ、ツボ押しなど)を実際に試し、効果を検証します。
脳科学や睡眠に関する論文を読み、居眠りのメカニズムについて知識を深めます。
- 得られる学び
科学的な探究心、データ分析能力、課題解決力。
19. 誰もが安心して使えるユニバーサルデザインの提案
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが使いやすい製品や環境を設計することです。このテーマでは、身の回りにあるユニバーサルデザインを探し、その改善策を提案します。
- 探究の切り口
学校や駅、公共施設で、ユニバーサルデザインが導入されている場所はどこか。
改善すべき点はどこか。
- 具体的な進め方
車椅子や高齢者の方にインタビューを試み、彼らが日常生活で困っていることを聞きます。
街の公共施設や交通機関を実際に歩き、ユニバーサルデザインが導入されている場所を特定し、その機能や改善点を分析します。
新しいユニバーサルデザインのアイデアを考案し、3Dモデルなどで視覚的に表現します。
- 得られる学び
多様な視点を持つことの重要性、課題発見能力、デザイン思考。
20. 地域の歴史を伝えるためのデジタルコンテンツ制作
地域の歴史や文化を、より多くの人に知ってもらうためには、新しい発信方法が必要です。このテーマでは、デジタル技術を活用して、地域の歴史を伝えるコンテンツを制作します。
- 探究の切り口
地域の歴史には、どのようなエピソードがあるか。
歴史をより面白く、分かりやすく伝えるには、どのような表現方法が有効か。
- 具体的な進め方
地元の郷土史家や歴史資料館の学芸員にインタビューし、地域の歴史について学びます。
歴史的な出来事を題材にした短編アニメーションや、歴史上の人物を主人公にしたゲームアプリを企画・制作します。
地域の歴史を巡るAR(拡張現実)コンテンツを制作し、スマートフォンをかざすと過去の風景が見られるような体験を提案します。
- 得られる学び
地域社会への貢献意識、企画力、情報発信力、デジタル技術のスキル。
まとめ
探究活動は、あなたの「好き」や「気になる」を、あなたの「学び」に変える、最高の機会です。
テーマが見つからなくても、焦る必要はありません。まずは、あなたの身の回りにある小さな疑問に目を向けてみましょう。そして、このブログで紹介したポイントや手順を参考に、あなただけの探究の旅を始めてみてください。
この経験は、あなたの将来を豊かにする、大きな力になるはずです。