中1の中間テストの5教科平均点は?1年生ならではの定期テストの注意点やポイントを解説
中1の中間テストの5教科平均点は?1年生ならではの定期テストの注意点やポイントを解説
中学生の定期テストは、小学生の頃までのテストとは違いがあります。
いずれは受験に関わる内申点にも加味されるようになるため、中学1年生の間に、中学校のテストに慣れておくのが理想的です。
特に、主要5教科のみが行われる中間テストは、勉強のペースをつかんでいくために大切な役割を果たします。
ここでは、中学1年生の中間テストについて、その平均点や、1年生ならではの注意点、ポイントについてまとめました。中1ならではの中間テストとの向き合い方が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
中1の中間テストの5教科平均点は?

ほとんどの中学校では、年間で4〜5回の定期テストが行われます。
- 1学期:中間テスト(行わない学校もある)、期末テスト
- 2学期:中間テスト、期末テスト
- 3学期:学年末テスト
1学期、2学期に行われる中間テストは、主要5教科のみのテストであることがほとんどです。
では、そんな中間テストの平均点はどれくらいの点数なのでしょうか。
定期テストの5教科平均は約300点
中学生の定期テストは、基本的にどの教科も平均点が60点前後であることが多いです。つまり、5教科を合計した点数の平均は約300点ということになります。
とはいえ、平均点はそのときのテストの難易度や、学校ごとに違いがある場合もあります。
定期テストでは、平均点との差を考えて、自分が全体のどれくらいの順位にいるのかを考えてみるといいでしょう。
中1の1学期中間テストは平均がやや高めになる場合がある
1年生の1学期中間テストは、実施される学校と、実施されない学校があります。
実施される場合、平均点が他のテストと比べて少し高めになる場合があることに注意が必要です。
理由はどの教科も基本の内容であること、出題範囲が少ないことなどが挙げられます。
平均点が高めになる1学期中間テストで良いスタートを切ること、そして次回以降のテストで油断をしないことが大切です。
1年生の1学期中間テストが行われる学校は、そうした傾向について理解しておきましょう。
中1の中間テストのポイント

では、中学1年生の中間テストならではのポイントは、どんなところにあるでしょうか。
ここでは大切なポイントを3つに分けて解説します。
5教科の勉強ペースをつかむ
国語・数学・英語・理科・社会の主要5教科は、入試でも筆記試験が行われることもあり、誰にとっても重要な教科です。
中間テストでは、そんな5教科のみのテストとなるため、5教科の勉強ペースをつかむいい機会になります。
定期テストは基本的に、2週間前から勉強を始めるのが理想的です。
中間テストの際には、5教科をどんな計画で、どんな方法で対策していくのがベストか試行錯誤してみましょう。
1年生の間からしっかりと勉強ペースをつかんでおけば、いい形で3年生を迎えられるはずです。
定期テストに対する苦手意識を作らない
中学校の定期テストは、入試に関わる内申点に大きく影響を与えます。
高校受験に向け、3年間で満足のいく成績を残していくためにも、1年生の間にテストに対する苦手意識を作らないことが大切です。
1年生の間に、5教科のみの試験である中間テストでつまずくと、どうしても定期テストに対する苦手意識が生まれやすくなります。
毎回のテストに前向きな気持ちで臨めるよう、まずは中間テストでその学期のいいスタートを切ることを目指してみましょう。
教科数が増える期末テストに備える
中間テストは5教科のみの試験がほとんどですが、期末テストでは副教科のペーパーテストが加わり、教科数が多くなります。
1年生の間は特に戸惑うかもしれませんが、中間テストで5教科の勉強ペースをしっかりとつかんでいれば、教科数が増えた場合にも落ち着いて勉強を進めることができるでしょう。
期末テストで教科数が増えた場合にもスムーズに対応できるよう、中間テストでしっかりと5教科の学習ペースをつかんでおくことが大切です。
また、主要5教科の期末テストの出題範囲は、中間テストの範囲がベースとなっていることが多いです。
期末テストの勉強を進めやすくするためには、中間テストにしっかりと取り組んでおく必要があることも、理解しておきましょう。
2学期以降の中1の中間テストの注意点
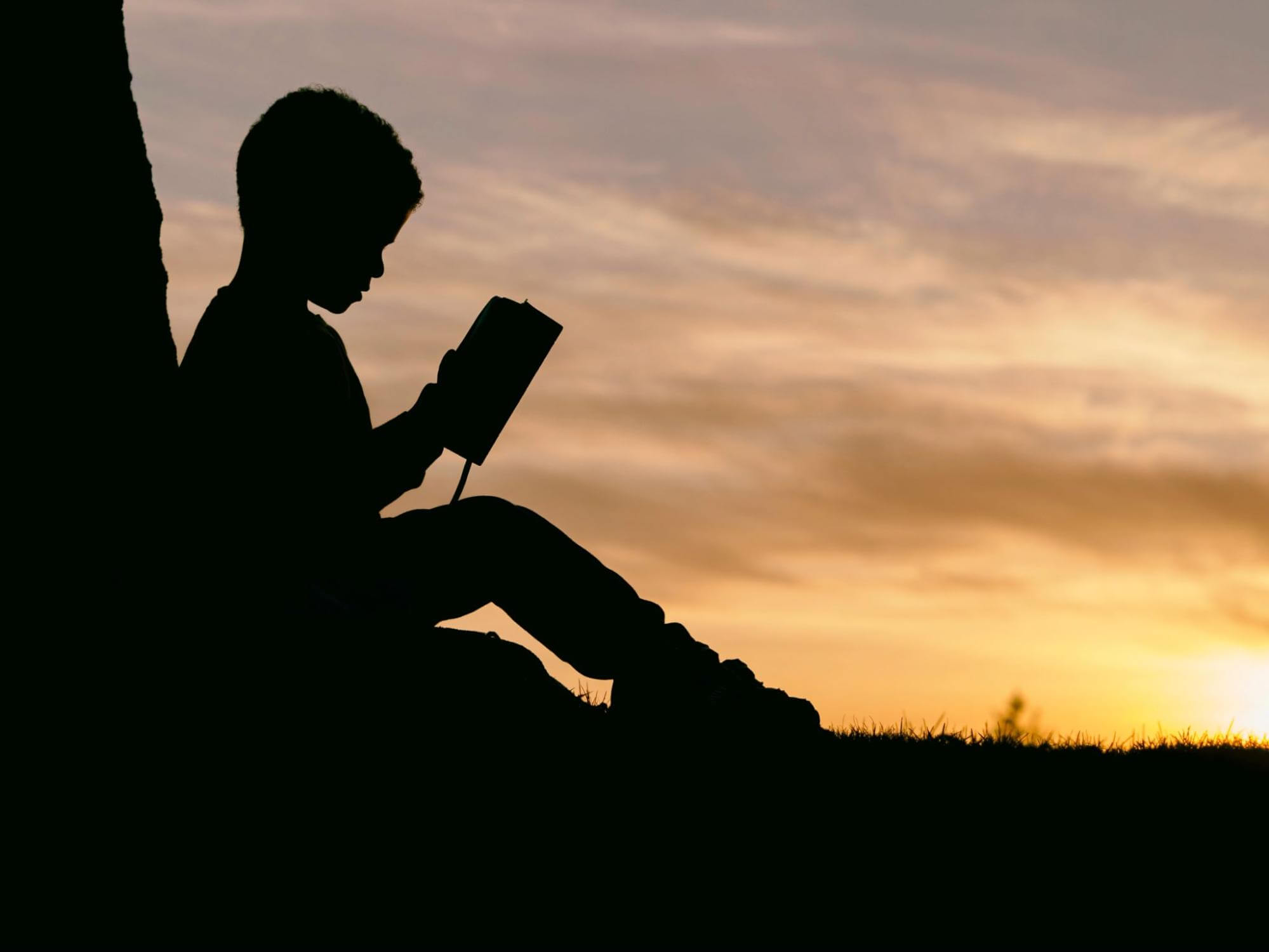
1年生の1学期は、テスト範囲が少なかったり、基本的な内容が多かったりと、比較的取り組みやすい傾向にあります。
しかし2学期以降に関しては、さまざまな理由でつまずきやすくなることがあるため、注意が必要です。
ここからは、そんな2学期以降の中1の中間テストの注意点について解説します。
内容が難化する
中学1年生の定期テストは、2学期以降で内容が難しくなる傾向にあります。
小学校で習ったこと、中学1年生の1学期で習ったことを土台としながら、応用的な内容も少しずつ増えていくからです。
特に2学期は夏休みを挟んでいるため、しっかり復習していないと2学期以降の内容についていくことが難しくなるかもしれません。
1学期は調子が良かった場合も、2学期以降は少し難しくなることを覚悟しておきましょう。
テスト範囲が増える
新学年のオリエンテーションなども多い中学1年生の1学期に比べ、2学期は扱う内容も少し多くなります。
1学期の中間テストと比較すると、その分テスト範囲が増える学校も多いです。
そのため、1学期の中間テストと同じ勉強量では少し足りないこともあるかもしれません。
その後の定期テストの対策ペースをつかんでいくためにも、2学期以降は1学期よりもエンジンをかける必要があるでしょう。
部活動や学校行事が活発になる
中1の1学期は本格化していなかった部活動も、2学期に入る頃には活発に活動するようになっている場合がほとんどです。
部活に入った人は、2学期以降は特に勉強と部活をうまく両立することが求められます。
また、部活だけでなく、2学期以降は行事などが活発に行われる学校も多いです。
中学校生活が本格化する2学期以降で、日々どんな勉強習慣を確保できるかが、定期テストの結果を左右する部分も出てくるでしょう。
テストの緊張感が失われる
1学期は「中学校になって初めてのテスト」と、緊張感を持ってテストに臨む人が多いものです。
しかし、何事も慣れてくると緊張感が薄れるもの。定期テストにおいても、2学期以降は学校生活にもテストにも慣れてきて、気が緩みがちな時期でもあります。
1年生の成績は入試に関係ないという学校も多く、勉強にどうしても身が入らないかもしれません。
とはいえ、1年生の間にしっかりと定期テストに向き合う姿勢が身についている人と、そうでない人とでは、3年間で大きく差がつくことでしょう。
1年生のうちから、しっかりと緊張感を持って毎回の定期テストに臨む姿勢を身につけることが大切です。
中1の中間テストでつまずいたときの対処法
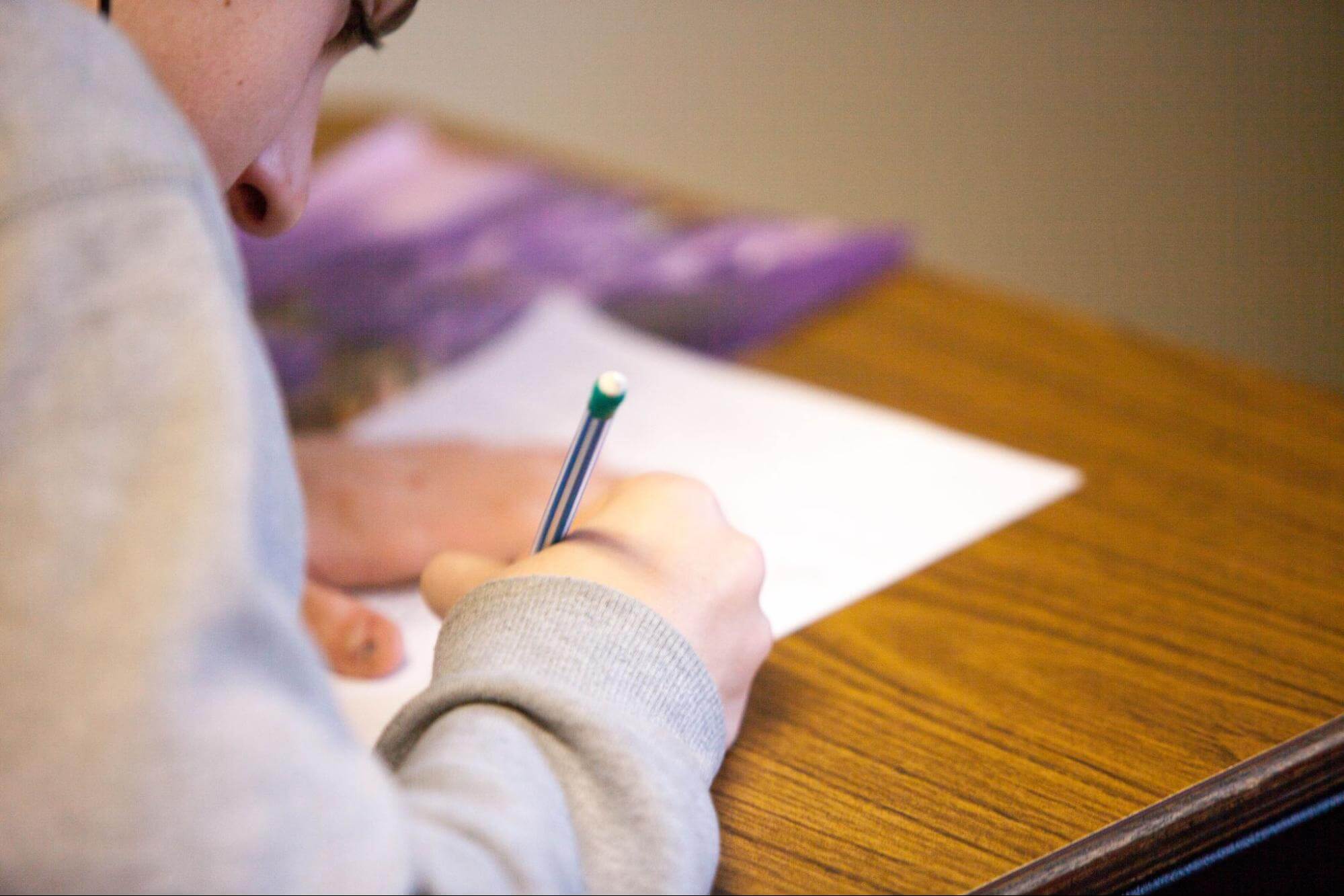
1学期中間テストなど、中学生になって初めてのテストでつまずいてしまった場合、その後の中学校生活に不安を覚えてしまうかもしれません。
最初のテストでうまくいかなくとも、その後しっかりと勉強の仕方を見直せば、軌道修正することも難しくありません。
もしもつまずいてしまったときは、自分一人ではなく、保護者の方や学校の先生、塾などの先生の力を借りながら、以下の3つのことを見直してみましょう。
勉強のペースややり方を確認する
まずは、5教科のテスト対策の勉強ペースややり方を確認してみましょう。
テスト対策を始めた時期から本番までの過ごし方を振り返ることで、どこに原因があるのかが見つかりやすくなります。特に、以下の2つについて振り返ってみましょう。
- テスト範囲はすべて勉強しきれていたか
- 勉強したところはテストで解けたか
テスト範囲をすべて勉強しきれていなかった場合は、勉強計画の立て方に問題がありそうです。
また、勉強したはずの箇所がテストで解けなかった場合は、勉強のやり方に問題があるかもしれません。
テスト本番の結果や、テスト対策の計画表などを見返しながら、丁寧に振り返ってみましょう。
授業や宿題の理解度を確認する
学校の授業や宿題を、どれくらい理解できていたかどうかを確認することも大切です。
「授業で習ったときや、宿題に出されたときは理解していた」という場合は、テスト対策の時点での復習が不足していたことになります。
もしも、授業で習った時点でよく理解できていなかった場合は、日々の授業の受け方や、予習・復習の勉強習慣から見直す必要があるでしょう。
勉強計画を一緒に考える
中学生になって初めての定期テストで、いきなり最適な勉強計画を立てることは誰にとっても難しいことです。
1学期中間テストなど、最初のテストでうまくいかなかった場合は、相談できる人と一緒に勉強計画を考えてみましょう。
保護者の方が相談に乗ってくれる場合は一緒に考えるのも一つですし、学校や塾の先生も、相談すれば応じてくれるはずです。
アドバイスをもらいながら、日々の勉強の仕方、テスト対策の取り組み方について、今の課題や、よりいい方法を見つけてみましょう。
中学生の定期テストの重要性とは
中学生にとって、定期テストは非常に重要なものです。まだ中1だからと安心はできません。
こちらでは、中学生の定期テストの重要性について3つご紹介します。
内申点に直結
中学生の定期テストは、内申点に直結します。
内申点は高校入試になくてはならないものです。ほとんどの公立高校では、内申点と入試の得点を合計して合否を判定します。そのため、入試で高い点が取れても、内申点が足りていないと合格できなくなってしまいます。
高い内申点をとるためには、真面目に授業を受けたり、提出物をしっかりと出したりするだけではなく、テストで高い点数をとる必要があります。
そのため、定期テストは高い内申点をとるために重要です。
学習の習慣をつける
定期テストは、学習の習慣をつけるためにも必要です。
医学部を目指す場合、多くの勉強時間が必要になります。高校入学を期に始めれば間に合うと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、勉強習慣は一朝一夕では身につきません。
中学生のうちからある程度学習習慣をつけておくことで、高校に入ってからストレスなく医学部受験に向けた勉強ができるようになります。
また、中学校の定期テストは複数の単元が一度に出題されるため、小学生の時よりも多くの勉強量が必要になります。
小学校の時に勉強習慣がなかった人はこれを期に勉強習慣をつけ、計画的に定期テストに臨むことで高得点を狙えるようにしましょう。
高校や大学の勉強の土台となる
中学校の勉強の多くは、高校・大学で勉強する内容の基礎であることが多いです。
そのため、中学生のうちに基礎を固めておかないと、高校・大学に入ったときに授業内容についていけなくなってしまいます。
大学受験で医学部を志望するときにも、基礎ができていないと勉強のスタートダッシュが遅れ、受験で不利になってしまいます。
中学生の定期テストで高得点を取るにはどうすればいい?
中学生の定期テストで高得点を取るために、必要なコツを3つご紹介していきます。
2週間前までには勉強をスタート
遅くても2週間前までには、定期テストの勉強を始めましょう。
早すぎる!と思う方もいるかもしれませんが、5教科すべてが範囲になるため、テスト前に提出する課題の量が多くなります。
テスト前2週間を切ってから勉強を始めると、課題をこなすだけでテスト対策が終わってしまいます。課題をやっているだけでは、定期テストでの高得点は望めません。
課題のほかに、定期テストの過去問なども解くことによって、問題の傾向を把握することが高得点につながります。
以上のことから定期テストで高得点を取るには、2週間前から勉強を始める必要があります。
中学校のワークやプリントを最低2周する
定期テストで高得点を取るには、中学校のワークやプリントを最低2周しましょう。
定期テスト前には、各教科の先生からワークやプリントが課題として出されることが多いです。そして、多くの場合、この課題の中からテストの問題が出題されます。
全ての問題を2周するのは大変なので、1周目に解いてできなかった問題だけ、2周目で解くようにしましょう。
課題に指定された問題をすべて解けるようにするだけで、定期テストの点数は大きく上がりますので、ぜひやってみてください。
塾や家庭教師を利用する
ここまでは、自分でできるテスト対策について解説してきましたが、自分でできる対策には限界があります。
そこでおすすめなのが、塾や家庭教師を利用することです。
定期テストは課題から出題されることが多いですが、全ての問題が課題から出されるわけではありません。
過去問の出題傾向や、学校の特徴を把握している塾や家庭教師を利用することで、周りと差がつけられますので、ぜひ検討してみてください。
★こちらもチェック!
【中学生】定期テストで400点なら順位はどれくらい?目安や点数UPにつながる勉強法を紹介
定期テストで10位以内に入るには?必要な点数・勉強法を詳しく解説
中学生の定期テストの教科別勉強法
ここからは、中学生の定期テストの教科別勉強法についてご紹介していきます。
ぜひ、参考にしてくださいね。
国語
漢字・古文の語句・文法が出題される場合は、学校のワークなどを活用し、完璧に暗記しましょう。
特に漢字は複数出題されるため、対策しておくことで高得点が望めます。読解問題では、授業で習った文章がそのままテストに出題されることが多いです。
国語の試験問題では、先生が授業中に黒板に書いたことや、話していたことが出題される傾向にあり、テスト対策として使えるのが授業ノートです。
そのため、国語の定期テスト対策として、しっかりと授業ノートをとるようにしましょう。
数学
数学は、公式を暗記するだけではなく、公式の使い方まで覚えるようにしましょう。
公式を暗記しただけでは応用問題が解けません。公式の使い方を覚えるには、学校指定のワークを活用しましょう。
何度も繰り返しワークを解くことによって自然と公式が身につき、応用問題に対応できるようになります。
英語
英語の定期テストでは、長文と文法問題は必ず出題されます。
長文は、教科書と全く同じ英文が出題されることが多いです。そのため、教科書を何度も読み、英文とその日本語訳を暗記するようにしましょう。
また、文法問題は学校指定のワークを何度も繰り返し解き、ワークの問題を完璧に解けるようにしましょう。
暗記は一見面倒に思いますが、ほかの参考書をたくさん解くよりも、教科書や学校指定のワークを解いたほうが高得点が狙いやすくなります。
理科
理科は、分野ごとに別の勉強法で取り組むのがおすすめです。
生物と地学の場合、語句の暗記をするだけで高得点が狙えます。語句の暗記をするために、学校指定のワークを繰り返し解きましょう。
また、物理や化学の分野では、法則や公式、元素記号を暗記することに加え、法則や公式の使い方をマスターする必要があります。
学校のワークを何度も解き、公式や法則を完全にマスターできるようにしましょう。
社会
社会は暗記する量が膨大です。
そのため、テスト直前に始めると覚えきれないため、2週間前くらいから学校のワークを中心に、コツコツと勉強を始めましょう。
また、時間に余裕がある人は教科書を読むこともおすすめです。教科書を読むことで、語句をただ暗記するだけではなく、語句同士を関連付けて覚えることができます。関連づけて覚えることで忘れづらくなるため、ぜひやってみてください。
副教科
「副教科は高校入試で使わないからやらなくてもいい!」と思っている人も多いのではないでしょうか?しかし、高い内申点を獲得するためには、副教科もしっかりと勉強する必要があります。
課題が出されている場合は、課題のワークやプリントを最低2周、時間に余裕がある場合は完璧に覚えるまで繰り返し勉強しましょう。
課題の内容を覚え終わったり、課題がなかったりする場合は、塾や家庭教師でもらう過去問を解きましょう。副教科の先生は過去問と似たような問題を出すことが多いので、過去問題対策は必須です。
わからなかったり、間違えたりした問題はノートにまとめ、覚えるまで何度も復習をすることで、高得点間違いなしです。
定期テスト勉強のポイント
最後に、定期テスト勉強のポイントを2つご紹介します。
ポイント①テスト対策は教科書・ワークを中心に行う
定期テストでは、教科書・ワークを中心に問題が出題されます。
そのため、教科書・ワークを完璧にしていれば高得点を狙えます。反対に、複数の参考書に手をつけてしまうとどれも中途半端になってしまい、点数が伸びません。
教科書・ワークを何度も解いて完璧にすることを目標に、テスト勉強をしてみてください。
ポイント②授業ノートをしっかりとる
日々の授業でノートをしっかりと取っているだけで、テスト対策になります。
特に国語の定期テストでは、授業で先生が黒板に書いたり、話していたりしたことがテストに出題される傾向にあります。
また、授業態度の評価をするために、先生にノート提出を求める学校が多いです。そのような学校の場合は、ノートを丁寧にとっていないといくらテストで点数をとっていても、高い内申点が望めなくなってしまいます。
そのため、日々の授業に真面目に取り組み、ノートをしっかりと取るようにしましょう。
テスト対策はオンライン家庭教師ピースで!中1から受講するメリット

中学生の定期テストは小学生までとは異なり、多くの範囲から出題されるテストに備えなくてはなりません。
教科数も多いことから、どうしても自分一人で勉強のペースをつかむのが難しいことも少なくないでしょう。
中1から勉強でいいスタートを切っていくためにおすすめなのが、オンライン家庭教師という、自宅でパソコンやタブレットを使って授業が受けられる教育サービスです。
中でも「オンライン家庭教師ピース」には、中1から始めるのにおすすめな理由がたくさんあります。
ここでは「オンライン家庭教師ピース」のおすすめポイントについてまとめました。
相性の良い講師が学習習慣の定着をサポート
「オンライン家庭教師ピース」には、それぞれのお子さまにとって相性のいい講師をマッチングするシステムがあります。
登録講師は3,000人以上。その性格や趣味、教え方、個性をすべて把握し、お子さまにぴったりな1人を厳選してご紹介するシステムです。
そんな相性の良い講師が、中学生からの学習習慣の定着を徹底的にサポートします。
お子さまの生活に合わせた専用授業スケジュールや学習計画を担当講師が作成し、普段の勉強に関してもフォローが可能です。
1年生の間から受講すれば、定期テスト対策はもちろん、中学校生活における勉強習慣をしっかりと身につけることができるでしょう。
不明点や苦手はすぐに質問&解決できる
「オンライン家庭教師ピース」は、毎回の授業を講師とマンツーマンで受講することができます。
不明点や苦手についてもすぐに質問でき、解決するまで粘り強くサポートするため、わからないところや不安なところを残したまま先に進むことはありません。
1年生からの学習が大切である中学生にとって、苦手を解消しながら勉強を重ねていくことはとても重要です。
「オンライン家庭教師ピース」の受講を通じ、苦手を確実に解消していくことで、最短ルートで成績を上げていくことが期待できます。
高校受験を見据えた学習が進められる
「オンライン家庭教師ピース」では、一人一人の学習目的や志望校に合わせたオーダーメイドカリキュラムに基づいて指導を行います。
1年生から受講することで、高校受験を見据えた学習にコツコツ取り組むことが可能です。
また、担当講師は東大・京大・早慶・医大など難関大学の学生講師、指導実績豊富なプロ社会人講師がそろっているため、受験に対するノウハウも豊富にそなえています。
目標に合わせた日々の学習と定期テスト対策で、高校受験での志望校合格に向けて計画的に学習を進められるでしょう。
まとめ
中学1年生の中間テストの平均点は、300点前後です。1学期に中間テストが実施される場合は、少し平均点が高くなる傾向にあります。
特に1年生は、5教科のみの試験が行われる中間テストで勉強のペースをつかむことが大切です。つまずいてしまったり、不安があったりする場合は、周りの人の手を借りながら、学習計画や勉強の仕方を考えてみましょう。
中学1年生からしっかりと勉強習慣を定着させておきたい場合は「オンライン家庭教師ピース」がおすすめです。
相性ぴったりの講師と、定期テスト対策はもちろん、高校受験を見据えた学習を計画的に行うことができます。
「オンライン家庭教師ピース」は無料体験授業を実施しています。まずはお気軽にご相談ください。
















