中学生の自己推薦書の書き方とは?書き方を5STEPにわけて解説
自己推薦入試とは、高校からの推薦が不要な、自分が受験したい大学に出願できる受験方法です。
受験生の中には、自己推薦入試を利用して志望大学を受験するか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、自己推薦入試の概要を説明した上で、他の推薦入試や総合型選抜との違いを解説します。
また、志望校に自己PRするための自己推薦書を書く必要がある方の中には、どのように書けばよいかわからず困っている方もいらっしゃいますよね。
中学生の自己推薦書の概要について説明した上で、書き方についても解説しています。自己推薦書の書き方が分からない方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
自己推薦入試とは?

自己推薦入試とは、自分を推薦する入試方式であり、大学の出願条件を満たせば誰でも受験できる試験です。
他の推薦入試との大きな違いは、自己推薦入試は高校からの推薦は必要がないことです。
自己推薦入試を利用して志望大学を受験するとき、高校での活動内容や実績が主に評価されます。また、志望理由や高校での活動内容についてまとめる「自己推薦書」も評価対象です。
自己推薦入試を利用して大学受験をしようとしている方は、高校で努力したことや学んだことをアピールする必要があります。
自己推薦入試と公募推薦・指定校推薦の違い
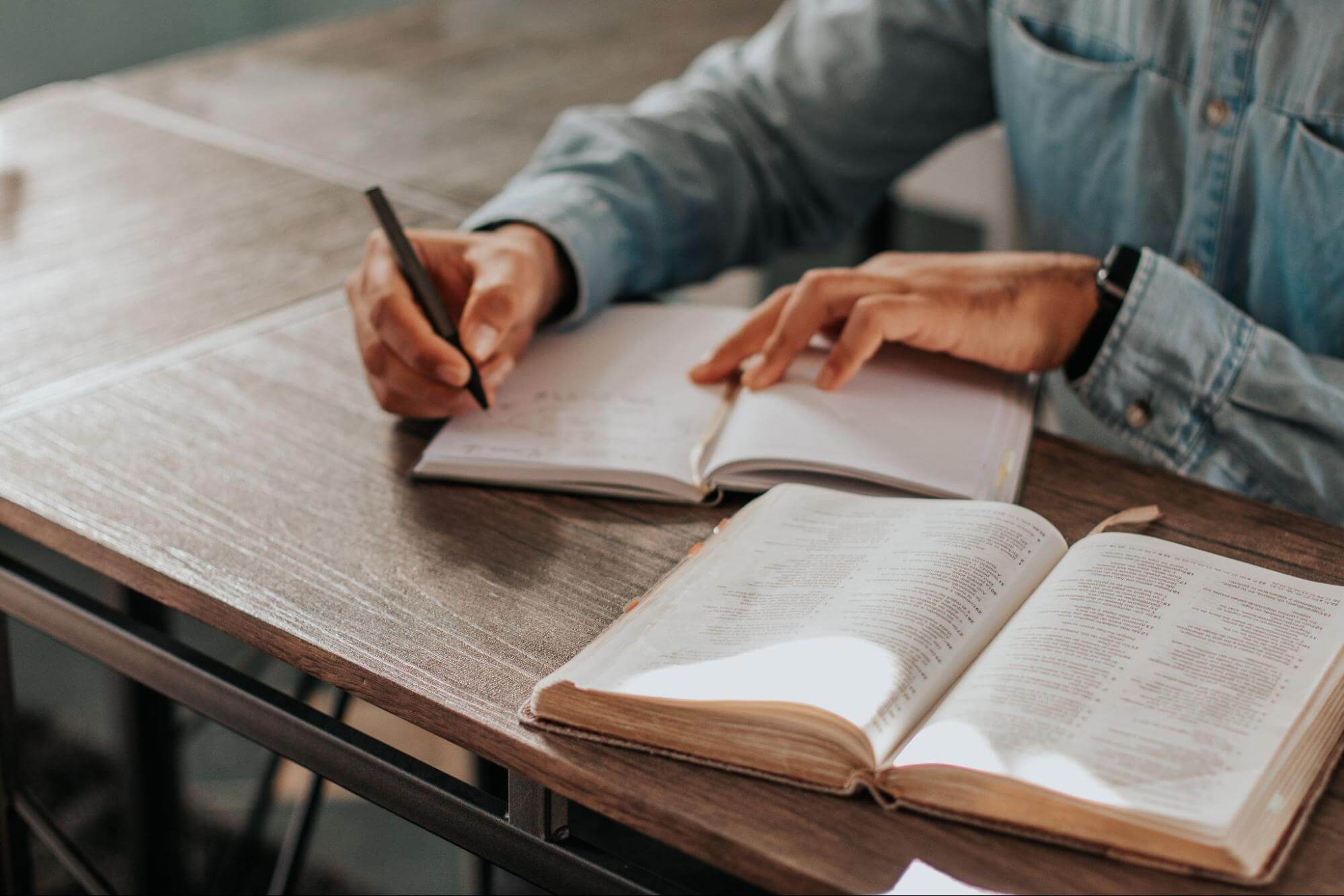
自己推薦入試と公募推薦・指定校推薦は、高校の推薦の要不要や必要な評定平均、専願の可否が異なります。
各受験方法のポイントの違いについて、以下の表にまとめました。
| 高校の推薦 | 評定平均 | 専願・併願 | 受験できる大学 | |
| 自己推薦入試 | 不要 | 不要(大学によっては基準あり) | 併願可能 | 応募している大学であればどこでも可能 (私立大学のみ) |
| 公募推薦 | 必要 | 基準を満たす必要あり | 専願制 | 応募している大学であればどこでも可能 (国公立大学のみ) |
| 指定校推薦 | 必要 | 基準を満たす必要あり | 専願制 | 高校が指定した大学 |
このように、自己推薦入試には評定平均に関する出願基準が、基本的に設定されていません。また、自己推薦入試は私立大学でのみ実施しているので、私立大学に推薦で受験したい方におすすめです。
自己推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)の違い

自己推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)は、評価されるポイントや選考方法が異なります。
総合型選抜(旧AO入試)とは、アドミッションポリシー(大学が求める人物像)とマッチしている受験生を大学側が判断する受験方法です。
自己推薦入試と総合型選抜(旧AO入試)の違いについて、以下の表にまとめました。
| 評価されるポイント | 選考方法 | |
| 自己推薦入試 |
|
|
| 総合型選抜(旧AO入試) |
|
|
自己推薦入試では、高校でがんばったことや学んだこと、実績が主に評価されるポイントであり、自己推薦書や面接で選考が行われます。
一方で、総合型選抜(旧AO入試)では、高校でがんばったことに加えて、大学に入ってやってみたいことや将来の目標が評価されるポイントです。
総合型選抜(旧AO入試)で合格しやすい受験生は、将来やりたいことや大学・学部に入学する目的が明確になっています。
自己推薦入試を導入している大学

自己推薦入試を導入している大学の一部を抜粋して、以下にまとめました。
【自己推薦入試を導入している一部大学】
|
|
(参考:ドリコムアイ.net)
日東駒専やMARCH、早慶など多くの大学で自己推薦入試を行っています。
受験を考えている大学の受験要項を確認して、自己推薦入試を実施しているか確認してみてください。
自己推薦入試の倍率

自己推薦入試を実施している大学・学部のうち、5大学を抜粋して倍率についてまとめました。
【大学の倍率(2022年度入試)】
| 大学 | 自己推薦の倍率 | 一般入試の倍率 |
| 早稲田大学社会科学部 | 7.6 | 8.8 |
| 明治大学文学部史学地理学科アジア史専攻 | 2.0 | 3.0 |
| 青山学院大学地球社会共生学部 | 3.3 | 4.6 |
| 駒沢大学文学部地理学科 | 1.4 | 3.6 |
| 東洋大学経済学部経済学科 | 1.8 | 3.7 |
(参考:大学受験パスナビ)
自己推薦入試の倍率は大学・学部によって異なりますが、一般入試より倍率が低い傾向にあります。
ただし、人気の大学・学部によっては、一般入試よりも自己推薦入試の方が倍率が高いケースがあります。志望大学がすでに決まっている方は、志望大学の倍率を早めに確認してみてください。
自己推薦入試で合格するためのポイント
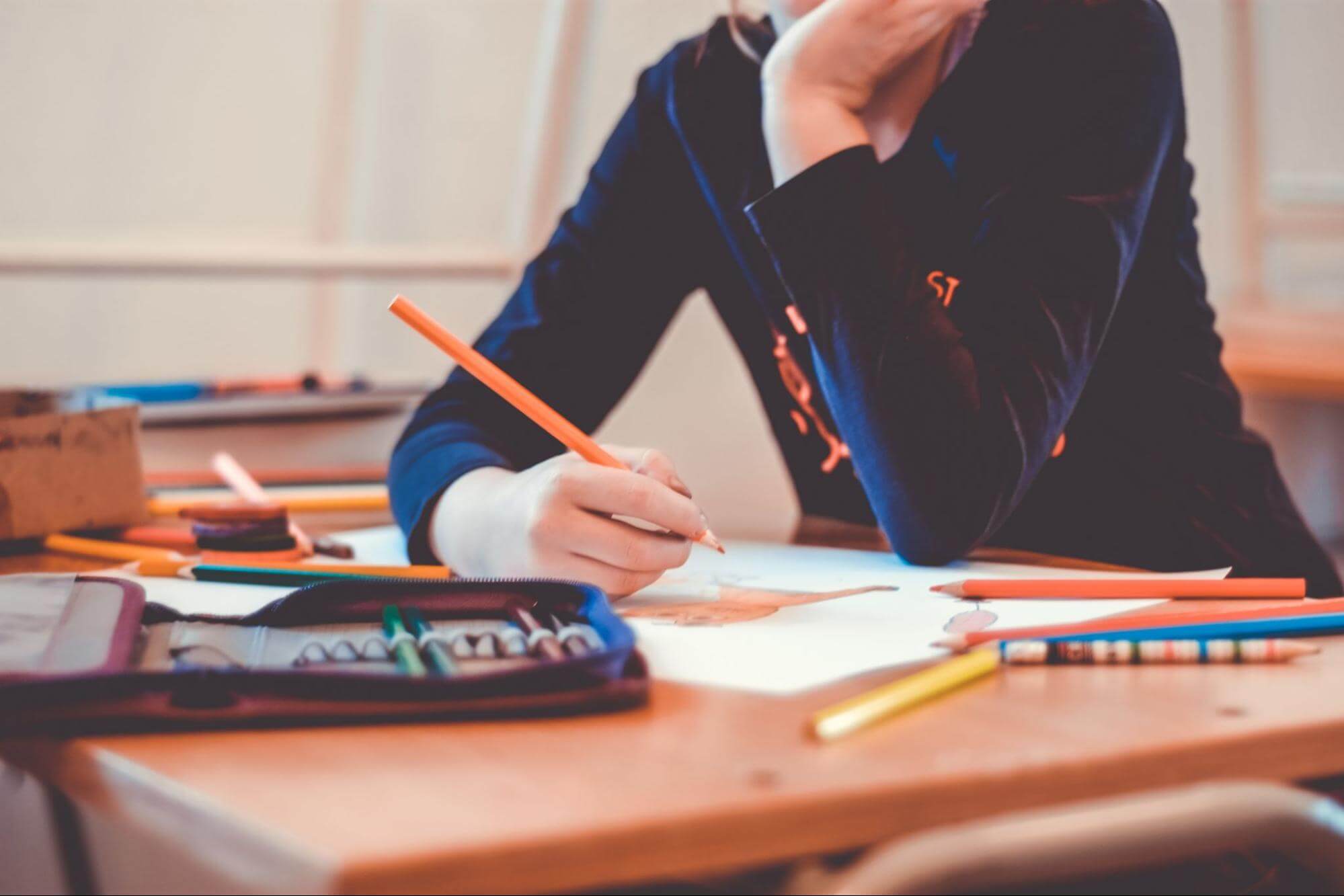
自己推薦入試で合格するためには、以下の2つのポイントを意識して受験対策する必要があります。
- 質の高い自己推薦書を書く
- 自己推薦入試の面接対策をする
ここからは、それぞれのポイントについて解説するので、自己推薦入試を検討している方は参考にしてみてくださいね。
合格するためのポイント1:質の高い自己推薦書を書く
自己推薦入試で合格するためのポイントの1つ目は、質の高い自己推薦書を書くことです。
質の高い推薦書を書くためには、以下の4つを実践しましょう。
- 高校生活を振り返る
- 大学のアドミッションポリシーを自分なりに解釈する
- 大学でしたいことを考える
- 添削してもらう
まずはできることから、受験対策を始めてみてください。
高校生活を振り返る
質の高い自己推薦書を書くためには、高校生活でがんばったことを振り返ることが大切です。
高校生活を振り返るとき、まずはがんばったことをすべて洗い出してみましょう。そして、以下の表の内容を参考に、振り返りを行ってみましょう。
| 振り返る項目 | 詳細 | 例 |
| 活動の目標や目的 |
|
|
| 自分の役割 |
|
|
| 活動で発生した課題 |
|
|
| 課題の解決方法 |
|
|
| 活動の結果 |
|
|
| 活動を通して得た学び |
|
|
このように、高校生活で努力したことや学んだことをまとめてみましょう。
大学のアドミッションポリシーを自分なりに解釈する
志望大学のアドミッションポリシーを自分なりに解釈することも、自己推薦書を書くために必要です。
アドミッションポリシーとは大学が求める人物像であり、各大学・各部学科ごとにアドミッションポリシーが存在しています。
例として、早稲田大学商学部のアドミッションポリシーをご紹介します。
【早稲田大学商学部のアドミッションポリシー(一部抜粋)】
| 国際感覚・倫理観を兼ね備えた企 (起)業家精神を養い、深い学識と教養に裏付けられた実業家を目指し、ビジネスリーダーとして地球社会に貢献しようと志す学生を受け入れたいと考えている。 |
早稲田大学商学部は、ビジネスに興味がある方や、実業家になりたい方を募集しています。
このように、求める生徒の人物像が明確に記載されているので、志望大学のアドミッションポリシーを読み込み対策を行いましょう。
大学でしたいことを考える
質の高い自己推薦書を書くためには、大学生でしたいことを考えることも大事です。
「将来の目標ややりたいことのために必要なことが学べる」ということを、志望する大学・学部に対し伝えられると大学からの評価が高くなります。
将来やりたいことや、学びたいことをぜひ考えてみてください。
添削してもらう
自己推薦書の下書きを作成したら、第三者に添削してもらってブラッシュアップしましょう。
第三者に添削してもらうときは、内容がわかりやすいか、日本語が間違っていないか、確認してもらうなどチェックしてもらうことをおすすめします。
合格するためのポイント2:自己推薦入試の面接対策をする
自己推薦入試では面接選考も行われるので、面接対策を行う必要もあります。
具体的には、以下の3つの面接対策を行いましょう。
- 面接のマナーを身につける
- よく聞かれる質問の回答を準備する
- 模擬面接を何度もする
それぞれの対策内容について解説していきますので、面接が苦手な方は参考にしてみてください。
面接のマナーを身につける
面接対策の1つ目は、面接のマナーを身につけることです。
具体的には、身だしなみや入退室のマナー、言葉遣いなどに気をつける必要があります。
面接で気をつけるべき代表的なマナーについて、以下の表にまとめました。
| 面接以外のマナー |
|
| 入室時のマナー |
|
| 着席時のマナー |
|
| 退室時のマナー |
|
あせらず、同時に2つのことをしないことが、面接において重要です。
面接のマナーをあまり知らない方は、書店で面接マナーの本を購入して読んでみることもおすすめですよ。
よく聞かれる質問の回答を準備する
自己推薦入試の面接でよく聞かれる質問を事前にまとめ、準備することで問題なく答えられるようにしておくことも大切です。
特に以下の内容は面接でよく質問されるため、事前に回答を準備しておきましょう。
- 志望した理由
- 志望校の特徴
- 自分の長所と短所
- 高校でがんばったことや実績
- 気になったニュース・時事ネタ
- 自己PR
一度紙に回答内容を書き起こしてみると、より質の高い回答を準備できます。
模擬面接を何度もする
学校の先生や塾の講師と模擬面接を何度も行うことも、自己推薦入試の効果的な面接対策です。
何度も模擬面接をすることで、面接マナーを身につけられ、面接官の質問に適切に回答できるようになります。また、模擬面接終了後には、面接官役をしてもらった方から改善点を聞いてノートにまとめることがおすすめです。
次の模擬面接の前や面接本番の前に、まとめたノートを見返すことで改善点を意識しながら面接に臨めるでしょう。
中学生の自己推薦書とは? | 志望校に自己PRするための書類

志望高校に提出する中学生の自己推薦書とは、志望校に自己PRを行うための書類であり、願書とセットで提出する書類です。
高校受験の面接や、入学前の生徒指導の参考資料として、自己推薦書が利用されることが一般的です。また、中学から推薦で高校を受験するときの学校内推薦書として、自己推薦書を高校に提出する場合もあります。
自己推薦書は高校受験の合否に関わってくる書類であるため、しっかり書く内容を考えて執筆しましょう。
【5STEP】自己推薦書の書き方
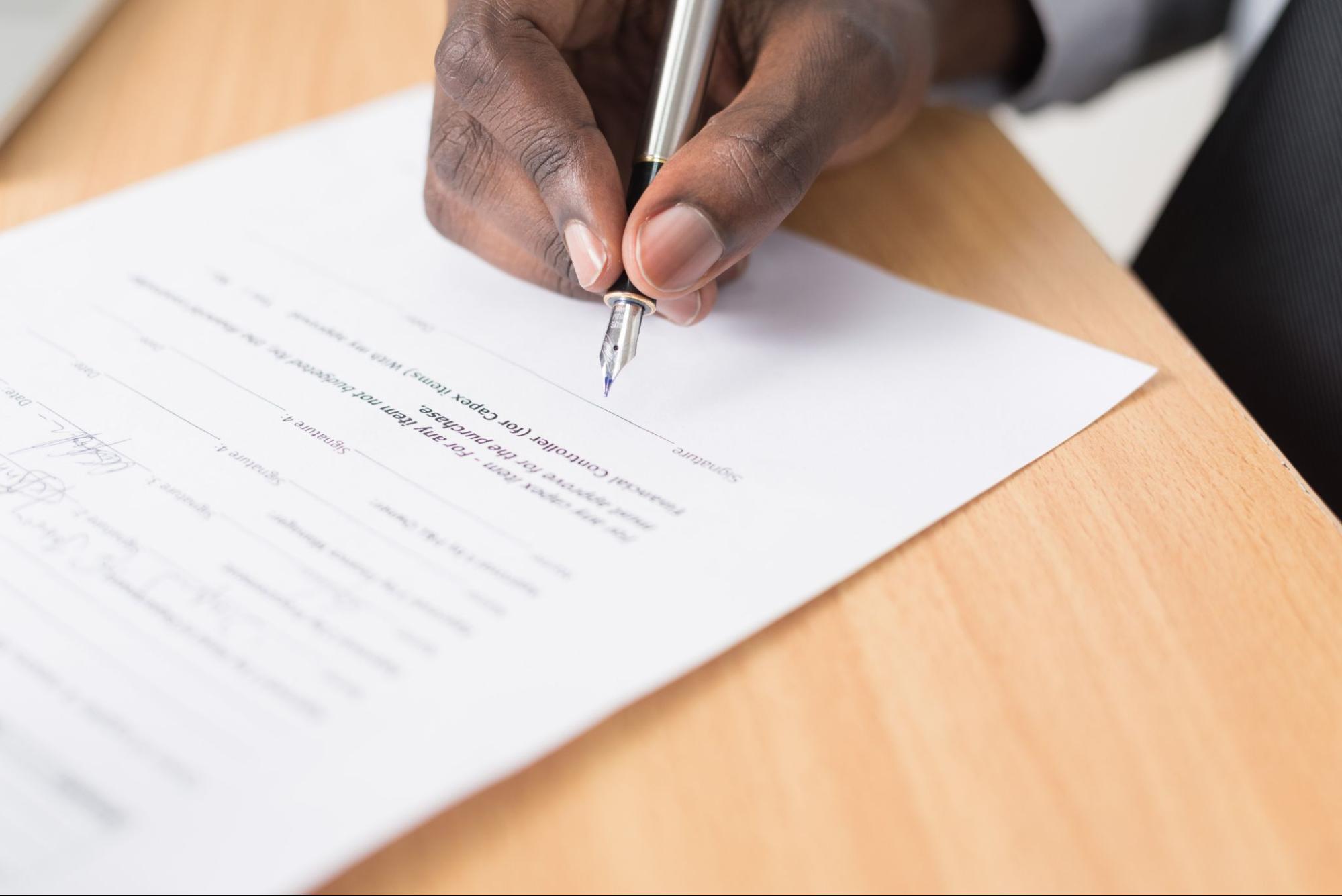
相手に自分のことをわかりやすく伝える自己推薦書を書くためには、以下のような手順を踏むことがおすすめです。
- STEP1:自分の経験や今後の目標を書き出す
- STEP2:文章の骨組みを作る
- STEP3:下書きを作る
- STEP4:第三者に添削してもらう
- STEP5:自己推薦書に清書する
自己推薦書をどのように書けばいいかわからず困っている方は、参考にしてみてくださいね。
STEP1:自分の経験や今後の目標を書き出す
まず自分の経験(中学での活動内容)や、今後の目標をノートにできるだけ数多く書き出してみましょう。
中学での活動内容を書くときにテーマが思い浮かばない場合は、以下のテーマから選んでみてください。
- 部活動
- 習い事
- ボランティア活動
- 生徒会活動や委員会活動
- 資格取得
- 海外留学
- 市民団体での活動
- インターン
- 家事や家業の手伝い
- 趣味や特技
部活動や学校行事にあまり積極的に参加していない方は、資格取得や家事の手伝い、趣味などを書き出してみましょう。がんばってきたことを書き出したら、自分の活動内容を振り返っていきます。
例として、サッカー部でがんばった場合の内容を表にまとめてみました。
| 振り返る項目 | 詳細 | 例 |
| 活動の目標や目的 |
|
|
| 自分の役割 |
|
|
| 活動で発生した課題 |
|
|
| 課題の解決方法 |
|
|
| 活動の結果 |
|
|
| 活動を通して得た学び |
|
|
このように、中学校生活でがんばったことに対して振り返って、活動から得た学びをまとめます。
STEP2:文章の骨組みを作る
次に、自己推薦書に書く文章の骨組み(構成)を作ります。
文章の骨組みを作るとき、以下のような構成で考えるとわかりやすい文章になります。
- 結論(アピールポイント)
- 根拠
- 具体例(エピソード)
- 結論(アピールポイント)
上記の4つをそれぞれ段落ごとにまとめると、きれいな構成になるのでおすすめです。根拠や具体例が2つある場合は、段落を2つにわけると読み手が読みやすくなりますよ。
例として、サッカー部の経験を踏まえて文章を作るとこのようになります。
| 骨組み | 内容 |
| 結論(アピールポイント) | 目標を達成するためには、自分たちで達成したい目標を決めることが大切 |
| 根拠 | 他人から与えられた目標では、自分たちが達成したいと思えない |
| 具体例(エピソード) |
|
| 結論(アピールポイント) | 目標を達成するためには「自分で目標を決めること」が大切 |
上記の表のように骨組みをまとめると、下書きをしやすくなります。
STEP3:下書きを作る
自己推薦書の骨組みができたら、下書きを作りましょう。
下書きを作る時に、下記のポイントを意識するとより良い自己推薦書が作成できます。
- ルール通りに書く(あれば)
- ですます調で執筆する
- 結論からわかりやすくまとめる
- 一文一意を守る
まず、全体を通して敬体(ですます調)で記入すると、読みやすい文章になります。
「〜です。~である。」と文末が敬体と常体(〜である)が混ざってしまう文章は読みにくいです。文章全体を敬体にすることによって、読む方が読みやすい文章を目指しましょう。
例として、このように下書きを作成します。
| 骨組み | 骨組みの内容 | 例文(下書き) |
| 結論(アピールポイント) | 目標を達成するためには、自分たちで達成したい目標を決めることが大切 | 私はサッカー部の活動から、目標を達成するためには、自分たちで達成したい目標を決めることが大切だと学びました。 |
| 根拠 | 他人から与えられた目標では、自分たちが達成したいと思えない | なぜなら、他人から与えられた目標では、自分たちが達成したいと思えずモチベーションが上がらないからです。 |
| 具体例(エピソード) | サッカー部の目標は顧問が決めた「県大会出場」だったが、誰も達成したいと思っていない
部員で目標を決め直した 結果、自分たちで決めた「県大会出場」という目標を達成 |
サッカー部の目標は顧問が決めた「県大会出場」でしたが、あるとき部員に浸透していないことがわかりました。
自分はキャプテンとして、顧問に相談して話し合いの日を設けました。 自分たち部員で一から話し合って達成したい目標を決め直しました。 そこからチームの士気が上がり、県大会出場という結果を残せました。 |
| 結論(アピールポイント) | 目標を達成するためには「自分で目標を決めること」が大切 | 目標を達成するためには「自分で目標を決めること」や「なぜ自分は目標を達成したいのか」を考える必要があると学びました。 |
文章の論理展開やですます調を意識して、下書きを作成しましょう。
STEP4:第三者に添削してもらう
下書きを学校の先生や塾の講師などの第三者に添削してもらうことによって、より質の高い自己推薦書を書くことができます。
添削してもらうときは、以下のポイントを確認してもらいましょう。
- 誤字脱字
- 文法
- 言い回し
- 論理性(根拠の有無)
- わかりやすさ
下書きを添削してもらったら修正して、再度確認してもらうとよいでしょう。
STEP5:自己推薦書に清書する
添削後に修正したら、下書きを自己推薦書に清書します。
清書する前に、自己推薦書の書き方にルールがあれば、ルールを再度確認してください。ルールを確認したら、下書きの内容を丁寧に、かつ間違いがないように清書しましょう。
自己推薦書を書くときに気をつけたいポイント

自己推薦書を書く時に、以下のポイントに気をつけると質の高い自己推薦書になります。
- 自分のエピソードを具体的に書く
- 文章に一貫性をもたせる
- 卒業後の目標を考える
- 自分を高校に合格させるメリットを記載する
- 何度も添削してもらってブラッシュアップする
自己推薦書をこれから書く、という方は参考にしてみてくださいね。
自分のエピソードを具体的に書く
自己推薦書を書くとき、自分のエピソードをできるだけ具体的に書きましょう。
目標や結果などは数値を使って表したり、そのときに感じたことや考えたことを具体的に書いたりすることが大切です。自分のエピソードが具体的になればなるほど、自分のがんばりや経験からの学びが明確になり、他の志願者との差別化につながります。
文章に一貫性をもたせる
文章の内容に一貫性を持たせることによって、自分の主張の説得性が増すので、自己推薦書の評価が高くなります。
文章同士や段落同士の関係性が「並列」「対比」「因果」のどれに当たるか明確にすると、文章に一貫性が生まれます。構成を作るときに、段落ごとの内容をしっかり決めておくと、意味がまとまった文章を書きやすいですよ。
卒業後の目標を考える
まず高校卒業後の目標を考え、次に高校でやりたいことをイメージすると、志望理由が明確になります。
「どんな仕事につきたいか」「どんな大学に入りたいか」など、理想とする進路を考えてみましょう。将来の目標を達成するために「高校でしたいこと」を自己推薦書に書けると、根拠のある志望動機になります。
自分を高校に合格させるメリットを記載する
自分を高校に合格させると「どのようなメリットがあるか」を記載できると、他の受験生との差別化を図れます。
自分を合格させるメリットを記載するためには、高校の求める人物像を募集要項や入試説明会などからリサーチします。「自分は高校の求める人物像に近いこと」を記載した上で、自分の価値を提示しましょう。
何度も添削してもらってブラッシュアップする
学校の先生や塾の講師に何度も添削してもらうことで、自己推薦書の内容をブラッシュアップすることができます。
第三者に添削してもらうと自分で気づけなかった部分を修正でき、文法や日本語の使いまわしだけでなく、自分の主張やアピールポイントをわかりやすく伝えられるようになるでしょう。
自己推薦書の添削ならオンライン家庭教師ピースがおすすめ

自己推薦書を添削してもらうなら、オンライン家庭教師ピースがおすすめです。
オンライン家庭教師とは、自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンを利用して、オンラインで家庭教師の授業を受講できるサービスのことです。
オンライン家庭教師ピースの講師は、高校受験に精通しており、自己推薦書の適切な添削ができます。
さらにオンライン家庭教師ピースの講師は、本部教務によるマンツーマンの教育研修を受けているので、生徒の特徴に合わせた指導法を実践できます。また、筆記試験を受ける方向けに、学習スケジュールの管理も行っているので、受験勉強の進め方がわからない方にもおすすめです。
オンライン家庭教師ピースでは無料体験授業を実施しているので、気になる方は下記のリンクから申し込んでみてください。
オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業お申込みはこちらから
まとめ
中学生の自己推薦書は志望校に自己PRをするための書類であり、願書とセットで提出します。
自己推薦書を書く時は、自分の経験を整理して将来の目標を考えてから構成を作成し、下書きを添削してもらうことがおすすめです。先生や塾の講師など第三者に添削してもらうことによって、より質の高い自己推薦書を書くことができます。
さらに高みを目指し、受験のプロに自己推薦書を添削してもらいたい方は、オンライン家庭教師ピースも検討してみてくださいね。

















