いよいよ本番直前!受験生の冬休みの過ごし方|勉強、生活、親のサポートまで解説
冬休みが明けると、間もなく入試が始まります。受験生本人も親も「いよいよ本番だ」という気持ちになると同時に、「逆に何をすれば良いのか」と迷いやすいのも冬休みです。
受験前最後のまとまった学習時間である冬休みは、本番で1点でも多くとるための勉強を進めましょう。親御さんの役割は、お子さんを信じ、適度な距離感でサポートすることです。
この記事では、受験生の冬休みにやっておくべき勉強・教科ごとの学習ポイントも紹介、「冬期講習は受けるべき?」という疑問にも答えます。また生活面を中心に親にできるサポートも紹介しております。
いよいよ本番直前の冬休み、事前にしっかり準備をし、有意義に過ごしましょう。
全受験生共通!冬休みにもっとも注意すべきこと

中学受験・高校受験・大学受験…、すべての受験生に共通する「冬休みにもっとも注意すべきこと」は、次の4つです。
- 体調管理
- 感染症対策
- 健康的な食事
- 睡眠時間の確保
この4つをおろそかにすると、万全な状態で受験当日を迎えられなくなるおそれがあります。冬休みに生活習慣が崩れないよう、基本的なリズムに目を配りましょう。
基礎体力をつけ、体調を整える
体調管理の基本は、適度な運動とこまめなセルフチェックにあります。
受験勉強中は座っている時間が長くなりますが、1日に数回は適度な運動をはさむようにしましょう。基礎体力の維持と免疫力向上が期待できます。
運動は「動画を見ながらストレッチをする」「外を散歩する」などでOK!気分もリフレッシュでき、一石二鳥です。
また体調の変化を早めに察知するため、セルフチェックも心がけます。「おかしいな」「風邪かな」と感じたら、無理せずしっかり休むのが長引かせないコツです。
基本的な感染症対策を徹底する
新型コロナウイルスへの対策はもちろん、冬は感染症が流行りやすい季節です。
◎ 冬に流行しやすい感染症
- インフルエンザ
- ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルス)
- RSウイルス
手洗い・うがいなど、基本的な感染症対策を徹底しましょう。
また、受験直前に感染症と診断された場合の対応を確認しておくと安心です。追試や振替受験が受けられる場合もあります。
健康的な食事を3食とる
クリスマスや年末年始などご馳走が多い冬休みですが、受験生は食べ過ぎやダラダラ食べに気を付けましょう。
普段と変わった食事は胃腸を刺激し、消化不良の原因になります。また、食べ続けると生活にメリハリがなくなり、勉強の邪魔にもなってしまいます。
できるかぎり普段と同じ食生活を意識し、健康的な食事を心がけてください。
脳のエネルギー補給をサポートする豚肉、認知機能の低下を防ぐサバなどは、受験生におすすめの食材です。
夜更かしは控え、睡眠時間を確保する
学校がない冬休み中は、睡眠時間の乱れに要注意です。朝は学校がある日と同じ時間に起き、夜は遅くなりすぎないように就寝します。
理想の睡眠時間は、小学生は9時間・中高生は7~8時間といわれます。朝6時に起きると仮定すると、小学生は21時・中高生は遅くとも23時までにベッドに入るのが目標です。
受験生にとっては現実的ではない生活リズムかもしれませんが、睡眠時間を削ることがないよう気を付けましょう。
冬休みに入る前に!万全な受験勉強のための準備5つ
 冬休みは期間が短いため、始まってからあれこれと準備を始めるのは時間の無駄です。冬休み初日からロケットスタートが切れるよう、休み前には準備を完了させましょう。
冬休みは期間が短いため、始まってからあれこれと準備を始めるのは時間の無駄です。冬休み初日からロケットスタートが切れるよう、休み前には準備を完了させましょう。
では、受験生が冬休み前にしておくべき準備は、どのようなものでしょうか?5つの観点から解説します。
1. 冬休みに達成したい目標を決める
はじめに、冬休み明けになりたい姿、つまり「ゴール」をイメージします。そのゴールを何かしらの数値に置き換えましょう。それが「目標」です。
イメージのままだと漠然としており、何をすれば良いかつかみにくいため、数値化するのがポイントです。
「過去問で80点以上取れるようになる」「長文読解を10分以内で解けるようになる」など、できるだけ具体的に表現してみてください。
2. 受験勉強計画は逆算して立てる
次に、目標達成に向けた計画を立てます。コツは、逆算思考で考えることです。
受験までの残り時間は限られています。
「1 → 2 → 3 → 4 →…」と積み上げ式に勉強すると、途中で時間がかかると最終的に受験に間に合わなくなるかもしれません。
「10を達成したい!そのために→ 9 → 8 → 7 →…」とゴールからさかのぼるようにしましょう。
3. 勉強時間は「1日10時間」が目安
受験生の冬休みは、「1日10時間」の勉強が目安です。1日のなかでどうやって10時間をつくりだすか、シミュレーションしておきましょう。
朝からダラダラせず、スッと机に向かうと、勉強時間が増やせます。下に「1日10時間」の作り方例を紹介しました。
10時間=2時間×5セットと考えると、意外とできそうに感じませんか?
◎ 「1日10時間」の作り方(2時間×5セット)
| 7:30~9:30 | 勉強① | 朝食後はすぐ机に向かう。朝のダラダラを防止できる。 |
| 10:00~12:00 | 勉強② | お昼までにもうひと頑張り! |
| 13:00~15:00 | 勉強③ | 眠くなりやすいので、場所を変えるのもおすすめ。 |
| 15:30~17:30 | 勉強④ | 脳が疲れてくる時間、リスニングや作文練習も◎。 |
| 10:00~12:00 | 勉強⑤ | 1日の復習や明日の準備も忘れずに。 |
4. 勉強する教材やノートを準備しておく
計画どおりの勉強をスムーズに進めるために、勉強に必要な教材やノート、筆記具は冬休み前に用意しておきましょう。
「ノートがない!」「問題集がない!」と気づいた都度買いにいっていては、時間がいくらあっても足りません。
できるだけ勉強を効率良く進められるよう、必要なものはあらかじめ準備しておくことが大切です。
5. 冬休みならではのイベントも考慮する
冬休みはイベントが多い期間です。親戚の集まりや祖父母を訪問する機会もあるでしょう。イベントのために勉強できない日があることも考慮し、余裕を持ったスケジュールを組んでおきます。
全受験生必見!冬休みの学習のポイント

受験生の冬休みは、まとまった自主学習時間が確保できる最後のチャンスです。実戦を見据えて勉強の完成度を高めましょう。
どの受験生にも共通する、冬休みの勉強効率を上げるポイントを解説します。
学校の課題は早めに終わらせる
学校の宿題や課題は、冬休みの初日~数日以内に終わらせましょう。
学校の宿題は受験の有無や志望に関わらず、全員一律で同じものが出されます。受験本番とは傾向やレベルが合わない教材が与えられるかもしれません。
冬休みの始めに「宿題を終わらせる日」をつくり、サクッと完了させましょう。後半をじっくり受験勉強に充てられます。
とくに後回しにしやすい「書き初め」は、年内に済ませるのがポイント!やり残すと「やらなきゃ」と気になり続け、集中の阻害要因になります。
受験勉強は計画を立てて進める
冬休みは、10日~2週間ほどしかありません。短い期間にイベントや集まりがあるため、実質的に勉強できる日数はかなり限られます。
少ない休みを有効活用するために、かならず計画を立ててから受験勉強を始めましょう。
受験勉強の計画は「冬休み明けになりたい姿」をゴールとして設定し、その達成のためにすべきことは何か?と考える「逆算思考」で立てるのがポイントです。
塾の冬期講習や自習環境も利用する
塾に通っている受験生は、塾の冬期講習や自習室の利用もおすすめです。多くの受験生とともに、緊張感と熱気に満ちた空間で集中できます。
冬期講習は、志望校に合った講座を受けましょう。冬期講習は入試の過去問演習に取り組んだり、「本番で1点でも多くとるテクニック」を教えてもらえたりすることも多いため、志望校対策ができるコースでないと効果がありません。
実戦を意識した模試やテストを受ける
冬休み中には、入試本番を想定した模試やテストを受けておきましょう。本番の予行演習として、また教科ごとの時間配分練習にも役立ちます。
模試の成績返却が受験本番より後になる場合でも、受けておきます。受験後の自己採点で、未完成の問題や確認しておくべき箇所が見つかる可能性が高いからです。
模試を冬休み前半に受けると、後半を弱点の克服に充当できます。
冬休み中にすませたい受験勉強のコツ【中学受験生編】

冬休みが明けると、間もなく中学受験本番を迎えます。最後の仕上げ期ともいえる冬休み、中学受験に合格するためにはどのような勉強をしておくべきでしょうか。
3つの観点から、中学受験生の冬休みを解説します。
志望校の過去問に挑戦する
冬休みはかならず「志望校の過去問」に挑戦してください。冬休みの過去問学習は、次の流れで進めます。
◎ 過去問の進め方
- 各教科の時間配分を決める
- 制限時間を厳守し、決めた時間配分で解いてみる
- 答え合わせをして見直しをする
◎ 見直しのポイント
- 間違えた問題をやり直す
- 時間配分が適正だったか見直す
- 改善策を抽出する
過去問は当日の時間割と同じ時間に解いてみると、より実戦感が高まります。また見直しは問題のやり直しだけでなく、時間配分が適正だったかも振り返りましょう。
もし受験当日、午前と午後で2つの学校を受ける予定にしている場合は、それぞれの学校の過去問を1日で解きます。気力や体力がどれくらい必要か体験するリハーサルにしましょう。
暗記を完成させる
中学受験は算数で差がつくケースが多いため、必然的に算数に力を入れるご家庭が多いはずです。
しかし直前期にもっとも伸びるのは「暗記系」だといわれます。冬休みは暗記科目の完成にも取り組みましょう。
理科・社会は一問一答形式の学習が有効です。問題を聞いたら反射的に答えが出るまで反復します。
一通り学習し終わったら、「逆方向」のアウトプットにチャレンジしましょう。
Q. 江戸幕府の五代将軍・徳川綱吉が出した、動物を極端に保護する諸法令を何というか。
A.「生類憐(あわれ)みの令」
Q.「生類憐(あわれ)みの令」とはどのようなものか。
A. 江戸幕府の五代将軍・徳川綱吉が出した、動物を極端に保護する諸法令のこと。
用語を答えるだけでなく自分の言葉で説明できると、記述問題対策にもなります。
時事問題対策に入る
中学受験では時事問題も頻繁に出されます。冬休みを利用して、時事問題対策も進めましょう。
冬休み中は、「1年前~今年の上半期」までに起きたニュースを中心にチェックします。冬休みには入試問題はすでに完成していることが多いため、冬休み中の出来事が出題されるケースは多くありません。
こども新聞や参考書を活用し、“少しだけ前の”ニュースを把握してください。
単に出来事を覚えるだけではなく、その出来事が起きた背景や社会的な影響も踏まえると、面接にも役立つ知識になります。
冬休み中にすませたい受験勉強のコツ【高校受験生編】

高校受験生の場合、第一志望の学校・入試方式によって、冬休みにすべき勉強は変わります。公立高校の前期入試(特色選抜、推薦選抜)を受験する場合は、面接・小論文などの対策も必要です。
私立高校を受ける場合は、2月の試験に向けて過去問対策に力を入れなければなりません。
ここでは公立高校の一般選抜(3月入試)を第一志望とする受験生を主な対象とし、冬休みにやっておくべき勉強を解説します。
既習範囲の総復習をする
冬休みは、受験前最後のまとまった勉強チャンスです。既習範囲を計画的に総復習し、知識の抜け漏れがないかチェックしましょう。
入試では中1・2の範囲からもよく問題が出されるからです。中3の学習範囲を中心に取り組んできた受験生は、中1・2の範囲も復習しましょう。
◎ 入試頻出の中1・2範囲
- 数学:確率・場合の数、連立方程式、一次関数、図形の証明
- 理科:光合成、状態変化、圧力、酸化・還元、天気
- 社会:地理、歴史
学校から配られたワークの「まとめ」ページは、重要な要点がまとまっています。一つひとつの用語を「自分で説明できるか」という視点で確認してください。
苦手分野の対策を完成させる
冬休みは苦手分野を完成させるラストチャンスです。苦手分野が残っている場合は、冬休みに集中的に対策しましょう。
苦手分野を克服するには、「苦手になっている原因」までさかのぼり、丁寧に解明することが重要です。1対1形式で解説してもらえる教育サービスを利用し、本質の理解を目指してください。
オンライン家庭教師などを利用すると、自宅にいながらマンツーマン指導が受けられます。塾に移動する時間も勉強にあてられるため、一日を効率よく使えます。
私立高校の過去問に挑戦する
冬休みが明けるとまもなく私立高校入試がスタートします。冬休みには、受験予定の私立高校の過去問を2~3年分、解いておきましょう。
私立高校は学校ごとに異なる問題を出すため、かならず受験校の過去問に取り組みます。時間配分を決め、本番さながらの気持ちで取り組んでください。
見直しの際は、「できなかった問題のやり直し」に加えて、「時間配分が適正だったか」も振り返ります。もし配分ミスが合った場合は、修正し再度チャレンジしましょう。
「これなら大丈夫」と自信を持てる配分を見つけるのが成功のコツです。
冬休み中にすませたい受験勉強のコツ【大学受験生編】

大学受験生は、冬休みが明けるとすぐ共通テストが控えます。共通テストが終わるとすぐに私立大学入試が始まるため、冬休みは「本番で1点でも多く取る」対策を徹底的に行いましょう。
共通テスト対策パックに取り組む
冬休みには、「共通テスト予想問題集(共通テストパック)」に取り組みましょう。
共通テスト予想問題集とは、全教科・1回分の予想問題が収録された問題集です。共通テストと同じ形式・同じマークシートで、予想問題が解けるように作られています。
1つのパックには1回分だけが入っています。受験予定の科目を、試験当日と同じ時間割で取り組んでみてください。
解いた後にはかならず見直し、同じミスを繰り返さないように完成度を高めておきます。
共通テスト予想問題集は、河合塾と駿台、Z会が出版しており、パックごとに難易度や傾向が異なります。「河合塾⇒駿台⇒Z会」の順に難しくなるといわれているため、目標やレベルに合わせて選んでください。
時間配分を決めて過去問に取り組む
共通テスト、また1月下旬からはじまる私立大学入試に向けて、過去問にも取り組みましょう。時間配分を決め、決めた時間配分が適正かどうか確かめるつもりで解くことが大切です。
時間配分がうまくいかなかったら、改善策を練って再度取り組みましょう。
また大学入試は、毎年かならずといって良いほど「傾向の変化」が起きます。本番に見たことがない問題が出ても焦らないよう、過去問以外にもさまざまな問題に取り組んでおくことも大切です。
モチベーションが下がらないよう気を付ける
大学受験生の冬休みは、モチベーション管理も重要です。「もうすぐ本番」「共通テストまであと2週間」という焦りから、気持ちが落ち着かなくなり、やる気やモチベーションが不安定になりやすいからです。
不安を感じたら、これまで勉強してきた問題集やノートをすべて出し、机に積み上げてみてください。勉強してきた量が目に見えてわかり、「こんなにやってきたんだ」「きっと大丈夫」と安心できるはずです。
冬休みにやっておきたい受験勉強<英語>
 冬休みの英語対策は、実戦力を高める狙いで取り組みましょう。
冬休みの英語対策は、実戦力を高める狙いで取り組みましょう。
過去問や予想問題にも取り組み、まだ力が足りない分野を見つける学習も大切です。
受験生が冬休みにやっておきたい英語学習について解説します。
単語
冬休みは単語量を一気に増やすチャンスです。
これまでの積み重ねで、ある程度の量は覚えられているはず。冬休みはさらに語彙数を増やしましょう。
冬休みにおすすめの単語ジャンルは、次の3つです。
- 形容詞、副詞
- 類義語、派生語
- 熟語
この3つは他の単語と深く関連しているため、一定の語彙を習得できていると、連想ゲーム感覚で覚えていけます。
英文法
英文法は「曖昧な箇所、不安な単元の完成」を目指しましょう。不定詞・動名詞、関係詞、比較などの頻出単元は、念を入れて確認します。
入試頻出の空所補充問題を解く際は、「なぜその選択肢が正解なのか/正解ではないのか」を自分の言葉で説明できるレベルを目指してください。解説を流し読みするのではなく、自分で解説できるようになると、得点が一気にアップします。
長文読解
長文読解は本番と同難易度の題材に取り組みましょう。
高校受験生なら他県の公立高校入試問題もおすすめ。大学受験生なら共通テストの予想問題がぴったりです。実戦さながらに時間設定をし、制限時間内で解ききれるよう練習しましょう。
冬休みなら、英語は「直読直解」できるのが望ましいです。英文のはじめから止まらずに、構造をとりながら文意を理解する読み方を意識してください。文意が把握できれば、「和訳する」必要はありません。
長文読解の時短には、「パラグラフリーディング」もおすすめです。
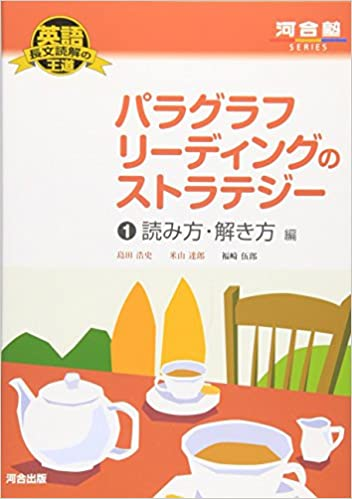 『英語長文読解の王道 パラグラフリーディングのストラテジー (1) 読み方・解き方編』島田 浩史|河合出版
『英語長文読解の王道 パラグラフリーディングのストラテジー (1) 読み方・解き方編』島田 浩史|河合出版
冬休みにやっておきたい受験勉強<数学>
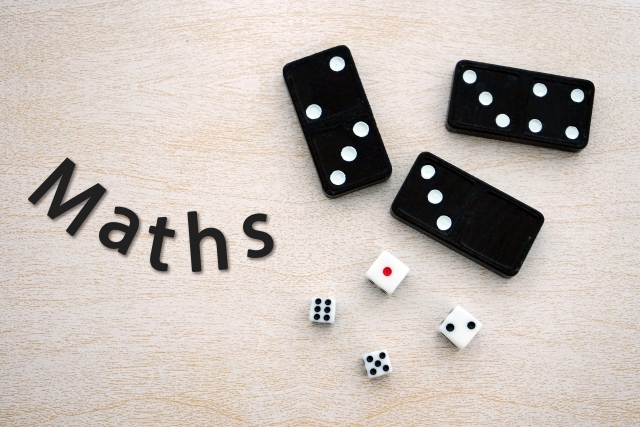 どの入試でも、数学で重視されるのは「基本の正しい理解」です。基本の正しい理解とは、教科書に載っている内容・定理を深く納得し、問題を解く際に使いこなせる力を指します。
どの入試でも、数学で重視されるのは「基本の正しい理解」です。基本の正しい理解とは、教科書に載っている内容・定理を深く納得し、問題を解く際に使いこなせる力を指します。
受験生の冬休みも数学は基本を大切に、良質な問題演習を繰り返しましょう。
基本計算
基本計算は、毎日のルーティンとしてかならず取り組みましょう。
計算問題は「反射神経」にたとえられます。問題を見た“瞬間に”解法が思い付き、手が勝手に動き出すことが大切なためです。
受験生の先輩の中には、「1日計算練習をサボったら、感覚が鈍った」といった人もいました。毎日20問程度で良いので、基本計算の練習を続けましょう。
関数
入試で出やすい「関数」分野は、徐々に取り組む問題のレベルを実戦にあわせていきましょう。
高校入試では「一次関数」に要注意です。一次関数は応用範囲が広く、バリエーション豊富な問題が作れます。実際入試でも、二次関数は小問として出されるのに対し、一次関数は文章題として大きな配点を占める場合も少なくありません。
共通テストでは新しいタイプの問題も増えています。融合問題にもなりやすいため、さまざまなパターンの問題演習に取り組んでおきましょう。
図形
図形分野は、基本的な定理をいまいちど確認しておきましょう。定理が成立する条件や、よく使われる場面も押さえます。
定理を間違って覚えていると、大問まるまる失点しかねません。
高校受験生は、作図のやり方も確認しておいてください。公立高校・私立高校とも、作図問題は頻出です。
冬休みにやっておきたい受験勉強<国語>
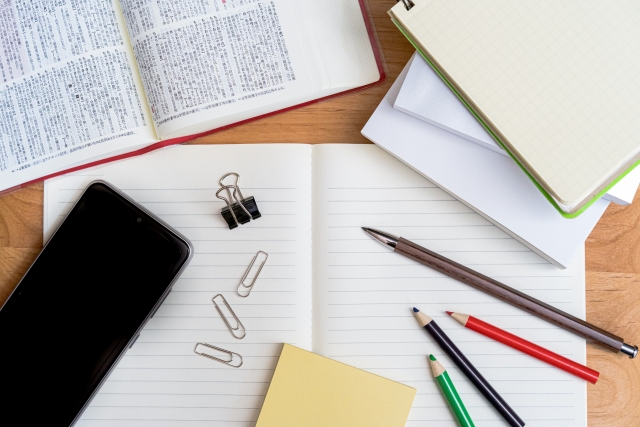 普段はどうしても英数が勉強の中心になる、という受験生も多いはず。時間がつくりやすい冬休みは、じっくり国語の読解問題に取り組みましょう。
普段はどうしても英数が勉強の中心になる、という受験生も多いはず。時間がつくりやすい冬休みは、じっくり国語の読解問題に取り組みましょう。
入試レベル相当の問題集を用意し、毎日コツコツと進めるのがおすすめです。
評論読解
評論文(説明文・論説文)は、解き終わって答え合わせが最重要です。単に「正解/不正解」をチェックするだけではなく、「自分は本文を“正しく”読めていたか」を確認しましょう。
やり方はとても簡単で、「問題の解説を熟読する」だけです。解説は読んでいるようで流し読みになっている受験生も多いため、ライバルと差をつけられます。
解説は、冒頭の「作品背景」「出題の狙い」から読み始めてください。その後、1問1問の解説を“選択肢1つずつ”、本文と照らし合わせながら読み進めます。
自分の解釈が間違っている箇所に気づいたら、「なぜ間違えたのか」原因を本文から探すようにしましょう。
古文読解
古文対策を完成させるポイントは「単語」と「本文解釈」です。古文単語は受験用の単語帳を使い、重要語句から確認します。とくに現代日本語と意味が違うことばは、解釈ミスを誘発します。ただしく押さえてください。
本文の解釈は、登場人物に印をつけながら、「誰が・何を・どうした」に注目して読みます。主語が省略されていたら、敬語や助動詞から推測します。
最後に必ず本文と解説の解釈を見比べ、自分が正しく読めているか確認してください。
漢字の確認
入試ではかならず漢字問題が出されます。冬休み中も隙間時間などをつかい、漢字を確認しておきましょう。
同音異義語や紛らわしい用法の漢字の使い分けは、入試でもよく狙われるポイントです。
冬休みにやっておきたい受験勉強<理科>
 理科は冬休みからでも逆転可能な教科です。「物理・化学・生物・地学」4分野それぞれの基本を再確認し、実戦問題演習に取り組みましょう。
理科は冬休みからでも逆転可能な教科です。「物理・化学・生物・地学」4分野それぞれの基本を再確認し、実戦問題演習に取り組みましょう。
もし苦手な単元があれば、克服できるラストチャンスです。
重要用語の総チェック
冬休みのできるだけ始めに、重要用語の総確認をしましょう。もし忘れていたり、理解があいまいだったりする用語が見つかれば、正しく覚え直します。
用語の再確認には、教科書や参考書の索引や確認用ページが便利です。太字の用語を中心に、全体を網羅しておきます。
計算問題
理科の計算問題には、数学とは異なるアプローチが必要です。小数の計算も正しくできること、単位を間違えずに扱えることなど、数学ではあまり意識しない作業が増えるため、スピーディーに処理できるよう練習しましょう。
計算問題だけを集めた問題集や、過去問の小問集合(問1)を反復するのもおすすめです。
考察問題
近年の入試は、実験や考察に関する問題が増えています。考察問題には「問題文が長く、情報の読み取りに時間がかかる」「グラフや表からデータを正しく読み取る必要がある」といった特徴があります。
慣れていないと「時間がかかる割に正答率が低い」結果になりかねないため、積極的にトレーニングしましょう。
考察問題は化学・生物分野によく見られます。化学・生物が苦手な受験生は、特に注意してください。
冬休みにやっておきたい受験勉強<社会>
 社会は直前まで伸びる教科です。これまであまり力を入れてこなかった受験生も、冬休みは社会に注力してみましょう。
社会は直前まで伸びる教科です。これまであまり力を入れてこなかった受験生も、冬休みは社会に注力してみましょう。
勉強すればするだけ得点に反映されやすいため、逆転合格を狙えるかもしれません。
重要用語の総チェック
社会も理科同様、重要用語の総チェックからはじめます。「地理・歴史・公民(政治・経済、倫理)」、3つの分野の重要用語を復習しましょう。
確認しておきたい点は、次の3つです。
- 意味を正しく理解できているか
- 似た用語と区別できているか
- 漢字で正しく書けるか(高校受験生)
資料の読み取り問題
思考力・判断力を重視する新しい学習指導要領の影響を受け、「資料を読み取る問題」が増えています。
見慣れない資料や馴染みの薄いテーマが与えられる場合も多いため、「根拠」を探しながら読み取る練習をしましょう。
問題にかかれている内容、また回答だと考えられる内容のいずれも、かならず資料中に根拠を探す癖をつけます。
記述問題
高校受験生、また個別試験で社会を使う大学受験生は、記述問題対策も必要です。
記述問題は「限られた字数に、必要な情報を、抜け漏れなく入れること」が重要です。書きたいことを端的に書けるよう、何度も練習しましょう。
書いた答案は塾の先生などに添削してもらいます。もし塾に通っていない場合は、オンライン家庭教師などを利用してみてください。自宅にいながら、マンツーマンで必要な指導を受けられます。
冬休みにやっておきたい受験勉強<その他>
 5教科の受験勉強以外にも、対策が必要な項目がある受験生も多いでしょう。小論文や作文、志願理由書などの準備も、時間がある冬休みに進めておきましょう。
5教科の受験勉強以外にも、対策が必要な項目がある受験生も多いでしょう。小論文や作文、志願理由書などの準備も、時間がある冬休みに進めておきましょう。
小論文・作文
公立高校の前期選抜(特色選抜、推薦選抜など)を受験する予定の中学生は、小論文や作文が課される場合があります。過去の出題傾向をチェックし、1~2本で良いので書いてみましょう。
小論文や作文は、いきなり書こうとしても失敗します。テーマを自分なりに解釈し、書く要素を洗い出して並べる「構成」を挟むと、グンと書きやすくなります。
小論文・作文の書き方について詳しくは、こちらの記事をチェックしてください。
「推薦入試の作文・小論文の練習手順!正しい書き方や今日からできる成功のコツも解説」
面接
面接の予定がある受験生は、冬休み中に「よくきかれる質問集」への回答を準備しておくと良いでしょう。
よくきかれる質問集は、インターネットで探すほか、学校の進路指導室でも見つけられます。過去に受験した先輩からヒアリングした質問集なので、より実戦的で志望校に即した内容が手に入ります。
自分の素直なことばで、質問に答えられるよう準備しましょう。
志望理由書
公立高校の前期選抜を受ける場合、冬休みがあけると「志願理由書」の準備が始まります。ただ冬休み明けは学校のテストがあったり、受験勉強も本格化させたりと忙しい時期とも重なります。
志望理由書は数回の書き直しが必要なケースがあるため、冬休みのあいだに「下書き」を済ませておきましょう。
志望理由書のフォーマットは、教育委員会ホームページからダウンロードできます。高校を志望した理由、高校で頑張りたいことを中心に書き、休み明けに学校の先生に添削してもらいましょう。
受験生の冬休みを支える親の心構え
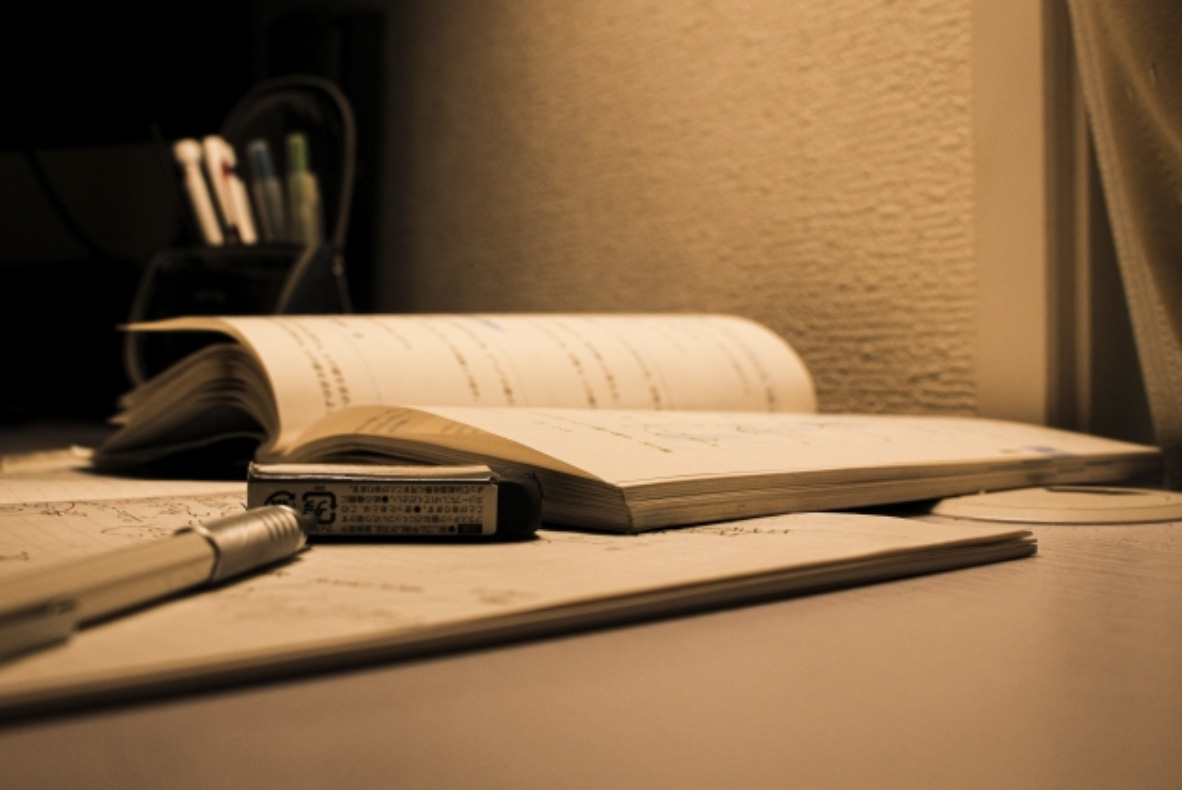
受験生がいる冬休み、親はどのようなサポートをすべきでしょうか。また勉強の邪魔をせず、しかし様子が把握できる適度な距離感とは、どれくらいなのでしょうか。
受験生を支える親ができる、冬休みのサポートを解説します。
規則正しい生活を意識させる
受験生はつい、夜遅くまで勉強に没頭しがちです。学校がない冬休みは起床のプレッシャーも少なく、夜型生活になりやすい点に注意しましょう。
「朝は学校がある日と同じ時間に起こす」「夜は必要な睡眠時間を見越し就寝させる」など、生活リズムを維持させる働きかけが重要です。
受験当日は、9時ごろから試験が始まります。朝から頭がフル回転できる状態にしておくためにも、規則正しい生活と睡眠時間の確保には気を配ってあげましょう。
消化のよい食事を用意する
体調を整え、感染症に対する免疫力を高めるために、食事は重要な役割を果たします。栄養が豊富で消化吸収のよい食事を用意してあげましょう。
旬の野菜や青魚には、脳に良い栄養がたっぷり含まれます。スープやあんかけで身体を芯から温める食事もおすすめ。デザートや軽食には、フルーツやナッツを用意しましょう。噛む動きが脳に刺激を与え、集中力向上が期待できます。
スマホやゲームの使い方ルールを決める
スマホやゲームは、受験生とはいえ気になってしまうお子さんもおおいはずです。冬休みに入る前に、使い方のルールを話し合っておきましょう。
受験生の中には、冬休みを機に「スマホ・ゲームを親に預ける」ケースも見られます。物理的に使えない状態にし、自分を追い込むのが目的です。
ご家庭ごと、親も子も納得できるルールを決めましょう。決めたルールは紙に書き、目につく場所に貼っておくと忘れません。
話し相手になる
家にこもり、誰にも会わずに毎日勉強勉強勉強……という受験生も多い冬休みです。いくら受験生とはいえ、部屋にこもってばかりでは気持ちが滅入ることもあるはず。
親御さんはぜひ、お子さんの気軽な話し相手になってあげてください。
話す内容は日常的なささいな話がおすすめです。降った雪に鳥の足跡が残っていた、朝日がキラキラ反射する朝もやがきれいだった、などで十分です。
一瞬でも勉強から離れられるとお子さんの気分もリフレッシュし、また意欲をもって勉強に向かえるようになります。
とにかく励ます
冬休み中の受験生は、親が思う以上に不安定です。ちょっとしたことで自信を無くしたり、落ち込んだり……、そんなときはとにかく「励ます」ことが大切です。
親からの「あなたなら大丈夫!」という言葉は、無条件にお子さんの心に残ります。自分の力を信じ、自己肯定感を高める原動力にもなります。
受験本番、最後の最後でお子さんを助けてくれるのは、「自分なら大丈夫」という自信にほかなりません。お子さんの強い自信を育むためにも、ひたすら励まし続けましょう。
冬休み中におすすめの受験準備

比較的時間の融通が利く冬休み中には、受験当日に向けての準備を薦めるのもおすすめです。冬休み中にやっておきたい受験準備を、4つ解説します。
志望校までの交通手段やルートを確認する
志望校、あるいは受験会場までの交通手段やルートを確認します。Googleマップなどで見るだけではなく、実際に足を運んでみるのがおすすめです。
降雪や悪天候、受験生で混み合うといったイレギュラーも想定し、準備しておきましょう。
初詣に行きお守りを買ってくる
お守りは気持ちのよりどころ・安心材料となってくれます。せっかくですから合格祈願をしてお守りを買ってきましょう。
元日の初詣は混み合うため、感染症の心配もあります。受験生の今年だけは混雑を避け、年が明けて3~4日経ってから行ってみてください。
友だちと勉強の進捗を報告しあう
代わり映えしない毎日が続くとメリハリがなくなり、勉強へのモチベーションが下がる懸念もあります。
LINEやチャットツールで適宜友達と勉強の進捗を報告しあうと、良い刺激になります。
また「Studyplus(スタディプラス)」「StudyCast(スタキャス)」などの学習管理アプリを活用すると、同じ目標に向かって頑張る全国の仲間と励ましあえます。
先輩の成功体験・失敗談をチェックする
先輩の体験談をチェックするのもおすすめです。成功事例は真似し、失敗談は糧となります。
思ってもみない体験をした先輩が多く、話を知っておくだけで心構えになるでしょう。
体験談はインターネットやSNSで見つかるほか、学校の進路室にストックされている場合もあります。
冬休みの受験勉強に塾の冬期講習は有効か
 受験生は、塾の冬期講習を受けるべきかどうか。
受験生は、塾の冬期講習を受けるべきかどうか。
まず、大学受験生には冬期講習は不要です。解説授業を受け、理解を深める段階はとうに終わっているからです。冬休みは共通テストに向けて、自分のペースで実戦演習を続けましょう。
塾は自習室として、あるいは質問する場所として活用してください。
高校受験生の場合は、自分の現状と冬期講習の内容を照らし合わせて受講するかどうか決めましょう。
「いま自分が困っている課題を解決するメニューがある」「志望校にピッタリの講座がある」等の場合は、有意義な冬期講習になります。一方で、自力でできる問題の指導を受けなければならない講座なら、受けても実力は伸びません。
受講を決める前に、冬期講習の内容をよく確認してみてください。
スポットの対策にはオンライン家庭教師おすすめ

冬休みは一つひとつの勉強を「完成度高く」仕上げることが最重要です。中途半端にやっても身につかず、本番前にかえって課題を残してしまいかねません。
冬休み中に解けない問題やわからない箇所が出てきたら、かならず冬休み中に解決しておきましょう。
自宅でマンツーマン指導が受けられるオンライン家庭教師なら、限られた時間を有効活用出来ます。塾に移動する必要もなく、勉強机に教材を広げたまま受講可能だからです。過去問の
解説や時間配分の相談など、必要な箇所をピンポイントでサポートしてもらえるのも魅力!
講師とお子さんとの相性をどこよりも重視するオンライン家庭教師ピースを、ぜひお試しください。冬休み開始と同時に指導を始められるよう、冬休み前の体験授業がおすすめです。
まとめ
冬休みになると、プレッシャーと不安におしつぶされそうな受験生が増えます。メンタルを落ち着かせるために、あえてぼーっとする時間をとったり、テレビを見て気分転換しようとしたりする受験生も少なくありません。
直前期の焦りは、お子さん本人が一番感じています。どうか、親御さんは不必要に焦らせることなく、ゆったり見守ってあげてください。お子さんはきっと、自分でまた勉強に戻っていきます。
勉強面で不安がある場合は、必要なサポートを適宜受けられるオンライン家庭教師の利用がおすすめです。「デバイスの画面越し」にやり取りをするため適度に距離感があり、不安定な受験生にはかえって心地よいという声もあります。
オンライン家庭教師ピースは随時無料体験を承っています。お気軽にお問い合わせください。
















