受験勉強は勉強計画表が重要!効率の良い立て方を現役国立医大生が伝授!
受験勉強を思いつくまま勉強している人は多いのではないでしょうか?ですが、受験勉強は、勉強計画表を作って勉強することが大切です。
なぜなら、計画表を手順に沿って作成していくことで、その週やその日にやるべきことが見えてきて、効率の良い勉強ができるようになるからです。
今回の記事では、計画表の作り方を解説していきます。ぜひ最後まで読み、自分に合った勉強計画法を選んで受験勉強に活用してみてください。
受験勉強に計画表が必要な理由
受験勉強は思い付きでやるのではなく、きちんと計画を立てて実行していくことが大切です。ここからは計画表が必要な理由を4つ解説していきます。
やるべきことを明確にするため
勉強計画法を作ることで、自分が今やるべき勉強が明確になります。このような目標を作っておくことで、効率的に勉強ができるようになります。
焦らずに勉強を進めるため
受験が近づいてくると、「本当に志望校に合格できるのか?」と焦りや不安が出てきてしまう受験生も多いのではないでしょうか?そんな人こそ、勉強計画表を作ることをお勧めします。
計画表に基づいて毎日勉強を続けていけば、自分がやってきたことが目で見て確認できます。そのため、入試に対する焦りや不安はなくなり、落ち着いた状態で試験に望めます。
勉強することを習慣にするため
なんとなく勉強をしようとすると、何をすればいいのかわからなくなって、結局ほとんど勉強しないという人も多いのではないでしょうか?
そんな時でも、勉強計画法があればその日に何をするかが決まっているため、計画に沿って勉強するだけでOKです。
毎日勉強しようと思っても勉強できず、勉強する習慣がない人はぜひ計画表を作成しましょう。
モチベーションをあげるため
勉強計画法があると、「今日はこれだけやった」、「今週はこれだけやった」というのが目に見えてわかるため、達成感が味わえます。思うように成績が伸びず悩んでいる人でも、計画表があれば、自分が前に進んでいることがわかりモチベーションが上がることにつながります。
勉強計画表を立てる前に知っておきたい大切なこと

勉強スケジュールの立て方を解説する前に、あなたにぜひ知っておいてほしい前提があります。
|
計画を一度立てると、何としても計画通りに進めないと!と計画に固執していませんか?
スケジュール通りに進めることを重視するあまり、ほんの少しでも計画とのズレが起きると計画を放棄してはいないでしょうか。
スケジュールは、その通りに進まないのが当然です。修正もつきものです。
スケジュールは目標(ゴール)を達成するための手段でしかなく、スケジュールを守ることが勉強の目的ではないことをあらためて確認しておきましょう。
効率的な勉強計画の立て方
ここからは勉強計画の立て方を解説していきます。手順に沿って考えて作成していくと、週や日の計画にまで落とし込むことができます。
手順①志望校を決める
志望校が決まっていたほうが計画が立てやすいです。まだ志望校が決まっていないようであれば、3年生の春夏くらいまではレベルが少し高めで使う科目が多い大学を志望校に仮設定しておきましょう。
また、この機会に自分が興味のある分野や学部について調べておくのもよいです。改めて自分に向き合うことで今まで気づかなかった自分の得意なことや好きなことに気づくかもしれません。それを基に志望校について調べてみましょう。
手順②志望校の入試情報収集と分析
最新の1次情報(大学公式サイト)などを見て収集しましょう。各科目の配点、共通テストと2次の配分、最低合格点、合格者平均点、共通テストの足切り点数、特徴的な問題形式、頻出の分野などの情報を調べてみましょう。
調べた情報をもとに、高1生や高2生の場合は入試で使う試験科目を中心に基礎を固めましょう。
高3生の場合は、試験科目をなんとなく全教科まんべんなく勉強すればいい、というわけではありません。調べた情報から見えてくる重要度を意識して教科や科目を細かく分析しましょう。
例えば、試験科目が英語、数学、理科2科目だったとします。すべて試験に使うからといってすべてに同じ勉強時間を費やしてしまってはいけません。もしこの中に特に苦手な科目があれば、その科目を克服できるように勉強時間を多めにしましょう。
また、一つの科目の中でも試験に多く出る分野とそうではないものを把握しましょう。
例えば、英語の入試問題が、長文問題が占める量が多い代わりに、英作文が簡単だったとしましょう。その場合は、長文の速読力を強化する勉強を多くする代わりに、英作文の勉強は必要最低限にするなどして効率の良い勉強を心がけましょう。
手順③目標点数と実力の差を埋めるために必要なものを洗い出す
調べた情報をもとに、一度過去問を解いてみましょう。
そして各科目何点届いていないか、何をすればその差は埋まるのかを考えましょう。
例えば、数学の場合目標点に届かない原因としては、「そもそも解法が思いつかなくて解けなかった」、「解法は思い浮かんだけれど、計算ミスをしてしまった」などが考えられます。
原因がわかれば、克服するための具体的な問題集や講座を選択しましょう。
基礎が固まっていないことが原因の場合は、どの教科も教科書レベルの問題集から始めましょう。
基礎ができるようになったら、入試典型レベル問題集を解き、最後に過去問に取り組みましょう。
計算ミスなどのケアレスミスが原因の場合は、自分のミスの傾向を探しましょう。例えば計算ミスの場合、同じような計算で間違っていることが多くあります。
よくミスをする計算に似た問題を中心に取り組むことで、ミスを克服できるようになります。
手順④年間計画を作成
やるべき勉強が全て見えたら、重要度や得意不得意などを考慮して、4月〜翌年3月の時期ごとの優先順位を決めていきましょう。年間計画をもとに月間、週間、一日の予定を決めていくので、しっかり作りましょう。
手順⑤月間計画を作成
作成した年間計画をもとに、月間計画を作っていきましょう。具体的であるほど実践しやすいので、科目別、分野別に詳しく作りましょう。
ポイントは勉強する科目に大きな偏りが出ないようにすることです。苦手科目や苦手分野があるからといってそればかりやっていては、得意科目だったものが出来なくなってしまいます。得意科目を伸ばしつつ、苦手科目を克服できるように勉強計画を立てましょう。
手順⑥週間計画を作成
作成した月間計画をもとに、週間計画を作っていきましょう。科目別、分野別に具体的に作りましょう。週の中で加減して計画を進めればいい人は、日ごとの計画を立てずにここまででもOKです。
ここでも月間計画と同様に得意科目と苦手科目の成績をどちらも伸ばせるようにバランスよく勉強しましょう。
手順⑦日ごとの計画を作成
1日単位でノルマをきっちり決めたい人は日ごとの計画を立てましょう。7日全部決めるのではなく、6日決めて1日を調整に使えるように計画を立てましょう。1日余裕があることで、6日間で終わらなかったものを終わらせることができ、計画をずらさずに取り組めます。
また、1日ごとの勉強計画を立てるときは、一つの科目を一日でやろうとしてはいけません。なぜなら、一つの科目を2時間以上続けて勉強すると頭に入らなくなると言われているからです。
これではせっかく勉強しても頭に入っておらず、勉強の効率が悪いです。そのため、2時間以上勉強する場合は、一日に複数の科目を勉強するようにしましょう。
具体的な勉強スケジュールの立て方

いよいよ、勉強スケジュールの立て方を具体的に解説します。
誰でもできる勉強スケジュールの立て方は、次のステップで進めます。
やるべき勉強内容をピックアップする
目標が決まったら、達成のために必要な勉強内容をピックアップしましょう。
勉強内容を的確にピックアップするには、次の視点で普段の勉強を振り返ってみてください。
目標にたどり着けそうかな? |
1つの英単語を覚えるのに3回の繰り返しが必要な人が、1週間後までに100個の英単語を覚えたい場合を例にしてみます。
| どの教材の | 普段使っている英単語帳の |
| どの部分を | 英単語100個分のページ数を |
| どのくらいのペースで | 1週間後に100個/覚えるのに3周必要 → 100語×3周=300語 → 300語分÷7日間=1日に42個ペース |
| 何回繰り返せば |
目標達成に必要な勉強内容は、目標によって異なります。
これまでの勉強を振り返りながら、じっくりピックアップしてみてください。
<勉強内容の精査は、実はとても難度の高いプロセスです。自分では難しいと感じたら、プロに相談するのもおすすめです>
ゴールから逆算して勉強に使える日数・時間を割り出す
次に、設定したゴールまでの残り期間を割り出しましょう。ゴールまでの「日数」「勉強可能時間」の2つを算出します。
勉強可能な時間まで算出するのは、意外と自由に勉強できる時間は少ないためです。
計画を立てているとき、私たちはつい気持ちがおおきくなり「これくらいいけるでしょ」「頑張ればできるって!」と安易にタスクを詰め込みがちです。
実はこれが、勉強スケジュールが“計画倒れ”する原因!
欲張りすぎた計画は初日から達成できず、やる気が一気に削がれてしまいます。
本当に勉強できる時間を算出し「余裕かな?」と感じるくらいの計画に抑えておくのが成功の秘訣です。
勉強できる日にやるべきことを割り振る
「勉強するべきこと」と、「勉強できる日数・時間」が明確になりました。
続いて「勉強できる日数・時間」に「勉強するべきこと」を割り振っていきましょう。
ここはある程度機械的に割り振って構いません。
計画はやりながら微調整していくため、はじめからパーフェクトでなくて良いのです。
「この日は部活があるから、重い勉強は避けよう」「土日は時間があるから、じっくりやろう」など、自分の予定とも相談しながら割り振ってみてください。
これで計画が完成です。
受験勉強の計画表の作り方のコツ
先ほど解説した手順を基に計画表を作っていきましょう。はじめは大変かもしれないですが、手順を踏んで作っていけば、後はそれに従うだけです。ぜひやってみてください。
余裕を持たせた計画を立てる
月や週の計画はギチギチに詰めずに、ところどころ余裕をもった計画にしましょう。(例えば、週間計画で1日は予備日にするなど)
余裕を持たせた計画を立てることで、体調不良は突発的な用事、思ったより勉強に時間がかかるなどの想定外なことに対応することができます。
計画通りに勉強できないことが焦りにつながってしまい、勉強を作業としてこなすようになってしまいます。それを避けるためにある程度余裕を持った計画を立てるようにしましょう。
毎日かならず進捗をチェックする
進捗とは「進み具合」を意味します。実際の進み具合と計画を照合し、予定通りに進んでいるか・調整が必要な箇所はないか、毎日チェックしましょう。
わずかな遅れも、早期発見できればすぐに修正できます。しかし遅れを放置すると、気づいたときにはすっかりスケジュールとズレてしまっていた、最悪のパターンでは目標達成が難しくなってしまいます。
迷ったら第三者にも相談しよう
自分をよく知る第三者、例えば学校の先生や塾の先生などに計画表を見てもらうのもおすすめです。学習のプロが客観的に判断してくれるアドバイスを、計画表に反映しましょう。
相談していく中で、自分では気づいていなかった勉強内容の偏りなどに気づくことができます。そしてより効率よくスキのない勉強計画が立てられるようになります。ぜひお願いしてみてください。
定期的に修正する
勉強の進み具合・遅れ具合や習得度などに応じて、その後の計画を修正していきましょう。先月の自分と今の自分は違っています。夏休みなどの長期休みも途中で修正をしてそのときの自分にフィットさせていきましょう。
また、模試の結果が返ってきたらそれをもとに計画を修正するのもよいです。模試は受けた時点での苦手分野などを明確に反映しています。そのため、ぜひ模試も活用してみてください。
勉強「量」を大切に
勉強計画を勉強「時間」で計画すると、机の前に座っているだけで勉強した気分になって、終わりの時間が来たらノルマが終わっていなくても切り上げてしまう人も多いのではないでしょうか?
そんな人は一日のノルマを「問題集を〇ページ」などと勉強する「量」を決めましょう。
定期的に成果を測る
勉強の成果を定期的に計測すると、勉強スケジュールがきちんとゴールに向かっているか確認できます。
- 暗記できているかセルフチェックする
- 自分で確認テストをする
- できなかった問題を解き直してみる
以上のような方法で、勉強がしっかり身についているかチェックしましょう。
もし目標に近づけていないと感じたら、計画を見直す勇気も必要です。
「勉強のやる気が出ない…」そんなときに試してみたい5つのテクニック
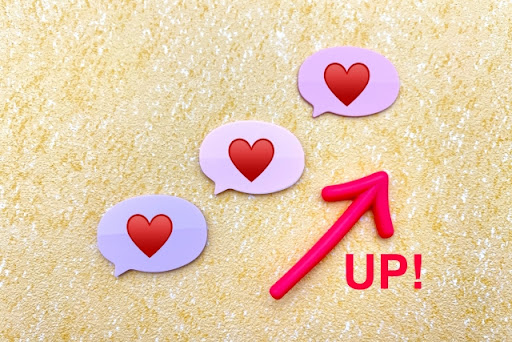
「どうも今日はやる気がでない」「勉強がなぜか手につかない」、そんな日は誰にでも訪れます。
とはいえ受験やテストは待ってくれませんから、やる気の有無にかかわらず勉強は進めなければなりません。
やる気がないときにモチベーションをあげてくれるテクニックを5つ、紹介します。
「ちょっとだけ」やってみる
今日やるべき勉強を思い浮かべて気持ちが萎えているときは、計画にある勉強のすべてをやろうとしないでください。
(もちろん、最終的には全部やりますよ。やる気を出すためのテクニックです。)
やるべきタスクがやる気を上回ると、人はやる気をなくします。
そこで「全部じゃなくていい、まずちょっとだけやってみよう」と視点を切り替えてみます。
「ちょっとだけなら……」と、気持ちが動くはず。
その瞬間を逃さずに、机に向かいましょう。
ほら、あんなにやる気がなかったのに勉強にとりかかれたでしょう?
簡単な内容から始める
「ちょっとだけ」「とりあえず」勉強を始める際は、いきなり難しい内容に取り掛からないことも大切です。
難しい問題演習からやろうとすると、脳が「ちょっとだけ(=軽いタスク)って言ったじゃないか」と反発し、すぐにやる気がなくなります。
まずは以下のような簡単な勉強から始めてみましょう。
- 知っている英文法を確認する
- 基本の計算練習をする
- 古文を音読する
- 理科・社会の重要用語を振り返る
どうしても勉強のやる気が出ないときは「机を片付ける」「ノートを新しくする」などでも構いません。
とにかく机に向かうことが大切です。
ルーティンをつくる
勉強にとりかかりやすくするために、ルーティンも作ってみましょう。
ルーティンとは決まった手順やお決まりの所作、日課などの一連の動作です。勉強を始める前の準備体操と考えてください。
勉強の前にやるルーティンを決めて習慣にすると、脳は「ルーティンをやったから次は勉強だ」とすんなり勉強にとりかかれるようになります。
ルーティンにする動作は、自分がストレスなく続けられるものなら何でも構いません。血行を良くするストレッチや勉強にとりかかりやすくする整理整頓などは、実益を兼ねる点からもおすすめです。
黙って30分続けてみる
机に向かったら、まず30分!黙って続けてみてください。
不思議なもので、15分を過ぎたころから徐々に集中力が高まってきます。「まだ5分か」「まだ12分か」と何度も時計を見ていたはずなのに、気付いたら30分、40分……と集中モードに入れます。
人間の脳は常に多くのことを考えているため、集中するまでには時間が必要なんだそうです。ずっと机に向かい続けるうちに徐々に思考が整理され、集中できるというわけです。
昨日できたことを数え上げる
どうしてもやる気が出ないときは、昨日できたことをできるだけたくさん数えてみてください。意外とあるはずですよ。
できたことを自覚すると、自己肯定感が高まります。自己肯定感は「自分ならできる」「もっとできる」という気持ちを生み出してくれるため、やる気を起こしやすいのです。
小さなことでも構いません。
自分が「できた」と感じたことにフォーカスしてみましょう。
「勉強に集中できない…」そんなときに試してみたい6つのテクニック

「机には向かっているが、どうしても集中できない」「すぐに集中が切れてスマホを触ってしまう」、そんな悩みを持つ受験生におすすめの集中テクニックを紹介します。
どれも気軽にできるものばかりです。ぜひ今日から試してみてください。
ポモドーロ・テクニック
ポモドーロ・テクニックとは忙しい社会人に人気の時間管理術です。生産性を高め効率良くタスクを進めることを目指しています。
ポモドーロ・テクニックは「25分」の作業と「5分」の休憩をワンセットにして繰り返します。集中力が高まると同時に、やり切った達成感も得られ、また続けてやりたくなるメリットもついてきます。
ポモドーロ・テクニックを実践する際は、時間を測れるタイマーを用意しましょう。スマホのタイマーでも構いませんが、ポモドーロ・テクニック専用のアプリを使っても便利です。

引用:Focus To-Do: ポモドーロ技術 & タスク管理|App Store
瞑想
瞑想は心の雑念を取り払い、集中しやすい精神状態に導くのに役立ちます。また気持ちが落ち着くためポジティブになり、自信が持てるようになります。
瞑想はさまざまなやり方があるため、自分のやりやすいようにやって構いません。椅子に座ったまま、あるいは床にお尻をつけて、リラックスできる姿勢で始めましょう。
5分ほど目をつむり、深呼吸するだけでもOKです。
慣れないうちは瞑想用のアプリを利用し、音声ガイドに従ってやってみるのもおすすめです。睡眠導入として使えるものもあり、夜ぐっすり眠れず疲れが取れない人もぜひ試してみてください。

引用:Meditopia: 睡眠・瞑想・マインドフルネス|App Store
運動
運動はドーパミン(やる気や幸福感などに影響する神経伝達物質)を分泌させます。ドーパミンのおかげで感覚が研ぎ澄まされ、集中力が高まるそうです。
また運動は判断力や注意力、記憶力にも良い影響を与えることが分かっています。
「頭がすっきりしない」「なんとなくやる気がでない」人は、勉強の前に軽い運動をしてみましょう。
新鮮な空気を吸い込めるウォーキングやジョギング、室内でできるストレッチや体操はとくにおすすめの運動です。
スマホの電源を切り、別の部屋に置く
スマホは勉強中の調べものに役立ちますが、一方で集中の最大の敵でもあります。
私たちの脳は、実は「スマホがそこにあるだけ」で集中力が低下します。「どうも気になってしまう」のは気のせいではなく、事実です。
思い切ってスマホは電源を切り、別の部屋などすぐには手に取れない場所に移してしまいましょう。たったそれだけのことで、驚くほど集中できるようになります。試してみてください。
机と椅子の高さを調整する
見過ごしがちですが集中力を高めるために大切なのが「机と椅子の高さが身体に合っていること」です。
椅子に座ったときに机の高さが低いと、前かがみの姿勢になります。背骨や肩、腰に負担がかかり、集中力が続きにくくなるのです。
いつも集中できない場合は、机と椅子の高さを見直してみてください。
昇降式の机や高さ調整ができるチェアは、簡単に高さを合わせられ便利です。座るだけで正しい姿勢をキープできる椅子もチェックしてみてください。
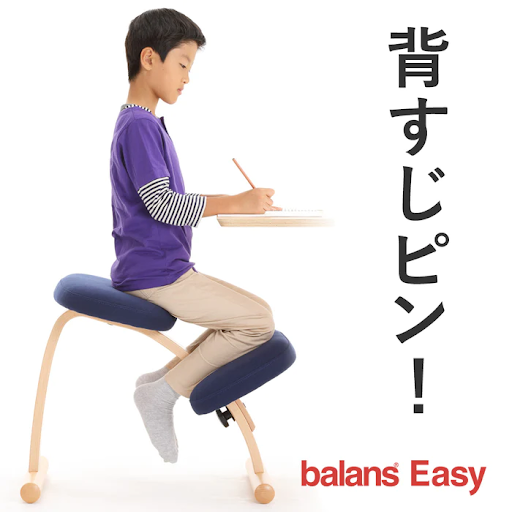
引用:ラクに姿勢がよくなる椅子「バランス イージー」|バランスラボ
モヤモヤを書き出してみる
「ちょっと気になることがあって、集中できない」「気持ちがモヤモヤして落ち着かない」、そんなときはモヤモヤを書き出してみましょう。
紙に書き出すと、モヤモヤを客観視できるようになるため気持ちが穏やかになります。書き出すうちに思考が整理され、いつのまにかスッキリしている効果も期待できます。
A4の白い紙と書きやすいペンを用意し、心を無にして思い浮かぶ言葉をどんどん書いていってください。紙が足りなくなったら裏面や2枚目に進みます。
あるところで「ふっ」と気持ちが軽くなる瞬間があるはずです。そうしたらこちらのもの、気持ちすっきりと集中できるようになります。
書いた紙を丸めてゴミ箱に捨てるまでをセットにすると、さらに前向きになりますよ。
自分だけの計画表に沿って勉強を進めよう
先ほど解説した手順をもとに計画表を作れば、どの友人とも違った、自分だけの勉強計画表ができあがるはずです。自分と向き合ってじっくり考えて作成した計画表をもとに、柔軟性をもって計画をこなしていきましょう。
食事、休憩、睡眠もきちんとスケジュールに入れて、無理せずこなせる現実的な計画にしましょう。
勉強スケジュールはアウトソーシングもおすすめ!オンライン家庭教師ピースへ

勉強スケジュールを立てるのは、難しくはありません。
ゴールを設定し、いつまでに・何をやるべきかを整理するだけです。
しかし実際にやってみると、言うほど簡単ではないとわかります。スケジュールを立てるのに時間がかかり、勉強する時間がなくなるという本末転倒を経験する人も多いのです。
そこでおすすめは「勉強スケジュールをプロに立ててもらう」方法です。プロに計画を立ててもらえば、高品質な計画がすぐに手に入ります。
自分は勉強だけに専念でき、時間を効率良く使えるようになります。
たとえばオンライン家庭教師ピースは、一人ひとりにピッタリのオーダーメイド計画を立案してお渡しします。受験勉強やテスト勉強はもちろん、「苦手克服計画を立ててほしい」「長期休みの宿題を終わらせる計画を立てて欲しい」などの要望もOK!
立案した計画に沿って勉強が進んでいるか、計画に修正が必要な箇所はないかなど進捗確認もついてきます。
自分のペースで勉強しやすい自宅受講スタイルも人気の秘密です。
まずは勉強スケジュールに関する悩みをお聞かせください。専任の教務と採用率5%の難関をくぐりぬけた講師が、最適な計画を考えます。
オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業申込はこちらから
まとめ
受験勉強は思いつくままに勉強するのではなく、計画表にもとづいて効率的に勉強することが大切です。勉強計画を立てるためには、志望校の情報収集と、自分の今の実力の把握が必要不可欠です。
自分の志望校の過去問や模試を活用して情報を集めて計画を立てましょう。勉強計画を立てるときのコツは、余裕を持った計画にすること、学校の先生など第三者にアドバイスをもらうこと、計画を定期的に修正することです。
また、勉強計画は勉強「時間」ではなく、勉強「量」を決めるようにしましょう。これらを実践していけば、自分だけの勉強計画が立てられるはずです。それをもとに勉強していけば、志望校合格は必ず近づいてきます。頑張ってください!応援しています!
















