発達障害の子の習い事が続かない!理由や選ぶポイント・おすすめの習い事とは
「発達障害の子の習い事が続かない原因は?」
「発達障害の子の習い事を選ぶポイントは?」
発達障害の子を育てる親御さんの中には、このような疑問をもつ人もいるのではないでしょうか。
この記事では、発達障害の子の習い事が続かない理由について徹底解説します。習い事を選ぶ際のポイントや、親の心得も具体的に解説します。発達障害の子におすすめの習い事も紹介しますので、習い事が続かずお悩みの親御さんはぜひ参考になさってください。
発達障害の種類と特性

発達障害は、生まれつき脳の働き方が違うために、行動面や情緒面で特徴がある状態の総称です。対人関係や集団行動で困難を感じやすく、周囲の理解と適切なサポートが欠かせません。
はじめに、「発達障害」とはどのような症状をいうのか振り返っておきましょう。
自閉スペクトラム症
かつては自閉症やアスペルガー症候群など、細かく分けられていましたが、現在は「自閉スペクトラム症」の名称で統合されています。具体的な症例はお子さんによってさまざまですが、大きく次の2点が特徴的な症状です。
- コミュニケーション能力の困難さと社会性の低下
- 独自のこだわりがあり、社会適応に困難
具体的には、「空気を読んだ会話が苦手」「表情から気持ちを察するのが苦手」といった症状が表れます。
ADHD(注意欠陥多動性障害)
ADHDは「不注意」と「多動・衝動性」が特徴的な発達障害です。小中学生の3~7%程度が持つと見られ、活動に集中して取り組む場面や、じっと話を聞く場面などで困難を感じやすいといわれています。
ADHDの診断は、不注意や多動・衝動性が家庭や学校など障害となっていることが条件で、行動観察により医師が判断します。
LD(学習障害)
LD(学習障害)とは、知的な遅れはないものの、読み書きや計算などの学習で特異的に困難を感じる発達障害です。学習障害には、読字の障害・書字障害・算数障害の3タイプがあります。
まだ理解が浸透しているとはいえない障害でもあり、「サボっているだけ」「やればできるはずなのに」と無理を強いられることもあります。ADHDや自閉スペクトラム症を併発するケースも多く、学習面・生活面ともに総合的な支援が欠かせません。
発達障害の子どもが必要とするサポート
発達障害は脳の機能障害に起因するため、本人の努力だけではどうにもならない場面もたくさんあります。ただ見た目では発達障害だと分かりにくく、偏見や誤解に苦しむお子さんも少なくありません。
発達障害のお子さんには、集団生活や社会生活に適応できるよう次のようなサポートが行われます。
- 指示は短く、具体的に
- 個別に声をかける
- 特性に応じてやりやすい環境を整える
- イラストや絵などで見える化する
- 活動時間とじっとする時間のメリハリをつける
発達障害の子の習い事が続かない理由とは?

発達障害の子の習い事が続かないと、親も心配になりますよね。習い事が継続できないのは、抱える特性によりさまざまな理由があります。ここでは、発達障害の子の習い事が続かない理由について具体的に解説します。
子どもの趣味に合わない
発達障害の子の習い事が続かなかった理由は、子どもの趣味に合っていなかった可能性があります。親の希望で習い事をやらせた場合にありがちです。
発達障害の子は白黒はっきりした考え方をする傾向をもつ子が多いです。好きなものには時間も忘れて打ち込みますが、興味のないことはさっぱりやろうとしません。
普通の子でも好みではない習い事は続かないでしょう。特性のため、好き嫌いがはっきりしている発達障害の子ならなおさらです。子どもの趣味に合わない習い事は、興味を持つどころかますます嫌いになってしまうでしょう。
難易度が合っていない
習い事の難易度が合っていないと、発達障害の子は習い事を続けようと思わないでしょう。上達が難しいと思えば、手をつけない子が多いためです。
発達障害の子は勝ち負けにこだわりをもつ子も多く、自分には難しいと思うことはやろうとしません。すぐあきらめるので、努力して達成する楽しさを経験していない子も。習い事の難易度が高すぎると、心が折れてしまい、うまくなるまで続けようとは思えないのです。
ペースが合っていない
発達障害の子にペースが合っていないと、習い事も続かないでしょう。周りと歩調を合わせるような習い事は、発達障害の子にとってつらいためです。
発達障害の子は特性により、行動や理解に時間がかかる場合があります。人よりゆっくり取り組めばできることでも、友達や先生に合わせて行う習い事ではできないかもしれません。取り組むペースが合わないと感じれば、続かないのは当然なのです。
発達障害の子の習い事を選ぶ際のポイント

発達障害の子の習い事は、ポイントを押さえて選ぶと長続きしやすいです。努力が結果につながる経験を積ませるためにも、取り組みやすい習い事を選んであげましょう。ここでは、発達障害の子が取り組みやすい習い事を選ぶポイントについてくわしく解説します。
親がやらせたいものを選ばない
発達障害の子の習い事は、親の希望だけで選ばないのが鉄則です。人からやらされるのが嫌いなので、押し付けられた習い事では長続きしません。
「小さい頃に習っておいたほうがよい」と、子どもに取り組ませたい習い事がある親御さんもいるでしょう。しかし、発達障害の子は興味の幅が狭く、好きなもの以外はやろうとしない場合も。そのため、親の選んだ習い事が向かない場合も多いのです。
また、特性により大人の指示に従うのが苦手な発達障害の子もいます。勝ち負けで物事を考えるので、指示を受けるのは負けと感じるのでしょう。親から押し付けられた習い事では拒否する可能性があるのです。
子どもの好きなことから選ぶ
発達障害の子の習い事は特に、子どもの好きなことから選ぶと長続きしやすいです。興味のあるものに没頭する特性をうまく利用するのがポイントです。
発達障害の子は好きな分野がはっきりしている場合があります。パソコンやレゴ、お絵描きなどマイペースでできるものを好む子が多いです。プログラミング教室や絵画教室など、興味のある分野の習い事を選ぶと、本人も納得して続けられるでしょう。
教室の規模に注意する
教室の規模は、大きすぎない方が良いです。
大規模な教室は、お子さんの緊張感を高め、また注意が散漫になる原因にもなります。周囲の音に過敏なお子さんなら、大勢の子どもたちが集まって騒ぐ雰囲気だけで、拒絶してしまうかもしれません。
発達障害のお子さんには、可能な限り小規模な教室がおすすめです。あわせて、指導形態もチェックしましょう。マンツーマンなのか、少人数なのかなど、同じ習い事でも教室によって指導スタイルはさまざまだからです。
お子さんの特性と合う習い事をチョイスする
発達障害のお子さんは、好きなこと・興味があることには周囲が驚くほどの集中力を見せることがあります。得意を伸ばし、自信をつけるためにも、お子さんの特性と合った習い事を選ぶことが大切です。
また、未経験のジャンルでも「好きになれそうなこと」ならチャレンジする価値はあります。もし習い事で好きなことが見つけられれば、お子さんはどんどん頑張れるようになり、意欲もわいてくるでしょう。
発達障害に理解がある教室・先生を選ぶ
発達障害に理解がある教室や先生を選ぶことも大切です。教室見学や体験授業の際は、お子さんが発達障害であることを正直に伝え、十分な受け入れ態勢があるか確認しておきましょう。また過去に発達障害のお子さんを預かった経験があるかを尋ねても参考になります。
発達障害に理解がある先生がいれば、集団行動が苦手でもチームプレイで活躍できる場を作ってくれるかもしれません。また唐突な行動もむやみに叱らず、お子さんに分かるように諭してくれる指導も期待できます。
サポートブックを作る
習い事には、お子さんの「サポートブック」を渡しておくのも効果的です。サポートブックとは、お子さんの症状や特徴的な行動、関わる際の注意点などをまとめたメモのこと。初めてお子さんに関わる方でも、特性を把握し、お子さんに合ったコミュニケーションを取ってもらうのに役立ちます。
発達障害のお子さんは、「普段と違う」ことに敏感です。新しい環境でもいつもと同じかかわりが受けられると安心し、適応しやすくなります。
体験できるところを選ぶ
習い事は体験できるところを選ぶと、子どもに合っているかがわかります。実際にやってみると、子どもに合うかどうか判断しやすいでしょう。
発達障害の子は未体験のことを想像するのが苦手です。習い事をやってみたいと始めても、実際にやってみたら合わない可能性もあります。費用を無駄にしないためにも、体験レッスンを受けてから入会を決められる習い事がおすすめです。
合わないと感じたらすぐやめる
もしも習い事が合わないと感じたら、やめても大丈夫と子どもに伝えましょう。つらい思いをし続けるより、他の習い事を始めたほうが本人のためです。
発達障害の特性のため、一度始めたことをやめてはいけないと思い込んでいる子もいます。やめると負けだと考えてしまうのでしょう。好きな分野でも先生との相性やペースが合わないなど思っていたのと違う場合があります。
発達障害の子の習い事で親が心得ておくべきこと

子どもに合う習い事を始めたあとも、心配や不安を抱える親御さんもいるでしょう。習い事への考え方を変えると気持ちが楽になりますよ。ここでは、発達障害の子の習い事で親が心得ておくべきことを解説します。
合わないことを続けるのは親も子も苦痛
合わない習い事を続けるのは、親も子も苦しいものです。子どもに合わないと感じたら、思い切ってやめることをおすすめします。
発達障害の子を抱える家庭は、普段からストレスが多いもの。合わない習い事で消耗するよりは、見切りをつけたほうが楽になるでしょう。
早くやめるほうが経済的にもいい
合わない習い事は早くやめるほうが経済的です。長く続けるとわかることもありますが、発達障害の子は成果がはっきりわかる習い事のほうが続けやすいです。合わない習い事を無理に続けるのはお金の無駄であり、もっと子どもの役にたつことに使ったほうがよいでしょう。
継続に意味があると思わなくていい
習い事を続けることにこだわらなくても大丈夫です。発達障害をもつ子のペースに合わせて習い事を見直してよいと考えると楽になります。
「石の上にも三年」ということわざがあるように、苦しいことでも長く続ければ成果が出ると考えがちです。しかし、子どもが苦しい思いをし続けるのに意味があるでしょうか。普段から疲れやすい子の負担を減らすためにも、習い事の継続にこだわらないほうがよいのです。
発達障害の子におすすめの習い事

「発達障害の子に合う習い事がわからない」とお悩みの親御さんもいるでしょう。発達障害の特性に合うものを選べば楽しく取り組めますよ。ここでは発達障害の子におすすめの習い事を紹介します。
プログラミング
パソコンが得意な子にはプログラミング教室が合うかもしれません。ゲーム作成など、自分の考えを作品にする方法が学べ、発達障害の子にぴったりの習い事です。
発達障害の子には、国語より算数が好きなタイプが多い傾向です。登場人物の気持ちを想像するより、方程式など決まった解き方のあるほうが理解しやすいのでしょう。プログラミングは自分で指示を出せば思った通りに動かせるのでわかりやすいです。
プログラミングは個人で取り組めるのも発達障害の子に合っています。作った作品を友達に見せるなど、コミュニケーションにも使えるでしょう。
英語
英語も発達障害の子におすすめの習い事です。日本語より英語を好む子もいるので、英語力を高めたほうがよいかもしれません。
数字が好きな発達障害の子もいますが、同時にアルファベットの形が好きな子も多いです。ひらがなと比べて直線的ではっきりした形なので、発達障害の子の興味を引くのでしょう。英語教室に通い、アルファベットから英単語、会話など興味を広げられる可能性も。
日本語に興味がない子でも英会話を通して、日本語訳を見ることで日本語の力が伸びる可能性もあります。
ピアノ
ピアノも音感がよいタイプの発達障害の子におすすめの習い事です。個別レッスンの教室を選べば、集団行動が苦手な子でも自分のペースで練習できるでしょう。
ピアノが弾けると学習発表会など学校行事での演奏を任されることがあるかもしれません。みんなに能力を認めてもらう良い機会となるでしょう。
スイミング
水の好きな発達障害の子には、スイミング教室がおすすめです。自分の目標に向かって取り組めるので、マイペースな発達障害の子に合っています。
自閉スペクトラム症の子など、水の流れを体で感じたり、キラキラ光る水面を見たりするのが好きな子も多いです。身体を動かすのが好きなADHDの子にも、体力を使うスイミングはぴったりです。
泳げるなら自分の目標に向かってマイペースに練習するとよいでしょう。顔をつけるのが怖い子には無理をさせず、発達障害に理解があり楽しく活動できる教室を選びましょう。
ダンス・リトミック
ダンスやリトミック(音楽に合わせて身体を動かす運動)もおすすめです。発達障害の中でも、ADHD(多動・衝動性)の強いお子さんにはピッタリでしょう。じっとしていられない、動かずにはいられないという特性を存分に活かせます。
ダンスがおすすめの理由は、ほかにもあります。
- 先生を見て真似る力(見る力)が育つ
- 柔軟性や体幹が育つ
- 身体を思った通りに動かす力が育つ
発達障害のお子さんが苦手としやすい複数タスクの同時処理や、ボディイメージの育成にもダンスは有効だといわれています。
ダンス以外にもバレエやチア、フラなどもおすすめです。
公文
発達障害の程度や特性にもよりますが、公文もおすすめの習い事です。公文と発達障害の相性が良い理由は、次の3つです。
- スモールステップ構成なので達成感を得やすい
- 無学年式・自学教材なので自分のペースで進めやすい
- 得意を伸ばし、相対的に苦手を小さくしやすい
公文の教材は、学校の進度とは無関係に「得意な科目はどんどん先取り・苦手な科目はさかのぼって」学習できるよう作られています。一人ひとりの習熟度や得意不得意、ペースに合わせて進められるので、能力の凹凸が大きい発達障害のお子さんでも取り組みやすいのです。
得意を伸ばし、苦手を相対的に小さくしたい方にもおすすめです。
通信教育
発達障害の子に勉強系の習い事をさせるなら、通信教育も合っています。自閉スペクトラム症など計画どおりに課題をこなすのが得意な子にはぴったりです。タブレット教材を利用すれば、イメージのつかみにくい図形の学習なども、アニメや動画でわかりやすく学べるのもメリットです。
しかし、ADHDなど計画的に学習できないタイプの子では教材をためてしまう可能性も。そこでおすすめなのがオンライン家庭教師です。オンライン機器を通した対面学習なので、発達障害の子でも計画的に勉強できます。
オンライン家庭教師なら、発達障害の子への指導実績が豊富なオンライン家庭教師ピースがおすすめです。豊富な講師陣の中から、お子さんと話が合いそうな先生をマッチング。信頼関係を大切にしながら学習を進めていきます。
また、学校の授業でわからなかった部分をリアルタイムで聞けるのはオンライン家庭教師の強みです。わからない部分を質問できるのは、学習面の不安を抱える発達障害の子にとって心強いですよね。
ピースでは無料体験学習を受付中です。発達障害のお子さんに合うかどうか確かめてから、受講を決められるので安心です。発達障害の子の習い事をお探しなら、ぜひ無料体験学習にお申込みいただき、ピースのよさを実感してください。
芸術系
発達障害と芸術系の習い事も、相性が良いといわれます。お絵描き教室や造形教室、工作などは、自由度が高く、どのような発想や工夫でも否定せず受け入れてくれるからです。個性的な発想が出やすい発達障害のお子さんほど、創作意欲がかき立てられることもあります。
芸術系の習い事がおすすめの理由は、ほかにもあります。
- 指先のトレーニングになる/li>
- 伸び伸びと取り組める
- 集中したいときは存分に集中できる
お近くに芸術系を習える教室がない場合は、オンライン受講もおすすめです。オンラインなら、ご自宅のいつもの環境でリラックスしながらレッスンを受けられます。
書道
書道は落ち着いて字を書く経験を積めるので、発達障害の子におすすめです。鉛筆で書くのが苦手でも、筆なら書きやすいと感じるかもしれません。
普段使う鉛筆は発達障害の子にとって軸が細い場合も。指先の細かい動作を求められるので書くことに疲れてしまう子もいます。その点、筆は鉛筆より太く、字も大きく書くので楽しいと感じる子も多いです。
短時間の集中で作品が仕上がるのも、上達を感じやすく発達障害向けです。集中力も養え字の形も覚えられるので一石二鳥です。
発達障害のお子さんが習い事をするメリット

発達障害を持っていると、学校や集団で遅れたり、困難を感じたりする場面が人並み以上に多くなります。結果的に勉強面・運動面で苦手意識が根付いてしまうことも多く、自己肯定感が下がってしまうことも。
しかし、誰にも負けない個性を持つお子さんが多いのも、発達障害ならではの特徴です。苦手ばかり注目せず、良さを伸ばすために習い事を活用してみましょう。
発達障害のお子さんが、習い事を通じて得られるメリットを3つ解説します。
達成感や自己肯定感が得られるチャンスになる
習い事は、「これまでできなかったことができるようになった!」と達成感が得やすい点がメリットです。達成感はやがて自己肯定感になり、大きな自信となってくれるでしょう。
習い事選びでは、お子さんができるだけ頻繁に・回数多く達成感を得られるよう、お子さんが得意なジャンルから選定してあげましょう。
幅広い人間関係やコミュニティを学べる
習い事には、さまざまな学校から子どもが集まります。先生とも毎日顔を合わせるわけではありません。学校とは違った環境に身を置くことで、人間関係やコミュニケーションを学べる点も、習い事のメリットです。周囲の人との適度な距離感を知り、挨拶や礼儀作法を学び、社会性を育てるきっかけになってくれます。
また習い事のメンバーとは、深い人間関係を築かなくて良い点も発達障害のお子さんたちが居心地よく感じる理由かもしれません。万一、何かトラブルがあっても、学校と違って「辞める」選択肢がある点も安心感につながるようです。
自分なりの居場所ができる
どんなお子さんでも、「居場所」が必要です。居場所とは、安心して自分をさらけだし、ありのままでいられる場所のこと。特に発達障害のお子さんは、学校などで強いストレスを感じやすいため、居場所を確保してあげることはとても大切です。
習い事には「好きな分野に没頭できる時間」「適度な距離感の人間関係」など、居場所になりやすい要素がそろっています。自宅以外に、お子さんがリラックスして過ごせる場所があるという安心感が得られる点も、習い事のメリットだといえるでしょう。
発達障害のお子さんが習い事を続けられるコツ
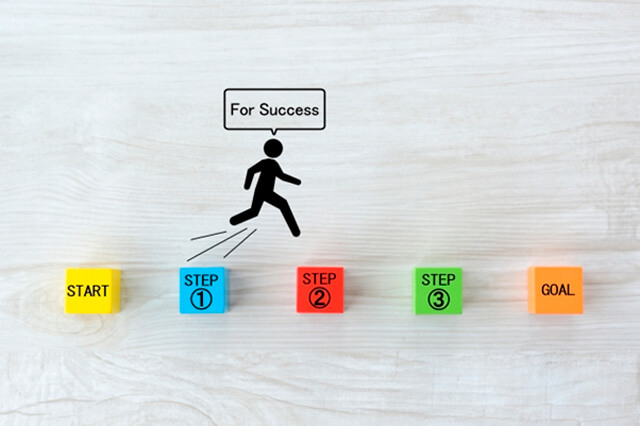
新奇場面への抵抗が強い、飽きっぽい、こだわりが強い……。発達障害の特性は、お子さんによってさまざまです。しかしせっかく始めた習い事なら、できれば長く続けて良い成果につなげたいですよね。
発達障害のお子さんが習い事を継続するためには、親御さんの適切なサポートが欠かせません。親御さんがすべきサポートとコツを解説します。
スモールステップを大切にする
習い事を続ける秘訣は、「できる!楽しい!」気持ちを持ち続けることです。発達障害のお子さんは特に、スモールステップを意識し、「できる!楽しい!」実感を頻繁に味わえるようにしてあげましょう。
たとえばレッスンの都度、「ちょっと頑張れば達成できる」目標を約束するのはおすすめの方法です。毎回目標をクリアしていくうちに自信が持てるようになり、やる気やモチベーションも上がります。
日頃、困難に直面する機会が多い発達障害のお子さんだからこそ、「小さな成功体験」を意図的に経験させることが大切です。
親は承認とサポートに徹する
親は“欲張り”です。最初は習い事に行けるだけで満足していたのに、徐々に「もっと上手に」「もっと上を」と欲が出る。ついにはお子さんに助言や指導をしてしまい、お子さんにうっとうしがられる、というのはどのご家庭でもある光景です。
習い事を長続きさせるコツは、お子さんのやる気をそがないこと。やる気をそがないためには、親御さんは承認とサポートに徹するようにしましょう。
上達するように指導するのは、先生の役割です。習い事に行き、先生の話を聞いて取り組んでくるお子さんを、「お帰り!頑張ったね!」と迎えるのが親の役割です。役割分担を徹底してみてください。
ただし、お子さんの様子で気になることや教室に伝えておくべきことがあった場合は、必ず伝えましょう。
無理をさせない
発達障害のお子さんは、親が思う以上に環境変化や不安に敏感です。また自分なりのペースやこだわりが強いお子さんも多いため、無理をさせるとかえって習い事嫌いになることもあります。お子さんの様子を見ながら、バランスを取ってあげるようにしましょう。
気分が乗らない日に無理に参加させようとしても、余計こじれるだけかもしれません。成功がイメージできないと、やる気にならないタイプもいます。お子さんの特性を踏まえ、「ちゃんとできる」を求めすぎないようにしましょう。
教室や先生と密にコミュニケーションを取る
お子さんの様子は、常に教室や先生と共有します。
先生はレッスンの時間の様子しか把握していません。発達障害児の指導に慣れていなければ尚のこと、今のやり方で良いのか、もっと工夫できる点はないかと思い悩んでいるはずです。ご家庭や学校での様子は、よりお子さんに合った指導をしてもらうヒントとして役立ちます。
連絡の方法は対面や電話、メール、LINEなど、教室や先生の都合に合わせます。レッスン時間や生徒が出入りするタイミングを避ける配慮も大切です。
発達障害の子が好きで楽しめる習い事を探していこう

発達障害の子が習い事をするなら、好きな分野で楽しめることが一番です。親がさせたい習い事より、子どもが好きな分野でさがしましょう。
発達障害の子は、好きなものには驚くほどの集中力を発揮する場合があります。子どもの興味にうまくマッチする習い事を始めると、思わぬ才能が開花するかもしれません。
子どもの興味がわからない場合は、合いそうな習い事をピックアップして体験クラスに参加してみましょう。子どもが実際に体験し、やってみたいと思った習い事なら、楽しく活動できるでしょう。
習い事を始めたあとでも、やっぱり合わないと感じる場合があるかもしれません。成果を求められるなど子どもが苦しくなる可能性もあります。合わない習い事は、子どもや家族のストレスになり経済的にもマイナスです。スパッとやめることをおすすめします。
まとめ
発達障害の子の習い事が続かない原因には、親の押し付けや子どもの興味に合っていないなど多くの原因が考えられます。興味のある分野でも、難易度が合っていなかったり、指導方針が合わなかったりして、やめたいと思う可能性もあります。
発達障害の子は個性的な子が多いため、子どもの性格や特性に合った習い事を選ぶのが大切です。好きな子が多いプログラミングや英語、個別指導で学べるピアノ、楽しく運動できるスイミングなどがおすすめです。
学力アップの習い事なら、先生とリアルタイムでやり取りできるオンライン家庭教師がぴったりです。発達障害の指導に長けたオンライン家庭教師ピースなら、お子さんの学力アップにつながります。この記事を参考に、お子さんの特性に合った習い事を探してくださいね。
















