高校生の勉強はこれでバッチリ!定期テストから受験まで対策できる勉強法を完全解説!
「高校の勉強はどんな風にやれば効率がいい?」「学校の勉強と受験勉強の両立が難しい」…、そんな悩みを持つ高校生に届いてほしい記事です。
これまで1,000人以上の高校生を指導してきた元予備校校舎長が、「効率的で要点を押さえた勉強のコツ」をまとめました!授業の予習復習からテスト対策、受験勉強まで網羅した内容です。
どれも今日から取り入れられる方法ばかり。最後まで読み、ぜひ効果的な勉強法を実践してみてくださいね。
高校生が勉強効率をグンと上げる3つのポイント

高校生の勉強は進度も速く内容も難しく、気を抜くとあっという間に置いていかれてしまいます。そんな高校の勉強を効率よく進めるには、押さえるべきポイントが3つあります。
ポイント① 常に目的・目標を定め、意識する
まず「目的・目標」を定める思考習慣を身につけましょう。
「目的」とは「なんのためにその勉強をするのか」ということです。高校生の勉強の目的は「大学合格」か「定期テスト対策」のいずれかに当たりますね。
「目標」とは「達成したい数値」のことです。「小テストで満点をとる」「定期テストで学年50位に入る」、あるいは「模試で偏差値50以上をとる」といったものです。
高校生の勉強は「今やっていること」が「目的・目標」に向かっているか、という視点で常に振り返りながら進むことが大切です。何となく取り組んで何とかなるほど、テストも受験も易しくはありません。まずは「目的・目標」を定めてみましょう。
ポイント② 高校生の勉強の基本は「授業の予習&復習」
高校生の勉強の基本は「学校の授業の予習・復習」です。特に高1・2年生の志望大学が決まり切っていないうちは、学校の授業に力を入れてください。学校の授業は定期テストに直結しますし、定期テストの結果は内申点に影響し、内申点は大学入試の合否に関わったり、推薦入試を受けられるかどうかの決定打になったりする重要なものだからです。
また「予習・復習」で身につけられる勉強のやり方は、テスト対策や受験勉強の土台になります。後ほど「予習・復習」の具体的なオススメ勉強法を書きますので、そちらも参考にしてくださいね。
ポイント③ 定期テスト対策と受験勉強は両立できる
高校生の勉強では「定期テスト対策と受験勉強の両立が難しい」という話を聞きます。でも実は両立は可能ですよ。なぜなら定期テスト対策も受験勉強も、出題範囲は「高校の教科書内容」だからです。
定期テスト対策に苦戦するのは、もしかしたら「テストを暗記で乗り切ろうとしている」からかもしれません。あるいは「テスト勉強に割く時間が少ない」のが原因かもしれません。短期間に詰め込み暗記したものは、すぐに忘れます。それではテストの度に苦労するばかりで、力になっていきませんよね。
高校のテストも大学入試も、勉強しているのは「高校の教科書内容」であるという事実に立ち返り、「教科書の基本を計画的に勉強する」ことに力を入れましょう。そうすればテスト対策と受験勉強は自然と繋がっていきます。具体的な勉強法は、この後まとめていきますね。
(番外編)分からなくなりそうな予感がしたら、プロを頼る!
分からないことが出てきたら、早めに対策することが肝心です。「これくらいなら」と放置すると、あっという間に教科全体が分からなくなってしまうのが高校生です。
「あ、ヤバイな」「自力では難しくなってきたな」と感じたら、塾や家庭教師を頼るのがオススメ。プロの力を借り、分からなくなった根本からやり直すのが最短距離です。
本格的に受験勉強を始めてみたら、実は高1からやり直しが必要だった…、では入試に間に合わないかもしれませんよね。分からなくなりそうな予感がした段階で、早めに塾や家庭教師を検討してみてくださいね。
高校生にオススメの「予習・復習」勉強方法
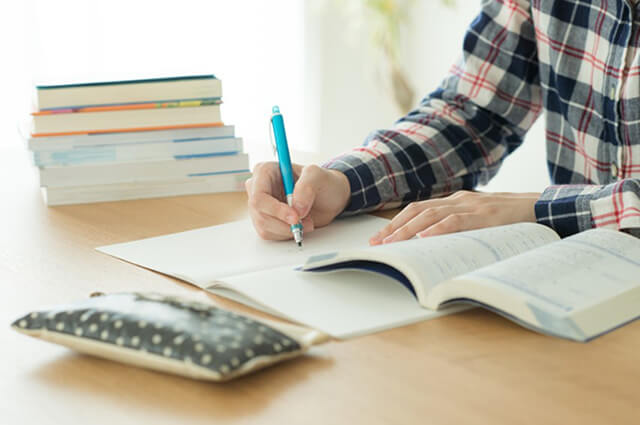
ここからは「予習・復習」の具体的なやり方についてまとめていきます。学校の先生から「予習・復習をちゃんとやるように」と言われたものの、具体的なやり方までは聞いていない…、と困っていませんか?
全教科に使える、効果的な「予習・復習」のやり方を伝授します!
予習は「理解の境目を見つけること」が大事!
予習中に分からない問題に当たり延々と悩んで時間が過ぎ、結局他の勉強に手が回らなかった……、という経験はありませんか?これは予習の目的があいまいなまま取り組んだために起きてしまう現象です。では、予習は何のためにやるのか知っていますか?
予習の目的は「自分の理解の境目を見つけること」
予習の目的は「ここまでは分かる/ここからは分からない」という境目を明確にすることにあります。この境目が明確になっていれば、「分からない点を分かるようにする」という意識で授業を聞くことができる、つまり授業中に集中力のメリハリがつけられるのです。
ところが目的を持たず、何となく問題を解く・何となく教科書を読んでおくだけでは、結局自分は何をどこから理解すればよいのかが分からないまま授業に臨むことになってしまいます。その結果、授業中にどんどん分からない点が出てきてしまうのです。
予習の段階では解けない問題があってOK!
予習では分からない問題があってOKです。ここまでは自力でできたけれど、この先どうすればよいかわからないという境目をノートにメモしておきましょう。「5分悩んで分からなかったら止める」「参考書を見てもわからなかったら止める」などと、自分なりに予習をストップする基準を決めておくと迷わなくて済みますよ。
復習は「何度もやる」が大事!
復習は「毎日・何度も」が大切です。大手予備校の大学受験科(既卒生コース)では、1冊のテキストを7回繰り返すよう指導されるほど、繰り返しは大切です。授業を聞いただけ、1回やり直しただけでは身につきません。
高校生なら最低3~4回は反復したいですね。
オススメの復習法「習った時点で、復習する日を3回決める」
習った時点で、復習する日を3回分決めてしまいましょう。計画表やノートなど、自分が分かるところにメモしておくといいですよ。
「3回」は次のように配分します。
- 1回目:当日
- 2回目:3日後
- 3回目:1週間後
たとえば4/10に習った内容には、「4/10・4/13・4/16」と日付が入りますね。そして復習をしたら、日付を二重線などで消しておきます。復習の進み具合も一目で分かりますね。
高校生にオススメの「定期テスト対策」勉強方法
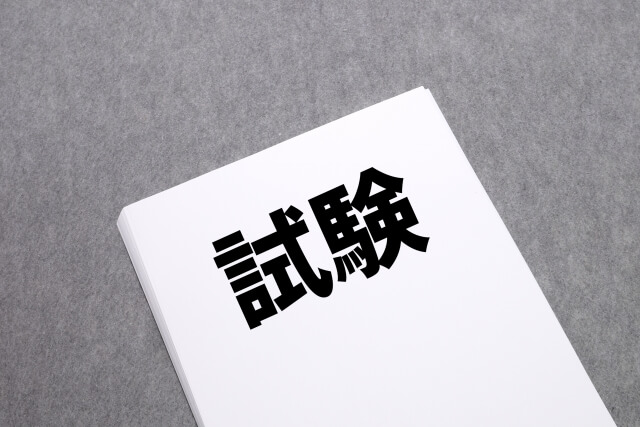
続いて「定期テスト対策」を効率的に進める勉強方法を解説します。やらなきゃと思いつつ、いつも直前に慌ててしまうという人は、ぜひ次のテストから実践してみてくださいね。
2週間前には始めよう!
定期テスト専用の対策は、遅くとも2週間前には手をつけましょう。このころテスト範囲が発表になる高校が多いと思います。また部活もテスト前は練習が休みになりますよね。この期間を最大に利用し、日頃の勉強をテストに向けて整えていきましょう。
過去問を入手するか、傾向を知ろう!
高校の定期テストは、高校や先生によって特徴的な出題形式や傾向があります。過去問や情報は入手したいところ。先生の「次のテストはこんな風に勉強しなさい」という発言を聞き逃さない、先輩に聞いてみる、過去問を見せてもらうなどの方法を駆使してください。
全体を網羅できる計画も忘れずに!
定期テスト対策は「計画」も大切です。テスト対策の計画は「全科目・テスト範囲を網羅し・演習量も確保できる」計画を考えましょう。テスト範囲の問題集のページを対策可能な日数で割って1日あたりの分量を出しつつ、かつ最後に演習用に1~2日の余裕を持たせられるペースで立てるのが理想的です。
高校生が「授業・テスト」と「受験対策」を両立するコツ

日々の勉強や定期テストと同じくらい、大学入試が気になるという高校生も多いでしょう。ここからは「授業(予習・復習)」と「受験対策」を上手に両立するコツを見ていきます。
志望校は早めに決めよう!
志望校は早めに決めることをオススメします。途中で変わっても構いません。早めに決めることで、自分に必要な学力レベルや力を入れたい科目・分野が明確になり、日々の勉強でも重点的に取り組めるようになります。遅くとも高2の秋までには「行きたい大学」を決めたいですね。
志望校との差を埋める計画を立てよう!
志望校が決まったら計画を立てます。この時大切なのが必ず「逆算」で立てること。目標レベルもスケジュールも、「入試当日に合格点を取るには?」という視点を基準に考えます。基礎の習得から演習まで十分に取り組める計画を立ててください。思ったより時間がない!と焦る高校生が多いのですが、だからこそ日々の勉強も気合が入る!というものです。
大学受験は「教科書=基礎」が最重要!
大学受験の勉強というと難しい発展問題を解けるようにならないといけないと思うかもしれませんが、一番大切なのは「基礎」です。難関大になるほどこの傾向は顕著で、基礎を徹底した高校生ほど合格していきます。まずは難しい問題集には手を出さず、教科書をしっかり理解しましょう。学校の授業を大切にすることが、基礎の習得の近道です。
高3生・時期ごとのオススメ過去問対策
高3生の大学別対策は、授業がない長期休みを利用します。まず夏休みに過去問に1回チャレンジ。これは過去問の傾向を知り、秋からの対策に活かすのが目的です。次は冬休み。本番を想定し、実戦力を鍛え得点する力を伸ばすのが目的です。長期休みを活用すると、高3になっても学校の授業と受験勉強は両立していけますよ。
高校生向け・科目別の「要点を押さえた勉強法」

いよいよ高校生の勉強法を科目別に見ていきましょう。大学入試まで通用する勉強法ばかりです!
英語
単語
単語は自分が学びやすくレベルが合った単語帳を1冊選び、徹底的に繰り返します。効率の良い暗記には「まとまった量を、何度も繰り返す」方法がオススメ。100語や10ページなどと範囲を決め、毎日取り組みましょう。ペンキを塗るように、薄く何度も記憶を上書きするイメージで。
文法・構文
文法・構文は早めに完成させたい項目ですね。長文読解の土台にもなります。使いやすい文法書と問題集を選び、短期集中でマスターしましょう。問題文の構造を説明できるレベルを目指してください。「SVOC」「語・句・節」部分は、全ての基本です。十分な理解を!
長文読解
長文はステップアップ学習で取り組みましょう。まずは1文1文の構造を正確に捉え、正しく訳せること。次に訳さなくても大意を把握できるように。最終的には問題を解くために必要な箇所をスピーディーに見つけられるように。勉強の順番は必ず「精読⇒速読」ですよ。
数学
数学は「なぜそうなるのか」という理論を理解することを大切にしましょう。近年は解法の暗記では太刀打ちできない、思考力を試す問題も多く出題されています。公式や解法の意味を理解した上で、基本問題・発展問題と演習を繰り返していくことが実力を伸ばします。
文系数学
文系数学は共通テスト対策がメインになりますね。まだマーク式のみですが、記述が導入される可能性も捨てきれません。マークに特化せず、総合的に勉強していくことがオススメです。学校の授業とテストを活用し、基礎事項の習得と共通テスト特有の「思考させる問題、読解させる問題」も練習していくことが大切です。
理系数学
理系数学は「数Ⅲ対策」と「記述問題対策」が重要です。既卒生と同じ試験を受けるにも関わらず、高校生が学校で数Ⅲの履修を終えるのは高3の終盤、ほとんど演習ができません。数Ⅲは先取りも視野に入れてみてください。また特に国公立大では「記述問題」が出されます。面倒がらずに、プロセス一つひとつを分かりやすく式にし書く練習を重ねましょう。
国語
現代文
現代文は「論理的な読み方対策」が肝心です。論理的な読解の助けになってくれるのが「文法」。文節間の論理関係、段落同士の関連性などを正しく理解するのに役立ちますよ。あわせて「現代文頻出キーワード」も覚えていきましょう。現代文で登場する言葉の意味を正しく知っておくと、本文の主旨が理解しやすくなります。用語集も利用してみてください。
古文
古文は得点しやすい科目のため、早めに完成させておきたいですね。ポイントは「単語」「文法」です。実は単語と文法をしっかりマスターするだけで、驚くほど古文が読めるようになるのです。「更級日記」「枕草子」といった比較的読みやすい文章を、1文1文文法的に説明した上で意味を正しくとれるようになればバッチリです。
漢文
漢文はまず、基本的な「返り点」「句法」を覚えてください。数はさほど多くはありません「否定」や「疑問・反語」、「使役」といった頻出句法を知らないままでは文章の理解もおぼつきませんからね。覚えた後は学校の問題集やセンター試験の過去問等を使い、演習を繰り返します。
理科
文系理科(主に生物、地学)
生物や地学は理科の中でも「暗記」が占める割合が多い科目ですね。まずは基本事項を正しく覚えてしまいましょう。その時に「なぜそうなるのか」という理屈を一緒に覚えること。特に共通テストで「考えさせる問題」が出たときに有効です。生物はグラフの読み取りや計算問題への対策も忘れずに。
理系理科(主に物理、化学)
物理や化学は暗記より「理論の理解」が重要です。数学同様、現象と公式をしっかり理解した上で、演習問題を繰り返して定着させていきましょう。はじめから終わりまで自力で解答を書ききる記述力も大切です。また化学は無機分野など暗記が必要な内容も多数あります。物質の性質を押さえた上で分類を暗記していくようにしましょう。
地歴公民
地歴公民は「地理・世界史・日本史・倫理・政治経済・現代社会」から2科目選択が多いですね。暗記だけで何とかなると言うには、ボリュームが多すぎます。大学入試では論述問題を課される場合もありますので、時代背景や出来事の原因、他との関連なども一緒に覚えるようにしましょう。一気に覚えるのではなく、少しずつコツコツがオススメですよ。
やる気が出ない時でも勉強できる!5つのメソッド

どうしても勉強のやる気が出ない…、でも勉強しないといけない…。高校生にはそんなときもありますよね。やる気が出ない時でも机に向かえる、簡単な方法を5つご紹介します。
1.「○時になったらやろう」はダメ!
勉強は思い立ったらすぐ行動!が基本です。「○時になったらやろう!」と思っていては、いつまでたっても始められません。
思い当たりますよね。「7時になったらやろう」と思い別のことをしていたら、いつの間にか7時を過ぎていた、ということ。「じゃあ、7時半になったら始めよう」、気付くと7時半も過ぎている…。
勉強も同じです。
勉強は思い立ったらすぐにやる!この鉄則を心に留めておきましょう。
2.やる気が出ないときは「ちょっとだけ」でOK!
思い立ったらすぐ!と言われても、なかなか体が動かないときもありますよね。そんなときは、「ちょっとだけ、やってみない?」と声に出して自分に語りかけてみてください。
声に出すのがポイントです。聴覚は脳の「意欲を持たせる」という部分にうまく作用するため、”その気になりやすい”のです。
また「ちょっとだけ」というのもポイント。10ページやると言われると萎えるけれども、「ちょっとだけ」ならやってみるか、という気になりやすいのです。
脳をその気にさせ、行動を起こしやすくするキーフレーズ「ちょっとだけ、やってみない?」を活用してみてください!
3.まず30分は「我慢して取り組む」!
机に向かうことができたら、はじめの30分は我慢してでも続けるようにしてください。
脳は目の前のことに集中するまでに20~30分かかると言われています。最初の30分の間に勉強をやめてしまったり、別のことが気になっていたりすると、せっかく集中モードに向かい始めていた脳の作用を中断させてしまいます。
初めは10分でも長く感じるかもしれませんが、計算でも英単語帳でもいいので30分続けてみてください。ふと気付くと、「あれ?もうこんなに時間が経っていたんだ!」という瞬間が訪れます。
集中できるか、集中力が持続するかどうかは「はじめの30分」が勝負です。
4.止めるときは中途半端なところで!
勉強の手を途中で止める時は、敢えて中途半端なところで止めてみてください。
たとえば勉強中に夕食に呼ばれたときは、キリの良いところまで終わらせたくなりますが、敢えて呼ばれた瞬間に手を止めましょう。すると脳は続きが気になり、夕食後に勉強を再開する時も驚くほどスムーズに戻れますよ。
この「中途半端に止められると、続きが気になって仕方がない」という脳の働きのことを心理学用語で「ツァイガルニク効果」と言います。脳の仕組みを勉強に活用した一例です。
5.集中できる「ゴールデンタイム」を見つける!
最後は「勉強のゴールデンタイムを見つけよう」という話です。自分が勉強に取り組みやすい時間帯を把握していますか?人にはそれぞれ集中しやすい時間帯があり、生活リズムや体調、日頃の習慣などの影響を受けて決まってきます。
よく「朝型がいい」と言いますが、高校生全員に当てはまるわけではありません。夜の方が集中できる高校生もいます。あるいは学校から帰ってきたらすぐに勉強するタイプもいれば、お風呂の後にじっくり取り組みたい人もいます。
自分の「勉強のゴールデンタイム」はどこかなと考えてみてください。その時間に勉強に向かえるように生活を整えると、急に勉強がはかどるようになるケースもありますよ。
高校生に最適な勉強場所を選ぶポイント5つ

「高校生の勉強」というテーマを本質的に考えてみると、実は勉強しやすい場所には5つのポイントがあります。そしてこの5つのポイントを網羅した場所は、あなたの受験勉強の拠点になってくれますよ。ではまず5つのポイントから見ていきましょう。
① 安心・安全であること
勉強できる場所の選び方1つ目は、「安心・安全であること」です。これはあなたが「高校生だから」、真っ先に必ず考えないといけないポイントですよ。
長時間勉強することも多い高校生は、帰宅時間が遅くなることも想定されます。一方、高校生を狙った犯罪は少なくないですし、路上に不審者が出没することもあるでしょう。時間帯と場所によっては、酔っ払いにからまれることもあるかもしれません。
自分の勉強や進路を応援してくれている親御さんに心配をかけるような場所は選ばないでください。安心して勉強に打ち込め、安全に行き来できる場所であることは、あなたにまず考えてほしいポイントです。
② 誘惑がない(少ない)こと
勉強場所の選び方2つ目は「誘惑」についてですね。ここでいう「誘惑」とは気になって集中力を削いでしまうもの、勉強の妨げになるものを指します。人によって何が誘惑に相当するかは変わりますが、一般的には漫画やテレビ、インターネット、ゲームなどでしょう。
集中しているときは目の前のことしか見えていない気がしますが、脳は視界に入るものすべて認識します。また耳から入る情報、鼻に入るにおいが気になってしまうこともありますよね。
自分の誘惑が何かを認識し、誘惑がない(もしくはできるだけ少ない)環境を見つけましょう。集中して勉強するためには大切な要素です。
③ 心地よい静けさと適度な雑音があること
うるさい場所で集中できるという人は多くはありません。では静かなら集中できるかというと、人は無音の状態ではかえって落ち着かなくなってしまうそうです。人が最も能率よく物事に取り組める環境というのは、心地よく静か・適度な雑音がある場所なのです。
また「騒がしい場所でも大丈夫、イヤホンをして音楽を聴きながら勉強するから」という高校生がいますが、実はこれもおすすめできません。自分は音楽を聞き流しているつもりでも聴覚(つまり脳)は情報として捉えています。脳が情報として捉えているということは、本来100%勉強に向けたい脳の情報処理力が少なからず音楽に向けられているということです(自分では無意識な点が厄介!)。
さらに入試本番ではイヤホンも音楽も使えませんが、日頃から音楽を聴きながら勉強してりいると音楽がないと集中できないという状態にもなりかねません。何のために勉強してきたのか分からなくなってしまいますよね。
イヤホンや音楽がなくても取組める、適度に雑音がある落ち着ける場所を探しましょう。
④ 教材を広げられるスペースがあること
高校生が使う教材というのは厚く、数も多くなります。ノートに問題集、参考書、単語帳や資料集、どれも勉強には欠かせないものですよね。これらの教材を伸び伸びと広げられるスペースがある場所、というのが勉強場所の見つけ方ポイント3つ目です。
東大生にはリビングのテーブルで勉強していた人が多い、という話を聞いたことがありますか?リビング学習にはさまざまなメリットがありますが、そのうちの1つが「広いテーブルで勉強できる」点にあります。広いスペースを前にすると、人の思考の幅や自由度も広がります。柔軟に考えられるようになり、能率が上がりやすいというわけです。
狭いテーブルで落とさないように気をつけながら…、では勉強ははかどりません。自分に必要な教材やノート、筆記具が十分に広げられるテーブルがある場所を見つけてくださいね。
⑤ Wi-Fiがつながること
高校生の最適勉強場所の見つけ方5つ目は「Wi-Fiがつながること」です。いまや高校生の学習にスマホは欠かせません。動画授業を見たり、単語アプリを使ったり、勉強管理もアプリで行えたり、ちょっとした調べものにも大活躍です。
スマホを勉強に使う際に気になるのが通信速度とデータ通信料ではないでしょうか。特にスタサプをはじめとする授業動画の視聴には、安定した通信品質が欲しいところです。またスデータ通信料に上限があるプランの場合、動画を見るとあっという間にすべて使ってしまいますよね。
スマホを勉強でもよく使うという人は、公共あるいは無料のWi-Fiが繋がる場所を選ぶというのも大切です。ただしTwitterや勉強に無関係なYouTubeを何時間も見るといったことには使わないように気をつけてくださいね。
高校生におすすめの勉強場所5選|メリットとデメリットも

さてここからは、先にまとめた「勉強場所の選び方5ポイント」を踏まえて、高校生におすすめの勉強できる場所を5つ、ご紹介します。それぞれメリット・デメリットがありますので、自分の勉強スタイルに合わせてピッタリの場所を見つけてくださいね。
1.自分の部屋
まずは一番安心・安全、落ち着ける「自分の部屋」です。とあるアンケートでも7割以上の高校生が勉強場所として選んでおり、予備校指導の現場でも「(塾の自習室以外なら)自分の部屋で勉強する」という高校生が圧倒的多数でした。
また使い慣れた教材がすべて揃っていることや、新型コロナウィルスやインフルエンザといった感染症がうつる心配が少ない点もメリットですよね。休憩時の飲食も自由、他人の目を気にせず気分転換のストレッチや仮眠もできます。
一方、自分の持ち物がすべてある場所ゆえに「誘惑が多い」という声がある点がデメリットでしょう。読みかけの漫画や雑誌、ゲームなど、好きなものが目に入るとつい気になってしまいますよね。
「自分の部屋は誘惑があって勉強できない」と感じる人は、「誘惑」を目に入らないように移動させるのがおすすめ。ダンボールや押し入れにしまい込むのも良いですし、勉強机に向かったときに目に入らない背中側に移動させるだけでも注意散漫になることを防げますよ。
2.自宅のリビングや茶の間
高校生におすすめの勉強場所2つ目は「自宅のリビングや茶の間」です。家族の気配が励みになったり、場合によっては良いプレッシャーになって集中できるという高校生の声を聴きます。また兄弟姉妹がいる人は、一緒に勉強すると良い刺激にになりますよ。
自室で勉強していると寝てしまう…、という人もリビングを利用する率が高いようです。寝ていたら起こしてくれるよう家族に頼んでおくというわけですね。また勉強や進路を含むさまざまな話題について、親御さんと話がしやすいというのもリビング学習のメリットです。
一方、リビングならではの悩みもあります。代表的なのはついているテレビが気になってしまうというもの。時間を決めてテレビを消してもらう、気にならない程度のボリュームにするなど、自分の希望と家族の都合を上手にすり合わせて解決策をみつけましょう。
3.塾の自習室
高校生には「塾の自習室」もおすすめです。高校生の中には、塾の授業を受けるより自習室を使いたいから塾に通う、という人もいるほど。多くの塾は在籍している塾生だけが使える場所として自習室を用意していますが、塾外生でも使えるケースやテスト前などに短期利用を可能にしている塾も一部にあります。お近くの塾の自習室開放状況を調べてみてください。
塾の自習室のメリットは、なんといっても「周り中、頑張っている人だらけ」という点です。大勢の高校生が集まり黙々と勉強する中に身を置くだけで、気持ちが引き締まりやる気が出ます。また勉強以外の要素がないため、誘惑があると集中できないタイプの人にも向いています。校舎備え付けの赤本や模試の過去問を利用できるのも助かりますよね。
デメリットは教材を持っていかないといけないという点でしょう。参考書や問題集も、いくつもの教科分となるとかなりの重さです。また塾ごとのルールに従う必要もあります。塾によっては勉強中のスマホ利用を禁止したり、塾以外の勉強を自習室でしてはいけないというルールを課す場合もありますので、事前によく確認しておきましょう。
4.公共図書館や学習会館
公共の施設を使うという方法もあります。図書館や学習会館と呼ばれる場所ですね。自治体が市民の生涯学習や教育のために用意している施設は、たいがいどの市町村にもありますよね。誰でも無料で使える点が魅力です。
図書館や学習会館は「学ぶこと」を目的に訪れる人が多いため、利用者のマナーもよく静けさが保たれています。多くの人が学ぶ場所特有の適度な緊張感が、勉強へのモチベーションを上げてくれます。また移動している間に単語を覚えるなど時間の有効活用も期待できますね。
ただし多くの公共施設では「館内での飲食禁止」となっている点に注意しましょう。昼食や休憩の際は、都度外にでる必要があり勉強を中断しないといけません。また多くの人が利用できるよう、1人あたりの利用時間に上限が設けられている場合もあります。
いずれの場合もあらかじめ勉強の計画を立て、利用時間を有意義に活用する工夫が必要となります。
5.学校の教室や学習室
高校生におすすめの勉強場所、最後は「学校の教室や学習室」です。友だちと一緒に切磋琢磨しながら、連帯感を持って勉強に取り組める点が魅力ですね。その教科が得意な子が教えてくれる、あるいはみんなで単語を覚えるスピードを競うといった取り組みができるのも、学校で気の置けない仲間と勉強する醍醐味と言えます。
また分からない点があったときは、すぐ先生に聞きに行けるのもメリットと言えますね。学校によっては休日でも先生が質問対応のために常駐してくれているというところもあります。また勉強方法の相談や発展学習のための教材・プリントなどをもらいやすい点も高校生には嬉しいポイントです。
ただし友だちと一緒に勉強する場合は、「勉強する」という目的を見失わないことが大切です。勉強していたはずが、いつのまにかグラウンドのサッカー部を見ている…、ということになっては本末転倒ですからね。また下校時間は必ず守りましょう。
高校生の勉強でやってしまいがちな失敗例

最後に、やってしまいがちだけれども成績が伸びない勉強法についても触れておきましょう。下に4つあげたものはいずれも「勉強した気になりやすいけれども、実力は伸びない」行動です。
模試は成績表を見たら放置⇒やり直しはマスト!
模試は実戦問題ばかり、弱点を見つけ実力を伸ばすヒントが詰まっています。必ずやり直しましょう。
日本で最大規模の大学入試模試である河合塾「全統模試」は、河合塾のサイトで問題解説動画を無料で見ることができます。活用してみてください。
覚えるばかりでアウトプットしない⇒アウトプットが成績を伸ばします
時折、「英単語を2000個覚えた!」と鼻を高くしている高校生がいます。しかし残念ながら、覚えただけでとれる得点には限度があるのです。覚えたら必ず「使ってみる」、つまり問題を解くようにしてください。アウトプットして初めて「実戦力」になっていきます。
ノートをきれいに作ることにこだわる⇒ノートの目的は「見直し」にあり
ノートは授業や演習の記録であり、自分の理解不足を見直すためにあるものです。いくらマーカーや付箋できれいに作ったとしても、後から見直さなければ役割を果たしません。色は3色まで、付箋はシンプルに最低限に。やり直しや後からの気付きをメモするスペースを空けておいても便利ですよ。
解答を見てわかった気になっている⇒自力で解けるかチャレンジは必須
解答を見て「なるほど、そうか!」と納得した後に、もう一度自分で解いていますか?納得してページを閉じていませんか?「わかる」と「できる」は、脳の別の分野の活動です。「あの時、この問題の答え見たはずなのに!」という悔しい思いをしたくないなら、かならず手を動かし実際に解く癖をつけましょう。
「高校生の勉強法」まとめ
高校生の勉強は簡単ではありません。投げ出したくなる時もあるでしょう。
だからこそ、一番はじめでお伝えした「目的・目標」が重要なのです。こんなに苦しい思いをして、なんで自分は勉強しているんだろう?と悩んだ時、自分を救い出してくれるのは「こうなりたい!」「合格したい!」「あの大学に行きたい!」という強い思いだけなのです。
すぐに結果が出なくても、あきらめないでください。現役生は、試験当日のその瞬間まで伸び続けます。この記事を参考に、1人でも多くの高校生が栄冠を勝ち取ってくれることを祈っています。
















