ADHDのお子さんにベストな習い事は?選び方の注意点や継続できるコツも解説
「ADHDの子どもに習い事をさせたいけれど、どの習い事が良いか」「習い事選びで注意する点は何か」、そんなお悩みをお持ちの親御さんも少なくないでしょう。
ADHD特有の行動特性のために、「他のお子さんに混じって習い事をさせても大丈夫か」「どんな教室ならADHD児でも受け入れてもらえるのか」と悩むケースも多いようです。
この記事では、ADHDのお子さんにおすすめの習い事やその理由、習い事をするメリット、習い事選びの注意点や親の関わり方についてまとめました。ぜひ最後まで読み、お子さんにピッタリの習い事を見つけるヒントにしてください。
ADHDとは?

ADHDを持つ子が集中して学習できるよう、どんな特性を持つのか理解しましょう。ここでは、ADHDの概要と特性、勉強との相性について分かりやすく解説していきます。
発達障害のひとつ
ADHD(注意欠如・多動症)は発達障害のひとつです。発達障害者支援法では、発達障害を次のように定義しています。
“この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。”
発達障害の子どもは、生まれつき脳の働きが違うため、小さいころから特徴が現れます。他の精神疾患でも発達障害と似た症状が見られるため、成育歴も診断の資料となります。
ADHDの特性
ADHDの特性は多くの子どもが持っているものです。しかし、集団生活が送れないほど困った状態の時には診断名がつけられ、治療やフォローが行われます。ADHDの主な特性は次の2つです。
- 多動性・衝動性
- 不注意
多動性・衝動性で一番分かりやすいのは体の動きです。じっとしているのが苦手で、気になることがあると衝動的に動いてしまいます。静かにしなければいけない場でも、気持ちのコントロールができず動きが止められません。
ADHDの子は思考にも落ち着きのなさが見られます。1つのことを考えようとしても、どんどん違うことが思い浮かんでしまい考えがまとまりません。一度にいろいろなことを考えるので、体も口もよく動くのが特徴です。
不注意の特性は整理整頓ができない、忘れ物が多いなどの行動に現れます。不注意が強い子はボーッとしていて迷惑をかけにくいため、ADHDだと気づかれにくいです。多動性・衝動性とは正反対に見えますが、これもADHDの特性です。
勉強との相性
ADHDは集中時間が短く、勉強方法によっては合わない場合もあります。ADHDと勉強との相性を、得意・不得意に分けて解説します。
【興味を持ちやすい勉強】
- 映像や音楽などを使った学習
- 自分の意見を発表する学習
- 新しい単元の学習
映像や音楽を使った学習はよい刺激となるため、ADHDの子の興味をひきやすいです。それでも長時間は飽きてしまうでしょう。発想が豊かなので、自分の意見を自由に発表できる場面は得意な子が多いです。
また、目新しいことに興味を持つので、新しい単元の学習には食いつきがよいです。しかし、自分の興味がない分野だったりするとやる気を失い飽きてしまいます。
【興味を示しにくい勉強】
- 漢字練習や九九などの反復学習
- 長文の読解や文章題
- 似たような問題が続くドリル
同じ漢字を何度も書いて覚えるなど、こつこつ積み上げていく学習は苦手です。努力して成績を上げようとはあまり考えないので、同じことの繰り返しは苦痛を感じます。予習すると学校での勉強は「もう家でやったからやらない」という子もいます。
あらためて、ADHDの子どもが持つ特性とは?

ADHD(注意欠如・多動症)は、小中学生の3~7%程度が持つと見られる発達障害です。学校などの集団活動で困難を感じる場面も多く、サポートを必要とするお子さんも大勢います。
はじめに、ADHDの特性について簡単に振り返っておきましょう。
ADHDの特性① 多動・衝動性
ADHDの特性の1つ目は、「多動・衝動性」です。「じっとしていられない」「静かに遊べない」「待つことが苦手で他人のじゃまをしてしまう」といった行動があてはまります。ADHDのお子さんは、「落ち着きがない」と称されることも多いのは、多動や衝動性といった特性が原因です。
また表情から相手の気持ちを察して適切な言葉を発したり、場の空気を読んで行動したりすることが苦手なお子さんもいます。一方的なおしゃべりなど、コミュニケーションに苦手意識を持つケースもあります。
ADHDの特性② 注意欠如(不注意)
ADHDのもう一つの特性は「注意欠如」です。不注意といわれる場合もあります。注意欠如特性を持つお子さんには、「するべき活動に集中できない」「気が散りやすい」「順序立てて活動に取り組めない」といった行動が見られます。
テストでもケアレスミスが多く、成績低迷などの影響が起きる場合もあります。整理整頓やモノの管理も苦手で、持ち物をよく無くす、片づけができないなどの困難に直面することもあります。
ADHDの子どもが必要とするサポート
ADHDは脳の前頭葉や線条体の機能障害や、脳内物質の異常作用により起こります。多動や衝動、注意欠如といったADHD特有の行動は、本人の意図とは無関係に起きるため、集団生活や社会生活に適応できるようサポートが必要になるケースもあります。
ADHDのお子さんに対しては、次のようなサポートが行われます。
- 個別に指示を与える
- 苦手を先回りして声掛けする
- イラストや絵などで見える化する
- 活動時間とじっとする時間のメリハリをつける
ADHDの子に向いている勉強法

ADHDの子に効果的な学習をするには、特性を考慮した勉強法を取り入れるのが最適です。ADHDの子に向いている学習法を6つに分けて紹介します。
図や絵を使って勉強する
図や絵を使っての学習はADHDの子に向いています。文章だけより直感で分かりやすく興味を持てるためです。
ADHDの子は、集中して文章を読み込むのが苦手です。長い文章を見ただけでやる気をなくし、できる問題でも拒否する場合もあります。
文章だけでなく図やイラスト、写真などが入っていると興味をひきやすいです。目で見る情報はインパクトが強いので内容が理解しやすいでしょう。
勉強の予定をリストにして確認する
ADHDの子は、勉強の予定をリスト化して確認するとよいでしょう。決められた学習をこなすのに役立ちます。
ADHDの子は特性により、予定を忘れて中途半端になることがよくあります。他の事に気をとられて忘れたとしても、リストを見れば勉強を再開するきっかけとなるでしょう。
学習を始める前に取り組む勉強の予定を子どもと一緒に確認するのがポイント。自分で決めた予定であれば納得して取り組みやすいです。
短期目標を設定しクリアしていく
短期目標を設定しクリアしていく学習方法は、ADHDに向いています。短時間で達成できる目標があるとやる気につながるためです。
ADHDの子は、脳の特性により集中力が途切れやすいです。長時間かかる目標では達成できないどころか、初めからやる気を持てず手を付けない恐れもあります。
確実に学習させるには、短時間で終わる目標を作るのがベターです。スモールステップで進むよう意識して課題を考えると、ADHDの子でも無理なく取り組めます。学習の手ごたえを感じさせるよう、少し頑張れば達成できる程度の課題を用意するとよいでしょう。
動いていてもできる勉強を取り入れる
多動がちなADHDの子には、動いていてもできる学習メニューを取り入れてみましょう。座っているのが苦手な子でも学習に取り組めます。
学習といえば座って取り組むイメージですが、発達障害を持つ子はじっとしているのが苦手です。親も座ることへの固定観念を取り払い、動いていてもいい課題を与えてみましょう。例えば、覚えたり話したりする課題なら動いていても取り組めます。
トランポリンやバランスボールなどを用意しておくと、その場で動けるのでおすすめです。
二者択一で勉強していく
2つの学習内容を見せ、どれからやるか選ばせるのもよい方法です。自分で選んだ学習には興味を持って取り組めるためです。
ADHDなど発達障害を持つ子は、人から押し付けられるのを嫌がる傾向が見られます。決められた学習メニューには、なんとなく反発してしまうことも。自分で選んだ学習なら、納得して取り組めるでしょう。
課題を与える際の注意点は、やらない選択肢を与えないことです。「やる」「やらない」では、やらない方を選ぶでしょう。必ず何か学習させるよう、子どもの興味関心も踏まえての課題選びが重要です。
好きな勉強は気が済むまでやる
好きなことがあるADHDの子には、得意分野の勉強を好きなだけさせてもよいでしょう。興味のある分野を追求し、才能が開花するかもしれません。
ADHDなど発達障害を持つ子には、苦手分野を無理に学習させようとしても伸びにくいものです。脳の特性が原因なのでなかなか伸びず、本人も周りもつらい思いをする恐れがあります。
逆に好きな分野には、ものすごい集中力を発揮します。得意分野の成績を伸ばしつつ、苦手分野の底上げを狙っていきましょう。
ADHDの子が勉強に集中するための工夫
ADHDの子は集中力が切れやすいため、学習環境の工夫が大切です。ここでは、ADHDの子が勉強に集中するためにできる工夫を3つ紹介します。
壁や仕切り板などで他のものが視野に入らないようにする
学習する際には、壁や仕切り板などを利用し、他のものが視野に入らないよう工夫しましょう。
ADHDなど発達障害の子は、目で見る情報から強い刺激を受けやすい子もいます。視覚優位という特性で、空間把握が優れている反面、見える情報をすべて受け取りがちです。見えるものが多いと気が散りやすく集中できません。
視野を狭めると、取り組む問題だけが見えて集中しやすくなります。壁を正面にして学習机を設置したり、机で使えるパーテーションなどを利用したりするとよいでしょう。
雑音などの刺激が少ない環境をつくる
雑音などが聞こえない、静かな環境を作ってあげましょう。音による刺激を受けにくくなり、学習に集中できます。
ADHDを持つ子には、先に紹介した視覚優位の他、音に敏感な聴覚過敏の子もいます。このタイプは話をよく聞き覚えていますが、ちょっとした音に反応し集中が途切れがちです。できるだけ静かな環境で学習させるようにしましょう。
しかし、音は突然聞こえるものなので防ぎきれない場合もあります。聞こえる音を小さくするイヤーマフの使用やデジタル耳栓、イヤホンのノイズキャンセリング機能を使うのも1つの手です。
疲労がたまらないようにする
ADHDの子が集中して学習するためには、疲労をため過ぎないことも大切です。集中しすぎる場合など、親が適度にコントロールしてあげてもよいでしょう。
発達障害の子は、周りからの刺激をダイレクトに受けやすく、普通の生活でも疲れがちです。疲労の自覚がない子もいるので、疲れがピークになるまで好きなことをやり続ける場合も。突然、電池が切れたように動けなくなる子もいます。
学校での学習に集中できるよう、生活リズムを整えてあげたり、そろそろ休むよう声掛けをしたりするのがおすすめです。
ADHDの子の受験勉強の工夫
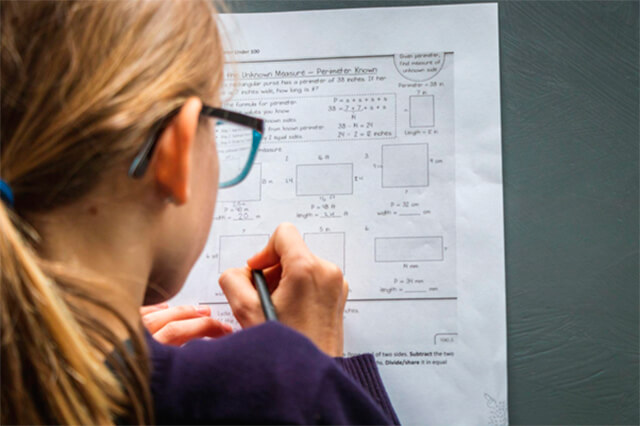
ADHDの子が受験に臨むとき、志望校に合格できるようフォローも大切です。ADHDの子が効果的な受験勉強をするための工夫を3つ紹介します。
志望校選びは慎重に
慎重な志望校選びがADHDの子には必要です。自分の特性にあったテスト方式を取り入れている学校だと、合格の可能性が高まるためです。
例えば、得意科目や分野の配点が高い学校だと、苦手分野があってもカバーできます。マークシート方式で転記ミスをしてしまうタイプは、記述式問題が多く配点の高い学校もいいでしょう。ケアレスミスを防ぎ、確実に点数を取ることができます。
学校で教わる範囲外の対策
志望校が決まったら、教科書の学習以外でテストに出そうな問題の対策も考えましょう。受験では、学校で教わらないことを出題するケースもあるためです。
受験勉強は、親では対策しきれない場合も多いものです。効果的に対策するなら、発達障害に理解のある塾や家庭教師の利用がおすすめです。子どもの特性に合わせながら、効果的な学習方法を模索してくれるでしょう。
得意不得意を把握して対策
ADHDを持つ子の受験には、子どもの得意不得意を把握し、特別な対策が効果的です。苦手分野をカバーするため、得意分野を重点的に伸ばすとよいでしょう。
しかし、発達障害の特性のある子どもに、親が勉強を教えるのは大変難しいことです。反抗期などで親の言葉に反応する時期は、声掛けが逆効果になる場合も。ナーバスな受験の時期、親子関係が悪化するのは避けたいところでしょう。
特性を持つ子どもの勉強は、プロに任せた方が安心です。発達障害の生徒を受け入れ可能な塾や家庭教師に依頼するのもよいでしょう。親は生活面のフォローに専念でき、子どもとの信頼関係を保ちながら受験に向かえます。
ADHDを持つお子さんの受験対策なら、オンライン家庭教師ピースをお試しください。発達障害や不登校の指導実績が豊富で、万全のサポート体制が特徴です。お子さんの特性に合わせた指導で、学習面を中心に総合的なフォローアップを行います。
ADHDのお子さんは対人面での不安を抱える場合も多いでしょう。採用率5%の選考を突破した3000人以上の講師が在籍しており、お子さんに合う先生をマッチング可能。大学生講師も在籍しているため、身近な先輩として学習以外の相談もできるのが魅力です。
また、担当教師が宿題スケジュールを無料作成し、ADHDのお子さんが計画的に学習できるようサポートします。まずは無料体験授業にお申込みいただき、オンライン家庭教師ピースのよさを体感してください。
ADHDの子の勉強への親の関り方

ADHDの子には、親の関わり方も重要です。どのような関わり方がよいのか、3つのポイントに分けて解説します。
勉強しやすい環境を整える
家庭では、ADHDの子が勉強しやすい環境を整えてあげましょう。気が散りやすいため、静かで物の少ない場所を用意します。
スマホが近くにあると脱線しやすいので、勉強中は離れた場所におくとよいでしょう。子どもが納得したうえで、スマホ依存対策のアプリやタイムロッキングコンテナの使用が効果的です。
いいところを褒めて伸ばす
いいところを褒めて伸ばすのは子育ての基本です。特にADHDなど発達障害を持つ子は失敗も多いため、意識的にほめてあげましょう。
発達障害を持つ子は、固定観念にとらわれないのでユニークな答え方をすることがあります。ADHDの子が持つ豊かな発想が課題解決の近道となることも。個性をつぶさないためにも「そういう考え方もあるんだね」と認めてあげるとよいでしょう。
特性を把握して有効な声掛けを
子どもの特性を把握すると、子どもに伝わりやすい声掛けができるようになります。同じ診断名でも、特性は子どもによって違います。ADHDの特性を踏まえつつ、子どもをよく観察し声掛けを工夫するとよいでしょう。
例えば、集中力がないタイプは、指示が長いと理解できない可能性があります。短い文章で伝えたり、図やイラストを使うと理解しやすいです。予定を気にするタイプなら、予定リストを一緒に確認すると安心します。
ADHDのお子さんにおすすめの習い事

ADHDのお子さんは、興味のある対象には強い集中力を発揮することがあります。興味・関心に沿った習い事を始めると、“水を得た魚”のように生き生き取り組む姿が見られるかもしれません。
また多動や不注意といった特性を踏まえると、集団活動よりも個人で取り組む活動の方がおすすめです。ADHDのお子さんに向いている習い事を5つ、紹介します。
スイミング
スイミングは、ADHDのお子さんに特におすすめできる習い事です。
水泳は、区切られたコースを一人でまっすぐ泳ぎ進めるスポーツです。周囲を気にせず、目の前のゴールだけに集中しやすいため、ADHDのお子さんも取り組みやすいといわれます。
また水泳は、浮力を受けながら全身をまんべんなく使います。体幹が弱かったり、姿勢の維持が困難なADHDのお子さんでも、比較的負担が少なく運動できる点もメリットです。
スイミングスクールは、規模や生徒数に注意して選びましょう。大規模スクールでは、周囲のざわつきが気になったり、順番待ちの長さがストレスになったりするかもしれません。できるだけ小規模なスクールを選んでみてください。
ダンス・リトミック
ダンスやリトミック(音楽に合わせて身体を動かす運動)も、ADHDのお子さんにおすすめの習い事です。じっとしていられない、常に動き回りたい多動傾向のお子さんに、特に向いています。「身体を動かしたくて仕方ない!」という欲求を存分に満たせるでしょう。
ダンスと一括りにいっても、ヒップホップやロック、ジャズなどさまざまなジャンルがあります。お子さんの好みに合うジャンルを探してみてください。
バレエやフラダンス、チアダンスなどもおすすめです。
ピアノ・楽器
音楽やリズム遊びが好きなお子さんには、ピアノなど楽器を習うのもおすすめです。音楽は脳に良い刺激を与えてくれますし、指先の微細運動トレーニングにもなります。感性と身体とを同時に育てられる習い事だといえるでしょう。
また楽器は、レッスン形態が先生と1対1である教室が多い点も要チェックです。マンツーマンレッスンなら、周囲が気になって集中できない、順番を待つストレスが多いといった心配も少なくて済みます。
リトミックはADHDの音楽療法でも使われています。ただし、習い事としてのリトミックは音楽に合わせて身体を楽しく動かすことを重視するのに対し、療法としてのリトミックはお子さんの課題を克服する手段として用いられる点が異なります。
公文
公文も、ADHDのお子さんに合った習い事の一つです。
公文は、自学自習のスタイルや、無学年制の教材が特徴です。自分のペースで、自分の課題に黙々と取り組む形態は、こだわりが強く出やすいADHDのお子さんでも進めやすいようです。
ただし、同じ公文の教室でも、教室ごとに先生の個性や雰囲気は異なります。お子さんに合った教室を見つけられるよう、いくつかの教室を見学してみましょう。
また公文は、教室で学習する日以外は宿題が出ます。ご家庭でサポートが必要になる点も押さえておきましょう。
芸術系
絵画や造形など、芸術分野に興味を示すお子さんなら、クリエイティブな習い事をさせてみても良いでしょう。
ADHDは興味を持った対象には周囲が驚くほどの集中力を見せるため、思いがけない才能が開花するかもしれません。お絵描き教室や造形教室、工作教室など、クリエイティブな習い事を探してみてください。
「飽きっぽい」「すぐに興味が移り変わる」といわれるADHDですが、裏を返せばアイディアが次々と浮かび、好奇心がわき続けているということ。豊かな発想を形にできる芸術系の習い事もおすすめです。
お近くに芸術系の教室がない場合は、オンライン受講も検討してみましょう。
ADHDのお子さんが習い事をするメリット

習い事は、学校とは違った人間関係やコミュニケーションを学べる場でもあります。先生や仲間とやり取りを通じて適度な距離感を知る、挨拶や礼儀作法を学ぶ、そして社会性が身につくことも期待できるでしょう。
ADHDの特性の一つに、「場の空気や相手の表情を読んだコミュニケーションが苦手」というものがあります。反対に気分が乗っている時や気に入った相手となら、とても良い人間関係を築ける子もいます。
良い人間関係やコミュニケーションのためにも、ADHDに理解がある教室や先生を見つけてあげましょう。
ADHDのお子さんは、学校や集団で困難を感じる場面が多いため、結果的に勉強や運動面の遅れなどが心配になることが多いようです。遅れをカバーするために、またお子さんならではの良さを伸ばすためにも、習い事はおすすめできます。
ADHDのお子さんが習い事を通じて得られるメリットを、3つ解説します。
達成感や自己肯定感が得られる
習い事の多くは、「できないことをできるようにさせる」ようにレッスンが組まれています。子どもたちも、習い事で「できるようになった!」という達成感を得やすい点がメリットです。達成感は自己肯定感向上にもつながり、お子さんの精神的な落ち着きにも寄与します。
また達成感や自己肯定感は、モチベーションの向上にもつながります。できるだけたくさんの達成感を得られるよう、お子さんが頑張りたいと思える習い事を選びましょう。
幅広い人間関係やコミュニケーションを学べる
自分の居場所ができる
ADHDのお子さんには“居場所”が必要だ、といわれることがあります。居場所とは、その子が安心して自分をさらけだし、リラックスしながら過ごせる場所のことです。過緊張や多動など、心身とも疲れをためやすいADHDのお子さんにとって、習い事が「居場所」となってくれれば、親としても安心できます。
学校のように複雑な人間関係や利害関係が生まれにくい点でも、習い事は居場所になりやすいといわれます。お子さんが伸び伸びと過ごせる場所を、確保してあげてください。
ADHDのお子さんが習い事を選ぶときのポイント

ADHDのお子さんが習い事を選ぶ際は、本人の特性に合っていて、理解ある先生がいる教室を選ぶことがとても大切です。
習い事選びで失敗しないために押さえるべきポイントを5つ、解説します。
1. 教室の規模に注意する
まず「教室の規模」に配慮しましょう。規模の大きさと、気が散る要素量とは比例します。大きな建物に大勢の子どもたちを集め、にぎやかに指導する習い事だと、注意が散漫になりやすく、レッスンに集中できない懸念もあります。
ADHDのお子さんには、適度な規模で、落ち着いてレッスンを受けられる雰囲気の教室を選ぶのがポイントです。マンツーマン指導がベストですが、仲間がいた方が頑張れる性格のお子さんなら、少人数(5人程度)のクラス指導を試してみても良いでしょう。
お子さんの特性と合う習い事をチョイスする
習い事はお子さんの特性や興味に合ったものを選びましょう。
ADHDのお子さんにおすすめの習い事を先に紹介しましたが、ADHDの全員にスイミングやダンス、公文が合うわけではありません。多動性が強いタイプと注意欠如が強いタイプとでは、向いている習い事も異なります。
さらに「多動のお子さんにはダンスやスイミングなど、身体を動かす習い事が向いている」「マイペースなお子さんには公文がいい」というのも、一般論でしかありません。
日々、お子さんの様子を最も近くで見ている親御さんだからこそ分かる、「お子さんに合う習い事」を探してみてください。
ADHDに理解がある教室・先生を選ぶ
ADHDは一般に知られるようになってきたとはいえ、まだ無理解の壁に直面することもあります。習い事を選ぶ際は、教室や先生が「ADHDに対して理解があるか」も確認しましょう。
集団行動やチームプレイが苦手でも、ADHDに理解がある先生がいる教室なら、サッカーや野球、バスケットボールなどに挑戦できるかもしれません。教室全体がADHDに対して理解があれば、先生がADHDのお子さんに付きっきりになっても、自然と受け入れる雰囲気が感じられるでしょう。
教室見学の折は、お子さんがADHDであることを伝えて話を聞いてみてください。また過去にADHDのお子さんを指導した経験があるか聞いてみても参考になります。
サポートブックを作る
「サポートブック」とは、お子さんの特性や必要なサポートを記録したツールのことです。お子さんに合った関わり方や注意してほしい点をまとめておき、初めてお子さんに接する方でも最適なかかわり方ができるよう補助するのが目的です。園や学校では専用書式のサポートブックが用意されることが多いのですが、ご家庭で作る場合は簡単なフォーマットで構いません。
サポートブックがあると、初回レッスンからお子さんに合った関わりをしてもらいやすくなります。お子さんの安心感も増し、習い事を続ける意欲にもつながります。
体験レッスンを必ず受ける
習い事を選ぶ際は、体験レッスンを必ず受けましょう。ADHDのお子さんの中には、気分にムラがあったり、初めての場所が苦手だったりするケースもあります。体験レッスンなしに入会を決めてしまうと、入った後に「こんなはずじゃなかった」「行きたくない」という親子衝突になりかねません。
体験レッスンを受けると、お子さん自身の習い事に対する理解が深まります。ミスマッチも減り、安心して通える心理的準備も整います。
ADHDのお子さんが習い事を続けられるコツ

飽きっぽかったり、こだわりがあったり。ADHDのお子さんには、それぞれ際立つ特性があります。習い事を続けるには、お子さんの個性に合ったサポートが大切です。
ADHDのお子さんが習い事を続けやすくなる、サポートのコツを解説します。
スモールステップを大切にする
ADHDのお子さんは、「周囲と同じように活動する」ことが苦手です。必然的に“できないこと・できない場面”に遭遇し、できない自分を実感せざるを得ないことが多くなります。これでは自己肯定感もやる気も低下するばかりです。
そこで、習い事ではスモールステップを意識してみてください。毎回のレッスンの度に小さな目標を設定し、「できた!」成功体験を積み重ねられるようにするのです。設定する目標は、お子さんが少し頑張ればできる程度が適切です。目標をクリアできる自分に自信が持てるようになり、やる気やモチベーションにもつながります。
親は承認とサポートに徹する
習い事を始めたら、親御さんは承認とサポートに徹するのが長続きのコツです。
「上達してほしい」「進級してほしい」という思いから、ついお子さんにアドバイスや指導をしてしまいがちですが、そこは教室にお任せし役割分担としましょう。
お子さんは教室に行き、一生懸命に先生の話を聞き、頑張っています。帰宅してからも「こうしたら?」と指摘されては、気持ちも疲れてしまうでしょう。
親からの承認は、子どもにとって何よりのエネルギー源です。親御さんの役割は承認とサポートだと押さえておきましょう。
無理をさせない
長続きのためには、無理をさせないことも大切です。お子さんのADHD特性を見極め、負担になりすぎないようバランスを取ってあげましょう。
体幹が弱く、筋力が十分でないお子さんが運動系の習い事を始めると、当然疲れます。こだわりが強く、自分のペースで進めたいお子さんは、習い事のルールや方針に慣れるまでストレスを感じるかもしれません。
大人が思う以上に、お子さんは環境の変化に敏感です。「これくらいはできるでしょ!」と無理させるのではなく、時には休みも挟みつつ、のんびり構えてみてください。
教室や先生と密にコミュニケーションを取る
教室や先生と、お子さんの様子について積極的にコミュニケーションを取ることも大切です。習い事の先生は、レッスンに来ているお子さんしか見ていません。学校や家庭の様子を知らせると、よりお子さんに対する理解が深まり、お子さんに合ったやり方で指導してもらえるようになります。
対面や電話、メール、LINEなど、どの連絡手段が良いかは、教室や先生に確認しておきましょう。また連絡の際は、レッスン中や生徒が出入りする時間帯など、忙しい時間を避ける配慮も大切です。
まとめ
ADHDのお子さんは人一倍、挫折を味わいやすいゆえに、習い事を通じて達成感や自己肯定感を高めるのは、効果的なアプローチです。
ただ、ADHDのお子さんは、文字通り一人ひとり個性や得意や不得意、困難を感じる場面が違います。習い事を選ぶ際は、お子さんの特性に合わせて、お子さん自身が「楽しい!」「やりたい!」と思えるものを選ぶようにしましょう。
入会前には見学や体験レッスンを受け、実際のレッスンをイメージしやすくするのも大切な準備です。体験レッスンを受けたからといって、入会しないといけないということはありません。気になっている習い事は、まず体験レッスンを受けてみてください。
















