「部活を辞めたい」とお子さんが言ってきたらどうする?親の対応方法やアドバイスのコツ
お子さんが「部活、辞めたい」と言い出した!さあ、親としてさまざまな心配が脳裏をよぎりますね。無理に続けさせても良い結果にならない気もしますし、かといって、ここまで続けてきたのに、ともったいなく思う気持ちもあるでしょう。
お子さんの「部活を辞めたい」気持ちに対して、親はどのように対応するのがベストなのでしょうか?
アドバイスの仕方やケース別の対応法、親の関わり方のポイントなどについて解説します。
部活を「本当に辞めて良いのか?」と迷う理由

「辞めたいからといって、辞めて本当に大丈夫なのか?」と、心配がよぎる原因を考えてみましょう。多くの親御さんに共通する心配を4つピックアップし、解説します。
心配1.「辞めグセ」がつかないか心配
「辞めグセ」とは、辛くなるとすぐ逃げ出してしまう、辞めることで問題の幕引きをはかろうとする心理のことです。「逃げグセ」とも言われます。
辞めることで問題との関わりを絶つのは、自分を守る方法の一つです。ただ、辞めグセは「癖」というだけあって習慣化しやすいのが難点。大人になり仕事に就いたときも、すぐ辞めてしまうのではないか、忍耐力や根気が身に付かないのではないか、と心配する親御さんもいます。
辞めグセが心配な場合は、なぜ辞めたいと思ったのか、原因別に対処することが大切です。後ほど、原因別の対処法をまとめていますので、あわせてチェックしてみてください。
心配2. 辞めたあとの人間関係が不安
部活を辞めたあとの人間関係を心配される親御さんもいます。
学校は非常に狭い人間関係で成り立っています。部活を辞めても、仲間や顧問と顔を合わせる機会も多いでしょう。顔を合わせたときに気まずいのではないか、辞めたことを理由に友達関係が悪化するのではないかと心配になるのです。
また人間関係のもつれから不登校になっては困る、と心配するケースもあります。
心配3. 内申点への悪影響が心配
「内申書」には、中学校生活のさまざまな記録が記載されます。ただ、どのような内容が書かれるのか、生徒やご家庭は把握できません。何が書かれるかわからないからこそ、「部活を辞めたことをマイナスに書かれては困る」と心配されるケースもあります。
ただし、この心配は杞憂であることがほとんどです。内申書には部活で好成績を残したなどのプラス要素は書かれても、「退部」については言及されないからです。
心配4. 辞めたことを後悔しないか不安
せっかくやりたいとはじめた部活、辞めたことを後悔してはかわいそうだと、案じる親御さんもいます。
退部を後悔するかどうかは、辞める理由によります。一時的な気の迷いなら、辞めてしまってから後悔するかもしれません。一方で、人間関係やどうしても解決できない問題が原因だった場合は、退部を後悔することはほとんどないでしょう。
辞めたあとまで想定し、お子さんとよく話し合うことが大切です。
お子さんにとっての優先順位をよく考える

中には勉強との両立ができずに、部活をやめることを考えるお子さんもいます。
その場合の対応方法についても解説していきます。
部活を引退まで続けるべきか、受験勉強のために辞めるべきか。これには、正解はありません。
部活には部活でしか得られないものがあります。一方、受験勉強は早いスタートを切るのに越したことはないのです。
正解がないからこそ、【自分にとって一番大切なこと】をじっくり考え、決めることが大切。後になって「あの時、やっぱり〇〇しておけば……」と思っても取り戻せません。
「部活を続けるか/辞めて受験勉強に専念すべきか」に悩んだら、それぞれのメリット・デメリットをお子さんと整理してみることをおすすめします。
たとえば以下のような表を作り、思いつくだけのことを並べてみても良いでしょう。
| メリット | デメリット | |
| 高3の引退まで部活を続ける | ・
・ ・ |
・
・ ・ |
| 部活を辞め勉強に専念する | ・
・ ・ |
・
・ ・ |
「書き出す」ことで、自分の気持ちや譲れない思いを客観的に捉えられるようになり、考えがまとめやすくなりますよ。
また「今決めなきゃ!」と焦る必要もありません!
しばらく考えても結論が出せなければ、もう少し部活を続けてみるという方法もあります。
時期が変われば、状況も変わるもの。テストや模試結果を見て、気持ちが変わるかもしれませんし、部活の大会が終わって決断しやすくなるかもしれません。
高校生活は一生に一回だけです。
周りに流されて大切なことを見失ったり、自分の本心とは異なる決断をすることがないよう、自分の内面とじっくり向き合うのも大切な時間です。
今日からぜひ!部活と勉強を「両立」させる方法
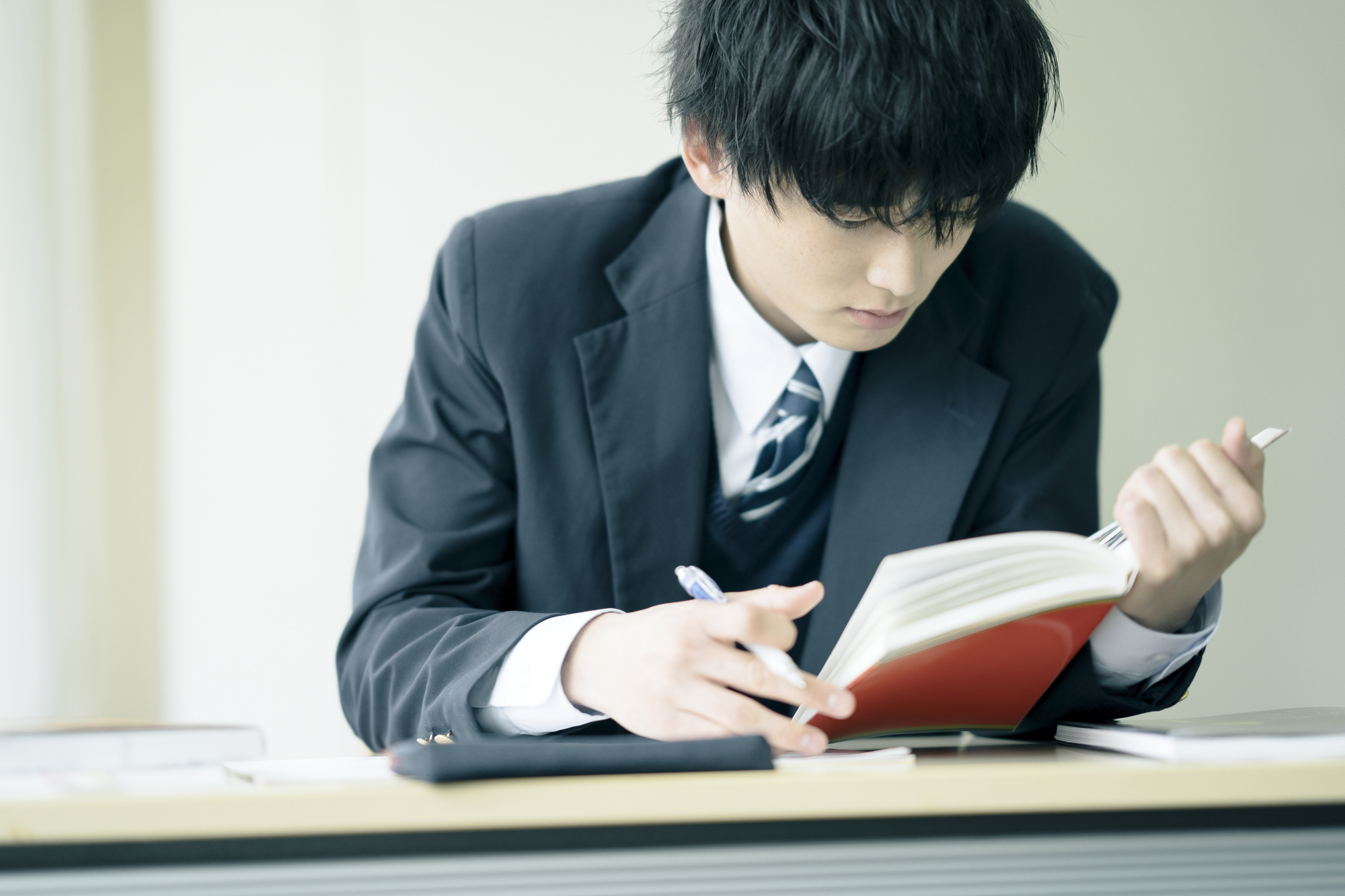
……とはいえ!!!
受験が待ってくれないのは事実です!
自分が部活をやっている間に、勉強を進めるライバルがいるのも、また事実……!
大学受験本番では、「部活をやっていたから勉強が間に合いませんでした」という言い訳は通用しません(目覚ましい実績を持つ場合は、推薦入試や総合型選抜の受験を考えてみるという手もありますが)。
「現役合格したい」という希望があるなら、部活と勉強の「両立」に挑戦しましょう。
ここからは部活真っ最中でもできる「要点をおさえた勉強法」を解説していきます。
部活生の勉強法① 毎日1時間でも勉強する!と決める
まずは決心しましょう。「どんなに疲れていても、必ず1時間は勉強する」と覚悟を決めてください。
「両立」と言うは簡単ですが、実践し続けることは、はっきり言って大変です。「今日は寝ちゃおうか」という誘惑に駆られる日がいかに多いことか!
そんな時に自分を奮い立たせてくれるのは、自分との約束を守るという「強い決心」しかありません。まずは気持ちを強く持つこと。このワンステップが、後々の”さぼり心”に効いてきます!
部活生の勉強法② 帰宅後は即!机に向かう習慣をつけよう
部活と勉強の両立には、「帰宅後、即机に向かうこと」がコツ!
帰宅後、「疲れたぁ~!」と横になってしまって、もう動くのが嫌になる…、そんな時ってありますよね。人間、横になった姿勢でやる気を出すというのは、なかなか難しいんだそうです。
だから、帰ったら即、机に向かい勉強を始めるようにしましょう。一息つく隙を与えないのがポイントです。
帰宅後はまず夕食、という場合は、単語帳やノートなどを脇に置き、「食べ終わったら勉強だ」と気持ちを整えながらいただきましょう。
とにかく、帰宅後に休んでしまわないこと!これが、部活をしながら勉強も頑張れる生活スタイルですよ。
部活生の勉強法③ 隙間時間をフル活用しよう!
2つ目、「隙間時間の活用」はよく言われますね。生活の中の隙間時間を見つけ、勉強に充てていきましょう。
短い時間が何度もある「隙間時間」には、暗記系の勉強がピッタリです。英単語や公式、重要用語など覚えるべき教材を持ち歩いておくと、隙間時間を無駄にせずすぐに取り組めます。
アプリも積極的に使っていきましょう!
勉強時間を記録できるものや英単語のアプリなど、さまざまな種類がリリースされていますから、使いやすいものを見つけてみてください。
部活を頑張っている高校生は、「自分は全然勉強できていない」という焦りが生まれやすいもの。でも、覚えた単語帳のページに印をする、アプリで勉強時間を記録する等、「勉強したこと」を記録していくと、自分の努力が目に見えるようになり、自身につながっていきます。
部活生の勉強法④ 勉強効率を上げる「できないことを、できるようにする」意識
短時間の勉強で効果を上げるには、勉強の効率を上げることが大事。そのためには、勉強する内容の見極めも意識していきましょう。
具体的には、「できないことを、できるようにする」勉強をすること。1日ひとつでもいいので、「できないことを、できるようにする」という勉強を取り入れてみてくださ。
「できないことを、できるようにする」なんて、当たり前のように聞こえますよね。
でもこれ、意識してみるとわかりますが、とても脳を使うので無意識のうちに避けがちなんです。特に部活で疲れているときは、なおのこと!
「復習だ」といって、できていることの確認をして「勉強したつもり」になったり……、そんなことはしていませんか?できることを何度繰り返しても、現状からは変わりませんよ。
勉強時間が少ないはずなのに、成績が良いアイツは、きっと「できないことをできるようにする」勉強を徹底しています。自分ができないことに真摯に向き合い、克服するための勉強を取り入れていきましょう。
部活生の勉強法⑤ 部活生こそ、塾や家庭教師を活用したい!
部活生こそ、塾や家庭教師を活用しても良いでしょう。
個別指導塾や映像授業型の塾など、部活をしながらも通えるスタイルの塾は数多くあります。週に1回でも、真剣に勉強する高校生が集まる環境に身を置くことは、モチベーションにとっても良い刺激になります。
また部活生には、特にオンライン家庭教師もおすすめ。
オンライン家庭教師とは、自宅にいながらにして、1対1の細やかな指導が受けられると近年人気が高まっている教育サービスです。パソコンやタブレットなどの機材とインターネット環境があればどこでも授業が受けられるので、近くに自分に合う塾がないという場合も大丈夫。
対面のマンツーマン指導より割安なのも取り入れやすいポイントです。先生も常に自分を見て声をかけてくれるので、一方的に授業を聞き続けて眠くなる……、ということもありません。
部活の大会など、授業予定の変更にも柔軟に対応してくれます。部活も勉強も頑張りたいという高校生は、ぜひオンライン家庭教師を体験してみてくださいね。
合格までの学習計画や進捗管理もおまかせ!オンライン家庭教師のピース無料体験は>>>こちらから
部活を辞めたいというお子さんにアドバイスするなら

「部活を辞めたい」と相談されたとき、親にできるアドバイスを紹介します。
まだ成長途上のお子さんたちは、自分の価値観や殻に閉じこもり、近視眼的に判断してしまっている場合があります。大人ならではの視点で、物事を広く見るようなアドバイスを意識してみましょう。
「友達に相談しておいで」
まず「友達に相談すること、話すこと」を促してみましょう。“友達”とは、部活の仲間でも、部活以外の友達でも構いません。お子さん自身が「この子なら」と安心して本心を打ち明けられる相手であることが大切です。
友達には、自分の内面のあらゆる気持ちを吐き出せるものです。ときには親に言えないことを話すこともあるでしょう。お子さん自身の内面を言葉にし、友達に伝えることで、気持ちをスッキリさせ、落ち着かせるのが目的です。
また言葉にするうちに、混乱していた考えが整理されることもあります。
「顧問以外の信頼できる先生に話してごらん」
顧問以外の信頼できる先生がいるようなら、先生に相談するよう促すのもおすすめです。客観的な視点からアドバイスをもらえることもあり、視野が広がることも期待できます。
また、部活を辞めると内申点に影響があるか、それとなく聞き出しても良いでしょう。退部が内申書に悪影響を与えることはないのですが、学校の先生の口から「大丈夫だよ」と言ってもらえる点が重要です。親が言うよりも説得力があり、お子さんの安心感につながります。
「ちょっと美味しいものでも食べに行こうか」
「ちょっと美味しいものでも食べに行こうか」と、お子さんを誘い出すのも有効です。気分転換になりますし、お子さんと向きあって話をよく聞ける機会にもなります。
「外に出かける」のがポイントです。家だとつい、家事や他のことが気になり、お子さんと向きあう気持ちになりにくいことも多いからです。大切な話を聞く際は、「話すこと」だけに集中できる環境を用意してみましょう。
原因別!お子さんが部活を辞めたいときの親の対応方法
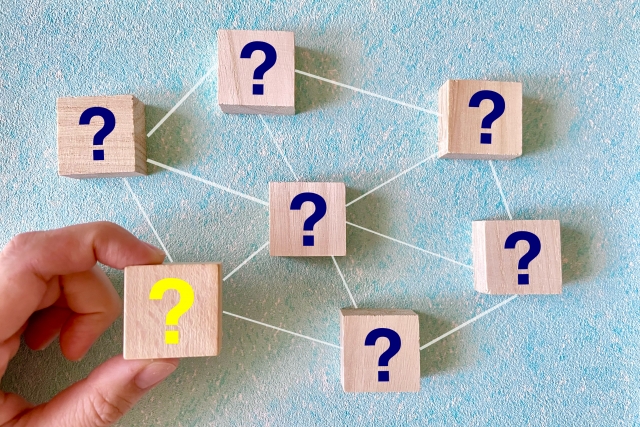
お子さんが「部活を辞めたい」と言ってきた原因によっても、親ができる対処法は変わります。部活を辞めたい理由で多いものは、次の4つです。
- 一次的な気の迷い、わがまま
- 人間関係の悩み
- 勉強との両立が難しい
- 他にやりたいことが見つかった
お子さんの話をよく聞き、原因がわかったらそれぞれ対処していきましょう。原因別の対処法を解説します。
一時の迷いやお子さんのわがままの場合
一次的な迷いやわがままで「辞めたい」と言っている場合は、初心を思い出させる声かけが有効です。どうしてその部活をやりたいと思ったのか、きっかけは何だったのか、一緒に思い出してみましょう。
入部前に抱いたイメージと、入部後の実際とにギャップがあるのは当然のことです。耐えきれないほどのギャップなら退部も視野に入れ、わがままを言っているだけならもう少し続けさせるのも方法です。
ただし親が思う以上にお子さんが思い詰めている場合もあるので、注意しましょう。継続の提案は、「夏休み前まで」など期限を区切るとお子さんのモチベーションも維持しやすいですよ。
顧問や仲間との人間関係に悩んでいる場合
人間関係の悩みは、深刻度合いによって対処法が変わります。
「先輩にキツイことを言われた」「顧問の言い方が気に入らない」といった程度なら、人間関係の我慢を学ぶ機会でもありますし、改善策を探すのも方法です。
ただ「イジメにあっている」「持ち物を隠される」などの陰湿さが感じられる場合は、スッパリ辞めても良いでしょう。改善を図っても解決までに時間がかかり、その間お子さんがつらい思いをし続けること、また本当に改善されるかどうか確証も持てないからです。
勉強との両立が課題である場合
部活と勉強の両立に悩んでいる場合は、部活に対するお子さんの本心を確認しましょう。内心では「辞めたくない」と思っているならば、両立できる方法を探し、サポートするのがおすすめです。
部活を辞めた方が勉強時間ができ、成績も上がると思われがちですが、実は部活と勉強を頑張って両立した生徒の方が土壇場の踏ん張りが利くケースも多いのです。時間を効率的に使えるようになるチャンスだととらえ、両立の方法を考えましょう。
自宅で授業が受けられるため、通塾の時間が節約できるオンライン家庭教師などの選択肢もおすすめです。
他にやりたいことが見つかった場合
成長するにつれ興味の対象が広がり、他に力を入れてやりたいことが見つかった、という理由で部活を辞めたいということもあります。部活を辞めるデメリットも伝えた上で、お子さん自身の選択を尊重すると良いでしょう。
ただし、精神的に成熟途中の子どもたちは、選択の局面において「0か100か」といったオール・オア・ナッシング思考になりがちです。やりたいことに意識を集中させたいからと部活を辞めるのが、本当にお子さんにとって良いかどうかはわかりません。意外と部活が息抜きになっていたり、友達との交流を深める時間になっていたりすることもあるからです。
経験を積み、大局的に物事を考えられる大人だからこその「やりたいことと部活の両立」という選択を提示するのもおすすめです。
部活を無理なく続けられる方法

部活を続けよう!頑張ろう、と気持ちが変わることもあります。しかし、一度「辞める」方に傾いた気持ちを立て直すのは、楽ではありません。理由があって「辞めたい」と思ったわけですから、改善が必要なポイントもあるはずです。
ここからは、「やっぱり部活を続けよう」と気持ちを切り替えたお子さんに必要な配慮について、解説します。
ペース配分を見直す
それまで部活に全力投球だったお子さんには、「ペース配分を見直す」アドバイスが必要です。以前と同じ加減で部活を頑張っていては、またモチベーションが下がる原因になります。良い意味で手を抜くことを教えてあげてください。
負担が少ない部活に転部する
取り組むペースを自分でコントロールするのが難しい部活、たとえば団体競技や吹奏楽などを頑張っていた場合は、負担の少ない部活に移るのも方法です。転部も内申書に書かれる心配はありません。お子さん自身が転部を前向きな選択だととらえられるよう、声をかけることも大切です。
目標を変える
「絶対レギュラーになる!」など、高い目標を掲げていた場合は、思い切って目標を変えるのもおすすめです。たとえば「好きなスポーツを仲間と楽しめれば十分」「頑張る仲間を応援しよう」といった具合ですね。
目標を変えたことは仲間にも積極的に伝え、理解を得ておくと誤解されずに済みます。
勉強方法を工夫する
勉強との両立に悩んでいる場合は、勉強方法を工夫してみましょう。隙間時間を積極的に活用する、学習アプリを利用する、勉強のやり方を変えるなど、改善できるポイントはたくさんあります。塾やオンライン家庭教師に、勉強法の相談をするのもおすすめです。
お子さんの気持ちを尊重しつつ、長期的視点で考えることが大事

子どもが部活を頑張る姿、それを応援したくなるのが親心です。しかし、中には応援が行き過ぎ「辞めたいのに、親が辞めさせてくれない」と悩むお子さんもいるのだとか。
「引退まであと数か月なんだから、最後まで頑張りなさい!」「途中で投げ出すと、辞めグセがつくよ!」と親に言われ、一人で悩んでしまうお子さんも少なくないそうです。
頑張りなさい!と言いたくなる親御さんの気持ちもわかりますが、まずはお子さんの気持ちをうけとめてあげましょう。お子さんは、お子さんなりに考えがあり、悩んでなやんで「辞めたい」と言ってきたはずです。頭ごなしに「続けなさい」と言われても、モチベーションが上がるはずはありませんよね。
一方で、親だからこそ、言えることもあります。自分自身の経験やお子さんの将来、学校の様子などを総合的に考え、長期的なアドバイスを与えることです。お子さんの成長に責任を持てるのは、親であるあなただけです。部活を続けることと辞めることを広く考え、お子さんをサポートしてあげてください。
まとめ
子どもたちの学校生活で、部活が持つ意味は小さくありません。目標に向かって一致団結し、“みんなで頑張る”雰囲気を持つ部活動は、子どもたちに「部活=自分の世界のすべて」と感じさせやすい要素でもあります。
しかし、部活は決してそれだけが人生のすべてではありませんし、「辞める」選択をしても何の問題もありません。
大切なのは、お子さんが自分でしっかり考えて結論を出すこと。そして親はお子さんの話をよく聞き、必要なアドバイスを適切なタイミングで与えることです。「辞めるか、辞めないか」の選択は、人生で数多く遭遇します。経験値を積むチャンスだととらえ、親子でじっくり向き合っていきましょう。
















