ルーズリーフを使った勉強法で成績アップ!勉強がはかどるおすすめの活用法まで解説!
皆さんは、日々の勉強にルーズリーフを取り入れていますか?「ルーズリーフなんか使わなくても普通のノートで十分だ」と思っているそこのあなた。それは大きな間違いです。ルーズリーフには普通のノートにはない利点がたくさんあります。 この記事ではルーズリーフを使った勉強法を詳しく紹介していきます。最後におすすめの商品も載せておりま す。
ルーズリーフ勉強法とは
ルーズリーフとは、バインダーなどで綴じるための穴が開いている用紙のことです。ここではルーズリーフを使って勉強の効率を上げ、成績を伸ばすための方法を紹介していきます。普通のノートではできない勉強法も紹介していきます。
基本的な使い方①まとめる
使い方はシンプルです。大事だと感じたポイントをまとめていけばいいのです。未来の自分が理解しやすいかどうかを常に意識してまとめていきましょう。次第に自分だけの参考書が出来上がっていきます。
基本的な使い方②問題を書き込んで解く
問題集やワークの問題を書き込んで解いていくのも良いでしょう。問題集に答えを書き込んでしまえば、その問題はもう使えませんが、ルーズリーフに解けば問題集の方に書き込まずに済むのでまた使うことができます。写すのが大変なら問題をコピーして貼ってみてください。
基本的な使い方③捨てる
もう習得したと思える問題と解答はノートから外していくことができます。もう必要ないと思える場合は捨てても良いですし、どこかに保管しておいても良いでしょう。ノートの中身が常に自分にとって重要な情報だけ担っているのがルーズリーフの便利なところです。普通のノートではこのようにはいきません。
基本的な使い方④必要な用紙だけ抜き出す
ルーズリーフは必要なページだけを抜き出すことができます。この特性を利用すればいちいち全ての紙を持ち歩く必要はなくなり、各教科の苦手問題ばかりを集めて持ち、学校で解くこともできます。 また、単元ごとではなくランダムな順番で問題を解けば、より一層試験本番と同じような条件で勉強を進めることもできます。
勉強の基礎となるノート作り
学生の多くは授業中に板書をノートに記録して満足しているでしょう。そのため、「なんとなくノートを取って終わり」となる方がほとんどです。 しかし、ノート作りは勉強の基礎となる重要なものです。 ここで、まずはノートを作る目的やメリットについて解説していきます。
ノートを作る目的
ノートを作る目的は下記の3つがあります。
- 予習
- 復習
- 授業の記録
授業の記録としてのノート作りは学校で行っています。そのため、個人的に行うノート作りは予習ノートと復習ノートです。 予習ノートで授業内容を前もってインプットしておきます。そして授業を受け、復習ノートで学習内容についてアウトプットして定着させます。 このように目的に合わせてノートを分ける必要があるため、教科ごとに3冊のノートを用意しましょう。
ノートを作るメリット
ノート作りを行うことにはいくつかのメリットがあります。 そのうちの5つをご紹介します。 まず1つ目は勉強効率がアップすることです。 予習ノートを作っておくことで、理解できなかったポイントを分かった上で授業を受けられます。 また、その範囲の知識を整理することができるため、効率的に勉強を進められるようになります。 次に2つ目は学習内容の定着です。 授業の記録だけをしていても学習内容は定着しません。その内容に関してアウトプットする必要があります。予習ノートと復習ノートを使い、インプット・アウトプットを繰り返すことで学習内容が定着します。 3つ目は苦手を見つけられることです。 予習ノートを作っておくことで、苦手分野を見つけやすくなります。また、復習ノートにも苦手をまとめておくことで自分の苦手を理解することができ、効率的に勉強を進められます。 4つ目は学習を習慣づけられることです。 ノート作りを毎日行うことで、学習習慣が自然と身につきます。難しい問題を解く必要もないので、ハードルは高くないでしょう。 最後に5つ目は自主的に勉強しているという自信がつくことです。 この自信がつくことで自分で考え行動する力が身につきます。将来学校を卒業した後もこの自信があることで大きく飛躍できるでしょう。
ノート作りの注意点
次にノート作りの注意点を解説していきます。学生がノート作りをする上で注意すべき点は以下の8つです。
- 学校用以外はきれいに作らなくていい
- 重要語句はオレンジペンで書く
- 色ペンを使いすぎない
- 日付やテーマなどを記入する決まりを作る
- 余白を空けながら書く
- 予習ノートでは不明点を書き出しておく
- 復習ノートは授業を受けてすぐ作る
- 間違えた問題やわからなかった問題を書いておく
1つずつ詳しく見ていきましょう。
学校用以外はきれいに作らなくていい
ノート作りをする上で、多くの方は「きれいに作ろう」と意識しますよね。 学校に提出するノートの場合は、内申点に関わってきますのできれいに作ったほうが良いでしょう。 また、板書以外で先生が話していたことをメモに取ると、内申点アップに繋がります。 しかし、予習ノートや復習ノートは提出したり誰かに見せたりするノートではありません。 そのため、時間をかけてきれいに作る必要もないのです。 時間をかけてきれいに作るよりも、自分がわかりやすいかどうかを重視しましょう。
重要語句はオレンジペンで書く
ノートを作る際は重要語句をオレンジペンで書きましょう。 オレンジペンで書くことで、重要語句が目立ち、確認しやすくなります。 また、オレンジペンで書いたものは赤シートで隠して確認することもできます。 重要語句を覚えているか後で確認するためにも、オレンジペンで書くことがおすすめです。
色ペンを使いすぎない
前述したようにオレンジペンで書くことをおすすめしましたが、色ペンを使いすぎることには注意しましょう。 色ペンを使いすぎてしまうと、ごちゃごちゃして何が重要なのかわからなくなってしまいます。 見やすくするためにも、色ペンは3色以内と決めておきましょう。 この際、それぞれに役割をもたせておくとより効果的になります。 例えば、
- オレンジペン➡重要語句
- 赤ペン➡重要語句にまつわる内容
- 青ペン➡間違えやすい内容
と言ったように自分でその色の役割を決めておくことで、より見やすいノートを作れます。
日付やテーマなどを記入する決まりを作る
色ペンの役割以外にも、ノート作りをする上での決まりを作りましょう。 例えば、
- ページが変わったら最初に日付やテーマを記入する
- 教科書の対応ページを記入する
- 問題集の対応問題番号を記入する
といったようにどのノートでも同じ決まりを作っておくことで自分だけのノートを作れます。
見出しをつける
例えば、「接続詞の機能」「接続詞の種類」といったように、少し大きめの文字で自分なりのタイトルをつけましょう。こうすることで1ページの中にいくつかの意味ごとのかたまりが存在する形となり、非常に見やすくなります。
余白を空けながら書く
余白を空けながら書きましょう。 もったいないからといってギチギチに詰めて書いてしまうと、とても見にくいノートになってしまいます。 これではノート作りの意味がありませんよね。見やすいノートにするためにも1行2行くらいずつ行を空けて書くように意識してください。 また、行を空けておくことで後からコメントを書き入れたり、見返したりするときに使いやすくなります。
予習ノートでは不明点を書き出しておく
まだ習っていないところを勉強することが予習ノートです。 わからないところが出てくるのは当たり前のことなので、そのわからないところを書き出しておきましょう。 そして、そのわからなかったところについて自分なりに調べておくとより効果的になります。自分で調べておくことでより記憶に定着します。
復習ノートは授業を受けてすぐ作る
授業を受けたらできるだけその日のうちに復習ノートを作りましょう。 授業を受けて時間が経ってから復習しても効果は半減します。また、時間を空けておくとどんどん新しい授業内容が増えていくため、やる気も削がれてしまいます。 記憶が鮮明なうちに復習ノートを作りましょう。
間違えた問題やわからなかった問題を書いておく
間違えた問題やわからなかった問題を復習ノートに書いておきましょう。 この際、解き直しをしやすいようにスペースを取っておいてください。 間違えた問題やわからなかった問題だけを集めた4冊目のノートを作るのも良いでしょう。
教科別ノート作りのポイント
次にノート作りのポイントを解説します。 教科ごとにノート作りのポイントがありますので、そのポイントを活かしてノートを作りましょう。
英語
まずは予習ノートから説明します。 英語の予習ノートのポイントは英文と和訳をセットで書くことです。教科書の英文を書き、セットで和訳も書いておくことで、効率的に復習できます。 この際に和訳を隠して勉強し直したい方は、和訳をオレンジペンで書いておくと赤シートで隠せるのでおすすめです。 また、次の英文を書くときには行間を空けましょう。行間を空けることで、英文と和訳のセットが見やすくなります。 次に復習ノートの説明をします。英語の復習ノートは授業でわからなかった、または間違えてしまった単語や熟語をまとめましょう。単語や熟語は覚えなければいけないものなので、覚えられるまで何度も確認できるようにしておくことがおすすめです。
数学
数学は積み上げの教科と言われており、反復学習が重要となります。つまり、何度も復習することが大切です。 まず、予習ノートには間違えた問題を消しゴムで消さないように注意しましょう。 間違いは重要なアイテムになります。 なぜ間違えたのか、何がわからなかったかを意識して授業に取りかかってください。 そして、復習ノートでは授業で間違えた問題をコピーして貼り付けましょう。貼っておくことで、問題と解答部分の区別がつきやすくなります。 そして、間違えた問題は何度も自力で解けるまで挑戦してください。また、時間が経てば忘れることもありますので、できるようになっても再度挑戦するようにしましょう。
国語
国語のノートは下3分の1程度の部分をメモスペースにしましょう。 国語で重要になることは、感想や疑問です。授業で感じたことや疑問に思ったこと、先生の発言などを忘れないようにメモしておきましょう。 中学の定期テストでは教員が質問を投げかけた箇所が問題となって出ることが多いです。
- 「このときの主人公の気持ちは?」
- 「筆者は何を伝えようとしているの?」
といったような質問は欠かさずメモしておきましょう。
社会
社会は暗記科目です。授業では重要語句が次々と登場しますよね。 まず、予習の時点で教科書の太字をオレンジペンでまとめておきましょう。 この際、重要語句の説明は黒字で書くように気をつけてください。 全部オレンジペンで書いてしまうと赤シートで隠した際にほとんど見えなくなってしまいます。 また、復習ノートには太字だけでなく先生が強調していた内容に関してもまとめましょう。
理科
理科は暗記分野と計算分野があります。 理科の暗記分野は社会同様、重要語句をオレンジペンでまとめ、問題の関連事項についても徹底的に書き出します。 また、物理のような計算色のある分野に関しては、数学のように問題と自分の解答を区別できるように問題をコピーして貼り付けましょう。再び復習ノートを見直す際に、解けるまで何度も挑戦し、定着させてください。
上手にノートを取ることのメリット
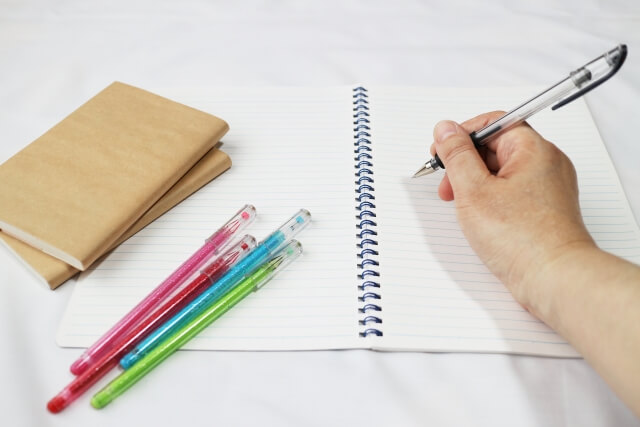
次に上手なノート術を自分のものにするメリットについてお伝えしています。正しいノート術を極めることは、あなたが思っているよりもずっと大切なことなのです。
ノートはポケットサイズの「黒板」である
ノートをきれいに、そして分かりやすく取ることは「黒板」を持ち運ぶことと同じようなものです。そうすれば、スキマ時間に手軽に復習ができるといったようにノートを効果的に使うことができます。
どんな参考書よりも最高のテキストになる
参考書は本屋さんに行けば手に入ります。そして、参考書には、先生が板書する内容や、塾で習うことも詰め込まれているのだからわざわざノートを取る必要はないのではないか。と生徒から質問されたことがあります。
その時、参考書とノートは全然別物なんだよ!と生徒に伝えたことがことがあります。。では、みなさんにお聞きします。参考書を常に持ち歩いている方はいますか。「重い」・「授業で使わない」という理由から学校に置きっぱなしになっている方も多いはずです。
確かに、参考書には大事なことが「全て」書かれています。しかし、その「全て」というのが裏目になってしまっていることに気づいていない生徒が多いのです。単元ごとの習熟度は人それぞれ違います。
当然、参考書でも苦手な単元を探して勉強しています。つまり、自分に必要な情報だけを選んでまとめておける「ノート」を分かりやすく作るということは勉強を効率的に進めるための最大の近道となるのです。ぜひみなさんも自分だけのオーダーメイド参考書を自分の手で作り上げましょう!
自分のことを把握できる
私も長く子どもたちに勉強の指導を行ってきました。子どもたちが人間的に一番成長しているなと感じる瞬間は「志望理由書」などで自分の想いを私とやり取りしているときでした。
自分はいったいどんな人間で、どんな想いを持っているのか、私と話をして、書き出していく中でそれに気づき、今後の方向性が見えてきたりします。「分かりやすいノートを作る」ということもこれに近いような気がします。
いったい自分は何の教科が得意で、不得意だと思っていた教科もさらに深堀りをして、分かっていない単元が明らかになります。自分の頭の中を整理することは勉強を効率的に進める上で非常に重要です。
ルーズリーフ勉強法のポイント
ここまで基本的なノート作りについて解説してきました。 ただ作ってまとめてを繰り返していくだけでも勉強にはなりますが、ルーズリーフを使ったポイントを抑えた作り方を知っておくとさらに便利で役に立つルーズリーフを作ることができます。
バインダーにとじる
ルーズリーフの紙はサラッと問題を解いたり何かをメモしたりするのに非常に役立ちます。しかし書いたり解いたりした後でそのままにしておくといつの間にかどこかに失くしてしまうこともあります。 そうならないためにもルーズリーフをバラのまま保管することはやめ、必ずバインダーにまとめるようにしましょう。無くしたり順番がぐちゃぐちゃになったりしてしまうと無駄なストレスがかかってしまいます。あくまでもノートを作っているのだという意識を持ちましょう。
きれいに作る必要はない
ノートを作る際にたくさんの色のマーカーやペンを駆使し見事と言わざるを得ないくらいのものを作る人がいます。確かに見た目が美しいと作り上げた満足感は感じられるでしょう。 しかし、落ち着いてみてください。そのレベルのノートを1枚作るだけでかなりの時間と集中力を費やしていませんか?何度も歴史をノートにまとめようとしても必死に作った縄文時代のページだけで疲れ果ててしまう中学生のように、ノートを豪華に作ることで疲れ果ててしまっては元も子もありません。 あなたのノートは誰かに見せるものではありません。自分だけがわかればいいのです。そのため全部を黒で書いて、あとで大事なことだけマーカーで色をつける程度の見易さがあれば十分なのです。 きれいさはほどほどで良いということは忘れないでください。しかし字が汚くて読めないまでいくと今度は汚すぎて後々役に立ちません。自分が見て理解できるレベルの見た目を意識していきましょう。
日付や番号を振る
意識してもルーズリーフというのは1枚ポロっとバインダーから外れた状態で見つかるものです。その度に必死にどこに収めればいいのかを調べていては時間の無駄です。 ノートの端に日付や番号をあらかじめ振っておけば、このトラブルを避けることができます。些細なことではありますが、ルーズリーフの枚数や冊数が増えていけばいくほどこの工夫が意味を持っていきます。
ルーズリーフ勉強法のやり方例
工夫次第でいろいろ使えるルーズリーフ。ここではおすすめの使い方例を3つほど紹介いたします。
例①縦半分に線を引く
これは暗記系の教科に効果的なやり方です。ルーズリーフの縦半分に線を引きます。そしてその線の左側には問題を、右側にはその解答を書いていきます。これで即席の一問一答の問題集が出来上がります。 市販の一問一答問題集を買った方が楽だという意見もあると思いますが、自分で作ったものはより自分自身に特化した一問一答となります。何度覚えようとしても、うまく覚えられない箇所は自分が一番知っているはずです。 そこを何度も勉強できるツールを自分で作ってしまえば、あとは繰り返し挑むだけです。覚え切るのは時間の問題と言えるでしょう。勉強していくうちに見つけた自分の苦手箇所をルーズリーフにまとめ、自分だけの一問一答問題集を作り上げてみましょう。
例②重要語句や単語はオレンジペンで書く
昔ながらの赤シートも暗記教科でその真価を発揮します。重要だと思う語句をあらかじめ色を変えて書き込めば、のちに赤シートを使い何度も勉強することができます。ここで大切なことは使うペンの色は赤でなくオレンジ色を使うことです。 赤い文字を赤シートで隠しても消えきれずに見えてしまうことがありますが、オレンジ色の文字ならばほとんど見えません。また筆圧をかけすぎないことも大事です。筆圧が強すぎるとノートの窪み方で赤シートの上からでも答えが読めてしまうからです。
ルーズリーフ勉強法のコツ
ルーズリーフ勉強法を始める際に大事なことは自分に合った商品を選び、自分に合った使い方を見つけ出すことです。自分のとって一番良い方法を追求していきましょう。
コツ①自分に合った罫線の用紙を使う
単にルーズリーフと言ってもB5、A5、A4、横線、方眼、英習字罫、音楽罫、無地などいろいろな種類があります。どれが正解といったことはありません。サイズや罫線の有無、紙の質など自分に合った使いやすい用紙を選んでください。 科目によって複数使っても良いでしょう。また、バインダーもサイズや収容枚数にも違いがあるため、文房具コーナーでいろいろ見てみると良いでしょう。あまりに収容枚数が多すぎるものは後々持ち運びに不便が生じるので気をつけてください。
コツ②科目を見出しで分けておく
科目ごとに別々のノートを作っても良いですが、そこまで枚数が多くならない場合は1冊に多くの教科をまとめるということもできます。その際は見出しを使って教科を分けてみましょう。また単元ごとに見出しをつけるのも使い勝手を良くしてくれます。見た目が良くなり、勉強をしている感が出てくるのも良いポイントですね。
コツ③大事なプリント類もはさんでおく
プリントなどを入れられるファイルに穴がついたものも売っています。それを使うとプリント類も一緒に挟んでおくこともできます。またお守りや写真など自分を励ましてくれるものを入れるというのも一つのアイデアです。どんどん自分のルーズリーフを自分らしいものにしていきましょう。
おすすめルーズリーフを紹介!
最後に著者が個人的におすすめするルーズリーフを紹介していきます。 定番や変わり種、バインダーをおしゃれにするグッズまで幅広く紹介していきます。
おすすめ①コクヨ キャンパス ルーズリーフ さらさら書ける シリーズ
おそらく誰しもが一度は目にしたことがある定番中の定番です。本屋だけでなくコンビニでも買えることが多いはずです。王道にして頂点と言っていいほどの製品。購入しやすさ、バリエーションの多さ、品質、どれをとっても素晴らしいとしか言いようがありません。どれを買っていいか迷ったらとりあえずこれを買っておけば間違いなし。唯一の弱点を挙げるとしたら、定番すぎることでしょうか。
参考URL:コクヨ公式
おすすめ②マルマン ルーズリーフ
勉強しているとき、お気に入りのペンや筆箱があるとやる気になることはありませんか?なにごともまずは形から入ることも大事です。 先ほど紹介したコクヨのルーズリーフは、みんなが使っているから自分は他のものを使いたい、という人はここから紹介するものを参考にしてみてください。 こちらの製品はその書き心地に定評があります。スパイラルノートが有名なマルハンですが、ルーズリーフにもそのノートに対するこだわりが溢れています。たくさん文字を書く学生時代、どうせならできるだけ書き心地の良い紙を使いたいと思う人は是非チェックしてみてください。
参考URL:マルマン公式
おすすめ③学研ステイフル STUDY STATIONERY ルーズリーフ
こちらは少し変わり種のルーズリーフです。東大王で有名な伊沢拓司さん率いるQuizKnockが制作に携わっている商品です。単語暗記用、誤答・暗記用、誤答・記述用、マークシート練習用の4種類があり、それぞれがそれぞれの目的に特化したフォーマットになっていて、すぐに狙いの勉強を始められることが最大の利点です。 マークシートのルーズリーフはかなり珍しいですね。痒い所に手が届く作りになっており、特に単語暗記用は反復学習を促す作りになっていてとてもおすすめです。
参考URL:学研ステイフル
おすすめ④マルマン ルーズリーフ バインダー B5 セッション
バインダーのおすすめはこちらです。理由はシンプルにカラーバリエーションが豊富だからです。いざルーズリーフを使い始めると教科数ごと、高校にもなるとさらに細分化して多くのバインダーを使うことになりますが、その際用意された色が豊富だととても便利なのです。 色違いを並べると視覚的にも可愛いですし、どの科目のノートか見た目で判断できないというトラブルも防ぐこともできます。
参考URL:マルマン公式
おすすめ⑤プラス インデックスシート
最後に紹介するのはインデックスシート、つまり見出しのページです。これ自体をノートとして扱うわけではありません。このシートは一言で言えばおしゃれのための商品です。 ルーズリーフ勉強法を進めてくると、もっと自分のバインダーを見栄え良くしたいと思う人も出てくるでしょう。そういう時は、こう言った商品が役に立ちます。なぜこの商品をチョイスしたかというと、単純に色合いがきれいだからです。 それだけなの?という方もいるかもしれませんが、道具の見た目というのは勉強意欲を沸き立たせる面で非常に重要なものです。見た目や色合いが好きなバインダーはもっと使いたくなるはずです。
参考URL:プラス公式
まとめ
自分にぴったりな教材を自分で作り出せる点、それを常に最新の状態にアップデートし続けられる点でルーズリーフ勉強法は非常に効果的です。最初は少し戸惑うかもしれませんが要領が分かってくれば、普通のノートを使う勉強法にはもう戻れません。この記事に書かれたことをヒントに自分だけのルーズリーフを是非作り出してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。
















