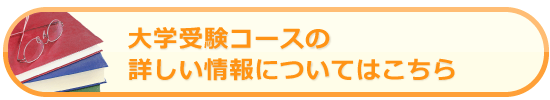【医学部受験】共通テスト対策~入試面接対策まで徹底解説
医学部受験において、共通テストはどの程度重要なのかご存じしょうか? 共通テストは、医学部の二次試験に比べて難しくないため、対策をしなくてもいいと思っている人も多いのではないでしょうか。 しかし、医学部受験において共通テストは国公立、私立関係なく重要です。 共通テストは、国公立では足きりに使われたり、私立では共通テスト利用選抜で使われたりするからです。 今回の記事では、医学部受験において共通テストはどれくらい重要なのか、どのような対策をしたらいいのか、また入試面接の対策方法も徹底的に解説していきますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。
医学部受験の特徴とは?
まずは医学部受験の特徴について解説していきます。医学部受験の形式は、国公立大学と私立大学で大きく変わってきます。
国公立大学医学部の場合
国公立大学医学部の場合は、毎年1月に全国一斉に行われる「大学入学共通テスト」を受けなければいけません。 どの大学でも、共通テストで受験する科目は5教科7科目(国語、数学1A2B、理科2科目、社会1科目、英語)です。 共通テストと二次試験の点数比率については各大学によって異なります。共通テストの割合が高い大学を志望する場合、共通テストの得点率が低いと合格の可能性が下がってしまいます。 そのため、共通テスト得点比率の高い大学を受けるときは、共通テストの対策をしっかりとしましょう。
私立大学医学部の場合
私立大学の医学部一般入試では共通テストを利用せず、大学独自の試験で合否を決める大学が多いです。 しかし、中には共通テスト利用選抜を実施する私立大学もあります。 多くの私立大学の場合、共通テストの受験科目は数学、英語、理科の場合が多いです。これらの3科目を重点的に勉強しておくと効率よく成績を伸ばすことができます。 そのため、共通テスト利用選抜を利用しようと考えている人は、早めにテスト対策を始めましょう。
共通テストでの一次試験とは
医学部受験をするにあたって、共通テストで高得点をとることは必要不可欠です。 多くの国公立医学部では85%以上、難関大学では90%以上の得点率が必要となってきます。つまり、共通テストで失敗してしまうと、二次試験で大きなハンデになってしまうということです。 私立大学の場合、共通テスト利用選抜の場合のみ、共通テストが合否判定の対象となります。 この受験方式を検討している人は、共通テストで高得点をとる必要があるため、早めに共通テストの対策を始めるようにしましょう。 こちらでは、国公立大学医学部と、私立大学医学部の共通テストでの一次試験の違いについて解説していきます。
国公立大学医学部の受験科目
国公立医学部を受験する場合、5教科7科目を受験することが必須になり、入試方式にかかわらずどの大学でも必須です。 しかし、どのような入試方式や大学を受けるかによって、共通テストの重要度が変わってきます。 地域枠入試など推薦入試を受ける予定のある人は、二次試験対策よりも共通テスト対策に重点をおいて勉強しましょう。地域枠入試では共通テストの得点と、大学独自の学力テストと面接によって合否が決まることが多いです。そのため、共通テストの得点が低いとそもそも大学独自のテストを受けることができません。 また、一般入試を受ける予定の人は、大学の得点の割合を見て共通テストと二次試験の勉強の割合を決めましょう。医学部受験で共通テストは重要といっても、大学によっては共通テストの配点が低い場合もあります。ここで勉強の割合を間違えてしまうと、合格の可能性が低くなってしまうので注意しましょう。 まず、共通テストの割合が高い大学の場合は、学校での共通テスト対策に加え、自分でも苦手科目の勉強をしましょう。このような大学を受ける場合、共通テストで失敗してしまうと、二次試験での逆転が難しくなってしまいます。 共通テストの割合が低い大学の場合は、学校での共通テスト対策で十分に対応できます。しかし、合計で得点が8割に達していなかったり、特に苦手な科目があったりする場合は自分で勉強をしておくと安心です。
私立大学医学部の受験科目
私立大学医学部の受験科目は大学によって異なりますが、数学・英語・理科2科目であることがほとんどです。 共通テスト利用選抜を受ける予定の人は、受験予定の大学の出願要綱を確認してください。共通テストで指定されている科目は、二次試験でも行うことがあるので、あらかじめしっかりと対策していても無駄にはなりません。
共通テストの足切りとは
医学部受験では共通テストで「足切り」が行われます。 足切りとは、共通テストでの得点がその大学のボーダーに達していない学生に二次試験を受けさせないというものです。 つまり、共通テストで失敗してしまった学生には二次試験での逆転のチャンスを与えられず、不合格になってしまうという仕組みです。
前期日程の足切り
2021年度の前期日程での足切りは、60%~70%です。 東京大学理科3類であっても、59%でした。そのため、医学部を受験する程の学力がある学生であれば、前期日程の足切りはあまり気にする必要はありません。
後期日程の足切り
後期日程のほうが受験生が集中するため倍率が高く、共通テストで要求される水準も高い傾向にあります。そのため、地方国公立大学でもボーダーが高くなる傾向にあります。 2021年度の後期日程での足切りは、80~90%です。得点率80~90%は、医学部受験生でもしっかりと共通テスト対策をしていないととれない点数なので、国公立大学専願の人はこのボーダーを超えられるように対策をしておきましょう。 参考文献:速報!医学部共通テスト/センター試験ボーダー・足切り(2022) | 医学部受験バイブル (xn--0kq33cz5c8wmwrqqw1d.com
医学部入試面接の概要

具体的な対策を解説する前に、医学部入試面接の概要について触れておきましょう。 まずは国公立大と私立大に分け、それぞれの特徴や傾向を見てみましょう。
国公立大学編
国公立大学志望の場合は一般入試と推薦入試によって大きく特徴と傾向が異なります。
【一般入試の場合】 一般入試の場合は、数学などの学科試験と面接というようにセットで面接試験が行われます。多くの大学では、学科試験の点数の割合が面接の割合よりも大きいので、面接練習は必要最低限で大丈夫です。 また、面接練習の点数の割合が大きい場合でも、大学によっては合格者全員が満点であることもあるので、自分が受けたい大学の面接の配点と合格者の得点は早めに調べておきましょう。学校の先生や塾の先生にも聞いてみてください。
【推薦入試の場合】 国立大学では、公募推薦と地域枠推薦の2つがあるので分けてお話しします。 まずは、公募推薦についてです。公募推薦は、大学の出願要件を満たし、高校学校長の推薦が得られれば出願できます。他の推薦方式より募集人数は多めですが、必ず合格できるとは限りません。 この形態の入試では、学力の他に、在学中に取り組んだ課外活動について問われることも多いです。医学部入試面接での頻出問題を対策するとともに、自分が取り組んだ課外活動についても振り返っておきましょう。試験時期も一般入試より早いので、志望校を決めたらすぐに対策を始めましょう。 次は、地域枠推薦についてです。医学部独特の推薦方式で、大学側が提示する「地域条件」を満たした受験生だけが出願できます。地方や僻地における医師確保のために始められた制度です。 地元出身者のための枠として用意されることが多いですが、近隣県であれば出願できる場合もあります。卒業後は指定された地域(病院)で一定期間勤務することが条件となっています。この入試形態では、共通テストと面接で合否を決めるケースが多いです。そのため、面接対策は一般入試を受ける受験生よりも集中してやる必要があります。 また、自分が受ける大学やその大学のある地域の抱える医療問題などについて、詳しい知識を持っている必要があるので、志望校を決めたらすぐに対策を決めましょう。また、試験の時期が一般入試よりも早い時期に行われるので注意が必要です。
私立大学編
私立大学志望の場合も一般入試と推薦入試で大きく特徴と傾向が異なります。
【一般入試の場合】 私立大学の一般入試も国立大学の一般入試と同じように学科試験とセットで行われます。私立大学を受験する場合でも、学科試験に比重を置いた面接対策で十分です。ですが、受験している私立大学を他大学と併願している場合は注意が必要です。 併願している大学との志望順位や、両方に合格した場合どちらに進学するかなどの質問に答えられるようにしておかなければならないからです。面接練習の中で自分の考えをすぐに答えられるようにしておきましょう。
【推薦入試の場合】 私立大学の推薦入試は大きく分けて2つに分けられます。 まず1つ目は指定校推薦です。大学側が高校に推薦枠を用意し、高校は条件に合致する受験生を推薦します。大学と高校の信頼関係の上で成り立っており、合格の可能性は限りなく高いです。小論文の試験に加え、面接試験が行われるので、一般入試を受ける場合よりも丁寧な対策が必要です。学校にある受験体験記などを参考にして対策をしましょう。また、試験が行われる時期が早いので注意が必要です。 2つ目は公募型推薦です。国立大学と同様、大学の出願要件を満たし、高校学校長の推薦が得られれば出願できます。この形態の入試では、学力の他に、在学中に取り組んだ課外活動について問われることも多いです。医学部入試面接での頻出問題を対策するとともに、自分が取り組んだ課外活動についても振り返っておきましょう。試験時期も一般入試より早いので、志望校を決めたらすぐに対策を始めましょう。
医学部入試面接対策の方法

本格的に対策を始めるべきタイミング
国立大学の一般入試が第一志望の場合、センター試験が終わった後に対策を開始するのが良いです。国立大学志望の場合はセンター試験の結果によって志望校が変わる場合があります。そのため、センター試験前から準備をしていても、二度手間になってしまう場合があるので、センター試験後に対策を開始した方が効率が良いです。 国立大学や私立大学の推薦入試が第一志望のとき、学校の先生と進路相談をして出願校を決めたらすぐに対策を開始しましょう。一般入試よりも、面接試験の割合が高かったり、聞かれる質問の傾向が一般入試と異なったりするので早めの対策が必要不可欠です。
面接テーマ・内容
ここでは、医学部入試面接でよく聞かれる内容についてお話しします。 まず、志望理由についてお話しします。志望理由は国立大学の入試面接で必ずと言ってもいいほど聞かれる内容です。どの大学でも聞かれるので、きちんと対策をしておく必要があります。大学の志望理由は、自分が受験予定の大学のパンフレットやホームページを参考に書くと良いです。 パンフレットやホームページには大学の建学理念やどんな人材を求めているかが書かれているので、それを参考にすると他の受験生との差をつけることができます。 また、自分で書いた志望理由は高校の先生や塾の先生などに添削をしてもらいましょう。自分では見落としていた思わぬ言葉遣いの間違いなどが修正できるのでぜひお願いしてみてください。 そして、書いた志望理由を元に面接練習を繰り返しやりましょう。ここでのポイントは内容を完全に暗記しないようにすることです。完全に暗記をしてしまうと、自分が想定していなかった志望理由の聞き方をされた場合うまく答えられなくなってしまいます。あくまで、自分が話したい内容を覚える程度にとどめ、臨機応変に対応できるようにしましょう。 志望理由の他には最近の社会問題や医療に関する問題(安楽死など)などが聞かれることも多いです。主要な問題については、自分の考えを持ち、面接で聞かれた時に答えられるようにしておきましょう。社会問題や医療の問題についての情報収集法については後に記述します。 推薦入試を受ける場合は、これらに加え、自分の入試形態で求められる内容の対策をしていきましょう。 指定校推薦では、大学のカリキュラムなどについての深い理解が問われます。自分が受けたい大学のカリキュラムがどうして自分に合っているのか、どうして自分はその大学でなければいけないのかを考えておきましょう。 公募型推薦では、前述したように自分が在学中に行ってきた課外活動についての質問に答えられるようにする対策が必要です。部活動などでの成功体験だけでなく、失敗体験についても話せるようにしておきましょう。失敗体験については、よく分析し、なぜ失敗したのか、その状況から何を学んだのかを答えられるようにしておくと良いです。 地域枠推薦では、自分が出願する地域、または病院でどうして働きたいと思っているのかが必ずと言ってもいいほど聞かれます。これが答えられないと合格は見えてきません。学校や塾などの合格体験記などで過去問を研究して、どのような質問が来ても答えられるようにしておきましょう。
医学部入試面接の情報収集法
ここでは、医学部入試面接での情報収集法についてお話しします。 まず1つ目の対策としては、面接や小論文の対策本を読むことです。これらの本には、全国医学部入試面接でよく聞かれる内容とそれに対するオーソドックスな答えがわかりやすくまとめられています。これを読むことが医学部入試面接を攻略する最も効率的な方法です。また、この対策をしておくことで、医学の知識がつくため、小論文でも役立ちます。ぜひやってみてくださいね。 筆者おすすめの参考書は「医系小論文 再頻出論点 20」(赤本メディカルシリーズ)です。ぜひ、読んでみてください。 2つ目の対策としては、学校や塾などの受験体験記を参考にすることです。受験体験記には、面接がどのような形式で行われたかや、面接室の配置、聞かれた質問などが細かく書かれています。何人もの先輩方が同じ大学を受けていれば傾向を把握することができるので、読んでみてください。
面接時の服装について
現役生は制服が基本です。制服がなかったり、浪人生の方はスーツが良いと思います。私が行った各大学の試験会場で私服で着ていた人はいなかったです。
面接練習について
まずは、入退室でのマナーです。大学入試の面接官は1日に何人もの受験生の面接をしているので、悪い印象を残してしまうのはマイナスポイントになってしまいます。学校の先生などと練習を重ねていく中で、マナーを身につけていきましょう。 頻出質問についての対策も欠かせません。よく聞かれる質問は、大学の志望理由、医師になりたい理由、最近の社会問題や医療の問題です。「医学部入試面接の情報収集法」を読んで自分なりに考えを考えておきましょう。隙間時間などに見直せるようにノートにメモをしておくと良いです。 実際に私も、よく聞かれる質問についてノートに自分の考えを書き、それを元に面接練習をしました。それをしておいたことで、試験の際も見直すことができ、試験前の緊張がほぐれました。ぜひ、実践してみてください。
医学部受験では共通テスト対策に力を入れよう
国公立大学の場合、共通テストの点数が低いことで足切りが行われてしまい、志望校の入試を受けることすらできずに受験を終えてしまう可能性があります。そのため、共通テスト対策はしっかりとしましょう。 また、共通テストで失敗してしまうと、共通テストの配点が高い大学での合格の可能性が低くなってしまうため、注意が必要です。 私立大学を受験する場合でも、共通テスト利用入試を受ける場合は共通テストが大切になってきます。共通テスト利用選抜を受ける可能性がある人は、対策をしっかりとしておきましょう。 そして、医学部入試において共通テストのボーダーラインは、大きく分けて2つあります。 1つ目は足切りを突破して、二次試験に進むための最終ラインです。前期日程ではさほど重要ではありませんが、国公立専願で後期日程の受験を考えている人は高得点を狙いましょう。 2つ目は、最終合格者の得点目安です。特に共通テストの配点が高い大学を志望する人はしっかりと対策をしておくと安心です。 この2つのボーダーを突破できるように、共通試験対策をしっかりとしていきましょう。 また、面接対策を行うことも医学部合格への大切な一歩です。入試面接の対策にも取り組んでおきましょう。