通知表の「思考力・判断力・表現力」の伸ばし方|子どもに接するときの注意点も紹介
小学校は2020年度から、中学校は翌年の2021年度から、そして高校も2022年度からはじまった新しい学習指導要領では、「思考力・判断力・表現力」の項目が追加されました。
「思考力・判断力・表現力」は、子どもがこれからの時代を生きていく中で、問題を解決するために自分の考えを自分の言葉で表現するために追加されました。
高校受験を控えている中学生にとって、「思考力・判断力・表現力」は内申に影響を与えるポイントであるため、対策が必要ですが伸ばし方が分からない人もいらっしゃるでしょう。
そこで、この記事では、通知表の「思考力・判断力・表現力」の概要について解説した上で、伸ばし方をご紹介します。
通知表の「思考力・判断力・表現力」の評価を高めて成績を上げたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
通知表の「思考力・判断力・表現力」とは?
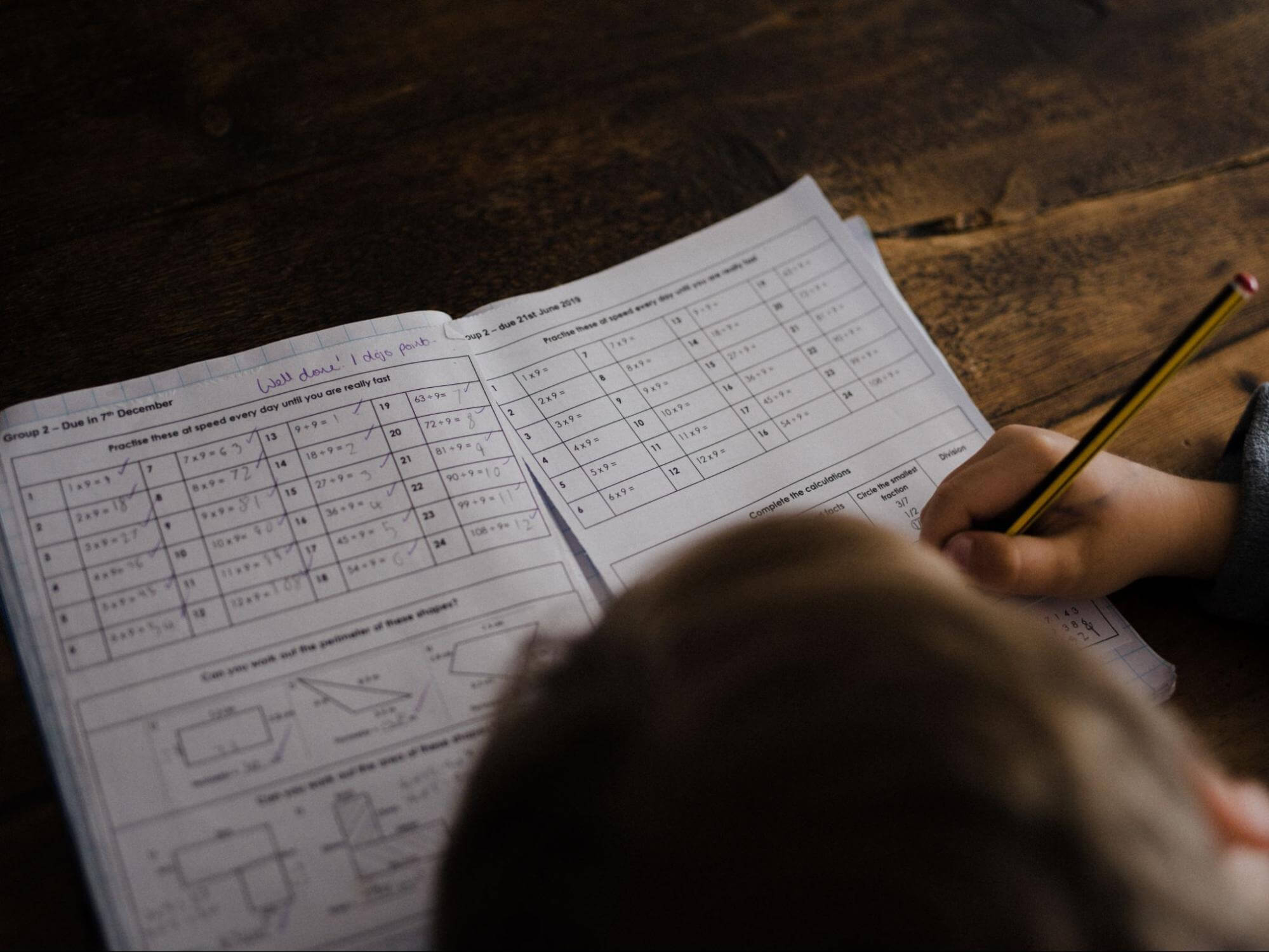
通知表の「思考力・判断力・表現力」は、新学習指導要領における3本の柱の一つです。
平成29年に新しく採用された学習指導要領では、新しい時代を生きる力を子どもたちに育むため、以下の3本の柱を導入しています。
【新学習指導要領の3本の柱】
|
3本の柱の一つである「思考力・判断力・表現力」とは、具体的には以下のような力を指します。
思考力とは
思考力とは、問いや考える対象が不明瞭な世の中において、みずから問いを設定し、あらゆる角度から「たとえば」「こうしたらどうか」と解決に向けて考え続ける力です。
変化が激しく、未来を予測することが困難な時代において、「誰かが設定した問い」や「一般的な問い」を考えるだけでは、自分の道を切り拓けません。
既成の思考の枠にとらわれず、自分の目で現実を見て問いを設置し、仮説や具体例を交えて考え、最適解を導く力が、これからを生きる子どもたちに必要です。
判断力とは
これまでの学習指導要領では強く意図されてこなかったのが、判断力です。判断力とは文字通り「選ぶ力」ですが、教育においては、子どもたち自身が「思考した上で」「選び、決める」力を判断力といいます。
学校でも教師が一方的に決めるのではなく、子どもたちの話し合いや選択を重視する指導スタイルに変化しつつあります。教師は、子どもたちに任せきりでは奔放になりすぎる部分を抑え、あるべき結論に導くファシリテーターとしてはたらきます。
判断力は経験によって育まれます。「主体的に判断する」場面を数多く経験させることが大切です。
表現力とは
表現力とは考えや思い、感情をさまざまな手法を使ってあらわす力です。
一般的に「表現」というと絵画や音楽などの芸術的手法や、言葉や文章などの言語的手法がイメージできます。しかし教育でいう表現力はより広義で、表情や身振り、態度、振る舞いなども含みます。
つまり、思考や判断を経て自分の内面を表出させる手段はすべて、表現力です。
【思考力・判断力・表現力の詳細】
|
このように「思考力・判断力・表現力」は知識をただ覚えるだけでなく、課題を解決するために知識を活用して、自分の言葉で表現する力のことです。
たとえば、英語であれば自分の考えを英語で発表したり、社会であれば社会問題について考察してわかりやすく記述したりすることが求められます。
「思考力・判断力・表現力」は暗記だけでは身につかず、長期的に伸ばす必要がある力です。また、通知表の「思考力・判断力・表現力」は、内申点に大きな影響を与えます。
中学生の場合、志望校に合格するために「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことが重要です。
参考:学習指導要領|文部科学省
通知表の「思考力・判断力・表現力」の判断基準
通知表の「思考力・判断力・表現力」は、下記のポイントで判断されます。
| 判断基準 | 判断するポイント | 具体例 |
|
|
|
通知の「思考力・判断力・表現力」の項目で高い評価を得るためには、授業で学んだことに対して自分の考えや感じたことを、わかりやすくまとめるようにしましょう。
「思考力・判断力・表現力」は内申書の評価基準
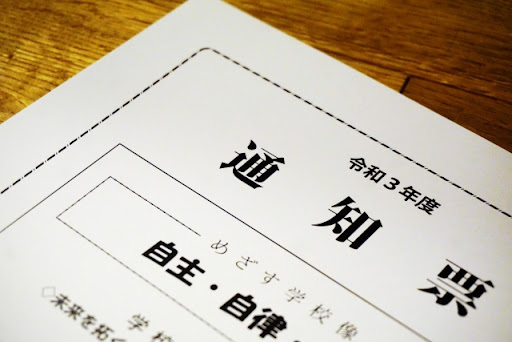
学習指導要領の改訂にともない、内申書の評価基準にも思考力・判断力・表現力がくわわりました。入試を控えた親御さんの中には、わが子がどのように評価されるのか基準が気になる人も多いはずです。
学習指導要領が定める思考力・判断力・表現力の3つの力と、内申書の関係を解説します。
内申書の評価基準3つ
現在、中学校の内申書で評価が書かれる基準は以下の3つです。
- 知識・技能
- 思考力・判断力・表現力など
- 学習に取り組む態度(主体性・人間性)
学習指導要領の改訂前は、以下の4項目でした。
- 知識・理解
- 技能
- 思考・判断・表現
- 関心・意欲・態度
評価基準が減ったからといって、評価が甘くなったわけではありません。一つひとつの項目を、より深く評価されるようになったとも言われています。
「知識・技能」の評価内容
知識・技能の項目は、学んだ知識や考え方をただしく捉えられているかが見られます。「わかっているか・いないか」「覚えているか・いないか」など、定量的に評価しやすい項目です。
英語なら「スペルを正しく書けているか」「正しい文法で英作文ができているか」、数学なら「公式を正しく理解しているか」「ルールに則って計算できているか」などの観点が該当します。
力が付いていないと、テストで得点が伸びません。反対に、テストでしっかり得点できている生徒は「知識・技能」項目で高い評価を得やすいと考えられます。
「思考力・判断力・表現力」の評価内容
試行錯誤しながら考える力や最適だと思われる選択肢を選ぶ力、思いや考えを表現できる力が評価されるのが「思考力・判断力・表現力」の項目です。
思考力・判断力・表現力は、テストの得点だけでは評価できません。日頃の授業への参加姿勢やアクティブラーニングでの主体性、グループディスカッションでの状況、レポートなどによって評価されます。
授業や宿題に真摯に取り組み、積極的に考え学びを得ようとする姿勢が高評価につながります。
「学習に取り組む態度」の評価内容
「学習に取り組む態度」の項目は、文字通り学習に対する意欲や興味、積極性が評価されます。授業時の態度や課題提出状況、発言の数などが評価につながります。
定性的な項目ですが、やるべき学習をきちんと進めていれば、高評価は得られます。反対に「課題を出さない」「期限を守らない」「授業をサボる」などの態度は、良い評価にはつながらないでしょう。
★こちらもチェック!
通知表の「家庭から」欄は何を書く?学年別おすすめ内容やNG例、例文も紹介
「学習指導要領」とは

よく聞く「学習指導要領」についても、あらためて理解を深めておきましょう。どのような目的でつくられているものなのか、またお子さんへの影響も解説します。
学習指導要領とは
学習指導要領とは、全国の学校で一定の教育水準を保つために定められている教育課程(カリキュラム)の基準です。文部科学省が制定し、公立・私立とも学校の指導は学習指導要領に従わなければなりません。
教科書や時間割も、学習指導要領に基づき作られます。
学習指導要領に思考力・判断力・表現力が導入された目的
学習指導要領は、世の中の変化にあわせて10年に一度改訂されています。
最新の学習指導要領改訂は、「予測困難な社会において自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、判断して行動し、それぞれの幸せを実現してほしい」という文部科学省の願いが込められています。
この目的達成に欠かせない3つの柱が「学びに向かう力、人間性」「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力」であり、思考力・判断力・表現力が柱の1つに取り入れられた理由です。
家庭でも思考力・判断力・表現力は伸ばせる
学校での教育はもちろん、大切です。
そして同じくらい、家庭での教育もお子さんの成長に大きな意味を持つことを忘れないでください。
学校で学んだことをを日常生活で活用したり、家庭での経験を学習に活かしたりと学習のサイクルを回すことで、お子さんの学びは深化していきます。
実際、家庭で保護者の働きかけがある子どものほうが、学力が高いともいわれます。以下を参考に、今日からできることを取り入れていきましょう。
◎ 子どもの学力が高い家庭でよく行われていること
|
※ 参考:平成29年度全国学力・学習状況調査を活用した専門的な課題分析に関する調査研究|お茶の水女子大学
通知表の「思考力・判断力・表現力」の伸ばし方
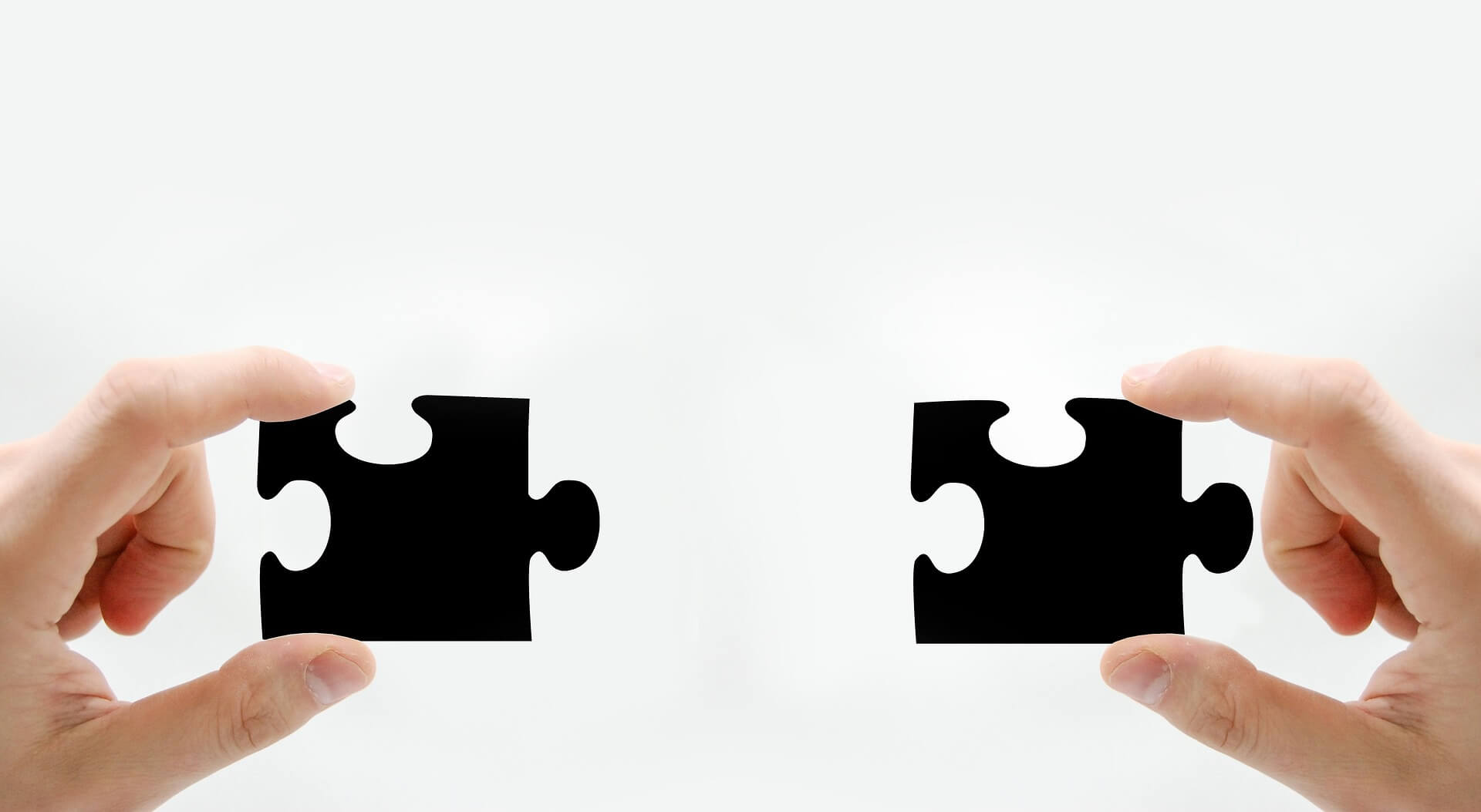
通知表の「思考力・判断力・表現力」を伸ばすためには、以下の4つの方法が有効です。
- 授業中に積極的に発言する
- レポートに自分の考えを記載する
- 定期テストで良い点数を取る
- 塾や家庭教師を活用する
それぞれの方法について詳しく解説しますので、「思考力・判断力・表現力」を伸ばしたい方はぜひ参考にしてみてください。
授業中に積極的に発言する
「思考力・判断力・表現力」を伸ばすためには、自分の考えを授業中に積極的に発言しましょう。
自分の考えを発言することによって、思考力や表現力が身に付く上に、先生から評価してもらいやすくなります。
またグループディスカッションで他の生徒の意見を受けて、根拠を持って自分の考えを発言できると、さらに成績が伸びるでしょう。
レポートに自分の考えを記載する
学校で出されるレポートには、授業内容をまとめるだけでなく、自分の考えを記載できるようになると「思考力・判断力・判断力」が伸びます。
特にグラフや表をレポートにまとめる場合、数値が変化している部分を中心に、自分の意見を書きましょう。たとえば、「もっとも数値が高い部分に対して、なぜ数値が高いのか」「数値が急激に変わっている部分に対して、なぜ変化したのか」などを記載すると良いです。
一部の数値が他の数値よりも大きく異なっていることには、何か理由があるため、理由を特定して考察することによって「思考力・判断力・判断力」が伸びます。
さらに、他の生徒との差別化にもなるため、成績が伸び、結果として内申点が向上するでしょう。
定期テストで良い点数を取る
定期テストで良い点数を取れるように、応用問題・記述問題の対策をしっかりすれば「思考力・判断力・判断力」が伸びます。
応用問題や記述問題は学んだ基礎的な知識を活用する必要があり、記述問題の中には自分の考えを記入することが求められる問題もあります。基礎的な知識をまずは理解・暗記して、複雑で難しい応用問題・記述問題の対策を行いましょう。
定期テストで良い点数を取れれば「思考力・判断力・判断力」があると評価してもらえるため、内申点が向上します。
塾や家庭教師を活用する
家庭で「思考力・判断力・判断力」を伸ばすことが難しい場合、塾や家庭教師を活用することもおすすめです。
教育のプロの講師の授業を受ければ、知識を活用して問題を解く論理的思考力を身につけられます。また、自分の考えをわかりやすく表現するための文章の書き方も学べます。
塾や家庭教師を活用すれば「思考力・判断力・判断力」を伸ばすために必要な基礎的な学力も伸びるため、活用を検討してみてはいかがでしょうか。
「思考力・判断力・表現力」が伸びるメリット

学習指導要領の3つの柱は、学びの場面で以下のように役割を分担します。
- 学びに向かう力、人間性→ 学びの意識づけ、将来への志向
- 知識及び技能→ 何を理解しているか、何ができるか
- 思考力・判断力・表現力→ 理解していること・できることをどう使うか
思考力・判断力・表現力は、「どう使うか」ときわめて実戦的な役割を担っていることがわかります。思考力・判断力・表現力が伸びるとできることが増え、豊かで充実した学び・人生を手に入れられるでしょう。
AI・ITが普及し、働き方も急速に変化する時代です。
2014年にオックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授が発表した「人間が行う仕事の約半分が機械に奪われる」という論文に衝撃を受けた親御さんも多いのではないでしょうか。
「銀行の融資担当者」「動物のブリーダー」「ネイリスト」「クレーム処理係」など、これまで人にしかできないと思われていた仕事がロボットに取ってかわられるという予測は、すでに当たり始めています。
子どもたちは、親世代とはまったく異なる世界を生きていきます。変化を前向きに受け止め、人間ならではの感性を働かせて豊かにしていくために欠かせない力が、思考力・判断力・表現力です。
子どもの「思考力・判断力・表現力」を伸ばすときに親が注意するべきこと

子どもの「思考力・判断力・表現力」を伸ばすとき、以下の2点に注意して子どもに接しましょう。
- 子どもにたくさん話をさせてあげる
- 失敗することがわかっていても止めない
それぞれの注意点について詳しく解説しますので、子どもの教育方法について悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
子どもにたくさん話をさせてあげる
子どもに接するときは、子どもにたくさん話をさせてあげる環境を整えることが大切です。
子どもは日々多くのことを感じ、考えており、感じたことや考えたことを言語化することで思考力や表現力が身に付きます。
また、子どもと話す中で「なんでそう思う?」と質問してあげることで、物事を深く考える力が伸びます。
親御さんは、子どもの話を遮らずに最後まで聞いてあげましょう。
失敗することがわかっていても止めない
子どもが失敗することがわかっていても、我慢して止めないことが親には必要です。
いろいろなことを経験している親からすると、子どもがやっていることに対して上手くいくかある程度想像がつきます。
子どものことを思うと、失敗しないように手取り足取りアドバイスしたくなるでしょう。しかし、子どもが失敗することが事前にわかってもアドバイスせずに、失敗させてあげることが大切です。
子どもは試行錯誤していく中で、問題発見・解決能力を身につけ、論理的思考力が向上するのです。
通知表の「思考力・判断力・表現力」を伸ばすならオンライン家庭教師ピースがおすすめ

通知表の「思考力・判断力・表現力」を伸ばしたいなら、オンライン家庭教師ピースがおすすめです。
オンライン家庭教師は、家庭教師の授業をオンラインで受講できるサービスであり、自宅から移動する手間がかからない点がメリットです。また、オンライン家庭教師ピースでは、生徒の特徴や学力に合わせて自由にカリキュラムを設定できるため、苦手な科目があっても心配いりません。
「思考力・判断力・表現力」は伸ばしにくいですが、オンライン家庭教師ピースであればプロの講師が徹底的に指導してくれます。
オンライン家庭教師ピースの講師は、本部教務によるマンツーマンの研修を受けているため、生徒一人一人に合わせて適切な指導ができます。
通知表の「思考力・判断力・表現力」を伸ばして成績を上げたい方は、ぜひ一度オンライン家庭教師ピースの無料体験授業を受けてみてください。
オンライン家庭教師ピースへのお問合せ・体験授業お申込みはこちらから
まとめ
通知表の「思考力・判断力・表現力」は、学習指導要領の変更に伴って新しく導入された、重要な教育指針です。
「思考力・判断力・表現力」とは、論理的に物事を考える力や、適切な情報を取捨選択して活用する力などのことです。
レポートの内容や、グループディスカッションでの発言内容をもとに「思考力・判断力・表現力」が評価されます。また、授業中の発言を増やしたり、レポートに自分の意見を記載したりすることで「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことができます。
家庭で「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことが難しい場合は、オンライン家庭教師ピースの活用をぜひ検討してみてください。
















