ADHDの高校生の困りごとは?勉強に集中できる工夫や支援の方法
ADHDの高校生を持つ保護者の中には、生活や学習面でどうサポートしていいのか悩んでいる人もいるでしょう。大人へと成長していくADHDの子には、小中学校時代とは違ったサポートの工夫が必要となります。
この記事では、ADHDの高校生が集中して学習するための工夫や、受験に向けた勉強方法なども分かりやすく解説します。親ができるサポート方法についても触れますので、ADHDの高校生を持つ人はぜひ参考にしてください。
ADHDとは?
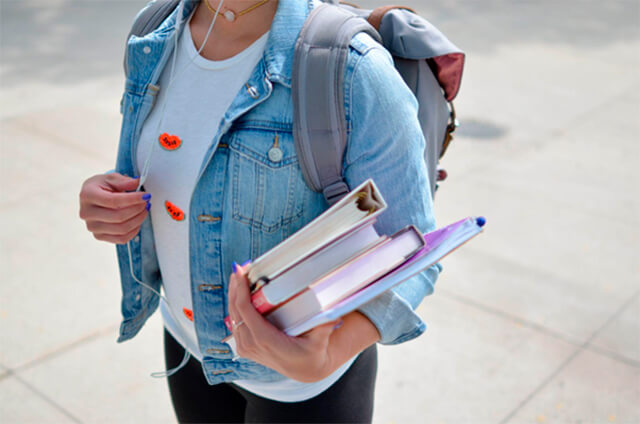
ADHDを持つ高校生の困り感を知るため、どのような障害なのかを確認しておきましょう。ここでは、ADHDの概要と代表的な特性、勉強との相性について分かりやすく解説します。
発達障害のひとつ
ADHDは「注意欠如・多動症」の略称で、発達障害のひとつです。同じ発達障害のカテゴリーには、自閉スペクトラム症や学習障害、チック症などがあります。
発達障害は生まれつきの障害で、育て方の問題ではありません。脳機能に原因があり、物のとらえ方や見え方が人と違います。そのため苦手なことがあったり、ちょっと変わった言動が目立ったりするのが特徴です。
発達障害の人が行う特徴的な言動を「特性」と表現します。誰でも少しは持っているものですが、自分も周りも困るほど特性が強い場合、診断名が付けられる傾向です。
発達障害の診断は医師が行います。診断がつくと学校や福祉の支援が受けやすくなったり、投薬治療などを受けたりできるのがメリットです。
ADHDの特性
ADHDの代表的な特性は、衝動性・多動性と不注意です。ADHDと聞くと、衝動性や多動性のイメージを思い浮かべる人が多いでしょう。教室を飛び出したり、突然怒り出してトラブルになったりなどするADHDの子どももいます。
しかし、激しい行動は年齢が上がるにつれ落ち着く傾向です。高校生ぐらいになると不注意の特性が目立ってきます。具体的には、整理整頓ができなかったり、提出物や約束を忘れたりなどです。
困った行動は特性のため、気をつけようと思っても同じ失敗を繰り返してしまいます。自分に自信が持てないことから、うつ病や摂食障害などの精神症状を引き起こす恐れも。高校では周りとの差を感じやすいため、ADHDからの二次障害にも注意した方がよいでしょう。
勉強との相性
ADHDと勉強の相性は、学習内容により変化します。子どもの特性を考えた学習内容の選択が重要です。
ADHDは発想が豊かなので、プログラミングや芸術系など、クリエイティブな分野が得意な傾向です。興味のあることはとことん追及するので、好きな分野の学習は進んで取り組むでしょう。
反対に、興味のない分野の学習にはほとんど興味を示さず、成績が伸び悩むことも。好き嫌いがはっきりしているのもADHDの特徴といえるでしょう。
また、発達障害の子は物事を0か100かで考えがちです。できないと思ったことには、最初から取り組もうとしません。テストの1問目でつまずき、他の問題には手をつけない子もいます。
ADHDの高校生の困りごと

ADHDの高校生はどのようなことで困り感があるのでしょうか。ここでは、ADHDの高校生が感じやすい困りごとを5つのポイントにわけて解説します。
自己管理
ADHDの高校生に多いのは、自己管理がうまくできず困ってしまうパターンです。年齢的に自分で時間管理をする時期ですが、特性によりうまくできません。
例えば遅刻や欠席の問題です。ADHDは気が散りやすい特性があり、十分間に合う時間があったとしても、余計なことを始めるなどして結局遅刻してしまいます。0か100かの思考パターンが災いし「どうせ間に合わないから今日は休もう」と極端な考えに走る場合も。
遅刻や欠席が重なると、留年の危機まで追い込まれる恐れがあります。親は何とかしたいと思いますが、プライドもあるため手出しされるのを嫌がる子もいるでしょう。
気持ちのコントロール
ADHDの高校生は、気持ちのコントロールが苦手です。周りの雰囲気を考えずに行動するので、周囲から誤解されがちです。
物事が自分の思い通りにならなくても、通常発達なら場の雰囲気を考え、気持ちを切り替えようとするでしょう。しかし、ADHDを持つ子は気持ちをうまくコントロールするのが苦手です。激しく怒ったり急に泣き出したりなど、自分の感情をストレートに表現してしまいます。
気持ちが高ぶり、自分自身でも何を言いたいのか分からなくなっている場合も。場をわきまえない言動で、わがままだと誤解されやすい面もあります。周りから非難されても、何が悪いのか理解できないため、自尊心の低下につながりやすいでしょう。
対人関係
対人関係はADHDの高校生が最も苦手とすることです。発達障害を持つ子には、同等に接してくる同年代とのコミュニケーションはハードルが高いためです。
ADHDなど発達障害の子には冗談が通じにくい傾向が見られます。言葉の意味をそのまま受け取ってしまうので、悪口を言われたと勘違いすることも。ふざけて言った言葉を本気で受け取られた相手は、コミュニケーションの差を感じ、離れていくかもしれません。
また、相手の気持ちを想像できないので本音と建前の区別もつきません。例えば、告白した相手からやんわりと断られたのに気づかず、猛アタックしてさらに嫌われてしまうケースです。人間関係の失敗を繰り返し、自尊心が低くなりがちなのもADHDを持つ高校生を悩ませる一因です。
勉強について
ADHDの高校生は、勉強面でも課題に直面します。不注意の特性により、計画通りに実行したり提出期限を守ったりするのが苦手なためです。
高校生になると、教科ごとの課題がそれぞれ出るでしょう。普通ならメモをするなど忘れないよう気をつけますが、ADHDはメモをしたことすら忘れてしまう場合が。計画通りに勉強しようとしても集中力が途切れがちで、うまくいかない場合も。
課題提出の遅れで単位を落とし、留年の危機に直面する恐れもあります。学校がくれたチャンスを生かせればよいのですが、努力が苦手なので初めからあきらめてしまう子も。適切な支援がなければ、退学を選ぶケースもあるでしょう。
進路について
ADHDは自分の進路について悩みを持ちやすいです。自分の気持ちを表現するのが難しく、進路希望をうまく伝えられないためです。
発達障害はコミュニケーション面での困難さが見られますが、自分との対話も苦手です。進路について考えてみても、なかなか気持ちがまとまらない場合も。自分の気持ちが固まらないまま、進路希望を人に伝えるのは難しいでしょう。
また、ADHDは思考も偏りがちで、興味の範囲も狭い傾向があります。いろいろな進路の中で、自分のやりたいものを見つけるのは難しいかもしれません。
ADHDの子の勉強面でのつまずき
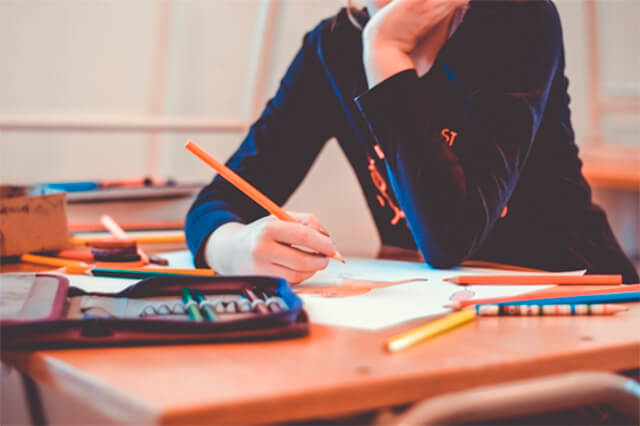
ADHDの子は不注意、多動性、衝動性の特性を持ち、勉強面でつまずく可能性があります。高校受験に影響を与える内申点が下がってしまう恐れもあり、周りの理解とフォローが必要です。ここでは、ADHDの子が勉強面でつまずくポイントを5つに分けてくわしく解説します。
勉強に集中できない
ADHDの子は、特性により勉強に集中できない場合があります。気分のムラが激しいことや感覚過敏などが原因で、集中力が切れてしまうのです。
ADHDの子は、何事にも飽きやすい傾向が見られます。特に興味のない学習には身が入りません。集中力が5分と持たず関係のないことをやりだしたり、その場から離れてしまうことも。高校受験の年齢なら多動が減り座っていられる子が多い傾向ですが、集中力の持続は難しいでしょう。
忘れ物が多い
忘れ物が多いのもADHDの子によく見られます。課題提出は内申点にも響くため、勉強のつまずきにつながると言えるでしょう。
ADHDは予定通りに物事をこなすのが苦手です。持ち物の連絡があっても覚えておらず忘れる傾向が見られます。気をつけようとメモを取っても、メモしたこと自体を忘れてしまう場合も。
ミスを指摘されるのを嫌い、忘れたことを認めず言い訳をする子も見られますが、忘れた事実は変わりません。結果、授業態度が悪いとみなされ、内申点の低下につながってしまうのです。
じっと座っていられない
ADHDの特性により、じっと座っていられないタイプが多い傾向です。講義型の授業スタイルは、ADHDにとって苦痛でしょう。
座っていられない理由は、集中力が続かない、体幹が保てないことなどが理由です。発達障害の子は筋肉をうまく使えず、同じ姿勢の維持が難しい場合もあります。1時間いっぱい教師の話を聞く授業スタイルは、ADHDには厳しいのです。
特性があるとはいえ、他の子が授業を聞いている中、別のことをしていると目立ちます。障害理解のない先生から「授業態度が悪い」と思われる可能性もあり、内申点に影響を及ぼすでしょう。
人の話を最後まで聞けない
ADHDの子には、人の話を最後まで聞かないタイプもいます。話に集中できなかったり、内容を覚えていられなかったりするためです。
人の話を理解するには、話を聞きながら内容を覚え、情報を整理する力が必要です。相手の話を要約できてこそ、内容を本当に理解したと言えます。定形発達の人なら無意識にできる行為ですが、発達障害の子には難しいのです。
やるべきことを忘れる
ADHDの子は、脳機能による特性のためやるべきことを忘れがちです。約束を覚えられないのはワーキングメモリの弱さが一因です。
ワーキングメモリとは、情報を整理し記憶にとどめておく力のこと。他の考え事をしても、約束などを忘れずに覚えておく時に使われる力です。
しかし、ワーキングメモリが弱いADHDの子は、覚えておこうと思っても、他の活動に移ると忘れてしまうこともあります。そのため、自分に不利益がある場合でも忘れてしまうのです。
ADHDの高校生に向いている勉強法

ADHDの高校生には、どのような勉強法が向いているのでしょうか。ここでは、家庭で取り入れやすい勉強法を6項目に分けて紹介します。
図や絵を使って勉強する
図や絵を使った課題は、飽きやすいADHDの高校生向けの学習です。文字だけの学習より情報が分かりやすく、飽きないためです。
ひたすら文章を読む読解や、似たような演習問題を解く学習はメリハリがなく飽きてしまいます。文章に付け加えて図や絵を使って学習すると、直感で分かりやすいので理解しやすくなるでしょう。
覚えた学習内容を、図やイラストを交えてアウトプットするのもおすすめです。人に説明できるくらい理解している証拠となり、学習内容の復習にも役立ちます。
勉強の予定をリストにして確認する
勉強の予定をリスト化して確認すると、学習すべき内容が分かりやすくなります。テスト勉強を計画的に学習する手立てとなるため、ぜひ取り入れてみましょう。
その時の気分で動くADHDは、やりたい学習だけ取り組んで苦手なものには手を付けない可能性があります。一旦、学習計画を立てておくと、やり忘れなく取り組めるでしょう。
計画を立てる際には、実現可能なものにすること。見ただけでやりたくなくなる計画は意味がないです。
短期目標を設定しクリアしていく
ADHDの高校生には、短期目標を設定しクリアしていく方法が合っています。集中力が長く続かないため、スモールステップで進む方が特性に合っているためです。
同じADHDでも集中できる時間は人それぞれです。子どもが集中して取り組める時間を目安とし、課題を用意するとよいでしょう。短時間でも小さな課題を積み重ねれば、達成したい目標をクリアできます。
学習時間の管理にはポモドーロテクニックの活用も効果的です。25分学習して5分休憩を繰り返す方法で、気分転換しながら無理なく取り組めるでしょう。
動いていてもできる勉強を取り入れる
体が動いていてもできる勉強法を取り入れましょう。同じ姿勢を続けるのは飽きてしまうためです。
高校生ぐらいになるとADHDの多動は落ち着きますが、基本的にはじっと座っているのが苦手です。動いていても勉強できるようなメニューを取り入れると、メリハリがつき長時間の学習時間が確保できるでしょう。
具体的には、椅子をバランスボールに変えたり、スタンディングデスクで学習姿勢を変えたりするとよいでしょう。イヤホンで講座を耳で聞くのも気分が変わるのでおすすめです。
二者択一で勉強していく
学習内容を2つに絞り、どちらからやるか選んでいくのも効果的です。課題を選ばせることで、取り組むことがはっきりするためです。
ADHDの子は、学習範囲が広すぎるとどれから手を付けてよいのか分かりません。そのうち違うことに気をとられ、学習時間が減ってしまうケースも考えられます。課題を決めるのを親がサポートし、とにかく学習に向かわせるのがコツです。
高校生ぐらいの年齢だと、親から口出しされるのが嫌だと感じる子も多いでしょう。親子関係の悪化を避けるため、発達障害に理解のある塾や家庭教師にまかせるのも1つの方法です。
好きな勉強は気が済むまでやる
好きな勉強は好きなだけやらせるとよいでしょう。興味のある分野はとことん追及するので、苦手科目をフォローできる場合もあります。
発達障害の子が、不得意な教科で大きく点数を伸ばすのは難しいものです。障害特性により、努力しても苦手なことは克服できず、ストレスの方が上回ります。
得意教科を学習し、苦手教科の分をカバーする考えがよいでしょう。得意なことには驚くほどの集中力を発揮する発達障害の子もいます。学習に特性をうまく生かすと、自信がつき自己肯定感も上がるでしょう。
ADHDの高校生が勉強に集中するための工夫

ADHDの高校生が効果的な学習を行うには、勉強に集中できる環境が大切です。家庭でできる工夫をして、学習環境を整えましょう。ここでは、ADHDの高校生が勉強に集中できるための工夫を3つ紹介します。
壁や仕切り板などで他のものが視野に入らないようにする
壁や仕切り板などを活用し、他のものが見えない環境を作ると効果的です。ADHDの集中を途切れさせず学習に向かわせることができます。
発達障害の人は、自分に関係のない情報もすべて受け止めてしまう傾向があります。勉強に関係ないものが見える環境だと集中が途切れる恐れが。視界をある程度狭くしてあげると、教材に集中しやすくなります。
すぐできる方法なら、机を壁につけるだけでも効果があります。パーテーションで横や前面を囲み個室のようにしたり、机の上で使えるパーテーションを使用したりする方法もおすすめです。
雑音などの刺激が少ない環境をつくる
ADHDの子が学習に集中するには、雑音などの刺激が少ない環境をつくりましょう。音に敏感な子もいるため、静かな環境が大切なためです。
ADHDを持つ子の中には、音に敏感なタイプもいます。聴覚過敏と言いますが、集中していてもちょっとした物音が気になるため、勉強から気持ちが離れてしまいます。
音を遮断するのは難しいので、グッズの使用もおすすめです。ノイズキャンセリング機能のあるイヤホンは周りの音が聞こえなくなります。聴覚過敏の人向けに作られたイヤーマフを購入するのもよいでしょう。
疲労がたまらないようにする
疲れがたまらないよう、生活リズムを整えてあげましょう。自分の疲れに鈍感なため、生活面のフォローが重要です。
高校生になると、学校までの通学距離が伸びたり授業時間が長くなったりして、義務教育より疲れがちです。楽しいことも多いので疲れていても行動したいと思うでしょう。特に、発達障害の子は自分の限界が分からず、疲れきるまで動いてしまう場合もあります。
疲れがたまるとマイナス思考になりがちで、二次障害になる恐れも。疲れている時のサインを見極めて、意識的に休ませるようにしてください。
ADHDの高校生の受験勉強の工夫

高校時代は短く、あっという間に大学受験の時期を迎えます。効果的な受験勉強をするには工夫が必要です。ここでは、ADHDの高校生の受験勉強の工夫を3つに分けて紹介します。
志望校選びは慎重に
ADHDの高校生が大学受験を突破するには、慎重な志望校選びが大切です。やりたいことが学べる学校はもちろんですが、テスト内容も確認しましょう。
志望校選びをする時、自分のやりたい学習ができる学校を選ぶでしょう。受験を突破するためは、試験教科や配点も重要です。得意不得意の差が大きいADHDの特性を生かすため、得意分野の配点が大きく、苦手分野をフォローできるような試験内容がよいでしょう。
マークシートの写し間違いなど、ケアレスミスが多いタイプなら、記述式問題の多い学校がおすすめです。志望校のピックアップとともに、過去問などを参考に出題傾向を掴むとよいでしょう。
学校で教わる範囲外の対策
受験勉強は、学校で教わる範囲外の対策も重要です。教科書で触れない範囲の問題が試験に出る学校もあるためです。
学校で教わらない内容を、家庭でフォローするのは難しいでしょう。受験に特化した学習なら、塾や家庭教師に頼むのも良い方法です。ポイントは発達障害に理解のある塾や家庭教師を選ぶこと。特性のある子でも先生と信頼関係を結びやすく、学習の成果につながりやすいでしょう。
得意不得意を把握して対策
発達障害を持つ子が受験勉強するには、得意不得意を把握して対策するのが大切です。苦手なことを頑張らせるよりは、得意なことをさらに伸ばした方が、良い結果につながりやすいためです。
子ども自身が得意不得意を分かっておらず、できない自分にイライラしてしまう場合もあるでしょう。子どもの小さいころのエピソードから「こんなのが得意だったよね」とヒントをあげるとよいでしょう。
学習面は発達障害の生徒を受け持ったことがある塾や家庭教師に依頼するのがおすすめです。子どもの特性を理解した教師が、子どもの良い面を伸ばしてくれるでしょう。
その子に合わせた勉強法をみつける
ADHDの子の高校受験対策は、好きなことや興味があることを伸ばすのがおすすめです。好きな分野なら集中力が続くので、受験勉強もやりやすいでしょう。
発達障害を持つ人の中には、好きな分野をとことん追及するタイプもいます。得意分野を学べる高校を目指せるなら、受験に対するモチベーションも保てるでしょう。
好きな科目もないADHDの子に、どのように勉強させるか迷う人もいるでしょう。家庭教師や塾など、受験対策のプロに依頼するのがおすすめです。特にオンライン家庭教師なら、インターネット環境があれば場所を問わず学習が可能。塾のように通う必要がないため、約束を忘れがちなADHDの子でも学習に取り組みやすいのがメリットです。
オンライン家庭教師ピースなら、ADHDなど発達障害を持つお子さんへの指導実績が豊富です。一人ひとりの特性に合った勉強方法を提案するので、高校受験に向け効果的な学習ができます。無料体験授業も受付中ですので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
早めに動き出す
ADHDの子の受験対策は早めに動き出すのが得策です。特性により、先の見通しが立てにくいためです。
ADHDの子は「今」を生きているので、過去を振り返ったり将来のことを考えたりするのは苦手です。高校選びには、将来どんな職業に就きたいかイメージするのも大切なこと。夢をかなえる途中に高校受験があると理解すれば、勉強する意味がはっきり見えてきます。
ADHDの子が受験勉強に取り組みやすいよう、中学2年から準備を始めるとよいでしょう。将来の夢がないなら、いろいろな高校のオープンスクールに行くのもおすすめ。実際の雰囲気を感じることで、自分に合う高校が選びやすくなるでしょう。
ADHDの子の進学先の選択肢
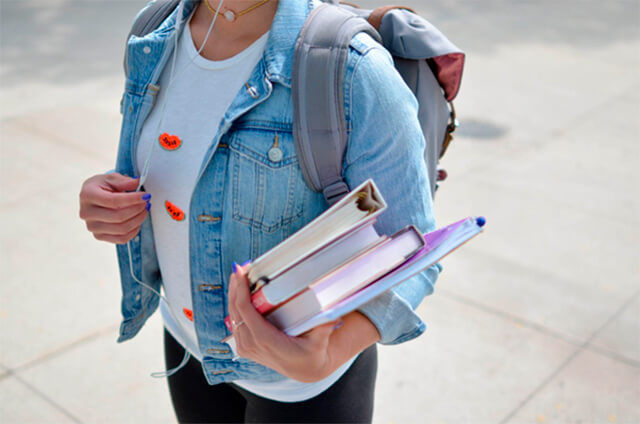
ADHDの子の進学先には、さまざまな選択肢があります。ここでは、ADHDの子の進学先を7つに分け紹介します。
全日制高校
ADHDの子の進学先として、全日制高校があります。中学校のように朝から夕方まで学校に登校し学ぶスタイルです。
全日制高校にはさまざまな学科があり、普通科には7割以上の生徒が在籍しています。工業や農業などに特化した専門学科や、科学・数学に特化した理数科なども設置。総合学科では、必履修科目と専門学科の両方が学べます。
定時制高校
定時制高校もADHDの子の進学先のひとつです。1日の学習時間が全日制よりも短いのが特徴で、卒業までの年数を3年か4年か選べます。
定時制高校は夕方から登校する夜間定時制のほか、午前中から授業を行う昼間二部定時制などもあります。働きながら学びたい生徒や、朝起きられず全日制高校に通うのが難しい生徒でも通いやすいでしょう。
通信制高校
ADHDの子の進学先として、通信制高校も候補のひとつです。私立の通信制高校は増えており、生徒数も年々増加しています。
通信制高校の特徴は、登校日数が少ないことです。自分で登校日を選択したり、決められた登校日に通ったりと学校により違います。インターネットやテキストで学習し、レポート提出やテストで単位を取得していきます。
高等専門学校
高等専門学校は技術者育成を目的とした高等教育機関で、得意分野のあるADHDの子に合った進路先です。
高等専門学校は5年一貫教育で、一般科目と専門科目が学べるのが特徴。実験や実習を中心に行うため、応用力を身につけることができます。学べる学科は学校ごとに違い工業系と商船系に分かれていますが、経営情報や国際ビジネスなどを学べる学校もあります。
高等専修学校
高等専修学校も、ADHDの子の進学先の候補です。将来の夢がはっきりしているADHDの子には、興味のある分野を学べるので合うかもしれません。
高等専修学校は、高校と同じように進学できる学校として、学校教育法上でも認められています。特色は、将来なりたい職業に直結する学習ができること。在学中に取得した資格を生かし、就職活動につなげていけます。工業分野や福祉・教育分野、理容・美容分野などの学科があります。
特別支援学校高等部
ADHDのほかに知的障害を伴う子の進学先として、特別支援学校高等部も選べます。障害に配慮した学習内容で、将来の自立を目指します。
特別支援学校高等部は小学部や中学部を併設しており、生徒の状態に合わせた自立を目指しているのが特徴です。実習やコミュニケーション練習など、働くことに重点を置いたカリキュラム構成です。
高等部のみ設置した高等特別支援学校では、一般就労に向けた専門教育が受けられます。就職率が高く人気で、特別支援学校高等部より受験倍率も高め。療育手帳を持つ生徒が対象で、知的障害のない発達障害では入学できない場合もあります。
その他の学校
ここまで紹介してきた学校以外にも、ADHDの子が中学校卒業後に通える学校があります。都道府県が設置するチャレンジスクールやクリエイティブスクール、パレットスクールなどです。
チャレンジスクールとは、東京都が設置した学校です。義務教育時代に不登校だった生徒や長期欠席などが原因で高校中退した生徒を対象にしています。埼玉県のパレットスクールも同様のシステムで、不登校支援のために設けられました。
クリエイティブスクールは神奈川県にあり、既存の教育では力を発揮できなかった生徒を受け入れています。
ADHDの高校生への親の関り方

高校生といえど、ADHDの子に学習させるには、家庭でのフォローが必要です。ADHDの高校生への親の関わり方について、ポイントを3つ解説します。
勉強しやすい環境を整える
ADHDの高校生のために親ができるのは、勉強しやすい環境づくりです。気が散りやすいADHDなので、落ち着いて学習できる環境が大切です。
雑音が聞こえにくく、パーテーションなどで囲むなど、学習に集中できる環境を作りましょう。スマホが近くにあると、着信音など気が散りやすくなります。本人が納得した上で、勉強中は親が預かるなど工夫するとよいでしょう。
いいところを褒めて伸ばす
高校生でもいいところを褒めて伸ばしましょう。褒める時のポイントは、子どもの感情に共感することです。
ADHDとはいえ高校生ですから、小さい子供みたいに褒めると逆に馬鹿にされていると感じるかもしれません。褒める前に、まず子どもの大変さに理解を示すことが大切です。
まず「苦手なことも学習しなければならなくて大変だよね」などと共感してください。その上で「計画的に学習していてすごく努力しているよね」と具体的に褒めると、子どもも受け入れやすいでしょう。
特性を把握して有効な声掛けを
特性を把握して有効な声掛けを心がけましょう。発達障害の子は、主語と結論が離れすぎていると、何を言いたいか理解しにくくなってしまいます。
ADHDの子に理解しやすく話すポイントは、短い文章で端的に話すことです。図や絵を使って説明するなど、視覚に訴える方法も効果的です。勉強の予定リストを一緒に確認し、学習状況を確認するとよいでしょう。
ADHDの高校生への支援のポイント

困り感の強いタイプには、どのような支援を行うのがよいでしょうか。ここでは、ADHDの高校生を支援するポイントを4つに絞って解説します。
先回りのサポートは難しい
高校生になると、親が先回りしてサポートするのは難しくなります。行動範囲や自分の世界の広がりにより、サポートしにくい場面が増えるためです。
小中学校の時は、学校などでのトラブルが起きる前に親がサポートできる機会も多かったでしょう。しかし、高校生になると行動範囲が広くなり、友達関係も複雑化します。子ども自身のプライドもあるため、あまり親に口出しされたくないと思う子もいます。
内申点の確認
ADHDの子が志望校を決める際には、内申点がどのくらいか確認しておくと安心です。普段の成績から予想したり、学校の先生に聞いたりするとよいでしょう。
公立高校受験の場合、内申点の取り扱いは都道府県により違います。1年生の内申点から対象となる場合もあれば、3年生の成績のみの場合も。実技教科の内申点も加味される点に注意です。
高校受験対策を早めに始めると、内申点の底上げもできるかもしれません。また、独自の評価基準を設ける私立高校を受験するのも選択肢に入れておきましょう。
選択は本人に
困った場面に出くわしたとき、どうするかはできるだけ本人に選択させるようにしましょう。自分で選んだことには自信を持って取り組めるからです。
発達障害の子は、人からの押し付けを嫌うことが多い傾向です。人の決めたことで失敗すると「そんなつもりじゃなかった」と相手を責める恐れも。行動に責任を持たせるため、最終的には自分で決めさせるようにしましょう。
選ぶのが苦手な子には、いくつか選択肢を与えます。志望校選びなら、子どもの希望に近い学校をピックアップし、その学校に通うメリットやデメリットを提示すると選びやすいでしょう。
整理整頓を指導する
整理整頓の指導は、家族がADHDの子にできる一番のサポートです。物の管理ができると、内申点アップにもつながるためです。
ADHDの子は、片付けが苦手で身の回りがごちゃごちゃしている場合が多いものです。課題プリントなども、他のものに紛れ込んでしまい、存在自体を忘れてしまいます。
提出物は内申点にも関わるため、家族のサポートが必要です。整理整頓で内申点が良くなる可能性を伝え、家族が片付け方法を教えてあげるとよいでしょう。
ご褒美をうまく使う
ADHDの子が高校受験に向けて学習できるよう、ご褒美をうまく使いましょう。メリットがあると学習に向かいやすくなるためです。
ADHDは目に見えないものは理解できない傾向があります。「勉強しろ」と言うより、「ご褒美があるから勉強頑張って」と言ったほうが分かりやすいのです。小さな目標をクリアするためご褒美を与え、高校受験に向かわせるとよいでしょう。
親子で勉強する
親と仲の良いADHDの子なら、親子で勉強するのも効果的です。リビングで学習させ、様子を見守るだけでもよいでしょう。
高校受験の学習は、親が教えるのも大変です。発達障害の生徒を受け持った実績のある、塾や家庭教師がおすすめです。
二次障害に気を付ける
発達障害を持つ子は、二次障害にならないよう十分注意しましょう。二次障害になると立ち直りに時間がかかるためです。
二次障害とは、合わない環境で生活することなどが原因で、心と体のバランスが崩れた状態のことです。小さい頃のように、親の考えを押し付けるやり方では本人のアイデンティティが失われかねません。周りに受け入れてもらえないと感じ、二次障害を引き起こすのです。
二次障害では、うつ病など心身の不調が起こります。引きこもりとなり社会生活が困難になったり、偏った考えから事件などに発展する危険も。二次障害のリスクを避けるため、周りの理解や過ごしやすい環境づくりが大切です。
第三者機関と連携を
ADHDの高校生をうまく支援するには、第三者機関と連携を取るのも大切です。気軽に相談できる場所があることで、本人も家族も楽になります。
相談先として、発達障害者支援センターに相談するのも手です。親の相談はもちろん、子どもが定期的に面談を受けアドバイスをもらえる場合もあります。病院を受診すれば、投薬治療やカウンセリングを受けることもできます。
また、勉強面のサポートは、発達障害に理解のある塾や家庭教師に依頼する方法もあります。特性に合わせた学習を行ってくれるので、無理なく成績を伸ばすことができるでしょう。
ADHDを持つ高校生の勉強でお悩みなら、オンライン家庭教師ピースがおすすめです。不登校や発達障害を持つ生徒への指導実績が豊富で、志望校対策から総合的なフォローアップまで対応します。
ADHDの特性により、人間関係の選り好みがある場合でもピースにおまかせください。体験授業から、お子さんとの相性を考え講師を紹介します。講師との相性がよい場合は、同じ講師が継続して授業を受け持ち、お子さんを力強くサポートします。
万一「相性が合わない」と感じた場合は、お子さんにぴったりの講師が見つかるまで無料で交代可能です。ADHDのお子さんが効率よく学習できるようサポートいたしますので、まずはピースの無料体験授業をお試しください。
まとめ
ADHDの子は、高校生ぐらいになると多動性や衝動性が落ち着いてきて、逆に不注意が目立つ傾向です。課題提出が遅れたり遅刻が多かったりと、物や時間の管理にルーズさが目立ちます。
受験に向けて静かで落ち着いた学習環境を用意し、集中して勉強できるよう工夫しましょう。二次障害にならないよう、特性に合わせた環境づくりも大切です。家庭だけで対応しきれない場合は、病院や発達障害者支援センターなど第三者の利用も考えてください。
志望校受験に向けた勉強は、発達障害に理解のある塾や家庭教師への依頼がおすすめです。二次障害により不安が強く、外出が厳しいならオンライン家庭教師という手も。無料体験授業もあるので、試してみてはいかがでしょうか。
















