現役東大生がおすすめする絶対使える古文の参考書・問題集7選
古文の参考書や問題集の選び方で困ったことはありませんか?古文は現代文、漢文とひとまとまりで一科目とされてしまうことが多いため対策が手薄になりがちですが、だからこそ対策をすることで他の受験生との差別化を図ることが出来ます。古文の勉強は英語と似ているといわれますが、英語よりずっと結果が出やすいのが嬉しいポイント。ちゃんとやれば、共通テストで「8割安定」できる科目です。今回この記事で古文の参考書・問題集を目的別に紹介するので自分に合ったものを見つけてみましょう!
古文が解けない・成績が上がらない原因

古文の勉強法を解説する前に、古文が伸び悩む人に多いパターンを見てみましょう。あなたが当てはまる項目はあるか?自分を振り返りながら読んでみてくださいね。
古文単語を覚えていない
実は一番多いのが「古文単語を覚えていない」というパターンです。このパターンに該当する高校生の多くは、「古文って言っても日本語なんだから、フィーリングで読めるでしょ」と思っているようです。
でも……、次の古文単語の意味は正しく把握できていますか?
- おどろく
- おこたる
- もてなす
- せめて
これらは「現代語の意味とは異なる意味を持つ古文単語」の代表選手です。「おどろく=驚く」「おこたる=サボる」「もてなす=接待する」、などと現代の意味で古文を読んでも意味は通じませんよ。
それぞれの正しい意味は次の通りです。
- おどろく ⇒ 目を覚ます
- おこたる ⇒ 病気が治る
- もてなす ⇒ 振る舞う
- せめて ⇒ 無理に、強いて
今から1000年も前に書かれた文章は、21世紀の私たちにとっては外国語も同然。英語学習は英単語の暗記から始まるように、古文も古文単語の暗記から手を付けることが基本です。
古文解釈の練習をしていない
古文ができないと悩む受験生に多い原因の2つ目は「解釈の練習をしていない」ということにあります。
解釈とは本文を時代背景や特徴を踏まえて、正しく理解するということ。さらに英語でいう「精読」、つまり一文一文の文法構造まで見抜きながら丁寧に読むことも含まれます。古文が読めるようになるためには欠かせないプロセスですが、「古文ができません」と訴える大学受験生は、どうも面倒がってこの解釈を飛ばしてしまう人が多いようです。
古文は当時、つまり同時代の人が読むことを想定して書かれたものですよね。同じ時代において「前提/常識」とされるものに、いちいち解説はつかないわけです。私たちが「Twitter」や「インスタ」という言葉に逐一説明がなくても理解できるのと同じように。
しかし平安時代の常識を持たない令和の私たちは、やはり勉強しないとあの頃の「前提/常識」は把握できませんし、理解できるようにはならないのです。
また古文法を勉強したにも関わらず(やっていない人は勉強してくださいね)、本文を読むときに文法知識を活かさない人もいます。動詞、形容動詞、助動詞、助詞といった区別をせずに「なんとなく感覚で」読み進めるため、平仮名が続くと文章の途中からわからなくなってしまうのです。
騙されたと思って、一度『枕草子』か『徒然草』の1段分を品詞分解してみてください。「めっちゃ読めるようになった!」という感想を持つこと、請け合いです。
問題演習量が足りない
絶対的な問題演習量が不足しているというケースもあります。古文は英語や数学に比べて優先度がどうしても下がるため、勉強時間を確保しにくいということが原因のようです。
しかしいくら単語を覚え、解釈の練習をしたとしても、実践経験が足りなければ得点にはつながりません。
解釈をしている段階では「読めたつもり」だったのに、内容一致問題を解こうとしたらまったくできなかった。あるいは「どういうことか」という説明問題の解答が、どのように書けば良いか言葉が出てこなかった。こうした経験を積んで、やっと古文の問題が解けるようになるのです。古文の問題演習も「量」多く取り組むことは必須です。問題集1冊を終わらせるつもりで進めてみてください。
古文ができるようになるための勉強のコツ

ここまで古文が読めない・できない人にありがちなパターンを3つまとめてきました。つまり、この3パターンの逆に取り組めば、古文はできるようになるというわけです!古文はきちんとした勉強に取り組めば、1か月で結果があらわれます。では古文が読めるようになる・できるようになる勉強法を紹介しましょう。
古文単語|まず300語覚えよう!
まずは古文の単語帳を用意してください。英語と同様、単語を覚えることから始めます。ただし、大学入試において「英単語は6000語必要」といわれるのに比べれば、古文で覚えるべき単語量は少なめ。重要単語を中心に「見出し語で300」覚えれば、まずは十分です。
単語は一度で完璧に覚えようとしないことがコツ。何度も繰り返しながら、徐々に記憶を固定させるイメージで取り組みましょう。またはじめは「主要な意味」だけを覚えていけばOK。登場頻度の低い意味や派生語は、解釈や問題演習を進める中で自然と頭にはいっていくものです。
古文法|単語と同時進行がおすすめ
古文単語と同時進行で取り組んでほしいのが、古文法です。古文法でおさえるべきポイントは「識別」「活用」「意味」の3つ。
「識別」とは、その単語がどの品詞なのかを区別する力のことです。古文は漢字より平仮名のほうが多い文章ですから、識別する力がないと「どこで区切って読めば良いのか」がわからなくなってしまいます。文法書には必ず「識別のポイント」といったものが書かれていますので、その項目を参考にまず区別できる力を身につけましょう。
次に「活用」です。用言(動詞・形容動詞・助動詞など)は、後ろに続く言葉によって語尾が変わります。語尾の変化の仕方を覚えていないと、文章がまったく読めなくなってしまいます。
- 「上一段活用/下二段活用」「変格活用」などは数が少ないので丸覚え。
- 「四段活用/上二段活用/下二段活用」「形容詞/形容動詞」は規則性で覚えましょう。
また歌や暗唱を何度も繰り返すのもおすすめです。
最後は「意味」です。これも覚えていないと読解が始められません。まず最重要・最頻出の意味、現代語と異なる意味をおさえ、次いで2番手・3番手の意味を暗記するという順番が取り組みやすいでしょう。
単語と文法は、とにかく「暗記」の完成度が勝負になります!
まずは「精読」、丁寧に解釈に取り組む
単語と文法がある程度進んだら、解釈に入っていきます。教科書や基本的な問題集を題材に、「精読」つまり一文一文丁寧に読み解く練習を始めましょう。先にも書きましたが、おすすめは「品詞分解」をしてみることです。本文の品詞分解が解説に載っている問題集(多くは載っています)をチョイスし、本文をコピーして一語一語「品詞・活用・接続・意味」を書き入れてみてください。
一文終わったら、解説の品詞分解と照らし合わせます。間違っている箇所は「どうして自分の品詞分解ではダメなんだろう」と考えることが大切!これを繰り返すと、1ページ終わるころには本文を読みながら品詞分解が脳裏に浮かぶくらいになってきます。もちろん、意味も把握しながら読み進められるようになっていますよ!
また解説は必ず隅々まで読みましょう。時代背景や作品知識なども書かれていることが多いので、合わせておさえていくことが大切です。
問題演習は基礎から無理なく
問題集は「基礎から無理なく」ステップアップできるように選ぶのもポイント。古文は題材や出題元によって難易度の幅が広い科目です。とくに難関私大は「知っていないと解けない」問題や非常に難しい問題も出題されるので、「難関私大の過去問」が収録された問題集にいきなり当たると挫折してしまうこともあります。
古文の勉強を始めたばかりの段階は、「慣れる」ことも重要。「基本」「基礎」という問題集から取り掛かっていきましょう。
古文の参考書・問題集の正しい選び方
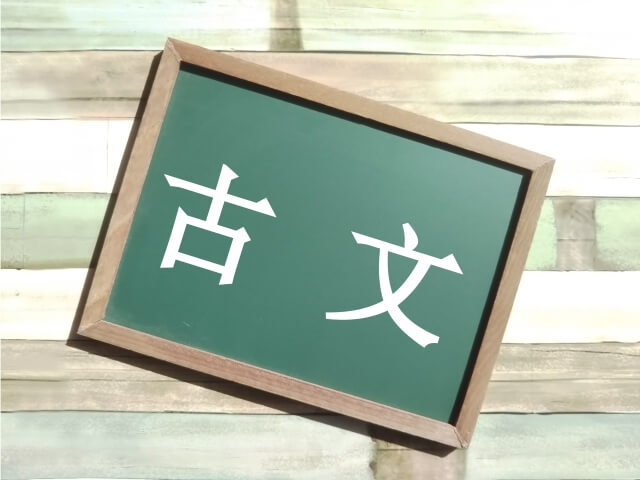
古文の参考書・問題集を選ぶ際のポイントを以下で説明していきたいと思います。
古文は三つの軸をバランスよく
英語を勉強するときに一般的に言われるのは英単語と文法が土台であるということです。しかし古文においてはそこにプラスαとして古文常識も必要になってきます。古文単語の意味を知り、助動詞などの文法を抑え、古文の物語の時代背景を知ることではじめて統合的な理解が可能となるのです。
その参考書・問題集に割ける時間はどの程度あるのか
本屋の棚に置いてある参考書・問題集はどれも良さそうにみえるのでつい買ってしまいがちですが、実際に一つの参考書・問題集を完璧に仕上げるとなれば一か月から三か月以上はかかりますので一度に複数の参考書・問題集を買ってはキャパオーバーになってしまいます。まずは自分がこなせる量がどのくらいか把握し、その次にやる問題集を精選しましょう。
古文のおすすめ参考書・問題集【古文常識編】
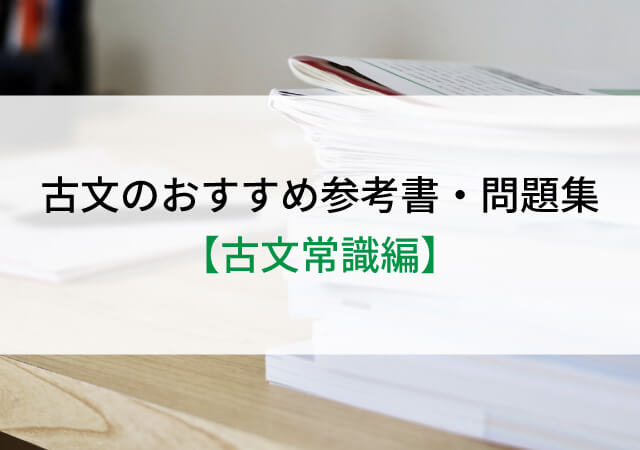
さてここからは古文常識のおすすめ参考書・問題集を紹介したいと思います。「古文常識って勉強する必要あるの?」と思われる方も多いかもしれませんが、古文常識は勉強するべきでしょう。なぜならその時代の常識を分かっていないと文章中で起こっている出来事の意味が理解できない可能性があるからです。古文の話題として出家や恋愛の話題が多くこれらの話題について定番の流れを抑えておくだけでも読解が非常に楽になります。
速読古文常識
まず初めに紹介するのはZ会の出版している速読古文常識です。この参考書の特徴はレイアウトが見やすいということです。1ページに一つの話題を収めているため大変読みやすく、内容としても解説に加え例文、関連語、例題など充実しています。古文を勉強する際には単語と文法が大切だとされていますが、それと同じくらい重要なのが古文常識です。古文の苦手意識を払拭するためにもこの本で古文常識を身に付けましょう。
マドンナ古文常識
次に紹介するのは学研が出版しているマドンナ古文常識です。この参考書では古文常識が種類別に章立てられて解説されています。古文にしか出てこない用語について取り上げ、その単語の意味を説明しています。古文特有の固有名詞などに対して、その意味と読み方に加えて語源、説明などがイラストを交えわかりやすく描かれています。古文単語を覚える時と違って一つの単語に対して一つの意味を覚えるのではなく、古文の固有名詞一つ一つに対してイメージを定着させることが目的ですのでじっくり読み進めるよりは、サラッと一周読んでしまいそのあとは忘れたときにその都度確認する、辞書的な使い方をするのが好ましいかと思います。
古文のおすすめ参考書・問題集【古文単語編】
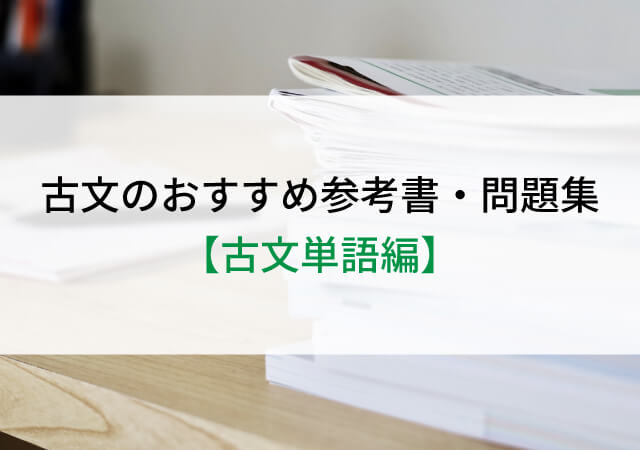
続いておすすめの古文単語帳を紹介していきたいと思います。
古文単語ゴロゴ
まず紹介するのはスタディーカンパニーが出版している古文単語ゴロゴです。この単語帳は古文が苦手でどうしても勉強が進まないという人向けに作られた単語帳です。一つ一つの単語に対してその意味を覚えるための語呂が用意されており飽きずに効率的に学習することが出来ます。単語を覚えられれば文法や古文常識の勉強にも勢いがついてくると思うのでまずはこのような単語帳からアプローチしてみるのもありでしょう。
理解を深める 核心古文単語
次に紹介するのは尚文出版が出している理解を深める 核心古文単語351です。この単語帳は正統派の単語帳といえる内容となっていて、単語の意味、そして例文が記載されています。さらに助かるのが「基本アングル」「入試アングル」という項目でそれぞれの単語の理解の仕方を解説してくれているので単語の学習がスムーズにやりやすいです。古文単語帳は数多くありますが個人的に一番おすすめです。
古文のおすすめ参考書・問題集【古典文法編】
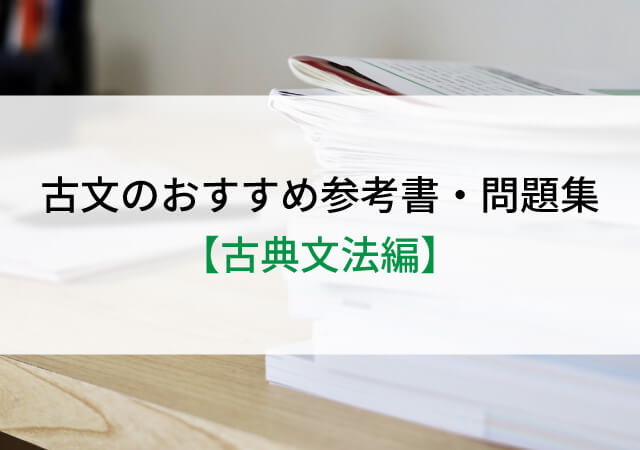
続いて古典文法のおすすめ参考書・問題集を紹介していきたいと思います。古典文法は古文を学び始めていちばん最初にやりますが演習を積んでいくうちに次第に軽視しがちになってしまう傾向にあるので時々振り返ってみるのが良いでしょう。
ステップアップノート30古典文法基礎ドリル
ここで紹介するのは河合出版の出しているステップアップノート30古典文法基礎ドリルという問題集です。問題集の題名にもある通りノートのような見た目をしていてレイアウトも大きく取り組みやすいという特徴があります。文法の復習をいざやろうと思っても活用表や助動詞表を見るだけじゃ復習しづらい!という人はこの問題集がおすすめです。
古文のおすすめ参考書・問題集【文章読解編】
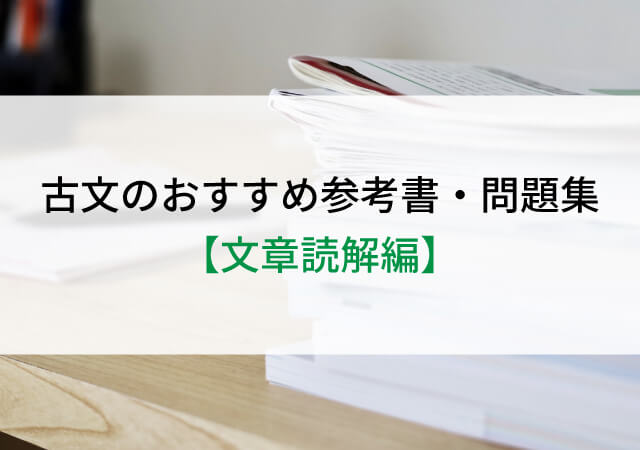
次に古文の文章読解のための参考書・問題集を紹介したいと思います。単語・文法・古文常識を一通り身に付けても実際に古文を読もうとすると躓いてしまうことがあると思います。このような場合には演習不足が考えられるので古文読解の問題集を試してみましょう。
読み解き古文単語
初めに紹介するのはZ会の出版している読み解き古文単語です。この参考書は単語帳という位置づけですが読解力向上に大変役立つので文章読解編のところで紹介させてもらいました。特徴としては古文の文章を読みながら古文単語を習得できる構成であることが挙げられます。見開き1ページの右側半分に古文、左側半分にその日本語訳が載っているため読みやすく、その次のページから重要な単語について単語帳と同じ要領で解説してくれています。古文になれるためには古文に触れる機会を増やすことが大切です。この参考書にはおよそ50題にも及ぶ長文が掲載されており、すべてをこなすには相当な時間と労力がかかりますが、すべてをこなすことが出来れば共通テストはもちろんのこと二次試験でも古文の読解で苦しむことはなくなるでしょう。
最強の古文 読解と演習50
次に紹介するのはZ会の出版している最強の古文 読解と演習50です。この問題集は私大対策・国立大対策として最高峰の問題集といえます。問題文自体の難易度は高くないものも含まれるのですが、別冊の解答解説の情報量が大変多くすべてを消化しようと思うと大変重たいことでしょう。古文と一口に言ってもその年代はバラバラで712年に編纂された古事記から江戸時代1702年にまとめられた奥の細道などおよそ1000年ものギャップがあり当然それぞれで使われる言葉にも差異があります。この問題集はそのような古代から近代まで幅広い問題を収録しているためどんな年代の問題が出ても対処できる総合力を身に付けることが出来るでしょう。
国公立大2次試験/難関私立大の古文対策
「古文は共通テストだけで使います」という受験生は、ここまでまとめてきた勉強法に取り組み、共通テストレベルの問題集やセンター試験の過去問を繰り返せば十分です。ただし国公立大2次試験や難関私立大個別試験で古文を使います、という受験生はプラスアルファの対策が必要。ここからは国公立大・難関私立大向けの勉強法について触れておきましょう。
古文の記述対策は「記述試験向けの問題集」を用意することから
国公立大2次試験は記述式の問題が多く出題されます。共通テストはマーク式ですから、2次試験で古文が必要という受験生は、記述対策もしておかないといけません。
古文の記述対策は「記述試験向けの問題集」に取り組むことがおすすめ。記述式独特の問題形式に数多く触れ、解答の作り方に慣れていきましょう。制限文字数内で必要な情報を抜け漏れなく網羅するためには、簡潔な文章表現力も欠かせません。模範解答と自分の答案を丁寧に見比べ、足りない部分を補っていってください。
また現代語訳の問題が出されることも多いので、古文を一文一文訳してみるのも良い勉強になります。この時「意味が正しく訳せているか」という観点のほか、「助動詞は識別できているか」「敬語は訳せているか」「敬意の方向は正しいか」といった減点されやすい箇所も忘れずにチェックしてくださいね。
難関私立大学古文対策は「過去問演習」が肝!
難関私立大学は大学によって出題傾向や出題意図が大きく異なります。そのため、まず「過去問」をチェックし、傾向をつかんでから対策を立てることがポイントです。
過去問をチェックする際は、次のような観点をおさえると良いでしょう。
- 本文の分量
- 出やすい題材・時代傾向
- 注釈の量
- 問題形式
- 選択肢の数、長さ
古文は現代文ほど長くなくても、冊子見開き2ページにもわたるものが出される場合があります。こうした大学を受験する場合は、「長い古文」に対応できる力が必要、ということになります。
また意外と見落としがちなのが「注釈の量」です。注釈は本文の解釈を助ける目的で置かれていますが、これが多いということは、それだけ解釈が大変である、本文が難しいということを意味するからです。
選択肢の長さも見てみてください。選択肢が長いと、それだけ読解の総量が増えるということになります。また選択肢内で吟味しないといけない要素も増え、時間がかかることも予想されます。
難関私大の個別試験で古文を使う場合は、自分がどのレベルで古文を完成させればよいのかを見極めてから、対策を立てていきましょう。
和歌・文学史が必要かどうかは「過去問で判断」
和歌・文学史は、勉強するべきか/どれくらい勉強すればよいのか、受験生を悩ませる要素ですよね。和歌も文学史も出題頻度は多くないくせに、知っていないとまったく解けない点が厄介です。
結論をいうと、自分に必要かどうかは過去問を見て判断すればOK。毎年のように出題している大学を受験するなら相応の対策は必要になりますし、隔年で出題するようであれば優先度は高くありません。
和歌や文学史は、真剣に取り組もうとするとそれなりに時間がかかる分野です。どうしても時間がないという場合は、和歌や文学史「以外」の完成度をあげ、合格点を目指すという戦略もあります。全体の学習計画と照らし合わせ、最適と思える方法を見つけていきましょう。
番外編・さらに得点を伸ばす!おすすめ勉強法
ここまでの古文勉強法で、大学入試は万全です。
さてここからは番外編!さらに古文の得点を伸ばす、速く解いて満点を目指せるちょっとした勉強のコツを3つ、お伝えしましょう。
古文の勉強法プラスアルファの3ポイントは、次の通りです。
- 主だった文学作品の「あらすじ」をおさえる
- 古代中国史や故事をおさえる
- 単語は文章をまるごと覚える
古文で出題される文学作品は、およそ決まっています。主要な題材は、あらすじを覚えてしまいましょう。あらすじを知っているということは、およその内容を把握できているということ。初見の文章でもぐんと読みやすくなります。
『伊勢物語』『和泉式部日記』『俊頼髄脳』といった出典を見た瞬間に、「あぁ、あの話ね」とピンとくるようになった自分、悪くないのではないですか?
また古文が書かれた時代というのは、中国からの政治的・文化的影響も大きかった時代です。具体的なエピソードとして登場することはなくても、そうした時代背景というのは行間にあらわれるもの。古代中国史や有名な故事を知っておくことも、古文読解の役に立ちます。
最後に、単語を覚える際は単体で覚えるのではなく、登場する文章を丸ごと覚えてしまうとより実用的な知識として活かしやすくなります。文章で覚えると、接続や活用はもちろん、周辺情報も一緒にインプットできるからですね。単語帳には「例」としてその単語が使われているシンプルな文章が書いてあることが多いですから、ぜひチェックしてみてください。
まとめ
さて今回は古文のおすすめ参考書・問題集について紹介してきました。古文の勉強はおろそかにされがちですが単語・文法・古文常識の土台をしっかり作ったうえで読解問題をこなして古文を得点源にすることが出来れば受験生の中から頭一つ抜け出すことが出来るでしょう。この記事が皆さんの役に立てれば幸いです。
オンライン家庭教師ピースでは、お子さんのタイプに応じてオーダーメイド授業を行っています。特定の苦手科目を伸ばしたい、個別に勉強方法を教えてほしいなどといったご家庭のおすすめです。
















