共通テスト「情報I」対策方法
2025年度から大学入学共通テストに新たに加わる「情報I」は、文系・理系を問わず、多くの受験生にとって未知の科目です。プログラミングやデータ分析など、これまでの学習内容とは大きく異なる分野が含まれるため、どのように対策すればよいか迷う方も多いでしょう。
しかし、共通テストの出題傾向や特徴を理解し、効率的な勉強法を実践すれば、高得点を目指すことは十分に可能です。
共通テスト「情報I」の出題傾向から具体的な対策方法まで、徹底的に解説します。
共通テスト「情報I」出題問題・特徴

2025年度から共通テストに加わる「情報I」は、単なる知識の暗記だけでなく、論理的思考力や問題解決能力を問う問題が出題されるのが特徴です。
配点が100点と高いため、情報Iは、得意科目として得点を稼ぐチャンスのある科目です。他の理系科目や社会科目が苦手な受験生にとって、情報Iは、合格に大きく貢献する可能性を秘めています。
出題分野は、大きく分けて以下の4つです。
「情報I」出題分野
- 1. 情報社会の進展と情報技術
この分野では、情報が社会に与える影響や、情報技術の役割について問われます。具体的には、情報セキュリティ、著作権、個人情報保護、情報モラルといったテーマが出題されます。単なる暗記問題ではなく、日常生活における情報技術の活用や、それに伴うリスクをどう考えるか、といった倫理的・社会的な視点が問われるのが特徴です。
【具体的な問題例】
- 著作権に関する事例問題で、どの行為が著作権侵害にあたるか判断させる問題。
- 個人情報保護に関する事例で、個人情報の適切な取り扱いについて問う問題。
- サイバー攻撃の種類や対策について、具体的な事例を挙げながら問う問題。
- 2. コミュニケーションとネットワーク
ネットワークの仕組みや、データの送受信に関する知識が問われます。例えば、Webサイトの仕組みや、SNSの特性、ネットワークにおける情報のやりとりなどについて出題されます。また、情報デザインやユーザーインターフェース(UI)の考え方など、情報を効果的に伝える方法についても問われることがあります。
【具体的な問題例】
- Webサイトの仕組み(クライアント・サーバーモデル)に関する問題で、それぞれの役割を問う問題。
- 情報の伝達速度や、データサイズに関する計算問題。
- 複数の情報の中から、目的に合ったものを選択し、利用する問題。
- 3. データの活用
統計データやグラフの読み取り、データ分析の手法、仮説の検証など、データの活用に関する問題が出題されます。この分野では、数学的な知識も必要とされますが、それ以上に、提示されたデータから結論を導き出す論理的思考力が求められます。
【具体的な問題例】
- 商品の売上データや、公共施設の利用者数に関するグラフから、特徴を読み取らせる問題。
- 複数のデータを比較し、仮説の正しさを検証する問題。
- データの特徴を把握し、適切なグラフを選択する問題。
- 4. コンピュータとプログラミング
プログラミング的思考力を問う問題が出題されます。特定のプログラミング言語の知識は必要なく、プログラムの流れ図や擬似言語の読み取り、あるいはプログラムの穴埋め問題などが出題されます。この分野では、与えられた条件の下で、どのような手順で問題を解決するかという思考プロセスが重要になります。
【具体的な問題例】
- 与えられた擬似言語やフローチャートが、どのような処理を行うか説明させる問題。
- 提示されたプログラムの穴埋め問題で、論理的に正しいコードを記述させる問題。
- ある問題を解決するための手順を、論理的に説明させる問題。
これらの分野は、それぞれ独立しているわけではなく、相互に関連しています。共通テスト「情報I」では、これらの分野を横断するような問題が出題されることも予想されます。
出題形式の特徴
- 複数分野の複合問題
単一分野の知識を問う問題だけでなく、複数の分野の知識を組み合わせた複合問題が出題される可能性があります。例えば、プログラミングの問題の中に、データ分析の考え方が含まれるなどです。
- 長文読解と論理的思考
共通テストは、問題文が長い傾向があります。情報Iでも同様に、長文の問題文を読み解き、必要な情報を抽出し、論理的に考える力が求められます。
これらの特徴を踏まえ、情報Iの対策は、単なる知識の暗記に留まらず、実践的な問題解決能力を養うことが重要となります。
共通テスト「情報I」試験概要
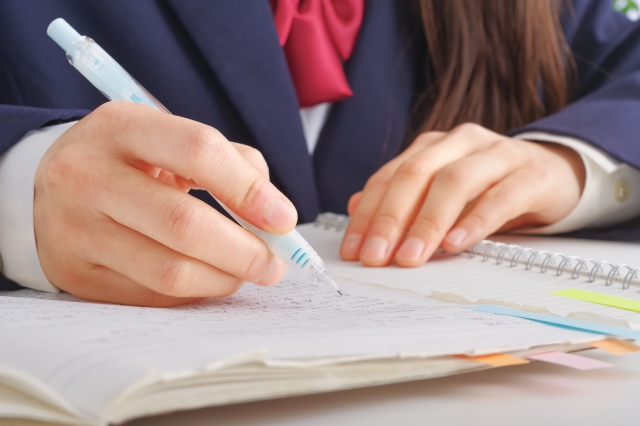
共通テスト「情報I」は、他の科目と同様、試験時間や配点が決まっています。事前に概要を把握し、対策を立てておきましょう。
- 試験時間
60分
- 配点
100点(第1問: 20点 第2問: 30点 第3問: 25点 第4問: 25点)
- 出題形式
従来の共通テストと同様、大問形式で、複数の小問から構成されます。
- 出題分野
「情報I」の学習指導要領の前述の4つの分野(情報社会の進展と情報技術、コミュニケーションとネットワーク、データの活用、コンピュータとプログラミング)から幅広く出題されます。
共通テスト「情報I」受験時の解き方のコツ

共通テスト「情報I」は、60分という限られた時間で、論理的思考力や問題解決能力を問う問題を解かなければなりません。そのため、本番で最大限の力を発揮するための解き方のコツを知っておくことが重要です。
試験開始直後の心構え
- まず全体をざっと見渡す
試験が始まったら、すぐに問題を解き始めるのではなく、まず全体をざっと見渡し、出題形式や問題数、おおよその難易度を把握しましょう。
- 得意な分野から解く
自分が得意な分野の問題から解き始めることで、スムーズに問題を解き進められ、自信につながります。
問題の解き方のコツ
- 問題文を丁寧に読む
共通テストは、問題文にヒントが隠されていることが多いです。問題文だけでなく、グラフ、表、図、あるいは擬似言語のコメントなどを丁寧に読み込み、何が問われているのかを正確に把握しましょう。
- 図や表を活用する
プログラミングの問題では、複雑な処理の流れを追うのが難しい場合があります。紙とペンを使って、図や表を書きながら、処理の流れを整理すると、ミスを防ぐことができます。
- 「なぜ?」を考える
単に答えを導き出すだけでなく、「なぜこの手順で解くのか」「なぜこの結果になるのか」という思考プロセスを意識することで、より深く問題を理解できます。
時間配分の工夫
- 1つの問題に時間をかけすぎない
もし、どうしても解けない問題があったら、いったん飛ばして、他の問題を解き終えてから戻ってくるようにしましょう。1つの問題に時間をかけすぎると、解けるはずだった他の問題に手がつけられなくなる可能性があります。
- 時間配分を事前に決めておく
事前に過去問や予想問題を解き、どの分野にどのくらいの時間をかけるか、おおよその時間配分を決めておきましょう。
これらの解き方のコツを事前に練習しておくことで、本番で落ち着いて問題を解くことができるでしょう。
通テスト「情報I」効率的な勉強法

共通テスト「情報I」は、新しい科目であるため、対策法が確立されていません。しかし、出題される分野を理解し、効率的な勉強法を実践すれば、高得点を目指すことは十分に可能です。
教科書・参考書で基礎を固める
まずは、教科書や参考書を読み込み、基本的な知識を身につけましょう。特に、プログラミングやデータ分析の分野は、用語や基本的な考え方を理解することが重要です。
- 用語の定義を正確に覚える
情報分野には、聞き慣れない専門用語が多くあります。単語帳を作るなどして、用語の定義を正確に覚えましょう。
- 各分野の「なぜ?」を理解する
単に知識を暗記するだけでなく、「なぜこの技術が使われるのか」「なぜこの処理が必要なのか」といった、本質的な理解を深めましょう。
過去問・予想問題集を解く
共通テスト「情報I」は、まだ過去問が少ないため、試行調査の問題や各予備校が作成した予想問題集を解くことが重要です。
- 出題傾向を把握する
問題を解くことで、出題傾向や自分の苦手な分野を把握できます。
- 時間配分を練習する
時間を計って問題を解くことで、本番での時間配分を練習できます。
- 復習を徹底する
解きっぱなしにするのではなく、間違えた問題や分からなかった問題は、教科書や参考書に戻って、なぜ間違えたのかを徹底的に復習しましょう。
プログラミングを実際に体験する
プログラミングの問題は、実際に自分でコードを書いてみることが何よりも大切です。
- Webサービスを活用する
Webサイトなどで無料でプログラミングを学べるサービスを活用し、簡単なプログラムを実際に書いてみましょう。
- 簡単なプログラムを作成する
プログラミングの基礎が身についたら、「じゃんけんゲーム」や「簡単な電卓」など、身近なものを題材にして、簡単なプログラムを実際に作成してみましょう。
- コードの流れを追う練習
複雑なコードの流れを追う練習をすることで、プログラミング的思考力が身につきます。
日常生活と結びつける
情報Iで学ぶ内容は、私たちの日常生活と深く結びついています。
- ニュースや新聞に注目する
情報セキュリティや個人情報保護に関するニュースに注目することで、学習内容をより深く理解できます。
- Webサイトの仕組みを考える
普段利用しているWebサイトがどのような仕組みで動いているのか、少し考えてみるだけでも、学習内容が身近に感じられます。
- バランス良く学習する
情報Iは、4つの分野(情報社会の進展と情報技術、コミュニケーションとネットワーク、データの活用、コンピュータとプログラミング)から出題されます。特定の分野に偏った学習をしてしまうと、配点の高い問題で得点を失い、致命的になる可能性があります。そのため、4つの分野すべてをバランス良く学習することが重要です。
これらの勉強法を参考に、計画的に学習を進めることで、共通テスト「情報I」で高得点を狙えるでしょう。
共通テスト「情報I」の勉強はいつから始めればいい?
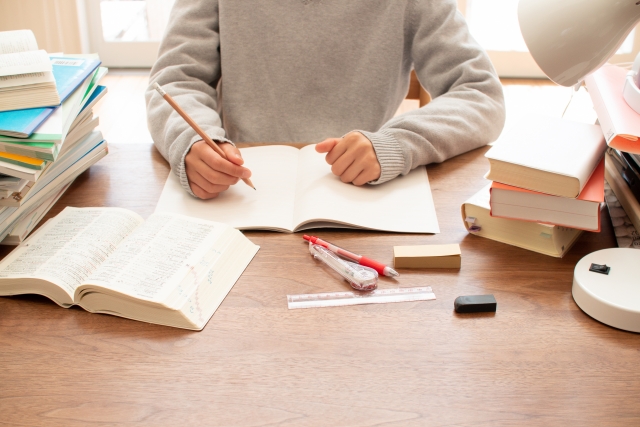
共通テスト「情報I」の勉強は、高校2年生の秋から冬にかけて始めるのが理想的です。この時期は、まだ他の受験生が本格的な受験勉強を始めていないことが多いため、科目全体を把握し、基礎を固めるのに十分な時間を確保できます。
なぜ高2から始めるのがいいのか?
情報Iは、単なる暗記科目ではなく、プログラミング的思考やデータ分析といった、論理的思考力を問う問題が中心となります。これらの力は、短期間で身につくものではなく、日々の演習を通じて、少しずつ養っていく必要があります。
- 十分な時間確保
高校3年生になると、他の受験科目(特に数学や英語)の学習が本格化するため、情報Iに割ける時間が限られてしまいます。高2のうちから始めておけば、焦らずじっくりと取り組めます。
- 苦手分野の発見と克服
早めに勉強を始めることで、自分がどの分野(プログラミング、データ分析など)が苦手かを発見し、集中的に克服する時間を確保できます。
- 「情報I」は高得点のチャンス
多くの受験生が対策を始めるのが遅いため、しっかり対策すれば他の受験生と差をつけ、高得点を狙えるチャンスのある科目です。
具体的な学習開始時期の目安
- 高校1年生
部活動や学校生活に慣れる時期なので、情報Iの授業内容を理解するだけで十分です。
- 高校2年生の夏休み
本格的な受験勉強のスタートを切るならこの時期です。教科書を読み込み、全体像を把握しましょう。
- 高校2年生の秋から冬
最もおすすめの時期です。この時期から、基礎的な問題集を解き始め、演習量を増やしていきましょう。
- 高校3年生
この時期から始める場合は、他の受験科目とのバランスを考え、効率的な学習計画を立てることが重要です。
まとめ
共通テスト「情報I」は、多くの受験生にとって未知の科目ですが、しっかりと対策を立てれば、得点源にできる可能性を秘めています。
他の科目の対策と並行して、合格に向けて、計画的に学習を進めましょう。
















